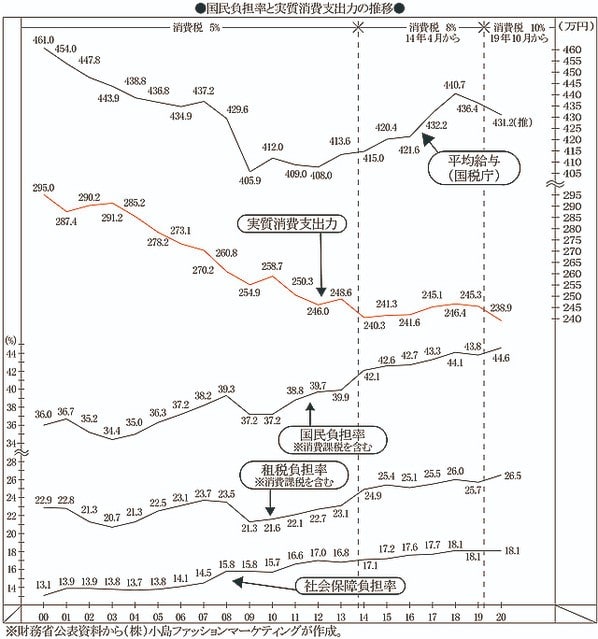日本の賃金や1人当たりGDP(国内総生産)は、アメリカの6割程度と低い水準だ。表面的に見ると、アメリカの成長率が高かったのに対し日本が成長しなかったことが原因だ。しかし、本来は為替レートが円高になって、この差を調整したはずだ。
“円安政策”を取ったことが日本を貧しくした基本原因だ。
日本の1人当たりGDPは
アメリカの63%でしかない
日本の賃金が安いことが問題になっている。OECDの賃金データで見ると、2020年に日本が3万8514ドル。これはアメリカの6万9391ドルの55.5%だ(注)。
その他の類似指標でも同様の傾向が見られる。
(注)OECDの賃金データは、実質賃金の購買力平価評価だ。このため、過去の時点での国際比較はできない。しかし、2020年基準であるので、20年の値は名目値を市場為替レートで換算したのと同じ値になるはずだ。
20年の1人当たりGDPは、日本では4万146ドルであり、アメリカの6万3415ドルの63.3%だ。
ビッグマックの価格で見ると、21年6月で日本の価格は390円。当時の市場為替レート(1ドル=109.94円)で換算すると3.55ドルで、アメリカの5.65ドルの63%だ。
このようにさまざまな指標で見て、日本はアメリカのほぼ6割程度の水準だ。これが「安い日本」と言われる現象だ。これは大きな問題だ。
とくに賃金が低水準なのは由々しき問題だ。
岸田文雄政権は「成長と分配の好循環」を掲げ、近くまとめる経済対策でも賃金を増やした企業の税を軽減するなどの「賃金引き上げ策」を盛り込むという。だがそれで効果があがるのかどうか。
まずはなぜこうなったのかを明らかにする必要がある。
アベノミクスの期間に、
日本の地位が急低下
賃金やGDPの問題でよくいわれるのは、過去20年以上にわたって日本がほとんど成長しなかったことだ。それに対して、世界の多くの国で経済が成長した。「このため、日本が取り残された」と言われる。
以下では、このことが正しいのかどうか検討を進めよう。
まず、1人当たりGDPについて考えよう。
1人当たりGDPは賃金とほぼ同じ動向を示す指標であり、各国の賃金データよりも1人当たりGDPのほうが国際比較データを入手しやすい。
これについての時間的な推移を見ると、図表1に示す通りだ。
2000年に、市場為替レートで換算した1人当たり名目GDPは、アメリカが3万6317ドル、日本が3万9172ドルであり日本が8%ほど高かった。
ところが、その後の成長に大きな差があった。00年から20年の間に、自国通貨建て1人当たり名目GDPは、日本では422万円から428万円へと1.4%しか増えなかったのに対して、アメリカでは3万6317ドルから6万3358ドルへと74.5%も増えた。
他方、市場為替レートは、00年も20年もほぼ105円~110円程度であまり変わらなかった。
このために、市場為替レートで換算すれば20年に日本はアメリカの63%になったということになる。
円高に向かう調整を抑制
円安で購買力が低下したことが問題
以上で見る限り、日本が貧しくなった原因は日本の成長率の低さだということになる。
確かに、表面的に言えばそうだ。しかしここで止まらずに、さらに検討を続ける必要がある。
なぜなら、アメリカで物価が上がり日本で上がらなければ、あるいはアメリカで名目賃金が上がり日本で上がらなければ、本来なら為替レートが円高になって調整するはずだからだ。
このことは、「実質為替レート指数」という概念によって表される。これは、実際の為替レートと購買力平価との比率で、ある国の通貨の購買力がどのように変化したかを、基準年次を100として示すものだ。
2010年を100とする実質実効為替レート指数は、00年で130程度だったが、20年では70台に低下している。
こうなったのは、日本で金利を低くして、円高になる調整を抑圧しているからだ。
購買力が00年と同じくなるには、円の価値が130÷70=1.9倍になる必要がある。つまり1ドル=105円でなく、計算上は1ドル=105÷1.9=55円になる必要がある(注2)。
このレートで換算すれば、日本の1人当たりGDPは7万7826ドルとなり、アメリカの6万3358ドルより高くなる。
これは、「非現実的な見方だ」と思われるかもしれない。
ポイントは、「1ドル=55円になるべきだ」というのが非現実的なのではなく、円の購買力が「非現実的なほどに低下した」ことだ。
もう少し現実的に、アベノミクス以前と購買力を同じにすることを考えよう。
13年の実質レートは100だった。20年に70だったから、100÷70=1.43倍にする必要がある。つまり、1ドル=105円でなく、1ドル=105÷1.43=73円にする必要がある。
このレートで換算すれば、日本の1人当たりGDPは5万8636万ドルとなる。アメリカより7.5%ほど低いが、「ほぼ同程度」と言ってもよいだろう。
(注2)実効レートは、ドルだけでなく、さまざまな通貨に対する平均値だ。ここではドルに対しても同じ値だと仮定している。
つまり、アベノミクス以前と同じ購買力を維持できていれば、日本の賃金はいまでもアメリカ並みであったはずだ。
ところがアベノミックスの期間に急激な円安が生じ、現在のような状況になったのだ。
したがって、現在の日本の低い賃金や「安い日本」を問題とするのであれば、その責任はアベノミクスにあるということになる。
シャーロック・ホームズ・シリーズの『銀星号事件』で、ホームズは、犯人が侵入した時間に「犬がほえなかった」ことが不思議だと言う。あって当然なのになければ、それが問題を解くカギだ。異常な円安に対して、番犬がほえなかったのが日本の問題なのだ。
ビッグマックのデータで見ても、
為替レートが物価の差を調整せず
以上で指摘したことは、ビッグマックのデータでも確かめられる。
この指標で、日本はいま調査国中の最下位グループにある。
アベノミクス前の2012年6月に、日本のビッグマック価格は320円だった。このときの為替レートは1ドル=78.22円。これで換算すると4.09ドルとなり、アメリカの4.33ドルとあまり変わらなかった。
21年6月では、日本のビッグマック価格は390円、市場為替レート(1ドル=109.94円)で換算すると3.55ドルで、アメリカの5.65ドルの63%だ。
ところが、為替レートが12年6月と変わらないとすれば、21年6月の日本のビッグマックは4.99ドルになったはずだ。これはアメリカのビッグマック5.65ドルの88.3%だ。アメリカより安いとはいえ、問題にするような差とはいえない。
ここから得られる結論も前と同じだ。為替レートが物価上昇率の差を調整していないことが問題なのだ。
円安は労働者に還元されず
生産性高めることにもつながらず
以上のような見方に対して、次のような意見があるだろう。
アベノミクス以前の円高は異常なものであり、企業(とくに製造業の輸出企業)が立ち行かなくなっていた。それを金融緩和で円安にしたから日本が立ち直ったのだと。
しかし、本来であれば、為替レートが円安になっても企業の利益が増えるはずはない。なぜなら、円安によって輸出物価は高くなるが、同時に輸入物価も同率だけ上がるからだ。
企業の利益が増えたのは、輸入物価の値上がりを消費者価格に転嫁する一方で、輸出物価の値上がりを労働者に還元しなかったからだ。
このようなメカニズムが企業利益を増加させたのだ。
本来であれば、円高に対して、技術革新で生産性を向上させて対応すべきだった。低成長をもたらしたのは、技術開発が行なわれなかったからであり、それは円安によって企業が安易に利益を増加できたからだ。
このことは本コラム(2021年10月7日付)「日本は『技術進捗率』マイナスの異常事態に陥っている」、同(2021年9月16日付)「円安の『麻薬』に頼りつづけ日本の購買力は70年代に逆戻り」でも指摘したので、参照してほしい。
だから、円安政策こそが日本を貧しくした根本的な原因だということになる。
「韓国並み」から
地位がさらに低下する懸念
こうして、日本の地位は、円安政策を取り続けたアベノミクスの期間に急激に低下した。
それに対して韓国では、2000年から20年にかけて自国通貨建て1人当たり名目GDPが1386万2167ウォンから3733万3541ウォンへと2.69倍にもなった。13年から20年だけをとっても、25.4%増加した。
これによって、韓国は世界経済における地位を高めたのだ。韓国の1人当たりGDPは 直近では世界で29位(日本は第24位)だ。
こうして「日本がアメリカ並みから韓国並みへ」という変化が起きた。
「韓国並み」が続けばよい。しかし、これまでのトレンドが続けば、韓国と日本の差は拡大していくだろう。
日本は近い将来に台湾並みになり、マレーシア並みになる。そこで止まらず、インドネシア並み、ベトナム並みになるのもそう遠い将来のことではないかもしれない。
(一橋大学名誉教授 野口悠紀雄)