いつかは海外でのんびり暮らしたい。語学力を身につける意味でも海外で働きたい――そう思う日本人は少なくありません。
しかし、何も調べずに準備不足で移住すると、思わぬ地獄を味わうことも残念ながら事実です。
私(宮脇咲)は宮崎県から大学進学を機に上京し、現在はドバイに移住し、海外の物件をメインとした不動産投資をしている他、富裕層向けの海外移住支援も行っております。そういった経緯もあり、これまでに多くの海外移住者の方と知り合ってきました。
この記事は、筆者が過去に見てきた思わぬ失敗を味わった方たちのエピソードを通し、移住に失敗しないためには何が必要か、どんなことに気をつけなければならないかを知っていただければと思います。
<button class="article-image-height-wrapper expandable article-image-height-wrapper-new" data-customhandled="true" data-t="{"n":"OpenModalButton","b":1,"c.i":"AA1BB0SR","c.l":false,"c.t":13,"c.v":"news","c.c":"newsopinion","c.b":"SPA!","c.bi":"BBhWlOq","c.tv":"finance","c.tc":"real-estate","c.hl":"マレーシアに移住した50代男性が見た地獄。4000万円で購入したコンドミニアムのせいで「破産するかも」――人気記事ベスト"}">

</button>
宮脇咲さん(写真左奥)© 日刊SPA!
◆ドバイ移住も、富裕層から一気に転落
海外移住で地獄を見るケースとして金銭面での失敗がまず挙げられます。海外移住者の中には、日本でビジネスで成功を収めた人も少なくありません。しかし、そんな成功者であっても築き上げた財産をなくしてしまうということがあるのです。
仮想通貨で財産を築いた中井さん(仮名)という30代男性の事例を紹介します。
彼は3年前、節税のためにドバイに移住しました。日本では仮想通貨で得た利益の55パーセントを税金として収める必要がありますが、ドバイではすべてを自分の手元に残すことができます。ただ、節税という堅実な手段での移住でしたが、移住後に彼は豪遊生活を始めてしまいました。
中井さんのドバイでの家賃は年間2000万~3000万円。富裕層向けのマンションで生活し、無計画に高級車やパテックフィリップなどの高級腕時計を購入し、イスラム教の国なのでアルコールが高いにもかかわらず、彼は気にせずに毎日のように飲酒もしていました。
◆結局日本に帰国も、いまどこで何をしているのか…
<button class="article-image-height-wrapper expandable article-image-height-wrapper-new" data-customhandled="true" data-t="{"n":"OpenModalButton","b":1,"c.i":"AA1BB0SR","c.l":false,"c.t":13,"c.v":"news","c.c":"newsopinion","c.b":"SPA!","c.bi":"BBhWlOq","c.tv":"finance","c.tc":"real-estate","c.hl":"マレーシアに移住した50代男性が見た地獄。4000万円で購入したコンドミニアムのせいで「破産するかも」――人気記事ベスト"}">

</button>
ドバイの街並み© 日刊SPA!
なお、ドバイに現在住んでいる筆者にはたくさんの富裕層の知人がいますが、中井さんのようなお金の使い方は一般的ではありません。むしろ富裕層であればあるほどビジネスでしっかりとした固定収入を得た上で堅実な暮らしをしています。
しかし、中井さんは違いました。
彼は固定収入も乏しく、お金の使い方も無計画でした。ドバイにいる本当の富豪とは違ったのです。当然ですが、毎月のキャッシュフローがマイナスになり続ければ破綻します。さらに彼はリスクの高い仮想通貨に手を出し、貯金は底をつきます。
結局、日本に戻った中井さんですが、ドバイ在住時にInstagramに毎日派手な生活を投稿していたこともあり顰蹙を買い、日本での人脈も失ったようです。いまどこで何をしているのかは筆者も知りません。
◆日本との感覚の違いが足かせに…ビジネスで失敗するケースも
中井さんの失敗は厳しい言い方をするならば「身から出た錆」とも言えるかもしれません。しかし、堅実に生活をしていれば海外移住に成功できるかというと必ずしもそうではないという現実もあります。
筆者の知人に東南アジアのある都市で飲食店を開業した和田さん(仮名)という40代男性がいます。現在、東南アジアでは寿司をはじめとした日本食が注目されていることもあり、和田さんのように国外での成功を夢見る飲食店経営者は多いです。
そんな大きな希望を持って海外移住した和田さんでしたが、彼は撤退を余儀なくされました。
「理由は現地の法規制や商慣習に適応できなかったことです。例えば、従業員に働いてもらうマネジメントひとつをとっても日本人と現地スタッフでは感覚が大きく違います。マニュアルを用意しても守らない、遅刻も当然。日本では当たり前にできることも現地では違いました」(和田さん)
こうした文化や慣習の違いに適応できずにBさんのビジネスは失敗に終わります。
「開業資金の1500万円はついに回収できませんでした。現在は日本に戻りましたが、40代ということもあり再就職先も限られており、帰国後も厳しい現実が続いています」(和田さん)
◆ローン返済は月40万円、家賃収入は15万円の大赤字
<button class="article-image-height-wrapper expandable article-image-height-wrapper-new" data-customhandled="true" data-t="{"n":"OpenModalButton","b":1,"c.i":"AA1BB0SR","c.l":false,"c.t":13,"c.v":"news","c.c":"newsopinion","c.b":"SPA!","c.bi":"BBhWlOq","c.tv":"finance","c.tc":"real-estate","c.hl":"マレーシアに移住した50代男性が見た地獄。4000万円で購入したコンドミニアムのせいで「破産するかも」――人気記事ベスト"}">

</button>
マレーシアのマンションはプールとジムつきが一般的だという© 日刊SPA!
筆者の周囲にいる海外移住した日本人は不動産や株式投資によって固定収入を得ているという人が多いです。
しかし、その投資によって借金を抱えてしまう事例もあります。
シンガポールからほど近いマレーシア・ジョホールバルに移住した50代男性の美濃田さん(仮名)はまさに投資によって失敗してしまったケースです。
「ジョホールバルでは2006年からスタートしたイスカンダル計画という大規模な開発計画があります。ジョホールバルはシンガポールにクルマで通勤できることもあり、国が資金を投じて開発させる目的でスタートした計画です。当時の私はここに目をつけました。土地やマンションの価格が上がるのではないか、と」(美濃田さん)
美濃田さん含め、当時このイスカンダル計画には多くの日本人投資家が目をつけました。
「2013年に約4000万円を投資してコンドミニアム(家具家電付きのマンション)を投資目的で購入しました。ここから計画通りにジョホールバルが発展すればよかったのですが、話はそう上手くは進みませんでした」(美濃田さん)
購入から10年以上が経ちましたが、美濃田さんはいまだに期待していたような収益を得られずにいます。
「現在もローンを返済している状況ですが、家賃として得られるのはわずか15万円程度。日本の貯金を切り崩して何とか返済をしている状況です。さらに、ジョホールバルの物件価値が上がらないため、売却しようにも買い手も見つからない状態が続いています」(美濃田さん)
たしかに、ジョホールバルはシンガポールまでのアクセスはよいものの、開発の計画が遅れたり、最悪の場合中止したケースもあります。
美濃田さんが「このまま好転することがなければいずれは破産するかもしれません」と吐露していたことが印象に残っています。
◆「金銭面に問題がないパターン」にも落とし穴が
ここまで紹介した3人の事例はどれも金銭面に関連する移住の失敗でした。では、金銭面にさえ気をつければ移住は成功するのかというとそうではありません。海外はやはり日本とは文化、習慣、天候などさまざまなことが違います。この違いによって移住を後悔することもあるのです。
マレーシアに移住した65歳の鈴木さん(仮名)という女性はその一人です。鈴木さんは楽園のような生活を夢見て夫婦での移住を決断しました。しかし、住み始めてから早々に大きなストレスを感じるようになります。
「日本人に比べて約束の時間を守らない、割り込みなど公共の場でのマナーが悪い、などちょっとしたことで苛立ちを覚えました。それに想像以上に英語力が必要でした」(鈴木さん)
さらには鈴木さんの夫が病気になってしまったことも追い打ちとなります。
「日本は国民健康保険もあり、医療費はやすいですし、病院で安心して通えます。しかし、現地の医療水準が低かったこともあり、夫と日本に一時帰国をして治療を受けることにしました」(鈴木さん)
◆移住費用がパー。貯金を切り崩して生活することに
こういった生活への負荷から、3年間のジョホールバルでの生活を経て鈴木さん夫婦は日本への帰国を決意しました。
「移住費用に加え、帰国してからの新居探しなど金銭的にも想定外の損失となりました。いまは、経済的な不安を抱えつつ貯金を切り崩して生活しています」
老後はあたたかい東南アジアで海外でのんびり生活を……と思っている高齢者の方には鈴木さん夫妻のような失敗談は耳の痛い話ではないでしょうか。
では、海外移住を後悔しないためには何が必要でしょうか。彼らのエピソードを通じてわかるのは、いきなり移住するのではなく、現地での短期滞在を経験すべきということです。特に現地での文化や慣習は旅行だけではわからないことがあります。最低でも季節を変えて3度、一ヶ月は滞在すべきです。
また、英語力が必要な国の場合、言語学習に取り組み、できれば現地の日本人コミュニティとも連携を取れるように知人や友人を作っておくことを筆者はおすすめしています。たしかに、海外は日本よりも労働賃金が高かったり、気候的に魅力的かもしれません。しかし、彼らの失敗事例からわかるように、できるだけ事前準備を行うことが必要と言えるでしょう。
<TEXT/宮脇咲(みやわき・さき)>
【宮脇咲(みやわき・さき)】
海外不動産投資家・海外移住コンサルタント。1997年宮崎県生まれ。UAEドバイ在住。お茶の水女子大学在学時に、暗号資産投資で大きな利益を出し、分散投資の一つとして不動産投資をスタートする。大学3年生の21歳から国内不動産投資を始め、国内3棟18室を保有し利回り20%以上の物件を運営し、その後いくつかの物件を売却。22歳で海外不動産投資へ進出し、ジョージア、トルコ(イスタンブール)、アラブ首長国連邦(ドバイ)に不動産を所有。現在は、個人投資家として資産運用をしながら、富裕層、経営者、投資家への資産コンサルティングのほか、海外移住のアドバイザーとしても活動。チャンネル登録者数約6万人のYoutubeチャンネル「さきの海外不動産しか勝たん」を運営。
 </button>
</button>










 </button>
</button>
 </button>
</button>
 </button>
</button>
 </button>
</button>
 </button>
</button>
 </button>
</button>
 </button>
</button>
 </button>
</button>
 </button>
</button>
 </button>
</button>
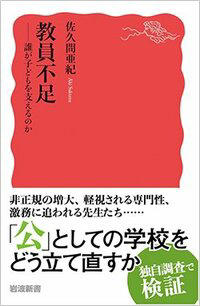 </button>
</button>
 </button>
</button>
 </picture>
</picture> </picture>
</picture> </picture>
</picture> </picture>
</picture> </picture>
</picture>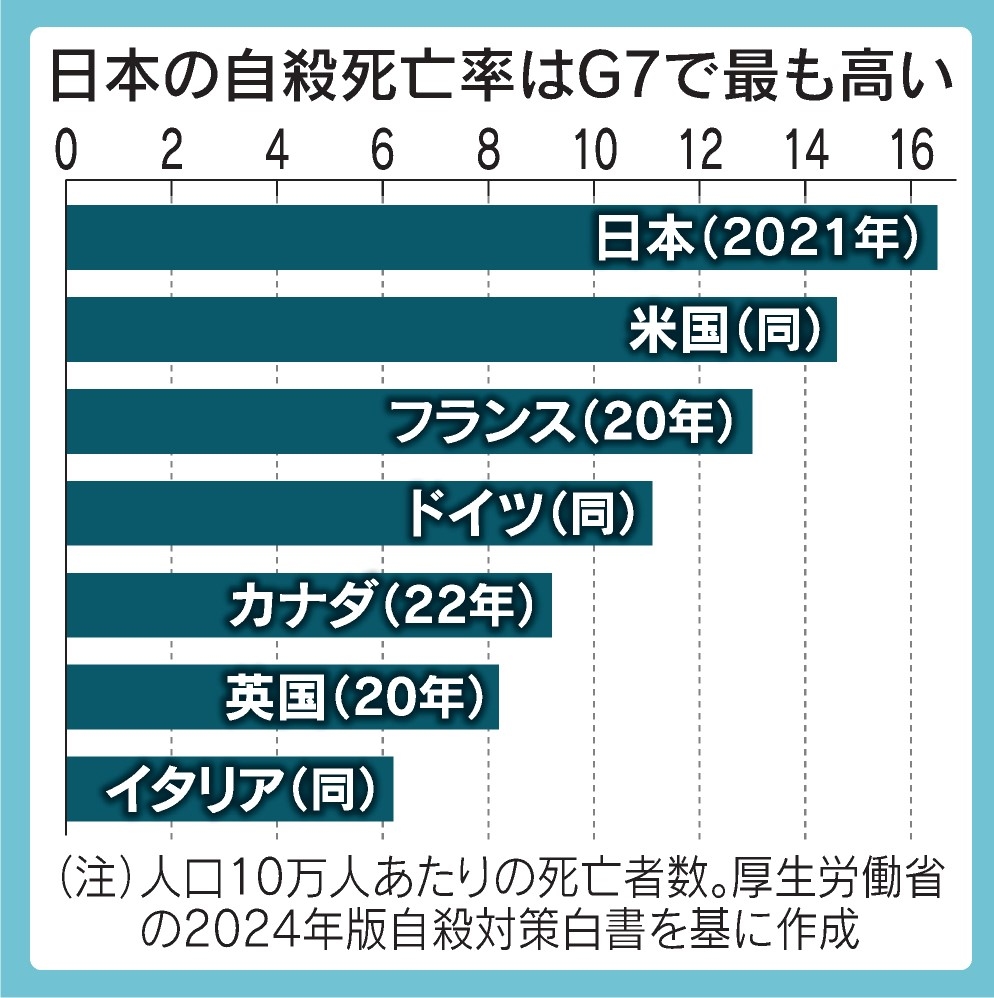 </picture>
</picture> </button>
</button>