Ⅶ
魔界と呼ばれるファールスは、エグラートの遥か彼方、約120万キロ先にある、月ほどの大きさを持つ天体である。
以前、ファールスはもっとエグラートに近い位置(約38万キロ)に存在していたと大陸史前に記されたレリーフにはそう記されてあったが、何故、およそ三倍も距離が離れてしまったのかについては、続きに書かれたより複雑な古代文字の記号のせいで、エグラートの地に住まう人類は、いまだにそれを知り得てはいなかった。
エグラートの大地でよく耳にする『ギーガ』という魔物のことであるが、有史以来、人々を苦しめてきたその厄災は、実はこの月型の天体ファールスにも被害をもたらし続けている。
しかも、どちらかと言えばエグラートより、このファールスはより大規模なギーガによる侵攻を受け続けており、魔王ディナスおよび、その四天王たちの働きで、そのギーガどもの攻撃を耐え抜いていた。
つまり、このファールスこそが、古代の人々の造りし、対ギーガ用の防衛要塞そのものなのである。
かつてエグラートの月だったと思われるこの天体は、鋼鉄の衣でその身を纏い、クレーターのように見える大きな陥没も、それは数多のギーガ戦が残した戦いの爪跡である。
エグラートの人々はその事実を知らされる事も無く、ファールスを魔界などと蔑み、比較的、平穏な日々を現在に至るまで送り続けている。
「いや~、なんか久しぶり帰って来たという感じがするよ」
そう、第一声を発したのは、銀髪の四天王・マイオストである。
彼はなにやら転送装置のような青銅色のサークルから、よっこいしょと出てくると、続いて現れた、唐草模様の大きな包みを担ぎ上げ、近くにいた一人の青い髪の長身の男の前に、ドシンとそれを差し出した。
「ご苦労なことだな、毎度毎度」
青い髪の男はそう言うと、先にためぞうやリリスが帰って来ていることをマイオストに告げた。
古代装置の塊の様な姿のこの空間は、青白い光に満たされ、天井も高く、それなりの広さがあった。
構造上のものなのか、少しだけ音が響きやすいこの室内には、青い髪を持つ長身の男とマイオスト以外の姿はない。
「まあ、とりあえずただいま、ホーネル」
そう呼ばれたこの男こそ、魔王軍四天王屈指の武闘派で知られる猛将ホーネルである。
ホーネルはスラッとした長身に、長く青い艶のある髪と、甘いマスクを持ち主で、澄んだエメラルドグリーンの瞳の美しい美青年である。
一見、彼がそのような猛将であるとは思えないほどに優美な男で、気品も感じられる。
表舞台に出てくることの少ない彼だが、それは彼の背負う任務の重さにあった。
ホーネルは、その戦士レベルが96にも達する、マスタークラスの戦士である。
神界ファールスの三神に最も近い存在の人間とされ、現在は、対ギーガ戦闘部隊の総指揮を握る司令官である。
彼の功績があればこそ、エグラートのギーガ被害は最小のもので済んでいる。
先ほど、ホーネルを人間と言ったが、実はこの魔界と呼ばれるファールスに暮らす人々のほとんどは、元はエグラートから移住した人間であり、このファールスにおいてその例外となる人物は、後に登場する事になる、戦士レベル最高値の100に達した無敵の魔王ディナスと、四天王最強の戦士レベル97、マベルの二人だけである。
つまり、マイオストもリリスもためぞうも、戦士としての才能を持つ、ただの人間である。
ホーネルはマイオストに、不可解な顔をしてこう尋ねた。
それは、ドシンと目の前に置かれた包みの中身の方ではなく、先に帰って来た、二人の事であった。
「ちょっと聞いておきたいんだが、あの二人の表情の落差は一体、何なのだ? エルランゼ(ためぞう)は異常なテンションで、うひょうひょとウルサイ上、珍しく私に土産など持ってくる始末。しかし、一方、リリスさんは血の気の引いた顔で、絶望感に打ちひしがれている様子にも見えた。・・・リリスさんが、心配だ」
その問いに、マイオストは口元をニヤリとさせ、ホーネルに掻い摘んで、事のいきさつを伝えてやった。
マイオストとしても、どちらかといえば愛想笑いより苦笑いの方が多い。
「ば、バカなっ!! ためぞうがまるで天使のように愛らしい美少女にモテたうえ、デートだと!? ありえん、・・・オレ達、三人の野郎四天王の中で、最後まで独身を通す予定のためぞうが、ためぞうの分際で、そんなに可愛いおにゃの子と、一流スウィーツショップでデートだなんて。・・・さ、最悪だ、土産のカツ丼を、チョーうめぇとか思いながら食ったオレが、途端に虚しくなってきたぞ!!! ああ、可愛そうなリリスさん。あんなに美人でしっかり屋さんなのに、バカに使役させられ、微妙に先を越されてしまうとは・・・。貴女の悔しさ、このホーネルも気持ちは同じですぞッ。なあ、マイオスト!」
「私に振られてもねぇ・・・、キャラ、壊れてるよ、ホーネル」
マイオストは、ホーネルを慰めるようにポンポンっと肩を叩くと、目の前に置かれた唐草模様の大きな包みを開けた。
「おお・・・さすが、マイオスト! 仕事の出来るヤツだ」
ホーネルは包みの中の物をパッと見て、少しだけ機嫌をよくしたのか、鋭い眼光で中身を物色し始める。
マイオストは言う。
「探し回るのに、結構骨が折れたけど、私としては合格点だと思っているが。どう?」
「ああ、120点だ!! 一体、どうやってこれだけの物を集められるのか、本気で関心している所だ」
そう言ってホーネルは、色んなディスクの入ったケースやアイドル風の女の子の写った下敷きなどを手に取り、ニンマリと笑顔を浮かべている。
他にも精巧に作られた一品物の魔女っ子フィギュアや、手作り風のコピー雑誌の山などが包み一杯に詰められており、ホーネルは子供のように瞳を輝かせていた。
おまけ付き駄菓子のカードも完璧にコンプリートされており、痒いところにも手が届く、マイオストのお土産だった。
ホーネルはそれらをさっそく端末に入力しながらリスト化し、荷物の整理し始める。
「いやー、ホーネル。カードのコンプとかは、特に大変だったよ。限定5枚のレインボーカードとか出すのに、どれだけ、スナック菓子を主食にして活動したから」
「だろうな。これ一枚でもオークションに出たら、100万近く行くんじゃないのか? 立体映像処理までされて、クロノス様(魔女っ子アニメの敵役の女幹部)の黒のオーバーニーソの絶対領域が、横に、斜めにと実に魅惑的に再現されている。退色防止加工もされていて、いやー、ロッチ(お菓子メーカー)は相変わらずいい仕事するなぁ」
「まあ、人の趣味にどうこう言う気はないけど、登場していきなりキャラが崩壊寸前だから、その辺にしといた方がいいよ、ホーネル。かっこいいんだから・・・さ」
マイオストはそう言うが、ホーネルは夢中になってカードの裏の解説とかを読みあさっている。
マイオストの方も、過酷な任務のストレス発散だと、ホーネルを温かく見つめて、心の中で「よかったね」と呟いた。
この青白い空間は、四天王を除いては、他に魔王ディナスとリリスくらいしか入室出来ない特別な場所であり、彼のその手の趣味も他に見られることもないだろうと思い、マイオストはこの場を立ち去り、魔王ディナスの居室へと向かうことにした。
「ありがとう、マイオスト!!」
「また、その内、集めといてあげるよ」
マイオストは、古代文字で転送の間と記された部屋を後にすると、移動式の床に乗って、魔王の部屋を目指した。
特別、礼服などに着替えるわけでもなく、普段着の木綿の長袖に麻布のズボン。対油加工のされた、少し蒸れそうな茶色の長靴に、腰には、武器屋で一番高かった剣『フレイムタン』を差し、宇宙船の船内でも思わせるようなこの通路とは、明らかに場違いな格好をしたマイオストである。
クルー(宇宙船ぽいのでそう呼ぶ)たちは、きちんと正装していて、宇宙空間に出てもヘルメット一つで何とかなるような装備をしている。
腰には光線銃のようなものと、ビームサーベルっぽいものがコンパクトに収まっていて、どうもここが宇宙映画の撮影現場で、マイオストはその裏方さんのようにも見えた。
しかし、通り過ぎるクルーたちは、田舎のにーちゃんみたいな格好のマイオストにこぞって敬礼し、マイオストの事を尊敬でもするかのように、口を揃えて「閣下」と呼ぶ。
マイオストは、任務ご苦労さんといった感じで気さくに手を振り、笑顔をみせるが、その人影も奥に進むほどまばらになり、魔王の居室らしき部屋の扉の前では、さっぱり誰の姿も見ることが出来なかった。
「まあ、四天王の中でも諜報活動メインの私が、いかにも四天王ですって格好もアレでしょ」
と、独り言を呟いたマイオストは、扉の右側にあるパネルらしきものを、ちょちょいと操作して扉を開けた。
中に入ると、いかにも魔王ですといわんばかりのごっつい甲冑が正面に飾ってはあるが、マイオスト以外の人影はない。
室内もそれほど広いというほどもなく、青白い内装の室内には白いランプが数箇所灯っており、壁を覆うのは、先ほどの転送の間で見た金属質の石のようなものであった。
よく見ると、魔王の甲冑の前には、人一人が入るのに十分な大きさのケースがあり、そのケースは美しい金の刺繍の施された白い絹のシーツで覆われていた。
中は確認する事は出来ないが、シーツの隙間からガラスのようなケースの蓋部分が覗き、確かにその中には誰かが眠っているようだ。
マイオストは壁に置いてある、折りたたみのパイプ椅子をケースの前で開くと、よっこいしょっと椅子に腰を下ろした。この椅子はマイオストが部屋に持ち込んだもので、元々この部屋の備品ではない。
マイオストは、ケースの前に鎮座する魔王の甲冑に向かって、頭を掻きながらこう話しかける。
「あー、起きてますか? あなたの愛人(ラマン)、マイオストでーす」
すると、甲冑の目が光り、その口元のマイクから音声が出た。
どうも、このケースの中の人物の意思を伝えるインターフェイス的、置物のようだ。
「まったく、誰がラマンですか、もう」
音声はマシンボイスだが、口調はどうも女性っぽい。
アホっぽいやりとりに見えるかも知れないが、このケースの中の人物こそ、神界フォーリナの主神セバリオスとも拮抗する力を持つ、正真正銘の魔王ディナスその人である。
「いい加減、ケースから出たらどうですか、魔王様」
「私だって、出れたら苦労はしませんよ。知ってて言っているのでしょうけど。あと、魔王様って呼び方もやめてくれません? いかにも悪役っぽいですし、だいたい、幼馴染みのあなたからそう呼ばれると、ワザと言っているとしか思えませんし、少々、不愉快です。普通に名前で呼んで下さいよ」
「了解っす、ディナス陛下」
「・・・もう、好きにして」
魔王ディナスがこのケースの中で、スリープ状態になっているのはそれなりの理由があった。
意識はあるのだが、身体は眠っている。正しくは、ある装置を動かすための動力源となる為にその力を使っていると言ったほうがいい。
「まあ、平たく言えば、乾電池ですな」
「誰が乾電池ですかっ!!」
ディナスをからかうマイオストであったが、意味合いからすれば似たようなものだった。ただ、その出力は、マンガンやアルカリ、いやオキシライドすら上回る大出力で、しかも人力なのでエコである。
「乾電池から離れなさいよ!!」
「まあまあ、魔王様。そんなこと、どうだっていいじゃないですか。ほら、頼まれてた、お笑いライブ4095のディスクもちゃんと買ってきたし、スカペーのお笑い専門チャンネルの代金もちゃんと振り込んでおきましたから」
ディナスが少し落ち着いた様子が、甲冑の目の光り方でなんとなくわかった。
そして、甲冑の右腕が動き出し、人差し指がある場所を示す。
「ディスクは後で、あっちのDドライブに入れといて」
「うい」
「それで、マイオスト。エグラートはどんな感じなの?」
ディナスがそう問うと、マイオストは少しの間だけ難しい顔をして、懐から取り出した手帳を手に、こう語り始めた。
「そうですなあ、今のところはまずまず平穏といったところでしょうが、スレク公国の一件以来、フォルミの動きが気になる所ですかねぇ。フォルミ軍の侵攻も、私らから言わせれば、むしろ正当な行為ですし、問題はそれを今の大公レオクスが、知っていたかどうかと言う事でして。私の勘では知っていたと思いますが」
マイオストの言葉に、ディナスは暫しの沈黙をおいてこう言った。
「私利私欲の為に、偉大なる『覇王姫・エストレミル』皇女殿下の眠りを妨げたスレクの痴れ者の行為は、万死に値すると言っていいでしょう。フォルミ大公が手を下さずとも、私が直接、マベルかホーネル辺りを差し向け、断罪した事でしょうし。おろおろ、・・・お可愛そうに、中途半端の覚醒のせいで、記憶も曖昧で、性格も捻くれて、ティヴァーテに身を寄せて、自らの正体も知らずに玉の輿など狙っているとは、笑える話ですが、ンンッ、・・・もとい、気の毒でなりません」
「それはもう、バカ盆のパパ君よりも酷い有り様で、比類なき麗しのレジェンドなプリンセスが、ずるくて小汚い田舎小娘へと堕ちて行くといった、いわばシンデレラストーリーを逆に進んだと申しましょうか。ド転落ぶりに涙が止まらず、腹がよじれそうです」
魔王の甲冑とマイオストは互いを見つめ合い、少し間を置いて、阿吽の呼吸でコクリと頷くと、マイオストは、ニヤつく口元を無理やり直して、話の先を続けた。
「まー、正直言って、今のエグラートの戦力は、先の大戦(大戦の子細については後に触れる事となる)前、覇王サードラル陛下が、エグラートの地に在られた頃に比べれば10分の1以下といった所でしょうな。覇王サードラル軍の、たかが後詰めの一部隊に過ぎなかった我ら現魔王軍でさえ、今のエグラートにとっては脅威足りうるのですから」
マイオストの言った『サードラル』という言葉に、言葉が詰まるディナス。
マイオストは、即座に自分の失言に気付いた。ディナスの前で、その言葉は禁句だったのだ。
沈黙が言葉の重さを物語る。
「セリカ・・・」
マイオストは銀色の瞳で切なげに、ケースの中の人物を想うようにそう呟いた。
刹那、ゴホンと咳払いをして、その「セリカ」という言葉をごまかすように、マイオストは少し慌てた様子で捲くし立てた。
「まあ、アホのためぞうを面白いからという理由だけで四天王に取り立ててしまう魔王様ですから、それだけ我が軍にも余裕があるというものですよ。切羽詰っていたら、バルマード剣王辺りの人物を即座に登用しなきゃいけないでしょうし、ホーネルがいれば、ギーガ級共の敵など、脅威とは呼べません。後詰めには、四天王最強のマベルもいますし」
身振り手振りで、あれこれ安心感をアピールするマイオストだった。
が、ディナスはマイオストに、絹地のシーツを少しめくるように指示する。
「ごめんな、うっかりしてた・・・」
マイオストは神妙な面持ちとなって、まるで割れ物でも扱うかのように、シーツの端を持ってゆっくりと丁寧と、徐にそれをめくった。
すると、ケースの中にはなんと、『天使』としか形容出来ない程に神々しくも美しい、一人の少女が横たわっていた。
プラチナの髪に、白磁のような肌。
絹の羽衣を纏うその背中には、まさに天使と呼ぶに相応しい一対の光の翼が、ケースの中を飾り立てるかのように、絢爛な姿で収まっている。
見慣れたはずのマイオストでさえ、言葉を失うほどに美しいその少女の容姿。
・・・そう、彼女は『人間』ではない。
伝説の覇王、サードラルの言葉にこうある。
「それは、この世界に残された唯一の希望。
紛れも無い、世界にたった一つだけの存在。」
そう残した彼、サードラルは、敬意を込めて彼女の事をこう呼んだ。
我が愛すべきエグラートの大地を守護する天空の翼、
『戦天使・セリカ=エルシィ』と。
魔王ディナスの声が、マシンボイスから、直接心に響く思念波へと変わる。
特殊な加工がなされた絹地のシーツは、彼女の光が漏れ出すのを防ぐ役割を果たしていた様子で、何らかの機械へと接続された彼女の二枚の翼から送られる、波紋のような高貴な光も、今、この瞬間、微かにだが弱くなっているように見えた。
胸に届く彼女の声は、どこまでも柔らかく、そして温かい。
「フフフッ、たまには自分の為に少しくらい力を使ってもいいでしょ、マイオスト。だからあなたも、昔みたく、私のことをセリカと呼びなさい。愛しのサードラル様を思い出させるものだから、少し、変な気分になっちゃったじゃないの」
マイオストはそんな、魔王ディナスのとしての仮面を脱いだセリカに、不覚にも少し和ませられていた。
マイオストは恥ずかしさを隠すように、セリカに向かって、口の減らない様子でこう返す。
「まったく、セリカにはかなわないな。しかし、いい加減、諦めないと前に進めないよ。だいたい、覇王陛下の嫁さんはアナタのお姉様で、その姉の旦那を好きとかいってたら、ドロドロの昼メロになっちゃうじゃないか。いい加減、乙女っぽいとこ卒業して、私の嫁くらいで手を打っとけよな、セリカ。でないと、シャイなホーネルは別として、ためぞうのバカに寝込みを襲われるぞ」
ケース内のセリカは、瞳を閉じて無表情だが、そのセリカの楽しげな感情は、思念波によってマイオストの心の奥に届いた。
「ためぞうさんは、しょっちゅう、私のスリープ解除キーを捜しに来ますね。ケースをどんなにやっても壊せないものだから」
「ためぞうらしいなぁ。・・・まあ、無害だから放置しておいてもいいんだが。だがなぁ、セリカよ。私もセリカも、独り身続けて五千年以上経つでしょ? そろそろ婚活考えてもいいんじゃない?」
「私はマイオストと違って、急いでないですし、どうせ結婚するならオーユ姉さまみたいに玉の輿に乗りたいですし。トレイメアス様クラスでしたら、喜んでこの身を捧げますけど、ネ」
「理想たけーーよ、オイッ! ・・・行き遅れ確定のサインを自分で書いてどーするんだよ、セリカ!(その名を出されちゃ、誰もおめーと結ばれねぇ)」
そのトレイメアス氏について少し語ると、彼は覇王サードラルの実弟で、『孤高の剣皇』としても知られる人物である。
先の大戦の後、サードラルの後を次いで、次期覇王となる事を期待された人物であった。が、現在、その行方は知れず。
しかし、その実力は、歴代戦士中最強であるとも言われ、大戦時、異界の神々である『六極神』(ギーガを統べる者として知られる古の神々)とも互角に渡り合い、その驚異的戦士能力で『剣神・グランハルト=トレイメアス』とも称えられた。
平たく言うと戦士レベル500相当の異界の神々たちと、本気でガチった漢で、レジェンドな英雄なのです。
その彼の前にして引けを取らない男を連れて来いというセリカの要求に、マイオストは、素でビンタの一発でも入れてやりたくもなったが、さすがに超超硬度を誇るトレニチウム製クリスタルガラスの上からは手が出らず、仕方なく、口を出すことにした。
「セリカ、現実を見ろ。出会いもない、理想は高い、おまけに悪の大魔王。そんなお前が、いっぱしにときめいても、どーにもならんだろ。地に足を付けろ、お前の背中の羽は、空を舞う為のモノじゃない、エコな電池だ。どうせ、このまま電池生活やってても、これから先にも出会いは無い。諦めて、身近な恋に生きれ」
「うん、ならホーネルにする」
「結局、顔かよッ!!」
ムキになるマイオストに、クスクスと笑うセリカ。
セリカは、ふと想う。
こんなに、素の自分で何かを話したのは、一体、いつ以来だろうと。
普段から明るく振舞う彼女だが、ファールスの魔王としての仮面を付けたときから、その目映いばかりの光の翼は、古代機械の鎖に繋がれ、エグラートの平和との対価に、彼女は自身の自由を失った。
セリカは想う。
そんな状態になっても、マイオストのように自らを励まし、寄り添ってくれる者たちがいるから、頑張っていられるのだと。
支えられているのを感じる事が出来るからこそ、今の自分が笑顔でいられるのだと。
だからこそ、五千年もの長きに渡り、呪いのように自らを縛り付けるこの運命にさえ、彼女は真正面から向かい合うことが出来た。
セリカがいくらその身が天使であるとはいえ、心は一人の少女である。
自分が愛したものがあるからこそ、
自分の愛するものが生きているからこそ、彼女はその、小さな心を強く持てた。
彼女が真に、自由をその身に取り戻す時、それは世界の破滅を意味しているのかも知れない。
かつて、『ルナ』という名で存在していた、惑星エグラートの月。
そのルナという衛星を科学という鋼鉄で覆い、エグラートから三倍もの距離へと移動させた古代文明。
ルナに新しい名前が付けられたのは、ルナが要塞化して現在の軌道に乗せられてからである。
その名は、ファールス。
古代、神聖ミストレウス帝国の言葉で『封印』を意味するこの星は、常に軌道修正を行いながら、エグラートの軌道を約一週間かけて周回している。
そのファールスが封印するモノこそ、異界への門であり、そのファールスの封印機能の中核を担っているのが、セリカのみが持つ特殊な力、戦天使能力・『守りの翼』である。
絶対的防御力を誇る戦天使セリカのその力によって、異界への門は封じられ、五千年もの時が流れた。
セリカは願う。
「たとえ、何千、何万年の月日が流れようとも構わない。この翼で世界を守ることが出来るのなら、私はあの生まれ育った蒼い星の存在を、いつまでもこの身に感じていたいから」、と。
- セリカの光の翼を繋ぐ鎖が砕け散り、ファールスが彼女を自由にしたその時、
異界の門から来る、漆黒の闇、『ダークフォース』は開放され、
人々は、再び、光と闇の大戦へと巻き込まれるだろう。 -














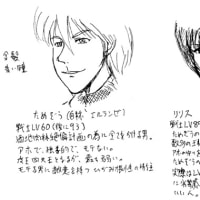

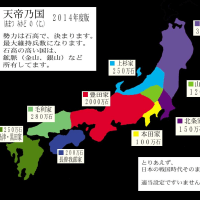









※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます