Ⅵ
フォルミ市街へとためぞうを連れ出したリシアが向かった先は、『モンブランシェ・フォルミ本店』と書かれた看板の、かなりの規模のスウィーツ&カフェの店だった。
顔なじみなのか、リシアが来店すると同時に店の支配人と思しきジェントルメンが現れ、明らかにVIPルームであろう豪華な個室へと案内される。リシアは着席すると同時に、支配人風の男にいつものをと頼み、ためぞうに好みのものを聞いてきた。
「エルランゼ様は何になさいます? オススメはパティシエ特製の虹色ケーキとか、レトレアンティーなどがありますが、他にもドーラベルンコーヒーや、あと100種類ほどスイーツがございますが、甘いものが苦手な方用に、カツ丼とかカレーなんかもありますよ」
「・・・では、カツ丼と水で」
リシアはコクリと頷くと、支配人風の男に「国産ブランド黒豚使用のカツ丼と、ガルトラント山脈の雪解け水の湧き水(150年物)」をと注文を伝えた。
オーダーを取った彼が部屋を退室すると、リシアとためぞうは個室に二人っきりとなる。
豪華過ぎる室内に、その雰囲気に慣れた感じの金髪の美少女と向き合って座ることになった、ためぞう。
ためぞうにこの手の経験値などない。微笑むリシアに、何から話していいやらサッパリわからず、その空気の重さにためぞうは酸欠になりそうだった。
一秒がこうも長く感じられる瞬間など、そうあるものではない。
ためぞうは必死に何か言わなければと、出来の悪いオツムを加熱させて言葉を捜す。
(いいか、落ち着けオレ。こんなチャンスをピンチにして、どーするんだ。マイオストのオッサンじゃこんな場合の対処法など知らんだろうし、リリスに至っては論外だ。誰に、オレの超高性能な思念波を送って、答えを貰えばいいんだ。100ドルやるから誰か、気の聞いたセリフの一つでも教えてくれぃ・・・。うっ! コテッ)
ためぞうは、・・・倒れた。
しかし、今日のためぞうは一日で一生分の運を使い果たしているのか、ウルトラ大吉なのか、なんと金髪の美少女の方から話を振ってきたのだ。
「私、男の方とこのお店に来たのって、実は初めてなんです。普段は館とメイドさんたちと来たりするんで、エルランゼ様とお話しが合わなかったらごめんなさいね」
と、軽く両手を合わせてウインクするリシア。可愛さ120%のリシアの姿に、ためぞうはもうどうとでもなれ! っと割り切って玉砕覚悟で喋りだした。
「ハッハッハッ、オレなんか若白髪の中年や、行き遅れの三十路女なんかと、おでん屋や焼き鳥屋に呑みに行くくらいなんで、オレこそ若い子に話を合わせられるか自信はないっす」
「うふふっ・・・気持ちは同じだったんですね」
とリシアに笑顔で振られたためぞうは、一気に緊張から開放され、その反動の大きさからか、リシアとの会話が楽しくて仕方なくなってきた。
ためぞうは饒舌になって、世界がどうだの、金融危機がどうだの、競馬やパチスロがどうこうと、明らかに的外れな言葉をリシアに浴びせかけたが、リシアはしっかり話題についてくる頭のいい子だった。ちゃんとした意見を返してくるし、冗談も時折混ぜてくるし、そうこうしている間に、テーブルはオーダーしたスウィーツや飲み物、高級カツ丼などで華やかに彩られた。
「なるほど、それが虹色ケーキなわけね」
七種類の異なる味わいと繊細な色使いが見事なケーキを、アメ細工が美しくアーチを架けるという手の込んだ作りで、見るだけで美味そうなのがためぞうにも容易に理解できた。
レトレアンティーの上質な香りに満たされた室内に、ためぞうはカツ丼の蓋を開ける。
「う、うめーーーーーーっ」
それはためぞうが、生まれて初めて口にした至高の一品だった。
それまで、うまか棒くらいしか美味いものを知らなかったためぞうには、まさに目からウロコである。ガツガツとカツ丼をほお張るためぞうを、ほお杖ついて楽しそうに見つめるリシア。
「気に入ってもらえてよかったです」
「うん、美味い! なんかお冷もすんごい滑らかな口当たりで美味しいんだけど。やっぱ、フォルミ(都会)は違うねぇ・・・」
「私も、こんなに楽しいティータイムは、ほんと久しぶりです」
無邪気に笑いながら、上品にスウィーツを口にするリシア姫と、カツ丼のおかわりを頼むためぞう。支払い額を心配しなくていいのかと突っ込んでやりたくもなるが、運のいいことにリシアの飲食代は同席者を含め、全てが大公の払いとなっていたりする。
それが面白くないのは、二つ穴の開けられた障子の向こうにいる、銀髪中年と三十路女だった。店の調度品に穴を開けるマナー知らずの二人。
歯軋り音を立てながら、リリスはマイオストに言った。
「なんで、なんであのバカが、よりにもよってあんなにもいい思いをしているわけ!? つか、あの子、何? 天使? どれだけ人がいいのよ! まったく、ためぞうなんかにあんなにサービスしちゃって、もう」
「わかるよ、リリス君。私も今まで、無意識の内に、自分より不幸なヤツがいるから、これまで自分は頑張ってこれたんだなって思っていたところだから」
「そう! 私を不幸にしている元凶が、あんなにもハッピーでだらしない顔をして、天使の微笑を受けているなんて、ヤツの転落を願って仕方ないくらいイラついてるわよ!!」
二人はためぞうを尾行するために、見栄を張ってリシアたちの隣の部屋を取り、ついでに頼み方もわからないオーダーを、リシアの口真似の如く同じもの注文した為、後にとんでもない請求書を受け取ることになる。
ついでに障子の穴も見つかって、最高級東方和紙の張替え代まで加算されるいう地獄を見る。それは、マイオストとリリスの給料三か月分という、何とも耐え難い出費であった。
一方、紙一枚向こうの世界では、和やかな談笑が続いていた。
「私、エルランゼ様をお誘いして、ほんとに良かったと思っています。小さな事で悩んでいた私が、本当に人として小さかったんだなって、そう思えるんです。女の子同士の会話だと言えないことも、なにかこう気楽に話せてしまうというか。今日のケーキはいつもより、美味しく感じるんです」
「ああ、うまいねーーっ! オレなんかもうカツ丼四杯目にいっちゃいそうだよ。いやー、うまか棒しか美味いものを、行き遅れのヤツが教えてくれなかったもんで、カツ丼がこんなにも美味いなんて。オレ、取調べを受けないとカツ丼喰えないって思い込んじゃってたから、大分、人生損してるよなあ」
そういいながらも豪快に食べまくるためぞうの姿に、リシアは本当に心が救われていた。
レオクスの期待に応えようと過度の重圧を自分にかけていた事。叶わない場所にいるエリク女王に、嫉妬していたのだと気付かされた時、涙と笑いが両方出る感じに、奇妙な安らぎを感じていた。
この、一見、無責任な黒マントの男に、人としての行き方の多彩さを教わるような気持ちだった。
レオクスは、常に自分にこう声をかけていてくれたではないか。
焦らなくていい、人のためを想うその行為こそ美しいのであって、結果は所詮結果でしかない。人を思うその行為の過程にこそ、清き心が宿るのであって、目的への到達はさらなる目的への始点でしかないのだ、と。
リシアはおおよそレオクスとは対極に位置するこの男だからこそ、自分の求めていた答えの一つを自分にくれたのではないだろうかと、彼との出会いに感謝し、好意的な想いで目の前の一人の男を見つめることが出来た。
作り笑いではない、本当の笑顔。
この笑顔をレオクスに、いや、エリクや他の人たちにも自然に出せたらどんなにか素晴らしいことだろうと、常に自然体のこの男を目の当たりにして、そう思い至ることができた。
「エルランゼ様、口元におべんと付いてますよ」
そう言ってリシアは、ためぞうの口元についたご飯粒を、人差し指で優しく取って、ぺロッと口の中に運んで、はにかんで見せた。
「うひょひょ、萌えますのう!! 今度は直接口でペロッてやってくれない?」
「えっ!? あ・・・それはちょっと」
カーーーッ、と顔が朱色に染まるリシアを見て、ためぞうはたいそうご満悦な様子だった。
その紙一枚向こうでうごめく、ドス黒い嫉妬心の渦に気付くことも無く、ためぞうはリシアとすっかり打ち解けて、うひょうひょ笑っている。
「あーー、マイオストさん。私、あのバカをす巻きにして、グレートフォールの滝の奥底に叩き込んでやりたい気分ですわ・・・ハハハ」
「うーん、エルランゼには悪いけど、その時はリリス君に協力するよ。ハハハハハ・・・」
アメジストガーデンが、淡いオレンジの光に照らされる時刻。庭は昼間とはまた違った美しさを放ち、見る者に安らぎを与える優しい色で、その場にいる者たちを等しく包み込んでいた。
リシアはこの庭に帰って来た時、その時間流れた時の速さに少し驚いていた。
彼女にとって、そんな経験は戦場を駆ける時くらいしか体感できないものだったからである。
リシアは自分の生まれた月日を覚えてはいないが、おそらく十四、五歳の年齢である彼女には、年頃の娘が経験するであろう、淡い青春めいたものもなく、ただ国家の安全とレオクスの為を想い、身を粉にしてギーガ討伐や戦争に関わってきた記憶しかない。
きっかけは小さかったかも知れないが、ごまかしでない自由というものを僅かでも感じ取れたこの数時間というものが、リシアにアメジストガーデンをこんなにも美しく、華やいだものに感じさせていた。
「また来てくれると嬉しいな。魔王軍四天王、エルランゼ殿下」
リシアは始めから、ためぞうの正体など見抜いていた。
リシアほどの戦士であれば、相手が実力を隠していたとしようが、実戦の勘が彼女にそれを告げるのだ。リシアはためぞうの戦士レベルが93である事も、他の怪しい二人が、マスタークラスの戦士一名と、レベル89の戦士である事にも気付いていた。
レオクスをこの命に賭けて守りたいというリシアの強い想いが、彼女の探知能力を極限にまで磨き上げていたと言っていいかも知れない。
リシアは戦士として心構えは、かの偉大なる剣王バルマードにすら引けを取らないほど、優秀で凛としていると言えた。
ただ、彼女に戦士としての弱点があるとすれば、それは純粋すぎるが故の優しさかも知れない。
先のスレク公国の戦乱でも彼女がその手にかけたのは、たったの二人。歴史的過ちを犯したスレク公(彼の大罪を知るものはレオクスなど、ごく限られた人物のみ。後にそれは公のものとなるが)と、禁忌を使用した騎士のみである。
味方の盾となり、攻撃を一身に集める彼女の戦い方は、バルマードらに言わせれば実力の浪費である。自分が倒れることが、味方により多くの、壊滅的な打撃を与えるのだという事を理解できれば、彼女の戦い方の無茶ぶりも、若さや甘さといった言葉で軽く切り捨てられる。
将軍としてのリシアは、そういう意味では未熟であった。
レオクスはそんな彼女を諭すような真似はせず、ただじっと彼女を見守り、出来れば戦士としての道よりも、一人の少女として、穏やかな日々を送って欲しいと願っていた。
リシアがアメジストガーデンの階段に腰掛けて庭の方を見つめていると、突然、冷たい感覚が頬を襲った。
「はい、リシアさん」
そう言って、虚を付かれたリシアに向かって、雫の滴るほどに冷えたラムネを手渡したのは、かのレムローズ王国の女王、エリクであった。
「エ、エリク様!?」
リシアは特別、油断などしていたわけではない。
リシアにその気配すら気付かせないエリクの方が、彼女を更に上回る実力者なのだ。
エリクはリシアを時々こうやって驚かせることがある。
エリクはそうやって、悩んで蹲るリシアの気を紛らわせ、励ましていたのだが、今日は思いのほか元気そうなリシアを見て、安心したように夕焼け色の階段に腰を下ろし、その手に持ったラムネをゴクンと飲んでリシアに笑いかけた。
「いいことあったみたいな顔しちゃって、ほらほら、お姉さんに話してみなさいよ」
エリクは大陸でおそらく1,2を争うほどの絶世の美姫でありながら、大陸有数の名門レムローズ家出身の王女でもあるのに、こと、リシアに対しては気取ったところがまったくなかった。
エリクは数年前にリシアと出会ってからというもの、まるで妹のように彼女を可愛がっている。
「え、いいことですか!? あはは・・・。そうですね、えっとある殿方とちょっと午後のお茶をしたと申しましょうか、ほんと、それだけなんですけど」
「お、男!? リシアさん、詳しくお姉さんに話してごらんなさい。お姉さんそういう話、大好きな方だから!」
「え、えーーーっ!?」
モジモジしながら下を向くリシアに、にじり寄るようにして顔を近づけるエリク。
話を話そうにも、ネタがカツ丼から始まるような話を、リシアはどう話していいものやらわからず、一口、ラムネを飲んだ後、エリクとよく一緒に行くお店で、いつものものを注文したとだけリシアは告げた。
「ちゅ、チューーゥ!?」
「注文ですって! ちゅーもん! 無理やり間違わないでくださいよ、エリク様」
「個室に、男、誘っといて、チューの一つもしてないなんて言わせないわよ、リシアさん。何処までいったか、お姉さんは知る義務があります。まさか!? モフモフとか、ニャンニャンとか、人に言えないような・・・」
「何ですか!? モフモフとかニャンニャンって!!」
意味不明の言葉を必死に否定するリシア。そのリシアの肩をエリクはガッツリ抱き寄せると、有無を言わさずたたみ掛ける。
「否定は、肯定の証。やってないといえば、やったと決まっているわ。・・・もう、このおマセさんったら。さっそく、レオクス様に報告しなくては」
「そ、それだけは勘弁してください!!!」
「まあ、男を二股にかける気かしら、この子ったら。・・・でも、お姉さん、ちょっと嬉しいわ。ようやくリシアさんが、女の悦びに目覚めてくれたなんて」
「ああもう! エリク様の言い方が卑猥すぎるんですよ!!」
ジュルルルルル~~~ッ!!
「!?」
すると突然、エリクはリシアの唇を奪い、ジュルジュル音を立てながらリシアのラムネ味の唾液を執拗に吸い上げた!!
「プハーーーーッ!! ごちそうさんッ!!」
「エ、エリク様・・・」
唖然とするリシア。したり顔のエリクは、シルクの袖でジュルリを口元を拭った後、リシアに向かってこう放つ。
「ああ、これが乙女の味なのね。クセになりそうですワ・・・。っていうか、先にいい思いをした野郎を探し出して、焼入れとかんと、な」
再度、リシアの唇を奪いにかかるエリクを、リシアは神速でかわし続け、心の中でこう自分を勇気付けた。
(・・・今のは、ファーストキスなんかじゃない。単なる不意打ちよ。・・・絶対、カウントしないで。お願い、心の中のわたし・・・)、と。
フォルミ市街へとためぞうを連れ出したリシアが向かった先は、『モンブランシェ・フォルミ本店』と書かれた看板の、かなりの規模のスウィーツ&カフェの店だった。
顔なじみなのか、リシアが来店すると同時に店の支配人と思しきジェントルメンが現れ、明らかにVIPルームであろう豪華な個室へと案内される。リシアは着席すると同時に、支配人風の男にいつものをと頼み、ためぞうに好みのものを聞いてきた。
「エルランゼ様は何になさいます? オススメはパティシエ特製の虹色ケーキとか、レトレアンティーなどがありますが、他にもドーラベルンコーヒーや、あと100種類ほどスイーツがございますが、甘いものが苦手な方用に、カツ丼とかカレーなんかもありますよ」
「・・・では、カツ丼と水で」
リシアはコクリと頷くと、支配人風の男に「国産ブランド黒豚使用のカツ丼と、ガルトラント山脈の雪解け水の湧き水(150年物)」をと注文を伝えた。
オーダーを取った彼が部屋を退室すると、リシアとためぞうは個室に二人っきりとなる。
豪華過ぎる室内に、その雰囲気に慣れた感じの金髪の美少女と向き合って座ることになった、ためぞう。
ためぞうにこの手の経験値などない。微笑むリシアに、何から話していいやらサッパリわからず、その空気の重さにためぞうは酸欠になりそうだった。
一秒がこうも長く感じられる瞬間など、そうあるものではない。
ためぞうは必死に何か言わなければと、出来の悪いオツムを加熱させて言葉を捜す。
(いいか、落ち着けオレ。こんなチャンスをピンチにして、どーするんだ。マイオストのオッサンじゃこんな場合の対処法など知らんだろうし、リリスに至っては論外だ。誰に、オレの超高性能な思念波を送って、答えを貰えばいいんだ。100ドルやるから誰か、気の聞いたセリフの一つでも教えてくれぃ・・・。うっ! コテッ)
ためぞうは、・・・倒れた。
しかし、今日のためぞうは一日で一生分の運を使い果たしているのか、ウルトラ大吉なのか、なんと金髪の美少女の方から話を振ってきたのだ。
「私、男の方とこのお店に来たのって、実は初めてなんです。普段は館とメイドさんたちと来たりするんで、エルランゼ様とお話しが合わなかったらごめんなさいね」
と、軽く両手を合わせてウインクするリシア。可愛さ120%のリシアの姿に、ためぞうはもうどうとでもなれ! っと割り切って玉砕覚悟で喋りだした。
「ハッハッハッ、オレなんか若白髪の中年や、行き遅れの三十路女なんかと、おでん屋や焼き鳥屋に呑みに行くくらいなんで、オレこそ若い子に話を合わせられるか自信はないっす」
「うふふっ・・・気持ちは同じだったんですね」
とリシアに笑顔で振られたためぞうは、一気に緊張から開放され、その反動の大きさからか、リシアとの会話が楽しくて仕方なくなってきた。
ためぞうは饒舌になって、世界がどうだの、金融危機がどうだの、競馬やパチスロがどうこうと、明らかに的外れな言葉をリシアに浴びせかけたが、リシアはしっかり話題についてくる頭のいい子だった。ちゃんとした意見を返してくるし、冗談も時折混ぜてくるし、そうこうしている間に、テーブルはオーダーしたスウィーツや飲み物、高級カツ丼などで華やかに彩られた。
「なるほど、それが虹色ケーキなわけね」
七種類の異なる味わいと繊細な色使いが見事なケーキを、アメ細工が美しくアーチを架けるという手の込んだ作りで、見るだけで美味そうなのがためぞうにも容易に理解できた。
レトレアンティーの上質な香りに満たされた室内に、ためぞうはカツ丼の蓋を開ける。
「う、うめーーーーーーっ」
それはためぞうが、生まれて初めて口にした至高の一品だった。
それまで、うまか棒くらいしか美味いものを知らなかったためぞうには、まさに目からウロコである。ガツガツとカツ丼をほお張るためぞうを、ほお杖ついて楽しそうに見つめるリシア。
「気に入ってもらえてよかったです」
「うん、美味い! なんかお冷もすんごい滑らかな口当たりで美味しいんだけど。やっぱ、フォルミ(都会)は違うねぇ・・・」
「私も、こんなに楽しいティータイムは、ほんと久しぶりです」
無邪気に笑いながら、上品にスウィーツを口にするリシア姫と、カツ丼のおかわりを頼むためぞう。支払い額を心配しなくていいのかと突っ込んでやりたくもなるが、運のいいことにリシアの飲食代は同席者を含め、全てが大公の払いとなっていたりする。
それが面白くないのは、二つ穴の開けられた障子の向こうにいる、銀髪中年と三十路女だった。店の調度品に穴を開けるマナー知らずの二人。
歯軋り音を立てながら、リリスはマイオストに言った。
「なんで、なんであのバカが、よりにもよってあんなにもいい思いをしているわけ!? つか、あの子、何? 天使? どれだけ人がいいのよ! まったく、ためぞうなんかにあんなにサービスしちゃって、もう」
「わかるよ、リリス君。私も今まで、無意識の内に、自分より不幸なヤツがいるから、これまで自分は頑張ってこれたんだなって思っていたところだから」
「そう! 私を不幸にしている元凶が、あんなにもハッピーでだらしない顔をして、天使の微笑を受けているなんて、ヤツの転落を願って仕方ないくらいイラついてるわよ!!」
二人はためぞうを尾行するために、見栄を張ってリシアたちの隣の部屋を取り、ついでに頼み方もわからないオーダーを、リシアの口真似の如く同じもの注文した為、後にとんでもない請求書を受け取ることになる。
ついでに障子の穴も見つかって、最高級東方和紙の張替え代まで加算されるいう地獄を見る。それは、マイオストとリリスの給料三か月分という、何とも耐え難い出費であった。
一方、紙一枚向こうの世界では、和やかな談笑が続いていた。
「私、エルランゼ様をお誘いして、ほんとに良かったと思っています。小さな事で悩んでいた私が、本当に人として小さかったんだなって、そう思えるんです。女の子同士の会話だと言えないことも、なにかこう気楽に話せてしまうというか。今日のケーキはいつもより、美味しく感じるんです」
「ああ、うまいねーーっ! オレなんかもうカツ丼四杯目にいっちゃいそうだよ。いやー、うまか棒しか美味いものを、行き遅れのヤツが教えてくれなかったもんで、カツ丼がこんなにも美味いなんて。オレ、取調べを受けないとカツ丼喰えないって思い込んじゃってたから、大分、人生損してるよなあ」
そういいながらも豪快に食べまくるためぞうの姿に、リシアは本当に心が救われていた。
レオクスの期待に応えようと過度の重圧を自分にかけていた事。叶わない場所にいるエリク女王に、嫉妬していたのだと気付かされた時、涙と笑いが両方出る感じに、奇妙な安らぎを感じていた。
この、一見、無責任な黒マントの男に、人としての行き方の多彩さを教わるような気持ちだった。
レオクスは、常に自分にこう声をかけていてくれたではないか。
焦らなくていい、人のためを想うその行為こそ美しいのであって、結果は所詮結果でしかない。人を思うその行為の過程にこそ、清き心が宿るのであって、目的への到達はさらなる目的への始点でしかないのだ、と。
リシアはおおよそレオクスとは対極に位置するこの男だからこそ、自分の求めていた答えの一つを自分にくれたのではないだろうかと、彼との出会いに感謝し、好意的な想いで目の前の一人の男を見つめることが出来た。
作り笑いではない、本当の笑顔。
この笑顔をレオクスに、いや、エリクや他の人たちにも自然に出せたらどんなにか素晴らしいことだろうと、常に自然体のこの男を目の当たりにして、そう思い至ることができた。
「エルランゼ様、口元におべんと付いてますよ」
そう言ってリシアは、ためぞうの口元についたご飯粒を、人差し指で優しく取って、ぺロッと口の中に運んで、はにかんで見せた。
「うひょひょ、萌えますのう!! 今度は直接口でペロッてやってくれない?」
「えっ!? あ・・・それはちょっと」
カーーーッ、と顔が朱色に染まるリシアを見て、ためぞうはたいそうご満悦な様子だった。
その紙一枚向こうでうごめく、ドス黒い嫉妬心の渦に気付くことも無く、ためぞうはリシアとすっかり打ち解けて、うひょうひょ笑っている。
「あーー、マイオストさん。私、あのバカをす巻きにして、グレートフォールの滝の奥底に叩き込んでやりたい気分ですわ・・・ハハハ」
「うーん、エルランゼには悪いけど、その時はリリス君に協力するよ。ハハハハハ・・・」
アメジストガーデンが、淡いオレンジの光に照らされる時刻。庭は昼間とはまた違った美しさを放ち、見る者に安らぎを与える優しい色で、その場にいる者たちを等しく包み込んでいた。
リシアはこの庭に帰って来た時、その時間流れた時の速さに少し驚いていた。
彼女にとって、そんな経験は戦場を駆ける時くらいしか体感できないものだったからである。
リシアは自分の生まれた月日を覚えてはいないが、おそらく十四、五歳の年齢である彼女には、年頃の娘が経験するであろう、淡い青春めいたものもなく、ただ国家の安全とレオクスの為を想い、身を粉にしてギーガ討伐や戦争に関わってきた記憶しかない。
きっかけは小さかったかも知れないが、ごまかしでない自由というものを僅かでも感じ取れたこの数時間というものが、リシアにアメジストガーデンをこんなにも美しく、華やいだものに感じさせていた。
「また来てくれると嬉しいな。魔王軍四天王、エルランゼ殿下」
リシアは始めから、ためぞうの正体など見抜いていた。
リシアほどの戦士であれば、相手が実力を隠していたとしようが、実戦の勘が彼女にそれを告げるのだ。リシアはためぞうの戦士レベルが93である事も、他の怪しい二人が、マスタークラスの戦士一名と、レベル89の戦士である事にも気付いていた。
レオクスをこの命に賭けて守りたいというリシアの強い想いが、彼女の探知能力を極限にまで磨き上げていたと言っていいかも知れない。
リシアは戦士として心構えは、かの偉大なる剣王バルマードにすら引けを取らないほど、優秀で凛としていると言えた。
ただ、彼女に戦士としての弱点があるとすれば、それは純粋すぎるが故の優しさかも知れない。
先のスレク公国の戦乱でも彼女がその手にかけたのは、たったの二人。歴史的過ちを犯したスレク公(彼の大罪を知るものはレオクスなど、ごく限られた人物のみ。後にそれは公のものとなるが)と、禁忌を使用した騎士のみである。
味方の盾となり、攻撃を一身に集める彼女の戦い方は、バルマードらに言わせれば実力の浪費である。自分が倒れることが、味方により多くの、壊滅的な打撃を与えるのだという事を理解できれば、彼女の戦い方の無茶ぶりも、若さや甘さといった言葉で軽く切り捨てられる。
将軍としてのリシアは、そういう意味では未熟であった。
レオクスはそんな彼女を諭すような真似はせず、ただじっと彼女を見守り、出来れば戦士としての道よりも、一人の少女として、穏やかな日々を送って欲しいと願っていた。
リシアがアメジストガーデンの階段に腰掛けて庭の方を見つめていると、突然、冷たい感覚が頬を襲った。
「はい、リシアさん」
そう言って、虚を付かれたリシアに向かって、雫の滴るほどに冷えたラムネを手渡したのは、かのレムローズ王国の女王、エリクであった。
「エ、エリク様!?」
リシアは特別、油断などしていたわけではない。
リシアにその気配すら気付かせないエリクの方が、彼女を更に上回る実力者なのだ。
エリクはリシアを時々こうやって驚かせることがある。
エリクはそうやって、悩んで蹲るリシアの気を紛らわせ、励ましていたのだが、今日は思いのほか元気そうなリシアを見て、安心したように夕焼け色の階段に腰を下ろし、その手に持ったラムネをゴクンと飲んでリシアに笑いかけた。
「いいことあったみたいな顔しちゃって、ほらほら、お姉さんに話してみなさいよ」
エリクは大陸でおそらく1,2を争うほどの絶世の美姫でありながら、大陸有数の名門レムローズ家出身の王女でもあるのに、こと、リシアに対しては気取ったところがまったくなかった。
エリクは数年前にリシアと出会ってからというもの、まるで妹のように彼女を可愛がっている。
「え、いいことですか!? あはは・・・。そうですね、えっとある殿方とちょっと午後のお茶をしたと申しましょうか、ほんと、それだけなんですけど」
「お、男!? リシアさん、詳しくお姉さんに話してごらんなさい。お姉さんそういう話、大好きな方だから!」
「え、えーーーっ!?」
モジモジしながら下を向くリシアに、にじり寄るようにして顔を近づけるエリク。
話を話そうにも、ネタがカツ丼から始まるような話を、リシアはどう話していいものやらわからず、一口、ラムネを飲んだ後、エリクとよく一緒に行くお店で、いつものものを注文したとだけリシアは告げた。
「ちゅ、チューーゥ!?」
「注文ですって! ちゅーもん! 無理やり間違わないでくださいよ、エリク様」
「個室に、男、誘っといて、チューの一つもしてないなんて言わせないわよ、リシアさん。何処までいったか、お姉さんは知る義務があります。まさか!? モフモフとか、ニャンニャンとか、人に言えないような・・・」
「何ですか!? モフモフとかニャンニャンって!!」
意味不明の言葉を必死に否定するリシア。そのリシアの肩をエリクはガッツリ抱き寄せると、有無を言わさずたたみ掛ける。
「否定は、肯定の証。やってないといえば、やったと決まっているわ。・・・もう、このおマセさんったら。さっそく、レオクス様に報告しなくては」
「そ、それだけは勘弁してください!!!」
「まあ、男を二股にかける気かしら、この子ったら。・・・でも、お姉さん、ちょっと嬉しいわ。ようやくリシアさんが、女の悦びに目覚めてくれたなんて」
「ああもう! エリク様の言い方が卑猥すぎるんですよ!!」
ジュルルルルル~~~ッ!!
「!?」
すると突然、エリクはリシアの唇を奪い、ジュルジュル音を立てながらリシアのラムネ味の唾液を執拗に吸い上げた!!
「プハーーーーッ!! ごちそうさんッ!!」
「エ、エリク様・・・」
唖然とするリシア。したり顔のエリクは、シルクの袖でジュルリを口元を拭った後、リシアに向かってこう放つ。
「ああ、これが乙女の味なのね。クセになりそうですワ・・・。っていうか、先にいい思いをした野郎を探し出して、焼入れとかんと、な」
再度、リシアの唇を奪いにかかるエリクを、リシアは神速でかわし続け、心の中でこう自分を勇気付けた。
(・・・今のは、ファーストキスなんかじゃない。単なる不意打ちよ。・・・絶対、カウントしないで。お願い、心の中のわたし・・・)、と。














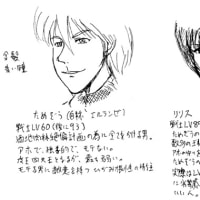

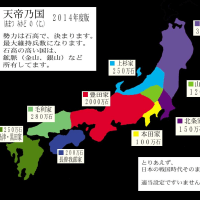



※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます