
京都駅からバスに乗り、京都国立博物館で下車。

博物館はまだ開館前だったので、先に三十三間堂を訪れた。
薄曇り。天気が怪しい。晴れてくれ~。
三十三間堂は、後白河法皇の御所、法住寺殿の西側に1164年に建てられたとのこと。
ちなみに同じ1164年に、延暦寺の僧徒が座主を追放し、その房舎を破壊しているし
3年後の1167年に平清盛が太政大臣に就任しているらしいので、平家の「この世の春」の頃。
んでもって、後白河上皇っていう方は、
1158年から院政を行い、平家や源氏の対立等々をうまく泳ぎ切って
1192年に没するまで頑張った方。 ただものではない…。
GOOGLEで「後白河法皇」で画像検索すると、こんな感じ。
見た印象で恐縮だが、あまり良い人には描かれていないようだ。
狡猾で策略家と言ったイメージかもしれない。
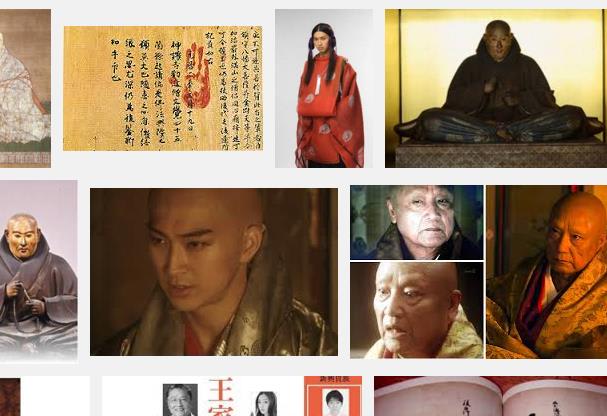
建物は三十三間もあるんだから、横に長い。
1間は1.818mくらいらしいんで、33間では60m。
デジカメで撮ろうと思っても、俺のカメラじゃ無理。
どこまで引いても、全容が納まりません。


何度来ても、圧倒される。
1001体の十一面千手千眼観世音様。
これもGOOGLEからの画像検索。
火災に見舞われ、1001体のうち124躯が当初からのものらしく、
その後、湛慶ほか多くの仏師により15年をかけて作られたとのこと。

勿論、堂内の撮影は厳禁。
下の写真は「新版 古都巡礼 京都 第18巻 妙法院・三十三間堂」から。
なんとも、ふくよかなお顔。
迷える衆生のひとりである俺を、どうか御救いください。

そうそう。
パンフレットで知ったんだけど
1001体全てがご本尊で、真ん中にお座りになってるでかい観音様を「中尊」と言うらしい。
こちらも運慶の長男である湛慶という人の作品なんだって。
極楽上等
極楽浄土
極楽はどんなところか知らないけれど、そして、知り得もしないけれど
平安貴族は、篤い信仰心から、その権力と財力に任せて、こんな大層なもんを築いたんでしょうね。
どれだけ、末法を恐ろしがったのか、どれだけ極楽浄土に行きたがったのか
なんとなく理解できるような気がします。
風神・雷神像も、二十八部衆も、みーんな存在感ありすぎ。
どれもこれも近寄りがたい…って近寄って見たいけど。
こんなに作ったんだもの、これで救われなきゃ、世の中どうかしてしてるよと言った感じです。
どれもこれも、国宝(又は重文)で
こんなに国宝(又は重文)がごろごろしていると、有難みも薄らぐような…。(罰当たり)
後白河上皇、って、波乱に富んだ人生の人だったんだろうなあ。

桜はちらほら咲いていました。
あと2週間も経てば、満開。 美しいでしょうね。
人並みの信仰心しか持たない俺だけど
こういう空間に来ると、やっぱり、その凛とした空気に圧倒されて、シャンとします。
背筋が伸びるような気がします。

1164年に平清盛により創建されてから、今日に至るまで、ずっと信仰の対象であったことってすごいよね。
いったいどれくらいの人たちの祈りを聴き、願いをかなえてくれたんだろうとも思います。

梅は盛りが過ぎてしまって、木蓮と椿が印象的でした。
春はやっぱり花が咲かなくちゃ、ですね。


不思議なことに、南大門って、ふつうの道路上にあるんだよね。
ね。下の写真の右下に「南大門」ってありますもんね。
三十三間堂は、後白河法皇の御所、法住寺殿の西側に建てられたってことでしたから
南大門って奴は、法住殿の門だったってことでしょう。(当てずっぽう)

さ。
自宅の仏壇に供えるお線香を買って、京都国立博物館へ向かいましょう。















