本日新宿初台にある東京オペラシティへ行き、”タケミツ・メモリアルホールで、新春の”ウイーン・ワルツ・オーケストラ”を聴いてきたが、一度はこのホールに来て見たかったので色々感じることが多かった。
オペラシティは、新国立劇場と隣り合わせで一体となっており、設計者は柳沢孝彦TAK建築計画研究所(竹中工務店の出身)である。
国際コンペで入賞したものだと言う。
三宅坂にある国立劇場も当時竹中工務店の設計部長岩本博行氏がコンペで勝ち取ったもので、正倉院を模した校倉風建築で話題となった伝統的な和の演劇のための劇場であった。
新国立劇場は、オペラや、ミュージカルを上演する洋楽のための国立劇場であるが、衆知のように当初から色々な意見が対立し、現在も海外の代表的なオペラが来日してもこの劇場では上演されていないと聞く。
もったいない話だと思う。
この複合施設の中には、コンサートホールとして作曲家の故武満徹が指導したと言う ”タケミツ・メモリアルホール”があり写真のような天然木(ホワイトオーク)を使用したインテリアとなっている。
特徴的なのは、変形ピラミッドの形をした高い吹き抜け天井部分で、客席よりは余程お金が掛かっているようだ。
音響的にどれほど効果があるのか、実際に聞いてみると音が上部に逃げていく感じがして仕方がなかった。
ホールの形状は、シューボックス型で2層のバルコニー席が廻っている。
シンプルな形で、中に入ってみると写真ほどの迫力は感じない。
今日は2階のバルコニー席で聴いたが、座席の前に手摺バーが廻されて、舞台を見るには、多少乗り出さなければならないのもいささか気になったところである。
それほど音響効果があるとは思えないピラミッド状の吹き抜け部分に、多大なエネルギーが費やされたようで、肝心の1階の客席や舞台周りは驚くほどシンプルと言うか、簡素なつくりで正直言って物足りない感じがした。
私も参加した黒川紀章氏設計の福岡銀行本店の地下部分にコンサートホールが組み込まれていた。
音楽ファンだった当時の蟻川頭取の意見を取り入れたもので、1970年代のものだがうねる様な天然木のブロックの組み合わせが特徴的なインテリアであった。
その時消防法が改正され、もうこれ以降木を使ったコンサートホールは出来ないと黒川さんは当時自慢していたが、防火処理が進歩したのかこのメモリアルホールは全部天然木の仕上げである。
しかし、客席以外のホワイエやロビー部分は随分贅沢なスペースで、敷地の狭さに苦慮しただろう東急文化村のオーチャードホールなどよりはるかに広く、さすが国が関与した文化財団のものだと思う。
肝心の今日の音楽は、ウインナーワルツとバレエのコラボで、ミニオーケストラであった。
ウイーンの宮殿音楽とバレエの新年らしいものだったが、その美しい音色と踊りとは裏腹に、どうも異常な大きさの天井の空間部分が気になった演奏会ではあった。













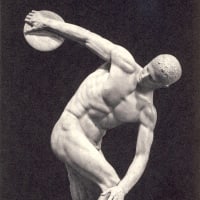









※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます