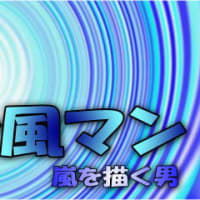風に吹かれて嵐を呼ぶ本屋 その3
ラッキョウ畑に宇宙が見える
輝く晴天の中、我々は目を覚ました。
雲一つ無い空と呼ぶのに似つかわしい、純粋な晴天である。
大山の山の清浄な空気も加味され、素晴しい朝となった。
早起きは三文の得と言うが、元々あの諺は「早起きしても二足三文くらいの得にしかならない」という、朝寝好きの江戸っ子の諺であるらしい。
しかし、すがすがしい新鮮な空気に満たされた朝に包まれると、980円くらいの得をした心持である。
それから暫らくして、台風難民達のコンサート会場へと向かう民族の大移動が始まった。
だが大山の麓は温泉の宝庫である、こんな爽やかな朝に温泉に行かないという手はない。
朝湯に入って小原庄助を決め込み、湯船でぶふぁぁ~!っと叫びたいのである。
昨夜のネイティブ・アメリカンのメディスンマンの祈りの神聖な気分はどこぞに吹っ飛んで、俺はまた元の自堕落で能天気なニッポンジンに戻っていた。
「この近所に皆生温泉があるらしいぞ・・・」
中上さんが、俺に言った。
「おおっ!良いね!行こうぜ!」
という寸法で、早速皆生温泉目指して車を走らせ、ぐるぐると山道を下りていった。
台風一過の青空は、本当に目に沁みるような青さだ。
大山の山道は、昨日の荒れ狂う景色とはうって変わって優しい癒される風景であった。
オゾンとフェトンチッドに満たされた山道を走るピースアイランドの軽バンは、まるでスポーツカーにも思われた。
窓を開けて走れば、少し冷たい心地よい風が無精髭の頬をなでて、無条件に幸せな気分に浸らせてくれる。
寝起きの重いまぶたはパッチリ開き、旅心は盛り上がる一方だ。
麓の道を走り、皆生温泉に近づくにしたがって、海の匂いが感じられるようになった。
潮の香りが、なぜか子供の頃の海水浴の記憶を呼び覚ました。
碁盤の目のように几帳面に通る道路に、一見教会のような建築物があった。
それが海沿いの皆生温泉浴場だった、いわゆる銭湯のようなものである。
入り口で入泉料をはらい、温泉の匂いで充満した幸せな浴場へと急いだ。
皆生温泉浴場は意外に広く、大きな浴槽が真ん中にあり、お湯があふれんばかりに張ってあった。
我々は、飛び込むかのように湯船につかり、「ぶふぁぁ~・・・」と溜息をついたのだった。
「嗚呼・・・愛しき日本人!」などと、自らの習性に感謝したい心持である。
昨日の台風の襲撃も忘れ、体中の疲れが消滅していく瞬間は、心の台風一過と呼ぶに相応しいのだ。
無言のまま湯船に浸かっっていると、湯気の中からぬぅ~っと現れた男がいた。
「おお!皆来とったんか!」一見アイヌ人のような面構えの大沼さんだった。
大沼さんは岐阜県瑞浪の陶芸家であり、俺や中上さんとは旧知の仲であった。
「いつ来た?」湯気で見え隠れする大沼さんに言った。
「さっき着いたばかりや!すごい台風やった」温泉好きなら朝一に温泉に行きたがるもんである。
「あの台風の中、走ってきたんか?」俺は驚嘆して言った。
人のことは言えないが、大沼さんの性格は、無謀というか豪胆というか傍若無人な性格だった。
しかし、このような遠い場所で友人にバッタリ会ったりするのは、妙に素敵で愉快な気分である。
湯船で3人で、ナンダカンダと話に花が咲き、小一時間も温泉に浸かっていた。
手の皮が皺皺になり、湯当たりする寸前で温泉から出た。
外の空気は日本海の潮の匂いで旅情を掻き立ていたが、もう昼近くになってしまっていた。
「腹が減ったなあ・・・」中上さんが言った。
そういえば、昨日の夜の差し入れのオニギリ以降、何も口にしていない。腹が減るのも当たり前だ。
というわけで、食事をするために喫茶店に入ることになった。
遥々鳥取まで来て、喫茶店でカレーやスパゲティを食うなど無策にもほどがあるのだが、昨日から何も食べていない状況であるので、これも止むを得ない。
俺と中上さんと陶芸家の大沼さんの3人は、皆生温泉浴場の近くの喫茶店に入った。
案の定、鳥取とはまるで無関係なカレーやスパゲティを注文し、話の花を咲かせたのだった。
喫茶店の窓から見える景色は、果てし無く続くのではないかとも思えてしまう、一面の広いラッキョウ畑である。
日本海側の土地はラッキョウ栽培に適しているのであろう、おそらく日本海の北陸から中国地方の海岸はラッキョウ・ベルトと呼んでも差し支えないかもしれない。
ラッキョウ・ベルトは実在する・・・しかし実在した所で何の意味もないのだが、そんな光景を思い起こすと可笑しいような気分になり、人生が少しだけ楽しくなるというもんだ。
あのホムンクルスのようなコロポックルのようなラッキョウ達が、真っ直ぐに行進しいている光景をイメージしたなら、微笑ましいような気分に浸るのがノーマルな人の精神状態であると言えるだろう。
宮沢賢治の「月夜の電信柱」ではないが、ラッキョウ畑はさしずめ「砂漠の小人の行進」のようだ。
ドッテテ ドッテテ ドッテテド・・・・
ラッキョウは小さいから、トッチチ トッチチ トッチチト・・かもしれない。
こんなラッキョウ畑の話題で2時間近くも話が出来るなんて、我々はなんて能天気野郎で暇人なんだろう。
悩みのない人生が幸福であるのか?悩まないから幸福なのか?定かではないが、少なくとも人生の多くの時間を笑い転げるような馬鹿げた空想で過ごせる人は幸福だと断言できる。
物事は無味無感・無味無臭・何の色合いも無く、中立であり続ける。
そして、それらの事物は人の解釈によって悲劇にも喜劇にもなることは、古今の賢者達が口をそろえて唱えているが、あれは真実だ。
ただのラッキョウ畑も、想像力によって一つの荒唐無稽な宇宙を形成させてしまう。
・・・などと含蓄有りげにさせてしまうのも、旅の高揚した心の成せる技であろうか。
旅の友人が一人増えた我々のテンションは上がる一方だ。
大山のコンサートも、今日は開催されるだろう。
コンサート会場へ向かう途中、ホームセンターやスーパーで、食料やキャンプに使用する道具類や食料をそろえた。
妙にテンションの高い3人組は、平穏な日常生活を営む住民には異様に見えたかもしれない。
「大山椒魚の肉、売ってませんか?」
そんなありもしない事を、スーパーの店員に聞いている大沼さんを見た時は、俺は大笑いをしてしまった。
旅の恥はかき捨てと言うが、好んで恥を作り出すのは青春の特権と言うことで許していただこう。
恥をかき捨てながら、また、元来た山道を戻り、コンサート会場へと車を走らせた。
麓近くの小さな雑貨店で、見たような人物とすれ違った。
我々は、車を急停車させ、その雑貨店に言ってみた。
「海で泳いどったら水母に刺されてまってよ、痛いでかんわ!キンカンあらへん?」
聞いたような名古屋弁が、店の奥から聞こえてきた。
雑貨店の中は、店のオヤジの使う鳥取弁と名古屋弁がチグハグに飛び交い、意思の疎通が出来ているのか出来ていないのか怪しい雰囲気だった。
俺は後ろから声をかけた。
「よっ!」
名古屋弁の男は、ビックリしたようにこちらを振り返った。
「おおっ!あんたらも来とったんか?」
名古屋弁丸出しの男は、知人の3流ミュージシャンの横井君だった、それに横井君の親しい友人である真野君まで、そこに居た。
「何時着いた?」
「昨日の夜や」
「台風は恐かったで!」
「あんたらぁも、命の祭りに来たんか?」
「そーや!」
「ほんとか、偶然やな!」
鳥取の辺鄙な雑貨店は、一瞬だけ岐阜弁と名古屋弁が交差する東海地方と化してしまった。
そして、旅の仲間が2人増えた。
コンサート会場は、昨日一緒だった台風難民のヒッピー達で盛り上がっていた。
舞台は修復中で、まだライブは始まっていなかったが、お祭りの雰囲気は会場全体に行渡り、高揚した気分にさせてくれる。
スキー場の殺伐とした風景の中に、屋台のような出店がそこここに出現し、あたかもどこか東南アジアの町の広場のようだった。
何を隠そう!と言ったりするが、誰も何も隠しちゃいない軽バンの中の絵本の山は、ここで絵本屋を開いてしまおうという中上さんの計画だった。
なんで岐阜県の山奥から、鳥取の大山まで来て絵本屋など開こうとするのか?
それは絵本屋の執念なのか?ただのお祭り好きなだけなのか?それはもう他人の図ることの出来ない絵本屋の店主の果てしない精神の産物であるのだろう。
また、そんなことを追求した所で、誰も何の徳にもならないのが常と言っても過言ではない。
一見馬鹿げた事に隠れた真実が隠されているのかもしれない。
ピースアイランドの軽バンの扉を開き、何冊もの絵本を運び出した。
簡単に仕組まれたビニールテントが、ピースアイランドの臨時の大山支店となった。
俺たちは、運び出した絵本を、ビニールシートの上に、丁寧に並べた。
色とりどりの表紙で飾られた絵本達は、今日のこの冒険活劇のような野外の出店を喜んでいるかのようにも見えた。
標高の高い山麓とはいえ、夏の日差しは涼しいとは言いがたい。
台風が完全に過ぎ去った直後は妙に蒸し暑く感じて、そよそよとそよぐ僅かな風にも涼しさを感じたりする。
そうして、ナンダカンダ本を並べているうちに、もっともらしい体裁の野外絵本屋が出来上がっていた。
ピースアイランド・支店第1号店・鳥取大山支店の開店である。
本を出した瞬間から大勢の人が集まり、大繁盛の兆しムンムンだった。
無理もない、コンサートはまだ直ぐに始まる様子も無く、手持ち無沙汰の家族連れや子供達がドーッと集まってきてしまったのである。
とはいえタダ見の客が多く、飛ぶようには売れなかったが、店主の中上さんは、それでも嬉しそうだった。
何故、彼が絵本屋をやっているのか判ったような気がした、炎天下の大山山麓である。