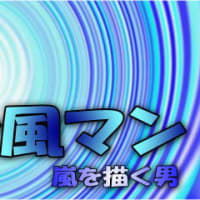待つ男
廃線になった駅の写真を撮影するため、私は、この朽ち果てた駅の構内に入り込んだ。
休日には1人で、このようなひなびた建築物や風景を写真に撮るのを趣味としている。
こんな寂れた町に来たのには、母が昔住んでいたという理由以外に何もない。
病気で亡くなった父と母と私は、私が3歳の頃まで住んでいたという。
私には、その記憶がまったく無いのだが、どこか懐かしさも感じさせる町であり、駅である。
病気で亡くなった父の後、数年して母は再婚したが、私を実の自分子供のように可愛がり育ててくれた父も、7年前に他界した。
母親も間も無く亡くし、今は天涯孤独で気楽だが淋しい身分であった。
廃線の駅は、朽ち果てるのを待つばかりの遺跡のようだった。
ここの駅も、もう数年前に廃線になったのにも関らず、何百年も経過したような雰囲気を醸し出している。
ペンキの剥げてしまったベンチは、もう人が座ることもないであろうに、人の温かを欲しているかのようにも見える。
駅の内壁に貼ってあるディスカバー・ジャパンの高峰峰子のポスターは、日光で焼け、脱色されて2色刷りの白々したポスターと化している。
外を見れば、剥げ落ちたペンキの間の外壁に、水原弘や由美かおるのホーロー看板が懐かしいような微笑を浮かべていた。
駅前の雑貨店は、もうとっくに店を止め、空虚になってしまったガラスのウィンドーには、紫外線で脱色されて痛々しい土産物の人形などが飾ってあった。
寂れて久しいのであろう、あるいは鉄道が走っていた時から、もう寂れていた駅前だったのかもしれない。
人道りはまったく無く、私の押すデジカメのシャッター音だけが、ガシャッガシャッと廃駅に響いている。
使われなくなった駅の錆びた改札口を通り抜け、線路を撮影しようと、私は外に出た。
線路の枕木の回りには雑草が伸び放題に生い茂り、長い時の間、車両が通過していないのを物語っていた。
雑草は、私の腰までも伸びているものもあった。
よく見ると、薄紫色や濃い黄色の小さな花を咲かせている草も、あちらこちらに生えていた。
そんな小さな花や線路を写真に納めていると、突然に人の気配を感じた。
ギクリとして後ろを振り返ると、50メートルほど向こうのベンチに、老人が腰掛けているのが視界に入った。
今時珍しく、昔の文士でもあるかのように、古びた黒いインパネスのコートを着ている。
老人は、こちらが気づいたのを察してか、軽く会釈をした。
私も、軽く会釈を返した。
どうしてあのような老人がここに居るのだろう・・・・?
いぶかしく思い、私は、その老人に近づいていった。
そんな老人と話をしたりするのも、こんな撮影の旅の楽しみの一つでもあったりするわけなのだが・・・・
その前に、そんな風景もなかなか良い風景であるので、その老人を中心に1枚写真を撮影した。
ガシャッとシャッターの擬音が、老人にも聞こえてしまったようだった。
老人は、私に向かって、手をやさしく振った。
私もつられて、老人に近ずきながら手を振ってしまっていた。
どこか懐かしさを感じてしまう老人の顔であった。
老人の目の前にくると、老人は微笑みながら私に言った。
「ワシを撮っても写真に写らんよ」
何のことか判らない私は、曖昧に返事をした。
どうせ、老人の戯言であろうとしか思えなかったからだ。
「良い天気ですね、何をしているのですか?」
話題が見つからない場合は、天気の話にかぎる。
私は、よくある普通の会話できりだしてみた。
「汽車を待っているのですよ・・・」
老人は、またも微笑みながら言ったのだった。
「汽車・・・ですか・・・・」
こんな廃線に、列車が行行き交うははずも無く、認知症の老人かと、とっさに思った。
きっと、意志も無く徘徊しているのであろう・・・・
そうは思ったが、顔の表情や話し方がシッカリしている。
「列車は来ませんよ・・廃線になってますからね・・」
そんな当たり前の返事を私はしたのだが、何か馬鹿げた返答にも思えた。
老人は、うふふ・・とでも笑うかのように言った。
「知ってますよ、そんなこと。ボケちゃいませんよ、ワシは・・」
私の心の中を見抜いたように、老人は話している。
「ワシは、列車を待っていると言っただけで、列車が来るとは言ってませんよ」
老人は、きっぱりと私に言ったのだった。
「列車を待っているのですか・・・」私は、意味不明な言葉に戸惑い、独り言のように言った。
「ワシはね・・こうやって随分前から待ち続けているのですよ」
老人は、しみじみして言った。
「かれこれ、70年くらいになりますか・・・」
遠くに1点で結ばれたような線路を見つめながら、老人は話を始めた。
「ワシが、最初に列車を待つようになったのは、3歳の頃だった・・・
随分昔のことだが、心の中ではついさっきのことと同じ出来事です・・・」
老人が自分の手のひらを拝むように合わせながら言った。
「ワシの母が、ワシを置いて汽車に乗って行った・・・・
きっと連れ戻しに来るよ!と良いながら、結局は2度とワシの所へ戻ることは無かった・・・」
老人の、列車を待つだけの人生が、それから何十年も続いているという。
母親が去ってから、「必ず返る」と言葉を残したまま、実の父親も列車に乗って消えていったという・・・
老人は、青年になるまで、従兄弟と共に叔父に育てられたという。
その、叔父の家族も、「いつか戻る」と約束したまま、この駅から列車に乗って、どこかの町に去っていった。
成人になり、老人は結婚をしたらしい。
しかし、妻との折り合いが悪く、3歳になる子供と共に、この駅から去っていった。
老人は、何時までも列車の窓から手を振る、子供の顔が忘れられないと言う。
それらの人々を、この駅で彼は、何時までも待ってた。
毎日毎日、ここで家族の帰りを待つのが日課になっていったのだと、老人は遠くを見ながら言った。
そんな、列車を待つ日々が長く長く続いたが、あるとき不思議な出来事が起こったのだ。
その日も、いつものように列車を待っていた。
その時、聞きなれた声が後ろからしたのだ。
フッと振り返ると、そこに立っていたのは、もう一人の自分だったのである。
着ている服から髪の形まで、寸分たがわない自分がたたずんでいたのだ。
「俺は、これから去っていった家族を探しに行く・・・」
もう一人の自分は、そう言ったのだった。
老人は何も答えられず、もう一人の自分の話を聞いてたのだという。
「お前は、ここで、俺の帰りを待っていてくれ!」
そう言いながら、もう一人の自分も、この駅から消えていった・・・・・
「ドッペルゲンガーというやつなんでしょうか・・・」
老人は、私の方を見ながら言った。
「あまりにも長い時間待ってばかりいたので、ワシの半分の存在も、痺れを切らしてどこかへ行ってしまったのかもしれん」
「今でも、もう一人のワシは、世界の果てまで家族を探していると思うよ・・・」
少し自嘲しながら、老人は言った・・・・
「もう一人の自分まで、見送ったのですね、この駅から・・」
私は、半信半疑のまま、老人の話を聞いている。
「君は、こんな話、信じてはいないのでしょうねぇ・・・」
老人は、私の目を見ながら、少し微笑みながら訊ねている。
「そうでもないですよ」と言おうとしたが、あまりにも嘘くさく聞こえるので、黙っていた。
黙っている私を眺めながら、老人は自分の手を、私に差し出した。
「うわっ!」
私は驚いて、1メートルほど後ずさりしてしまった。
ゆっくりと差し出された、老人の手は、薄っすらと透けて見えるのだ。
「自分の存在の半分が、何処かへ行ってしまったので、時々、ワシの体が、こうやって透けて見えてしまうのです。」
「もう一人の自分が、家族を探して戻ってくるまで、ワシはこうして待ち続けているのです。」
老人の体は、薄っすらと透けて見えたり、はっきりと存在したり、まるで風に揺らいでいるように見えた。
老人の話を聞いているうちに、私は、切ないような気持ちになっていた。
何かしてあげたいような気分だったが、私には何も出来ることはないだろうと感じた。
そう思うと、悲しくて、知らぬ間に老人の手をギュッと握っていたのだった。
ぎゅっと握った老人の手は、なんだか懐かしく、暖かだった。
ずっと昔に触ったことがあるような、心の奥底の悲しみを癒してくれるような・・・
そんな温もりであった。
「待ち続けた甲斐があったよ・・・・」
老人は独り言のように、ポツリと言葉を落とした。
黄昏が2人を包んでしまう頃、私は老人に別れを告げ、廃線駅から去っていった。
私は運転する車の窓から、老人を見た。
もう、人の顔の区別もつかないくらい、暗くなった廃線駅の構内で、古びたインパネスに包まれながら、老人は今も待ち続けている。