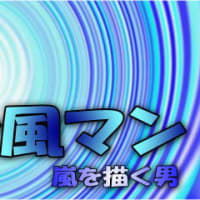風に吹かれて嵐を呼ぶ本屋 その4
深夜の森に条件反射の歌が流れる
夕暮れ時になって、1日半遅れでコンサートは始まった。
飛ばされひん曲がった雨よけのテントは取り払われ、青空天井のステージとなった。
その青空もしだいに夕焼けに染まり、ライトに照らされたステージは幻想的な雰囲気に包まれている。
均整のとれた雄大な大山をバックに、ライブは深夜まで続けられた。
会場は、出店のスパイスの効いたカレーの香りやフライド・チキンの香ばしい匂いが、時折風に乗ってフワリと漂い、どこか異国の情緒を醸し出している。
会場の中心部以外の周りは、いろいろな物売るフリーマーケット市場と化して、さながらバザールの様相だった。
月明かりが明るく大山を照らし、エスニックなスパイスの香りが漂い、音楽は深夜にまで鳴り響き、ここが日本だとは到底思えない大山の麓だった。
俺は、さながら異国にやってきた異邦人のように、このコンサート会場を楽しんだ。
そして、我らの野外絵本屋・大山支店も、そこそこ繁盛し、野外の絵本屋もそう捨てたもんじゃないと思わせてくれた。
「そろそろ夕飯にでもしようか?」と中上さんが言ったので、俺も賛同した。
我々は、コンサート会場から2分程度歩いた、山林の中にテントを張り、夕食の支度をし始めた。
森林の中は、無数のテントが張られ、ここも異国の風景が広がっているかのようだ。
そこここで、アウトドアの夕食の準備が始められ、食欲をそそるいい匂いが林の中に充満している。
「やっぱり、アウトドアには七輪やね!」
そう言いながら中上さんが、高山で購入したという真新しい七輪に、火を起こし始めた。
アウトドアに七輪があれば、天下無敵である。
常時、炭火が焚かれ、常にヤカンをかけておけば、いつも湯が沸いている状態で、好きなときにコーヒーが飲める。
また、調理をするにも、火力が携帯用コンロの比では無く、あっというまに料理が出来上がる。
飯ごうでご飯を炊くにも、一定の火力が維持でき、うまいご飯が炊き上がり、電気炊飯器の米と同じ米とは思えない美味さである。
あるいは、晩夏の夜に肌寒いときなど、この七輪の火で暖をとりながら、話に花を咲かせるのも一興である。
かように七輪はアウトドアには万能で最適な道具であので、俺は心の中でいつもこう叫んでいる「七輪を発明した天才に、栄光あれ!」。
俺は、昼に買出しにいった食材を出しながら、今日の献立を考えていた。
旅をしたなら、地元のスーパーに入るのが一番賢い買い物の方法だ。
土産物屋や観光用の市場に行っては駄目だ。
観光客用の店は、値段が高いだけでなく地元の食材さえ無いことが多い。
土産物に至っては業者が一括して卸しているので、広島の特産品と称するものが岐阜で作られていたり、北海道の物産とあるものが台湾で製造されていたり、それはもう興醒め状態甚だしいと言わざるを得ない。
そんな旅の失望感を味あわないためにも、地元のスーパーに趣いて珍しい食材を物色するのが達人のメソッドというものである。
地元の小さなスーパーに有るものは、地元で頻繁に食されている食材がほとんどである。
魚介類などにいたっては、見たことも無いような海の幸が日常的に並んでいたりするのを見つけた時など、旅の感動も倍増するのである。
野菜なども、まだ食べたことも無いような野菜を発見した喜びは筆舌に尽くしがたい!、と言うのは大げさではあるが、未だ食したことのない食品を発見した日には思わず購入してしまう衝動を抑えられない。
海岸沿いに、特にそのような食材が多いと思う。
「旅人は地元のスーパーへ行け!」これは旅の黄金律といっても過言ではないと信じる。
食材だけに及ばず、ホームセンターなどの道具類にも、同じような事が言える。
通常、平地の都市ではまったく使用しないような道具も、地元のホームセンターで発見できることがある。
雪深い土地では雪対策の道具が常備され、あるいは山深い土地では、林業に関する道具類が所狭しと並んでいたりもする。
また、妙にひなびた地元の雑貨屋などを見つけたなら、恥を忍んで一寸覗いてみるのも良い行動である。
店の奥にヒッソリと、埃を被ったまま死んだように眠り続ける昭和の道具達に遭遇する可能性も大きい。
昭和の時間が停止し凝固したような昭和の道具を発見した時など、使いもしないのに衝動買いし、後に後悔して落胆するのも旅の一部である。
そんな訳だから、名前も知らない未だ食していないような魚介類を七輪の網の上に乗せ、俺はジュウジュウ音をたたせながら焼いた。
魚の焼ける匂いと、醤油の焦げるいい匂いが、テントの周りに充満して、いやがうえのも食欲が増大してゆく。
匂いに吊られてか大沼さんや中上さんの友人や、友人の友人が集まり始め、そこいらは一大調理場と化した。
各自、思い思いの食材を調理し、料理の美味そうな香りと煙が、森の木々の間をユラユラと立ち上がってゆく。
森の中1人でジックリ孤独を楽しむアウトドアも良いが、こうやって大勢でワイワイ騒ぐアウトドアも、また楽しい。
飯盒がグツグツ煮えてきたので、逆さまにして蒸らす間に、魚や貝の海の幸を皿に盛り付けた。
カレーや味噌汁も出来上がったようだ。
「頂きます」の声もないまま、各自食事が始まってしまった。
誰だか知らないが、皿だけ持ってきてチャッカリ食事をしている輩もいる。
こう大勢居ると知り合いだかそうでないか判らないのだが、まあ、お祭り気分で許してしまおう。
食事が済み、食器を洗い、腹の虫も一段落したなら、俺は持ってきたギターをケースの中から出した。
そうすると、中上さんもすかさずギターを出し始め、これから盛り上がろうと考えているのだ。
こういう時にギターが弾けるというのは、とても重宝な才能であると思う。
どんな時にでも、ギターさえあれば退屈しない、そればかりか友人の輪も広がり、国籍すら超越してしまう。
本当に音楽、あるいは芸術というものは、人種や国籍を選ばないようだ。
70年代にラジオから流れていたロックやポップスは、ほぼ世界同時期で流行していた音楽である。
その共通の音楽を知っているというだけで、異国の人々に親近感を感じたりもする。
友人や友人の友人、友人の友人の友人が焚き火を囲んでのシング・アウト大会となった。
ボブ・ディランは言うに及ばず、70年代フォークの合唱の嵐となった。
誰かが「風に吹かれて」を歌い始めれば、誰彼ともなくハモッテしまう性分は、70年代を生きた世代の条件反射というべきものだろう。
懐かしい音楽というのは、何故こうも盛り上がってしまうのだ?
よく軍歌で盛り上がる高齢の集団を見かけるが、あれは戦争が懐かしいのではなく「青春」を懐かしんで歌うのだろうと思う。
「青春の歌」というのは、死ぬまで心の奥底に住み続け、時には生きる活力ともなる。
そんな沢山の歌を記憶していることに感謝したい。
歌の音や歌詞の襞の間に青春の出来事が事細かに住み着いている、そんな気がして心が熱くなる夜だった。
深夜近くなると一人抜け、二人抜け、焚き火の周りは、残り少ない人数となっていく。
暗闇の森の中、炭の赤い光が、各人の顔をユラユラと照らす。
焚き火の火も、チョロチョロと小さく燻ぶるような炎になっていき、「もう寝ろ!」と催促しているようだ。
もう少し唄っていたいと言うような、心残りを感じながら、我々はテントに入って寝た。
どこか遠くから聞こえる小さな咳払いの声が、森の静けさをより一層思い起こさせてくれるようだった。
台風で潰れたスケジュールをこなすために、朝早くからライブが始まっていた。
夕べ騒ぎすぎで、まだ重い眠い目をこすりながら、我々はテントから這い出し、顔を洗い、コンサート会場へと歩いていった。
会場への道を歩いて行く途中、あの転倒した黄色い軽のバンとすれ違った。
横のボディは凹んだままで、フロントガラスは全部取り外してあって、風通しが良さそうだ。
パフッ!とクラクションを鳴らしたのは、あの助けた髯男だった。
髯男の顔を見て俺はニヤリとして手を振った、髯男はクラクションを2度パフッパフッと鳴らし、俺の横をゆっくりと走り抜けていった。
会場には、朝も早いというのに、ステージの前は、もう数十人の観客達がライブを聞きながら踊っていた。
俺と中上さんは、昨日に場所にまた絵本を並べ、お祭り最後のピースアイランドを開店させた。
相変わらずダダ見客が多い本屋ではあったが、楽しそうに中上さんは店をキリモリしている。
徐々に店を開く人達も増え、ライブの観客も大勢になっていく。
最終日のコンサートは、盛り上がりと共に物寂しいような雰囲気も漂わせていた。
思えば、岐阜くんだりから遠路はるばるこの祭りにやってきたのだが、一気に起こった数々の出来事が旅の思い出としてどのようにインプットしたら良いのだろう。
これらは、まさに「無駄に中に価値が隠されている」という、哲学的命題の実践バージョンなのかもしれない。
あるは「青春」は永遠であるとの天啓か?
まぁ、物事は成るべくして成り、在るべくして在るということかもしれない。
突然、ステージのライブとライブの間の短い間に、ステージとは逆の方向に観客が集まっていった。
ザワザワと何かを見学しているようだった。
「何かあるのですか?」俺は、観客の一人に聞いてみた。
「パフォーマンスとかやってるみたいですよ」
「へぇ・・どんな、ハプニングなんですか」
「裸で、若い女が踊ってるそうですよ」
「ヌード・パフォーマンスですか・・・見たいなぁ!」
黒山の人だかりで、肝心なパフォーマンスが見られないのが歯がゆい。
そうこうしていると、裸体の女が踊りながらこちらの方向に移動してきた。
観客がモーゼの紅海の海割れのように左右に別れ、その真ん中をサロメのように踊りながら白い裸体が現れた。
このような裸体パフォーマンスをやる女というのは、70年代の生き残りのような年配の女傑が多いのであるが、その踊る女は意外にも若い女だった。
夏の眩しい太陽光線に黒光りする恥毛が眩しくて、目のやり場に困るが、ついついその部分に視線の焦点を当ててしまうのが男の性というもんである。
その全裸でクルクル踊る女は、アメノウズメのダンスのパフォーマンスをやっているのだそうだ。
真夏の大山の麓、現代版アメノウズメは、天照大神を目覚めさせたのではなく、男たちの情欲を目覚めさせただけのようであった。
中上さんも、いつの間にか現れた大沼さんも、みんなストリップ小屋の客のような表情で、そのパフォーマンスを凝視してた。
「ナンマンダブ・・ナンマンダブ・・・・・良いものを見せていただきました」
俺は、思わず拍手を打ち、八百万の神々に感謝したい心持になっていたのだった。
全裸パフォーマンスが終わってしまうと、群集はまた元のステージの方へと移動していった。
一瞬の出来事ではあるが、旅の思い出としては鮮烈なイメージを残したパフォーマンスであった。
昼過ぎになると、最後のミュージシャンのライブになった。
それまで出演したミュージシャンがすべてステージに上り、この「命の祭り」の大団円が始まった。
それを知ってか、大山山麓は凉風がゆっくりと吹き抜け、えもいわれぬ心地良い自然のオーラに包まれていくようであった。
I see my light come shining
From the west unto the east.
Any day now, any day now,
I shall be released.
ボブ・ディランの「I Shall Be Released」の大合唱で、大山の支離滅裂で魑魅魍魎なお祭りは終わりを告げたのだった。