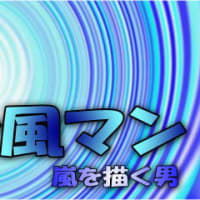見晴らし塔の男
男は、この工場に勤めて、もう40年以上になる。
工場は、小高い山の中腹にある。
セメントの材料となる石灰岩の採掘・加工工場である。
その現場の安全確保のための見張り番が、男の役目であった。
男は、10数メートルもある見張らし塔の上から、岩石を積載したトラックの行き交う光景を40年あまりも見続けてきた。
石灰岩を集める場所は数箇所あり、岩石の山の量を確認し、その結果を報告するのが日課であった。
高度成長期やバブル景気のころは、8時間の3交代制であったが、不景気が押し寄せてきた十年ほど前からは、男1人だけが工場の見張り番をしている。
見晴らし塔の中は4畳くらいの広さで、仮眠用のベッドや小型の冷蔵庫、また携帯ガスコンロまで設置してあり、内部だけでも生活はできた。
電話が設置されているので、業務連絡は、ここからしていた。
1日に1度は、食料や煙草や新聞を、事務員の女の子が運んできてくれるので、ここから出る必要もなかった。
「もう何年も地上には下りていないな・・」
男はしみじみ感じていた。
見張り番が男1人になってからというもの、この見晴らし塔の部屋から、随分長い時間下りていなかった。
下りようと思えばいつでも下りられた。
しかし、6,7年も前だろうか、たまに地上に下りてみたのだが、その時、足がすくみ動けなくなった経験が、男にはある。
建築物の屋根や塀が、自分より高いところにあり、自分が押しつぶされそうな恐怖を感じたからだ。
それ以来、男は地上に下りてはいないのだった。
今日も男は、眼下の岩石の山を見下ろしたり、遠くの風景を眺めたりしている。
塔の東側では、ブルドーザーやシャベルカーが、せわしなく作動し続ける、採掘現場の小高い山が見える。
西側は、遠くまで続く家々が建つ、町並みが見える。
それは、男が生まれ育った町でもある。
男がこの仕事を始めた頃は、高いビルなどなかったにの、今では、チクチクと空に突き刺さる針金のように高層ビルが建って、郷愁を忙殺させてしまっている。
そんな風景だったが、男はいつも思うのだった。
「手を伸ばせば、触れるようだなぁ・・・」
遠くの家々やビルや道は、天気の良い日など、遠近感を麻痺させ、手を伸ばせば触れるような錯覚を覚えさせる。
ここから空中を歩いて、すぐにでも遠くにたどり着けるような危険な感触を、心に生じさせてしまうのだ。
空気がとてつもなく澄んでいて、遠くと近くの区別がつかないのだ。
男は、この塔から、あの自分の生まれた町まで歩けるような気がした。
「町まで歩いていってみよう・・・」
その時の男の心の中には、空中を歩くという行為に、微塵の懐疑心も無かったからである。
男は唐突に、その高い塔の窓から出てみた。
塔から出した右足は、スポンジの上のように少し不安定だったが、フワッと男の体重を支えている。
左足も出してみた・・・
一瞬だけ沈んだ気配がしたが、空気がシッカリと男の体を抱きかかえているようだった。
二歩めも、フワッと少し沈み、空気のスポンジは男の体重を気にもしていないかのようだ。
三歩目、四歩目・・・・
まるで、果てしなく続く薄いスポンジの膜の上を歩いているようだ。
フワリフワリと、男は空中を散歩している。
強く足を下ろすと、下の方へ下がっていく。
軽く足を下ろすと、上に登っていった。
男は、空中を歩くコツを直ぐにつかんだようだ。
空気が足にまとわり付くので早くは歩けないが、こうやって空中を散歩できること自体が、すべてから開放された良い気分だった。
町の上空まで、歩いて来てしまった。
工場の有る小高い山から、一直線に歩いてきてしまったので、今居る高度は5・60メートルもあるかもしれない。
足の下には、道路や人が小さく動いているのが見える。
高いビルの屋上ならば、降りてみようかと思ったりもした。
学校帰りの小学生が数人、こちらを見て、男を指さしている。
そんな光景が、これが現実であることを認識させていた。
男は、手を振ってみたが、反応はなかった・・・
遠くで、何をしているのか判別がつかないのであろう。
男は、ふわふわと、また歩き続ける・・・
自分の生まれた家が見えた。
両親も他界し結婚もしていない男の家は、半分崩れかけ死にかけた動物のようにも見えた。
伸び放題の雑草の群れは、屍骸に手向けられた献花のようだった。
男の心が、急に悲しさを感じた。
子供のころの、幸福だった光景が目に浮かんだ。
あまりにも切なくて、その光景を消そうとしたが、心から離れなかった。
男は、耐えられない孤独感と後悔の念に襲われた。
人生を、無駄に過ごしてしまった・・・・
そんな、虚しく暗い幽霊が男を包み込んでしまうようだ・・・・・
心に感じていた開放感が、しだいに薄れ、重苦しい気分になっていくのを感じていた。
「ああ・・、もう、いい・・・はやく見晴らし塔に戻ろう・・・」
男は少し足早に、空間を歩いていく。
遠くから、カラスの鳴く声が、カアカアと悲しげに響いてくる。
回りの空気が、急に冷たくなったような感じがして、思わずポケットに手を突っ込んだ。
スポンジのような空気の膜が、妙にブヨブヨ粘りが出てきたような感触だ。
しばらく戻っていくと、見晴らし塔が見えてきた。
男は、少し安堵感を覚え、ほっとしてきたようだった。
カアカアとカラスの声が、大きく叫んでいる。
黒い影が、サァッっと、男の目の前を横切った。
また、もう一つの影が、男の顔を横切る・・・・
また、黒く素早い影・・・・!
何度も、男の目の前を横切る黒い影は、カラスの群れであった。
何匹も、何匹も、男の回りを取り巻くように、カラスが飛んでいる。
カラスの群れは、メリーゴーランドのように、男の体を中心に旋回を続けている。
男はポケットから手を出し、カラスを追い払おうとしたが、カラスの飛行の素早さには無抵抗だった。
カラスは亡霊のように、執拗に男をつけ狙っているようだ。
とっさに、1匹のカラス口ばしが、男の眼球めがけて突進してくるのが、男の網膜に映った。
彼の目玉の体液がブシュッと外部に漏れる音が、耳に聞こえた。
激痛と共に、男の心の中に疑いの念が、針のように刺さった!
「人間が、空を飛べるわけがない・・・・」
瞬間に、男の体は地面に叩きつけられ、骨や内臓が粉々になり潰れるのを感じた。
うわぁぁ~~!!
声にならない声が、見晴らし塔の狭い部屋の中に響いたようだった。
男は、仮眠用の簡易ベッドから、汗びっしょりになりながら、飛び起きたのだった。
「ああ・・・嫌な夢だった・・・」
男は、まだ現実感を取り戻せないまま、汗で濡れた額を拭いている。
「・・夢だったのか・・・・」
男は、ほんの少しだけ安心感を抱いている。
男は、ベッドから重い体を起こし、窓の外の風景を見回した・・・
「やはり、夢だったんだな・・・」
男は、そう思いながら、久しぶりに地上に下りてみる決心をしていた。
「地上に下りるのは、何年ぶりだろうなぁ。」
妙に感慨深げになっている自分の気持ちが、妙に可笑しいような心持だった。
もう、随分と開いたことの無いドアの取っ手を回し、外に出た。
男は、見晴らし塔の周りの壁面の螺旋階段を、下りていく。
クルクルと回りながら下りていく階段に、目が回ってしまうようだ。
地面に下りた男は、揺ぎ無い土の地盤に少々戸惑いなっがらも、土の匂いを嗅ぎ取っていた。
「土の匂いか・・・・久しぶりだな。」
なま暖かいようなやさしい風が、男の体を吹き抜けていく。
工場の中は静まりかえって、物音一つしていない。
「何か変だ・・」と、男は思った。
あの、機械の唸る音やトラックの音、人の話し声すら聞こえない。
時々、カンカンと、遠くから金属同士がぶつかる音が、かすかに聞こえるだけだった。
この工場内に、生きている気配がまったく無いのに、男は気がついていた。
見渡せば、ベルトコンベアーは微動だにせず、息絶えて硬直した蛇のようだった。
トラックの轍は、風雨にさらされ、形もさだかでない。
もう何年も使われていない、死んだ工場の成れの果ての姿のようだった。
トラックの行きかう工場の門は封鎖され、鉄の門柱は錆だらけで朽ち果てる寸前だった。
時折吹く風が、事務所と工場の機械の間で、小さな旋風を作っている・・・・
安全を謳う黄色い看板の人物は、錆に侵食され、怪物の絵ように見える。
風に飛ばされてきた新聞紙が、男の足にまとわりついた。
男は、その新聞を拾い上げ、読もうとした。
紙は黄ばんで、触るとボロボロと消滅しそうだった。
それでも男は、手に持ち広げ、新聞の日付に目をやった。
そして、仰天したのだった。
「昨日から、10年も経っている・・・」
脳の中の冷静な部分と混乱した部分とが、渦のようになり精神を攪乱させている。
混乱しながら、男は記事を読む・・・・
男は再び、仰天したのだった。
誰も気にしないような三面記事の片隅に、男の死亡記事が載っていた。
『 セメント工場の見張り塔から男性が転落死 』
そう、少し太いゴチック文字で見出しが載っている。
記事は、三行に満たない記事だったが、たしかに男の死亡を伝えている。
「・・俺は死んでしまったのか・・・」
男は、絶望し混乱し困惑した。
何十分か、何日か、数年、数十年か・・・・
あるいは、数秒にも満たない刹那の時間だったかもしれない。
しかし、死者に時間は無意味だ!
悩み続けているうちに、男はなんだか心のモヤモヤが吹っ切れて、心が晴れ晴れしていくように感じられたのだった。
そだ、あの空を飛んだときのような、開放された感覚と同じ感覚だった。
「同じだ・・生きてても、死んでも。」
男は、納得して安堵した。
「どうせ、見晴らし塔に居るだけの毎日だった・・」
「俺の世界は、あの塔の中だけにある!」
そう、思いが決まると、なんだか楽しい気持ちで心が満たされていくのを感じていた。
そうして、男は、朽ち果てていく廃工場の見晴らし塔のなかで、今日も下界を眺めている。
たぶん、宇宙が終るその日も、今日と同じように塔から世界を眺めているに違いない