2020/12/31(木) 13:45
田中良紹
(1969年TBS入社。ドキュメンタリー・ディレクターや放送記者としてロッキード事件、田中角栄、日米摩擦などを取材。
89年 米国の政治専門テレビC-SPANの配給権を取得。日本に米議会情報を紹介しながら国会の映像公開を提案。
98年CS放送で「国会TV」を開局。
07年退職し現在はブログ執筆と政治塾を主宰)
=
田中 良紹(たなか よしつぐ、1945年 - 76歳)は、日本のジャーナリスト。
宮城県仙台市出身。慶應義塾大学経済学部卒業。
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%94%B0%E4%B8%AD%E8%89%AF%E7%B4%B9
宮城県仙台市出身。慶應義塾大学経済学部卒業。
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%94%B0%E4%B8%AD%E8%89%AF%E7%B4%B9
<>
12月20日に『ジャパン・アズ・ナンバー・ワン』を書いた
エズラ・ボーゲル博士
<
エズラ・ファイヴェル・ヴォーゲル(Ezra Feivel Vogel、1930年7月11日 - 2020年12月20日[1]90歳没)は、アメリカ合衆国の社会学者。中国と日本を筆頭に東アジア関係の研究に従事した。中国名:傅 高義(フー・ガオイー)。
息子はカリフォルニア大学バークレー校教授のスティーヴン・ヴォーゲル
1972年から1977年まで東アジア研究所長、1977年から1980年まで東アジア研究評議会議長、1980年から1988年まで日米関係プログラム所長、1995年から1999年までフェアバンク東アジア研究センター所長などを歴任。
1979年に『ジャパン・アズ・ナンバーワン』を出版して日本でベストセラーになった。
2000年にハーバード大学を退職して以降、中華人民共和国の鄧小平の本格的な研究に取り組む。2011年に出版された『Deng Xiaoping and the Transformation of China』は中国語にも翻訳され(中国語タイトル:『鄧小平時代』)、中国大陸、香港、台湾など中華圏で100万部を超えるベストセラーとなった[2]。
2000年にハーバード大学を退職して以降、中華人民共和国の鄧小平の本格的な研究に取り組む。2011年に出版された『Deng Xiaoping and the Transformation of China』は中国語にも翻訳され(中国語タイトル:『鄧小平時代』)、中国大陸、香港、台湾など中華圏で100万部を超えるベストセラーとなった[2]。
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%A8%E3%82%BA%E3%83%A9%E3%83%BB%E3%83%B4%E3%82%A9%E3%83%BC%E3%82%B2%E3%83%AB
>
が90歳で亡くなった。ボーゲル博士はハーバード大学教授で中国問題の研究者だったが、1979年に『ジャパン・アズ・ナンバー・ワン』を出版し、日本で70万部を超える大ベストセラーとなった。
日本の高度経済成長の要因を分析した本だが、博士は日本人の学習意欲や読書量の多さに注目し、米国人にそれを教訓とするよう促している。世界一の経済大国である米国が日本を見習おうというのだから、日本人はこの本によって自信を与えられた。
しかしボーゲル博士は日本をただ賛美していたわけではない。私は博士から日本はまもなく没落するという予言を聞いた。1980年の秋ごろだったと思うが、博士が日本を訪れた際、直接お目にかかって2人だけで話をする機会に恵まれた。
場所は博士が泊まっていた東京六本木の国際文化会館だった。ラウンジでお会いしたのだが、博士が最初に私に言ったのは「ジャパン・イズ」ではなく「ジャパン・アズ」だということである。
つまり博士は「日本が一番」と断定しているわけではなく、米国民を発奮させる目的で「日本には一番と思えるところがある」と書いたのだと言う。それまで欧米諸国から「日本人はエコノミック・アニマル」と蔑まれていたから、日本人は自尊心をくすぐられたが、実は米国民に刺激を与え奮起させる目的の本だったのだ。
ただ博士は日本には優れたところがあると言い、それは日本は階級社会でないことだと言った。その例として取り上げたのが大平正芳総理と成田知巳社会党委員長の比較である。2人とも同じ香川県の出身で同世代だ。しかし2人の人生は対照的である。
大平は貧しい農家の生まれで、経済的に恵まれなかったため、苦学して現在の一橋大学に進んだ。官僚になる気はなかったが、同郷の大蔵次官に挨拶に行くと、即決で大蔵省に採用される。そして役所の先輩である池田勇人に誘われて政界入りし、田中角栄内閣の外務大臣として日中国交回復に貢献、田中の全面支援で1978年に総理大臣に上り詰めた。
一方の成田は、父親が市会議員で恵まれた境遇に生まれ、東京帝国大学に進学した秀才である。卒業後は三井鉱山に入社するが、戦後2回目の総選挙に社会党から立候補して初当選。一時は江田三郎の構造改革理論に共鳴するが、左派の社会主義協会とも近い立場を取り続け、1968年から77年まで社会党委員長を務めた。
ボーゲル博士は、貧しい農家に生まれた大平が、奨学金を得ながら苦学して大学に進学し、官僚となり、与党政治家となって、ついには総理大臣に上り詰めることができたケースを称賛した。その一方で、恵まれた生まれの成田が、社会主義思想を持ち、社会党委員長になったことにも注目する。そこに階級社会ではない日本の特質を見ていた。
そしてその柔軟さが日本の強さの秘密だと言った。ところがそれはまもなく終わる。まもなく日本にも階級社会が訪れると予言したのである。その原因を博士は「偏差値教育の導入にある」と言った。
「偏差値」は学力試験の志望校を判定するために導入された。模擬試験の得点などから各学校の「偏差値」が算出され、合格可能性が判定されて、生徒は教師から決められた学校の試験を受ける。そうなると小さな頃から将来の進路が決められてしまいかねない。
金持ちは小さなうちから子供の教育に資金をつぎ込み、エリートコースに乗れるようにする。そういう子供だけがエリートの道を歩み出せば、大平と成田に見られた人生航路はなくなる。そうなると日本の強さも薄れるというのである。博士は「日本は必ず没落する」と言った。
文部省担当の記者に「なぜ偏差値教育が始まったのか」を聞くと、息子や娘の「15の春を受験勉強で灰色にしたくない」という母親たちの声が教育現場を動かしたのだという。要するに「浪人生活を送らせたくない」という親心が、必ず合格できる学校を受けさせるために「偏差値」を必要にしたというのだ。
それはあまりにも近視眼的な考えではないかと私は思った。また自民党と社会党が対峙する当時の日本では、日本は階級社会でないと考える人間もいなかった。しかし私はボーゲル博士の考えに共鳴し、その予言が耳に残った。
以下下記URL参照











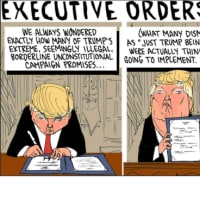

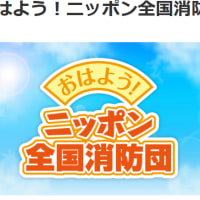


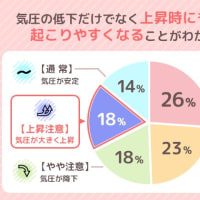


※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます