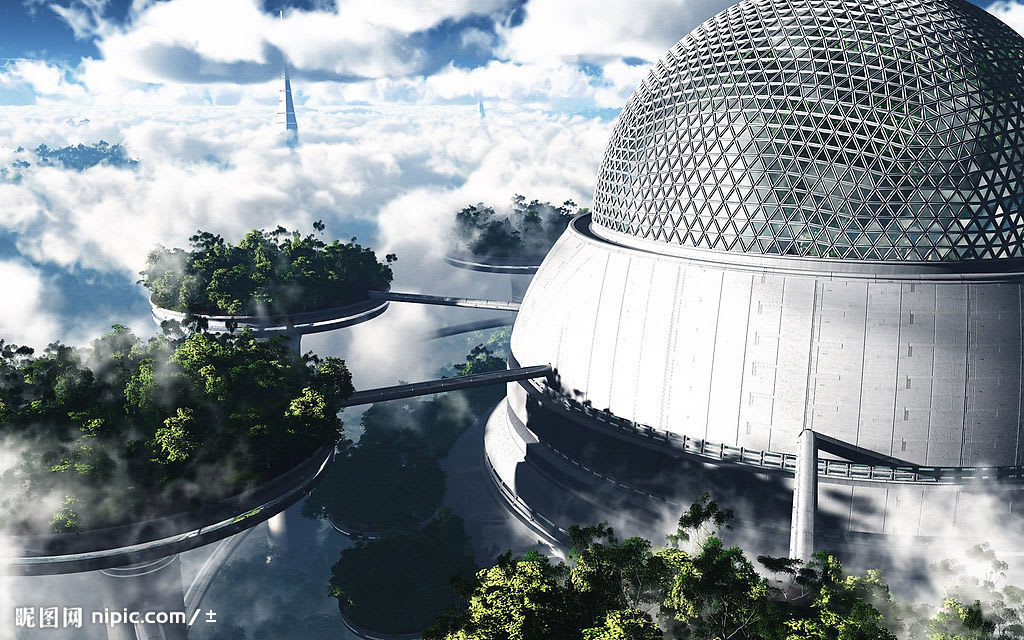姜尚中氏のベストセラーの続編『続・悩む力』に、次のことが書かれている。
『結論を先取りすると、人生に何らかの意味を見出せるかどうかは、その人が心から信じられるものをもてるかどうかという一点にかかわってきます。
「悪」に魅せられてそれに手を染めることも人生の意味だとは言いたくはありませんが、個人や集団に実害が及ばないなら、差し当たり何でもいいのです。
恋人でも、友でも、子供でも、妻でも、神でも、仕事でも。
というのも、何かを信じるということは、信じる対象に自分を投げ出すことであり、それを肯定して受け入れることだからです。
それができたときにはじめて、自分のなかで起きていた堂々めぐりの輪のようなものがブツリと切れて、意味が発生してくるのです。』
彼は、「信じる対象に自分を投げ出せば、生きる意味が発生する」と言っているが、私は彼が言っていることに賛同することはできない。
なぜなら、産まれて直ぐに亡くなる子には生きる意味はないのか?
また、一生、意識がなく寝たっきりの重度障害者には生きる意味はないのか?
私は、すべての人に生きる意味が発生する「生きる意味」でなければ、すべての人が納得するという普遍性のものにはなりえないと思う。
そして、私が求めている「生きる意味」は、そういうものである。
【閲覧者へのお願い】
忌憚(きたん)のないご批判も、大歓迎です。
お気づかいのなきよう、コメントして下さい。
『結論を先取りすると、人生に何らかの意味を見出せるかどうかは、その人が心から信じられるものをもてるかどうかという一点にかかわってきます。
「悪」に魅せられてそれに手を染めることも人生の意味だとは言いたくはありませんが、個人や集団に実害が及ばないなら、差し当たり何でもいいのです。
恋人でも、友でも、子供でも、妻でも、神でも、仕事でも。
というのも、何かを信じるということは、信じる対象に自分を投げ出すことであり、それを肯定して受け入れることだからです。
それができたときにはじめて、自分のなかで起きていた堂々めぐりの輪のようなものがブツリと切れて、意味が発生してくるのです。』
彼は、「信じる対象に自分を投げ出せば、生きる意味が発生する」と言っているが、私は彼が言っていることに賛同することはできない。
なぜなら、産まれて直ぐに亡くなる子には生きる意味はないのか?
また、一生、意識がなく寝たっきりの重度障害者には生きる意味はないのか?
私は、すべての人に生きる意味が発生する「生きる意味」でなければ、すべての人が納得するという普遍性のものにはなりえないと思う。
そして、私が求めている「生きる意味」は、そういうものである。
【閲覧者へのお願い】
忌憚(きたん)のないご批判も、大歓迎です。
お気づかいのなきよう、コメントして下さい。