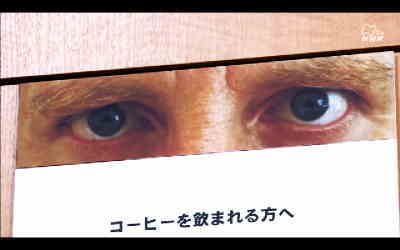プリンストン大学のリー・シルバー教授は著書『複製されるヒト』のなかで、遺伝子的強化の処置を施されて生まれる人々(遺伝子改良人間)のことを「ジーンリッチ」と呼び、この優れた人間集団がいずれ普通の人々である「ジーンプア」を置き去りにし、その結果、人類がふたつの種へと分岐していくことを懸念している。
そして、「ジーンリッチ」と「ジーンプア」の分岐は、最初は社会的なレベルではじまり、しだいに生物学的レベルにおよんで、ついにはホモ・サピエンスとは異なる新たな種を生み出すというのだ。
シルバー教授によると、このような分岐が人類に起こることは避けがたいという。
しかし、現時点では、子どもが特定の性質を持つように事前に遺伝子を設計することは、技術的にも倫理的にも強く問題視されている。
そして、「ジーンリッチ」と「ジーンプア」の分岐は、最初は社会的なレベルではじまり、しだいに生物学的レベルにおよんで、ついにはホモ・サピエンスとは異なる新たな種を生み出すというのだ。
シルバー教授によると、このような分岐が人類に起こることは避けがたいという。
しかし、現時点では、子どもが特定の性質を持つように事前に遺伝子を設計することは、技術的にも倫理的にも強く問題視されている。