8.厨川に散る
一気に書くつもりでいたのだが,2日空けてしまった。
・・・というのも,実は頼時が斃れ,頼義が吹雪の平原で惨敗を喫した黄海の戦いがあった天喜5(1157)年から康平5(1062)年まで,一体何があったのか浅学な私に皆目分からなかったからである。
2日間,家に有るだけの文献を漁り,ネットを駆使してみたが,結局何も無かった,というか,戦線が膠着し,束の間の平和が訪れたというべきなのかもしれない。
安倍氏としては,積極的に奥六郡から打って出て(既に奥六郡の南隣である磐井郡には,河崎柵という橋頭堡は築いていたが),栗原郡・新田郡(宮城県栗原市・登米市)を積極的に冒し,国府多賀城のある宮城郡へ押し出したりはしなかった(小競り合いはあっただろうが)。
これは,仮に頼義を斃したとしても,中央からの収奪者は必ずやってくるので,無駄に兵力を浪費せず,国力を充実させようとしたからかもしれない。
また,頼義としても,動くに動けない状況であったろう。
黄海の戦いは,頼時亡き後も安倍氏の士気は一向に衰えなかったことを示すと共に,源氏にとっては屈辱以外の何者でも無い惨敗となった。
齢70に近い頼義としても,よもや人生の終盤でこのような思いをするとは思わなかっただろう。
多分朝廷に奏上して,自己弁護と正当化,そして援兵をよこさぬ朝廷への責任転嫁をさかんに行ったのは間違いあるまい。
源氏の長としての矜恃が,からくも頼義を支えたのだろうか・・・。
いずれにしても,その後数年の奥州は,安倍氏の独立国の様相を呈し,頼義も幾度か再起を賭けて戦ったであろうが,安倍氏の優勢は変わらなかった。
その安倍氏の参謀格だったのが,経清であろう。
経清の命により,官物を徴納させたのである。
この時代を描いた軍記物のはしりともいうべき「陸奥話記」には,経清が「白符を用うべし」と命じたとある。
つまり,従来の官符たる赤符に替えて,経清が出した私符(白符)を-つまり,朝廷に徴税すべきものを,経清の命にて安倍氏が横取りした,と源氏の功績を伝えることが主たる「陸奥話記」は語る。
承平の乱における平将門を思わせる内容である。
将門は,官衙の鍵を奪い,板東の独立を図ったが,安倍氏もまた奥六郡の独立を図ったと言うべきだろう・・・。
局面が動いたのは,康平5年の7月以降である。
中央からの援兵も当てにならず,陸奥守としての任期も切れ(中央から高階経重が後継として赴任してきたが,すぐに追い返され,頼義が重任した。多分後継者に嫌がらせをして,諦めさせたのだろう),行き場の無くなった頼義のとった策は,出羽の俘囚の長である清原氏への援兵以来である。
臣従の例をとって,とあるが,頼義としてはこのまま帰京したりしたら,源氏の威勢は地に落ちるだけである。
なりふり構わず,清原を頼ったというべきだろう。
頼義が出した条件がどのようなものであったか,今となっては知るよしもないのだが,それは戦後処理から推し量るより他はあるまい・・・。
いずれにしてもこの年7月,出羽の清原氏が頼義の依頼によって動いた(当主光頼弟武則が兵を出した)。
清原・源氏両軍が合流したのは,栗原郡の営岡(たむろおか,たむろがおか)だったという。
これは,征夷大将軍坂上田村麻呂の故事にあやかったものらしい。
頼義軍は約2,000,清原軍はその数倍の軍勢だったという。
陣立てその他に二週間を費やした後,両軍は進発し,8月17日に安倍氏の前哨基地ともいうべき小松柵を攻め落とす。
頼義にとっては,初勝利である。
次いで9月5~6日は,衣川関に於いて両軍が激突。
貞任の善戦虚しく陥落。
頼義長子八幡太郎義家が,敗走する貞任に向けて,
「衣のたてはほころびにけり」
と詠ずると,貞任は,
「年を経し糸の乱れの激しさに」
と上の句を詠んで応えたという有名な故事が伝わるのは,この時のことである。
衣川関陥落後の安倍氏は脆かった。
黒沢尻柵,鳥海柵,鶴脛柵,比与鳥柵と立て続けに落ち,9月15日には奥六郡最北の岩手郡の厨川柵まで追い詰められた安倍軍は,最後の抵抗を試みる。
厨川柵は,日高見(北上)川と厨川(古代の雫石川)の合流点にあり,天険の要害であったという。
私など,てっきり現在の盛岡市にある厨川駅の近辺と思っていたが,大違いでもっと南の国道46号線沿線にある盛岡市天昌寺町付近と思われる。
その北に前九年,安倍舘町という,いかにもな町名があるが,これは厨川柵と連城を成す嫗戸柵があったかららしい。
川を外堀として,刃を上向きに底に立てたともいわれる。
当初は,攻め手も散々に悩まされたようだが,やがて清原軍が近隣の民家を破壊してそれを燃やす得意の火攻めに転じた結果,17日に厨川柵は陥落した。
大将である貞任は奮闘の後,倒れたところを戸板に乗せられて頼義の前に運ばれ,そこで息絶えたという。。
嫡子で13歳になる千世童丸と貞任弟重任も斬られた(重任は義家が討ったとも・・・)。
同じく弟の宗任・家任,叔父の良照は後に投降して,西国に配流となる(その子孫が,安倍晋太郎・晋三というから腹が立つ。しかも長州系だし・・・)。
とにかく,源氏と清原氏による安倍氏始末は苛烈を極めた。
柵内の非戦闘員は老若を問わず皆殺し。
妙齢の女は,兵たちに分け与えられたという。
では,経清はどうなったか。
逃げ遅れて捕らえられたとも,投降したとも言われるが,ここではやはり「炎立つ」にあるような頼義に近づくための投降説を採りたい。
頼義は恨み重なる経清に対し,自分に今一度仕えぬか,と度量の大きいところを見せる。
それに対して経清は,
「獣に仕える心は持ち合わせておりません」
と一蹴する(TV版では「豚め!!」と罵っていた)。
怒った頼義は,鈍刀をもって鋸引きの刑にする・・・。
康平5年9月17日。
奥六郡に覇を唱えた安倍氏は厨川柵に滅び,経清も逝った。
安倍氏が目指した奥六郡の独立は頓挫した。
経清には,貞任妹との間に一子があった(作中では清丸となっていた)。
安倍氏の血を引くその子の運命は・・・。










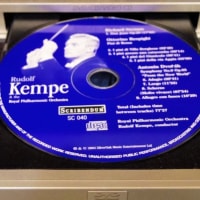
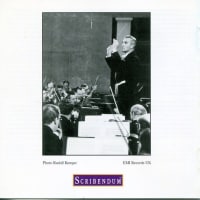
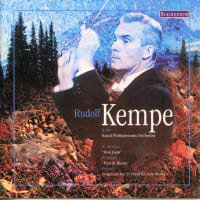







※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます