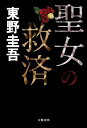ドラッグストアコスメといっても、何も特別なものではなく、資生堂とかコーセーとかカネボウとか、その多くが制度品の比較的リーズナブルな価格帯の商品を置いているだけだ。若干薬品系など毛色の変わったメーカーの商品もあるが、すごく個性的ではない。でも化粧品チャネルとしては注目されている。リーズナブルな商品がワンストップで揃うという意味では、以前からよく利用されていたが、最近はドラッグストア側が品揃えを増やして頑張っている感じだ。それは一つに来年の改正薬事法の施行で大衆薬がコンビニでも売れるようになるため、ドラッグストアが薬局として専門特化を追求する道を選ぶか、生活雑貨系、中でも化粧品で活路を見出すかの選択に迫られているためだ。うちの近所のそういう動きに敏感なチェーンストアは、早々に調剤薬局をおいた。一方で化粧品強化に向かう店舗も多い。薬局機能を強化すると、薬剤師を集めるコストと人材不足が課題となるからだ。
一方、消費者の立場でもドラッグストアの品揃えが豊富になり、買いやすくなることは歓迎だ。これまでのデパートや専門店の対面販売に辟易して、セルフ販売に流れる若い女性は増えていた。対面販売もスマートになった今はそうでもなく、使い分けをしている感じだ。私も百貨店コスメ中心で買っているが、随分ドラッグストアで買うものが増えた。マスカラやグロスなどの微妙な色味が関係ないが、消費の早いメイクアップ商品、クレンジングなどテクスチャーにこだわらない基礎化粧品、ブランド品を買うとバカ高い美容マスクなど。安くて済むものは安く済ませてこだわるものはこだわるという風に変わってきていると思う。
よくDMで美容クリームで5万円以上するブランド化粧品の案内が来る。私は買わないし買えないが、そういうものも結構売れているらしい。中途半端が厳しいというのは、他の商材でも言われることだが、化粧品は特にそうだと思う。よく今のように不景気になると、女性の美容への意欲は景気に連動しないので手堅いと言われるが、実際はどうなのだろう。確かに使用するのをやめることはしないが、徐々にシンプルに余計なものは使わないようになっている気がする。ドラッグストアが活況なのは、昔ながら専門店や訪問販売という業態がさまざまな理由で縮小しているという理由もある。街の電器屋さんがなくなっているように、街の資生堂やカネボウショップも少なくなっている。