作中、自らが江戸っ子であるかの如く語るエピソードも存在するが、パパの出身は熊本であり、実際にある菊池郡七城村立(現・菊池市立)七城中学校を卒業している。
七城中学校は、公立中学であるため、恐らくこの菊池郡(現・菊池市)周辺で生まれ育ったものと見ていいだろう。
因みに、この七城中学卒という経歴は、「長井リクツのクセなのだ」(「別冊少年マガジン」74年9月号)というエピソード内において、初めて語られたものだ。
これは、赤塚によって、アシスタントの出身中学の中で、東京から一番遠方にある所をパパの母校にしようという提案がなされた際、当時作画スタッフだった近藤洋助の出身地である七城中学校が選ばれ、生まれた設定である。(但し、七城中学校の創立年が1947年であるため、実際のパパの生年月日と重ね合わせると、タイムラグが生じる。)
一度決めたら梃子でも動かない、その妥協なき強情さ、また時折見せる天の邪鬼な性格ぶりは、日本三大頑固の一つ「肥後もっこす」に象徴される熊本人特有の県民性によるもので、パパは取り分け、肥後人としての血筋を色濃く引いているのではないかと思われる。
それを物語るパパの性格の一端に、一つのことに対し、徹底的に拘る粘着質的傾向が挙げられる。
パパの親族に関しては、前出のルーツ編二作で、一郎という名の父親(パパのパパ)と、パパにとって叔父に当たる一郎の実弟が登場しているものの、この時母親は、叔父の口から、三年前(1923年)からお産で入院しているといった情報しか語られておらず、パパの誕生後もその姿を表すことはなかった。
だが、その後描かれる「10本立て大興行」の一編「母をたずねて三千円」(72年51号)というエピソード内において、パパと母親が二〇年ぶりの再会を果たすことになる。
パパは、二〇年前、突然行方不明になった母を探し求め、流離いの旅路へと向かうが、その目的は、失踪前に母親に貸した三千円を返金してもらうためだった。
パパと母親が、再び巡り会えたその時、母親はパパを目の前にして、溢れんばかりの喜びを全身で表すが、パパは淡々と貸した三千円を返して欲しいとだけ言う。
その後も母親が、「なつかしくないのかえ?」と訊ねるも、パパは執拗に貸した三千円を要求する。
観念した母親は、パパに三千円を叩き付けるが、今度は元金三千円の利息分を請求され、またしてもパパは、母親に逃げられてしまうのだった。
もはや、この二人の間には、血の繋がった母と息子の絆や情愛など微塵もないが、ここで着眼すべきは、思い込んだら、猪突猛進する頑固一徹なパパの信念だ。
「これでいいのだ‼」と断定的に主張し、目的を完遂するためなら、どんな逆行も厭わない。
こうした直情径行に過ぎた行動を一つ取っても、肥後もっこすの精神が、その執念の根源に深く関わっているように思えてならない。
パパの肥後もっこすの精神が最も歪んだ形で表れたエピソードに、「未知との遭遇」(「月刊少年マガジン」78年4月号)がある。
その身体的特徴から、近所に住む星野というご老人を勝手に宇宙人だと思い込んだパパは、その正体を暴こうと、しつこく彼を追い回す。
当初は、「わしは人間だーっ‼」と、パパに食って掛かる星野氏であったが、それでも、宇宙人であることを信じて疑わないパパの激しい訊問に根負けし、遂にそのベールを脱ぎ捨てる。
「ウワーッハッハッ おみごと‼ 「地球のしつこいおじさん」」
「じつは わしが宇宙人だということを見やぶったのはこの八十年間にきみだけだ‼」
そうパパに言い放つと、星野氏は、人類の発展と地球の繁栄を祈願し、巨大円盤に乗って、地球を後にするのだった。
そう、肥後男児特有の激烈な気性を色濃く受け継ぎながらも、パパの勇往邁進なその肝魂には、このように妄想によって宇宙人をも追い詰めてゆく、恐るべき偏執病気質が軌を一にし、伏在していると見て間違いないだろう。










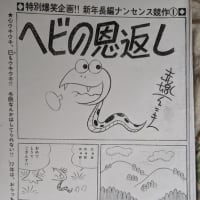
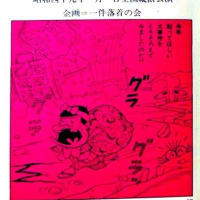




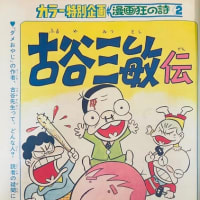



※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます