
※今年6月、ドネが「わかちあい」(寄付)させていただいた、
ミンダナオ子ども図書館↓松居友さんのお話のレポートです。
http://home.att.ne.jp/grape/MindanaoCL/
Nさんが丁寧に内容を書き起こしてくれました。
ありがとうございました!
多岐にわたる内容やテーマがつまっています。
当日来られなかった方にも読んでいただけます。
皆さんお時間のある時にゆっくり読んで下さいね。
あの日のゆったりした時間の流れを思いだします。
************************
◆ミンダナオ子ども図書館
松居友さんの話(2011・10・8) <報告>
10月8日、「ミンダナオ子ども図書館」の松居友さんのお話会がありました。
ミンダナオはフィリピン南端にある北海道ぐらいの大きさの島で、
「ミンダナオ子ども図書館」(略してMCL)は、2003年にフィリピンで発足した現地法人です。
松居さんは10年ほど前、落ち込んでミンダナオ島に行かれた時、
そこでの時間の流れや驚くほどに人の心を回復させる子どもたちの笑顔に慰められたそうです。
しかし偶然避難民キャンプに連れて行ってもらい、
地平線まで続く避難民の群れを見て(20万人だったのが50万人に膨れ上がった)、
そのあまりにもひどい状態に、子どもたちに笑顔が失われている事に、ショックうけられました、と。
子ども達のトラウマ解消に絵本の読み聞かせを3人の現地の若者達と一緒にし
(松居さんは言葉ができなかったので)し、
さらに病気の子にポケットマネーで治療を受けさせていると、
行政的許可がいると言われたそうです。
そこに病気の子どもたちがいるのに助けられないのは何と言う事だろうと思っていると、
現地の若者たちが法人資格を取ってくれてMCLが始まりました。
正式許可をとって8年、ミンダナオに行って10年になられます。
・・・・・・・・・・・・
・MCLは、1.5ヘクタールの農地内に宿泊できる建物があり、そこに図書室を持ち、住みこんでいる奨学生たちが、休日に僻村や難民キャンプに読み語りに行くという文化・教育活動を行っています。
住んでいるのは小学生から高校生・大学生の100人近い若者たちで、孤児・片親・崩壊家庭や学校までの距離が遠くて通えない山岳地域の先住民族、極貧家庭の子たちです。イスラム教・キリスト教・先住民族の若者たちが、仲良く共同生活を営んでいます。子どもたちが炊事、掃除、庭造り、家庭菜園作業等、生活全般の事を自律的に運営しています。
(子どもたちが本当にしっかりしています。子どもたちが全部してくれるから、朝4時から起きて炊事もしてくれてるので私は食べさせてもらってます、と松居さんは嬉しそうに言われます)
・MCLの活動は一本の木の様なイメージ、読み聞かせが中心の幹で医療・食糧とかの枝がある様な。
※映像を見ながらミンダナオの事やMCLの活動について、
松居さんのお話を聞きました
◆累計ではミンダナオは避難民世界一。
・「美しいところです、戦争さえなければ。」と松居さん。普段は平和な所なのに、戦闘がおこると別の世界になってしまう。「ここは文化の豊かな、マノボ族、イスラム、様々な民族の、音楽、文化、農業・自然の豊かな美しいところ。平和にさえなれば・・。」と。
・40年ほど前から数年ごと(5年おき位)に戦闘が起こっていて、今も続いている。
・和平会議があってもなかなか接点は見いだされない。
(映像では、人々が水牛の車に家財道具を載せて逃げていたり、MCLの人がビニールシートを届けていて、その背景から銃声が聞こえていました。)
・戦闘の後で支援が入って、道路が作られたりして、その中心部中心部に少しずつ広がっていきます。マキララという所では、戦闘があって3年間入れなくて、終わるとあっという間に道路ができていて、戦闘と支援が先住民を追い出すきっかけになっている。
・小規模な反乱、戦闘を繰り返されることで 、先住民は自分の土地に入れなくなって、戦闘が終わって帰ると荒れていて、お金は全くないので安い値で売り飛ばすしかなくて、豊かな土地と林業を持っていた先住民がどんどん山へ追いやられ 、どんどん貧しくなっていく。
・難民2000人だったのが50万人に膨れ上がる(普通ならそんなことにはならない)。小さな小競り合いはあるけど、本来ならそれほど大きくはならない。非常に計画的力が働いて作られている。常に(戦闘になるよう)用意されているよう。火付け役があるだけで、反政府軍を挑発して、後は国軍の参戦用意されている。小規模な戦闘が繰り返されて、先住民族は自給地を手放さざる負えなくなる。土地は移民系の地域有力者の物になってしまう。
・戦争は勃発するのではなく、非常に計画的に作られている。火種にされるのが対立です(イスラム教徒とキリスト教徒等)。イラク・アフガンも、海外でも同様に戦争が作られている、それが私の印象です。
・理由は石油です。膨大な石油と天然ガスをどこが持つかが。絶えず利権が働いている。
・生まれながらの奇形のある子、多いです。(米軍の)ヘリコプターからの爆撃のあった直後から、当時妊娠中の母親から生まれた子供達に多いようです。劣化ウラン弾のせいではないかと思います。竹の家を攻撃するのに貫通力は必要ないのに貫通力の高い劣化ウラン弾がどんどん使われた。
「あんまりだよね、不安ですね、原発のあれは(福島原発の事故)、劣化ウラン弾は体に影響ないレベルと言われているのに、それであれだからね。」
・日本に帰国される前、8月ごろにも戦闘が勃発していて、不安定で危険と聞いて今心配しています、と松居さん。現地で見てると、私は武器では解決しないと思います、と。
◆洪水・貧困
・洪水がひどいです。今年は雨がひどかった。
・洪水の起こる原因は上流の森林の伐採です。伐採がひどくて、上流に木が無くて草原です、
・ラワンはものすごく高い木ですが、殆ど伐採された(残っているのは6%)、殆ど日本に輸出されました。日本は自分達の木(杉とか)を残してフィリピンから買ったのだけど、現地の人は日本には木が無いから日本は木を輸入したのだと本気で思っています。
・上流に日本政府が作ったダムがあり、大雨で一斉放水すると、土地のない人は川沿いにいて、そこがいっぺんに流される。農業用水で田が増えるのはいいが、田を持っているのはお金持ち。貧しい人は川のそばで魚を採って暮らしている、そこに被害が出る。魚が取れなくなったり、家が洪水にあったり。支援の仕方難しいです。
・下流のスラム地域、トウモロコシも全滅です、床上まできます。水草が引っ掛かって家が傾いて、可也の人が死んで、その多くが子供、泳げないから。
・こんなところで(川の側)家が崩壊したら危険、赤ちゃんが川に落ちるかと心配。
・マノボ地域、追われた難民です。非常に貧しいです。大変だけど一生懸命生きているから、助け合って生きてるから、明るさが違う。川を渡るのに、小さい子が小さい子をおんぶして、よくやると思います。困ってるとああしてちゃんと助けるんです。本当にここの方が心癒される、。
川の水が少ない時はいいけど、大水の時小さい子が学校に行くのに川を渡るのが心配です。
靴が無いんです、それから着る物のない子もいます。
・エルニーニョのひどい年は芋も育たなくて本当にかわいそうでした。現実は厳しいですね。(家族が多いと食べられないから)14歳くらいで結婚する子が多いです。危険な地域で、役所の人も行かない、私達は行ける、私達と一緒なら大丈夫なんです。
・家族の捕った魚や、ホーキ等を町に売りに行ってわずかな銭を稼いでいる。
・食べられなくて、クリスマス頃にはダバオの道路に子どもたちが物乞いに。・素朴な生活です、皆魚を採って暮らしています。でも、戦闘が起こるたび自分の家を捨てて、帰ってくる頃は竹の家なのでボロボロになって、毎年繰り返されるとつらくなって町に出る人もいる。
・小学1年になる年で入学の手続きをするのだけど、2年半ぐらいなると。お弁当をもっていかないといけなくなると、お弁当持っていけないので、ここで学校に行くのは止まります。6年まで行って卒業できる子は20%です。
・山の奥の世界になると、もう何が起こっているか分からない。
・病院にかかることも考えられない貧困層が80%、村で病気になるとに頼む祈祷師(薬草を使う。)に頼む。それでだめなら死を覚悟するしかない。病院に入ろうとするだけでもお金がかかる。お金があれば治療は受けられる。
・もともと住んでいた土地から追いやられたマノボ先住民、屋根もほとんどない家に住み、靴が無くて殆ど裸足です。
◆海外から
・高原バナナは殆ど日本に輸出されます。日本の新聞が使われているこの広大なプランテーションの奥に先住民は追いやられている。国道からはプランテーションの奥は見えないが、そこに先住民が住んでいる。
・輸出用バナナの(外資系の巨大な)プランテーションのバナナの木の下は下草が無い、除草剤とか農薬とかを防毒マスクをつけて作業する。薬の空中散布で亡くなったおじさんがいて、裁判所に訴えたらと言っても、そうすると刺客に殺されるからと訴えられなかった、本当の話です。5年契約で、5年たつと戻されるけど、5年たつと化学肥料で土地が死んでしまっている。他にもニッケル鉱山から公害の水が出るとかいう事が起こっています。
・土地登記をしてないので(登記にお金がかかるのにお金がないから)、現地で何が起こったか、先住民族が終われたかどうかは、商社には分かりようがない、人々は自給自足で住んでるだけだから。
◆救済活動
・難民状態での洪水です。難民キャンプといってもテントではなくてバナナの葉の屋根だけがある所に人々がいる。そこに降る熱帯の雨は本当に凄いので、兎に角、次から次へとビニールシートを張っていく。
・雨の多いところなので、難民化した最初の1~2週間が重要なのだけど、国際的NGOはその頃は協議の段階で1ヶ月くらいは入れない。でも、私達は近いところにいるので、すぐに入れます。
・3~5年ごとに戦闘、小さな戦闘は今も山岳地域で毎年ある。そういう連絡が来ると、とにかく走る,そしてそこに行く。
・一週間~一ヶ月後くらいから病気の問題が出てくる。お腹を壊す、下痢・高熱など。そして3~4カ月後からは食糧問題、食べ物なくて体弱って病気になり易い。
・国際停戦監視団の人も私の案内で現地に行くのだけど、みんな車の窓を締めていく。MCLでは車の窓開けていきます。その地域の子供達がいるので、そういった地域からスカラシップ採ってるので大丈夫です。ふつうのNGOなら危なくて入れない所と既に関係を持っているので、国際的なNGOや監視団の入れないところでも、入れます。
・戦闘で難民化して家に戻れないと聞くと、炊き出しして行に行きます。
・本来殆ど外国人が入れない所で、考えると怖いですが、行かなくっちゃみたいな感じです。・こういう関係を8年間続けてきてるから、彼らもMCLのことよく知ってて、漸く信頼してくれていると言う感じです
・イスラム地域があって、殆ど報道されないし、国際的な援助も入らない。MCLだけです、スカラーがいるので大変な状況が分かり支援ができる。イスラム自治区の最も危ない入れない所にも入ってます
・僻村は美しいところですが、電気も何もない。学校が遠くて通えないので下宿小屋を建てました。それで学校に通えるようになりました。
・マノボ集落、こないだ保育所を作った、裏が原生林、これが本当のジャングル、凄い滝、道が殆どなくて、岩を登ったり、していきます。
・アポ山、3000メートル弱の山、頂上付近はブルーベリーが一杯です、こういう所に保育所を建てるんです。
・4輪駆動でも行けない所で、ちょっと雨が降っても動けなくなって、でも村人達が大勢駆けつけてくれて、車を動かしてくれる。凄い所に住んでいる。
・イスラム地域のマノボ族、非常に厳しい状況に置かれている。
保育所に行かないと小学校に行けないと言う法律を2年前に政府が出してから保育所が足りなくて。
既に40件くらい建てたかな、30万円で建ちます。
・丘の上にクリスチャン、下にイスラム教徒、40年以上前は道があって一緒にバスケットをしてたのが、40年間対立していた。それが共通の小学校を作ることで仲良くなった。みんなで必死で話し合いをして。
JAICA(日本の皆さんの税金で)で下のブアランに小学校を建てた。上のクリスチャンは下のイスラムが入ってきたら殺すと言う状態だった、下のイスラムに既にスカラーがいて、読み聞かせの事は上のクリスチャンにも伝わっていたので、そこから。四月着工で十月完成の予定が、両方の親が一緒になって大勢で働いたから、八月に完成した。びっくりした。上と下の村をつなぐ道路も作った。子どもの為だったら大人はなかよくなれる。
・正確な数字(人数)は分からない。出生届にお金がかかるので。届けに町まで行くのにも交通費がかかるし。小学校になる頃に私達が出生届を出す。鉛筆一本買えない、貧しくて。MCLの子たちが隔月に行って学用品を渡している。
・直接子供たちに渡します、必要としてる人に必ず渡る様に。新品で無くていいので、服でも靴でもおもちゃでもお鍋でも送ってください。服も、学校にはいていく靴も無い子たちなので、役に立ちます、喜ばれます。
・日本の立正佼成会の子どもたちから「夢ぽっけ」(手作り巾着の中に学用品とおもちゃが入っている)が届けられて、受け取った子ども達は嬉しそう。。
・皆さん(ドネーションシップわかちあい)からの寄付は洪水支援で使われました。あれは本当に助かりました。みなさんのカンパで買ったシート、何度も配りに行きました、400世帯かな、凄い雨なので、雨が乾いても穀物を干したり使えるので、とても喜ばれました。
◆MCLは医療活動の許可も得ています
・軍用車に撥ねられた子どもや病気や怪我、子先天的奇形のある子などの、軽度から重い手術まで年間約300人近くの子の治療をしている、貧しいから病院に行くのは不可能、薬も買えない。
・事情を分かってボランティアで来てくれるお医者さんがいる。。
・治療が終わるまで、最後のチェックまで、治るまで見ます。貧しくて町まで出るお金も無いし薬も買えない状態の人たちなので、大変です、医療は。
・お医者さんに説明するのもします。現地の人々は言葉が通じない(公用語ができない)ので、松居さんやスカラーの子が行って説明します。
(続く)
松居友さんの話2
http://blog.goo.ne.jp/donationship/e/8d3a8255709fc4203fe24e95010f2f2d
松居友さんの話3
http://blog.goo.ne.jp/donationship/e/1675832f8f3d21279104962a5a879035
ミンダナオ子ども図書館↓松居友さんのお話のレポートです。
http://home.att.ne.jp/grape/MindanaoCL/
Nさんが丁寧に内容を書き起こしてくれました。
ありがとうございました!
多岐にわたる内容やテーマがつまっています。
当日来られなかった方にも読んでいただけます。
皆さんお時間のある時にゆっくり読んで下さいね。
あの日のゆったりした時間の流れを思いだします。
************************
◆ミンダナオ子ども図書館
松居友さんの話(2011・10・8) <報告>
10月8日、「ミンダナオ子ども図書館」の松居友さんのお話会がありました。
ミンダナオはフィリピン南端にある北海道ぐらいの大きさの島で、
「ミンダナオ子ども図書館」(略してMCL)は、2003年にフィリピンで発足した現地法人です。
松居さんは10年ほど前、落ち込んでミンダナオ島に行かれた時、
そこでの時間の流れや驚くほどに人の心を回復させる子どもたちの笑顔に慰められたそうです。
しかし偶然避難民キャンプに連れて行ってもらい、
地平線まで続く避難民の群れを見て(20万人だったのが50万人に膨れ上がった)、
そのあまりにもひどい状態に、子どもたちに笑顔が失われている事に、ショックうけられました、と。
子ども達のトラウマ解消に絵本の読み聞かせを3人の現地の若者達と一緒にし
(松居さんは言葉ができなかったので)し、
さらに病気の子にポケットマネーで治療を受けさせていると、
行政的許可がいると言われたそうです。
そこに病気の子どもたちがいるのに助けられないのは何と言う事だろうと思っていると、
現地の若者たちが法人資格を取ってくれてMCLが始まりました。
正式許可をとって8年、ミンダナオに行って10年になられます。
・・・・・・・・・・・・
・MCLは、1.5ヘクタールの農地内に宿泊できる建物があり、そこに図書室を持ち、住みこんでいる奨学生たちが、休日に僻村や難民キャンプに読み語りに行くという文化・教育活動を行っています。
住んでいるのは小学生から高校生・大学生の100人近い若者たちで、孤児・片親・崩壊家庭や学校までの距離が遠くて通えない山岳地域の先住民族、極貧家庭の子たちです。イスラム教・キリスト教・先住民族の若者たちが、仲良く共同生活を営んでいます。子どもたちが炊事、掃除、庭造り、家庭菜園作業等、生活全般の事を自律的に運営しています。
(子どもたちが本当にしっかりしています。子どもたちが全部してくれるから、朝4時から起きて炊事もしてくれてるので私は食べさせてもらってます、と松居さんは嬉しそうに言われます)
・MCLの活動は一本の木の様なイメージ、読み聞かせが中心の幹で医療・食糧とかの枝がある様な。
※映像を見ながらミンダナオの事やMCLの活動について、
松居さんのお話を聞きました
◆累計ではミンダナオは避難民世界一。
・「美しいところです、戦争さえなければ。」と松居さん。普段は平和な所なのに、戦闘がおこると別の世界になってしまう。「ここは文化の豊かな、マノボ族、イスラム、様々な民族の、音楽、文化、農業・自然の豊かな美しいところ。平和にさえなれば・・。」と。
・40年ほど前から数年ごと(5年おき位)に戦闘が起こっていて、今も続いている。
・和平会議があってもなかなか接点は見いだされない。
(映像では、人々が水牛の車に家財道具を載せて逃げていたり、MCLの人がビニールシートを届けていて、その背景から銃声が聞こえていました。)
・戦闘の後で支援が入って、道路が作られたりして、その中心部中心部に少しずつ広がっていきます。マキララという所では、戦闘があって3年間入れなくて、終わるとあっという間に道路ができていて、戦闘と支援が先住民を追い出すきっかけになっている。
・小規模な反乱、戦闘を繰り返されることで 、先住民は自分の土地に入れなくなって、戦闘が終わって帰ると荒れていて、お金は全くないので安い値で売り飛ばすしかなくて、豊かな土地と林業を持っていた先住民がどんどん山へ追いやられ 、どんどん貧しくなっていく。
・難民2000人だったのが50万人に膨れ上がる(普通ならそんなことにはならない)。小さな小競り合いはあるけど、本来ならそれほど大きくはならない。非常に計画的力が働いて作られている。常に(戦闘になるよう)用意されているよう。火付け役があるだけで、反政府軍を挑発して、後は国軍の参戦用意されている。小規模な戦闘が繰り返されて、先住民族は自給地を手放さざる負えなくなる。土地は移民系の地域有力者の物になってしまう。
・戦争は勃発するのではなく、非常に計画的に作られている。火種にされるのが対立です(イスラム教徒とキリスト教徒等)。イラク・アフガンも、海外でも同様に戦争が作られている、それが私の印象です。
・理由は石油です。膨大な石油と天然ガスをどこが持つかが。絶えず利権が働いている。
・生まれながらの奇形のある子、多いです。(米軍の)ヘリコプターからの爆撃のあった直後から、当時妊娠中の母親から生まれた子供達に多いようです。劣化ウラン弾のせいではないかと思います。竹の家を攻撃するのに貫通力は必要ないのに貫通力の高い劣化ウラン弾がどんどん使われた。
「あんまりだよね、不安ですね、原発のあれは(福島原発の事故)、劣化ウラン弾は体に影響ないレベルと言われているのに、それであれだからね。」
・日本に帰国される前、8月ごろにも戦闘が勃発していて、不安定で危険と聞いて今心配しています、と松居さん。現地で見てると、私は武器では解決しないと思います、と。
◆洪水・貧困
・洪水がひどいです。今年は雨がひどかった。
・洪水の起こる原因は上流の森林の伐採です。伐採がひどくて、上流に木が無くて草原です、
・ラワンはものすごく高い木ですが、殆ど伐採された(残っているのは6%)、殆ど日本に輸出されました。日本は自分達の木(杉とか)を残してフィリピンから買ったのだけど、現地の人は日本には木が無いから日本は木を輸入したのだと本気で思っています。
・上流に日本政府が作ったダムがあり、大雨で一斉放水すると、土地のない人は川沿いにいて、そこがいっぺんに流される。農業用水で田が増えるのはいいが、田を持っているのはお金持ち。貧しい人は川のそばで魚を採って暮らしている、そこに被害が出る。魚が取れなくなったり、家が洪水にあったり。支援の仕方難しいです。
・下流のスラム地域、トウモロコシも全滅です、床上まできます。水草が引っ掛かって家が傾いて、可也の人が死んで、その多くが子供、泳げないから。
・こんなところで(川の側)家が崩壊したら危険、赤ちゃんが川に落ちるかと心配。
・マノボ地域、追われた難民です。非常に貧しいです。大変だけど一生懸命生きているから、助け合って生きてるから、明るさが違う。川を渡るのに、小さい子が小さい子をおんぶして、よくやると思います。困ってるとああしてちゃんと助けるんです。本当にここの方が心癒される、。
川の水が少ない時はいいけど、大水の時小さい子が学校に行くのに川を渡るのが心配です。
靴が無いんです、それから着る物のない子もいます。
・エルニーニョのひどい年は芋も育たなくて本当にかわいそうでした。現実は厳しいですね。(家族が多いと食べられないから)14歳くらいで結婚する子が多いです。危険な地域で、役所の人も行かない、私達は行ける、私達と一緒なら大丈夫なんです。
・家族の捕った魚や、ホーキ等を町に売りに行ってわずかな銭を稼いでいる。
・食べられなくて、クリスマス頃にはダバオの道路に子どもたちが物乞いに。・素朴な生活です、皆魚を採って暮らしています。でも、戦闘が起こるたび自分の家を捨てて、帰ってくる頃は竹の家なのでボロボロになって、毎年繰り返されるとつらくなって町に出る人もいる。
・小学1年になる年で入学の手続きをするのだけど、2年半ぐらいなると。お弁当をもっていかないといけなくなると、お弁当持っていけないので、ここで学校に行くのは止まります。6年まで行って卒業できる子は20%です。
・山の奥の世界になると、もう何が起こっているか分からない。
・病院にかかることも考えられない貧困層が80%、村で病気になるとに頼む祈祷師(薬草を使う。)に頼む。それでだめなら死を覚悟するしかない。病院に入ろうとするだけでもお金がかかる。お金があれば治療は受けられる。
・もともと住んでいた土地から追いやられたマノボ先住民、屋根もほとんどない家に住み、靴が無くて殆ど裸足です。
◆海外から
・高原バナナは殆ど日本に輸出されます。日本の新聞が使われているこの広大なプランテーションの奥に先住民は追いやられている。国道からはプランテーションの奥は見えないが、そこに先住民が住んでいる。
・輸出用バナナの(外資系の巨大な)プランテーションのバナナの木の下は下草が無い、除草剤とか農薬とかを防毒マスクをつけて作業する。薬の空中散布で亡くなったおじさんがいて、裁判所に訴えたらと言っても、そうすると刺客に殺されるからと訴えられなかった、本当の話です。5年契約で、5年たつと戻されるけど、5年たつと化学肥料で土地が死んでしまっている。他にもニッケル鉱山から公害の水が出るとかいう事が起こっています。
・土地登記をしてないので(登記にお金がかかるのにお金がないから)、現地で何が起こったか、先住民族が終われたかどうかは、商社には分かりようがない、人々は自給自足で住んでるだけだから。
◆救済活動
・難民状態での洪水です。難民キャンプといってもテントではなくてバナナの葉の屋根だけがある所に人々がいる。そこに降る熱帯の雨は本当に凄いので、兎に角、次から次へとビニールシートを張っていく。
・雨の多いところなので、難民化した最初の1~2週間が重要なのだけど、国際的NGOはその頃は協議の段階で1ヶ月くらいは入れない。でも、私達は近いところにいるので、すぐに入れます。
・3~5年ごとに戦闘、小さな戦闘は今も山岳地域で毎年ある。そういう連絡が来ると、とにかく走る,そしてそこに行く。
・一週間~一ヶ月後くらいから病気の問題が出てくる。お腹を壊す、下痢・高熱など。そして3~4カ月後からは食糧問題、食べ物なくて体弱って病気になり易い。
・国際停戦監視団の人も私の案内で現地に行くのだけど、みんな車の窓を締めていく。MCLでは車の窓開けていきます。その地域の子供達がいるので、そういった地域からスカラシップ採ってるので大丈夫です。ふつうのNGOなら危なくて入れない所と既に関係を持っているので、国際的なNGOや監視団の入れないところでも、入れます。
・戦闘で難民化して家に戻れないと聞くと、炊き出しして行に行きます。
・本来殆ど外国人が入れない所で、考えると怖いですが、行かなくっちゃみたいな感じです。・こういう関係を8年間続けてきてるから、彼らもMCLのことよく知ってて、漸く信頼してくれていると言う感じです
・イスラム地域があって、殆ど報道されないし、国際的な援助も入らない。MCLだけです、スカラーがいるので大変な状況が分かり支援ができる。イスラム自治区の最も危ない入れない所にも入ってます
・僻村は美しいところですが、電気も何もない。学校が遠くて通えないので下宿小屋を建てました。それで学校に通えるようになりました。
・マノボ集落、こないだ保育所を作った、裏が原生林、これが本当のジャングル、凄い滝、道が殆どなくて、岩を登ったり、していきます。
・アポ山、3000メートル弱の山、頂上付近はブルーベリーが一杯です、こういう所に保育所を建てるんです。
・4輪駆動でも行けない所で、ちょっと雨が降っても動けなくなって、でも村人達が大勢駆けつけてくれて、車を動かしてくれる。凄い所に住んでいる。
・イスラム地域のマノボ族、非常に厳しい状況に置かれている。
保育所に行かないと小学校に行けないと言う法律を2年前に政府が出してから保育所が足りなくて。
既に40件くらい建てたかな、30万円で建ちます。
・丘の上にクリスチャン、下にイスラム教徒、40年以上前は道があって一緒にバスケットをしてたのが、40年間対立していた。それが共通の小学校を作ることで仲良くなった。みんなで必死で話し合いをして。
JAICA(日本の皆さんの税金で)で下のブアランに小学校を建てた。上のクリスチャンは下のイスラムが入ってきたら殺すと言う状態だった、下のイスラムに既にスカラーがいて、読み聞かせの事は上のクリスチャンにも伝わっていたので、そこから。四月着工で十月完成の予定が、両方の親が一緒になって大勢で働いたから、八月に完成した。びっくりした。上と下の村をつなぐ道路も作った。子どもの為だったら大人はなかよくなれる。
・正確な数字(人数)は分からない。出生届にお金がかかるので。届けに町まで行くのにも交通費がかかるし。小学校になる頃に私達が出生届を出す。鉛筆一本買えない、貧しくて。MCLの子たちが隔月に行って学用品を渡している。
・直接子供たちに渡します、必要としてる人に必ず渡る様に。新品で無くていいので、服でも靴でもおもちゃでもお鍋でも送ってください。服も、学校にはいていく靴も無い子たちなので、役に立ちます、喜ばれます。
・日本の立正佼成会の子どもたちから「夢ぽっけ」(手作り巾着の中に学用品とおもちゃが入っている)が届けられて、受け取った子ども達は嬉しそう。。
・皆さん(ドネーションシップわかちあい)からの寄付は洪水支援で使われました。あれは本当に助かりました。みなさんのカンパで買ったシート、何度も配りに行きました、400世帯かな、凄い雨なので、雨が乾いても穀物を干したり使えるので、とても喜ばれました。
◆MCLは医療活動の許可も得ています
・軍用車に撥ねられた子どもや病気や怪我、子先天的奇形のある子などの、軽度から重い手術まで年間約300人近くの子の治療をしている、貧しいから病院に行くのは不可能、薬も買えない。
・事情を分かってボランティアで来てくれるお医者さんがいる。。
・治療が終わるまで、最後のチェックまで、治るまで見ます。貧しくて町まで出るお金も無いし薬も買えない状態の人たちなので、大変です、医療は。
・お医者さんに説明するのもします。現地の人々は言葉が通じない(公用語ができない)ので、松居さんやスカラーの子が行って説明します。
(続く)
松居友さんの話2
http://blog.goo.ne.jp/donationship/e/8d3a8255709fc4203fe24e95010f2f2d
松居友さんの話3
http://blog.goo.ne.jp/donationship/e/1675832f8f3d21279104962a5a879035










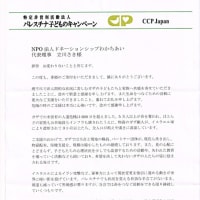















※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます