ポーが見た未来世界(1)の続きです。
『メロンタ・タウタ(Mellonta Tauta)』は語り手の手紙という形式ですが、語り手の正体、と言わぬまでも語り手の人物像というものははっきりとは描写されていません。これは本作品に限りません。ポーの多くの作品は"私"という一人称の語り手により語られるものが多いのですが、その語り手の人物像ははっきりしないことがほとんどです。まあ自然と言えば自然です。それでも語り手がどんな立ち位置の人物なのかは想像したり推定したりすることは可能で、それもポーの作品の楽しみのひとつになりそうにも思えます。
『メロンタ・タウタ』の語り手は「その全部が娯楽旅行のつもりで乗っている(ある人々は娯楽というものについてなんと奇妙な考えを持っていることだろう!)百人か二百人の愚民」と気球に同乗していますが、話し相手は昔のことしか話さないパンディットという名の人物ただ一人だけです。といいつつ船長とは気球の材料の話をしていますが。
パンディットは非常に物知りですが昔のことにしか興味がないようです。現代のSF作品の中なら「パンディットはもしかして人工知能か?」と疑うところですが、コンピュータも知られていない時代にそれはないでしょう。パンディットは語り手と同類のただの人類の一員と思われます。そして語り手とパンディットとの詳しい関係も不明ですが、最後の方では、『E・A・ポー ポケットマスターピース09 (集英社文庫 ヘリテージシリーズ)』(2016/6/23)収録の『お前が犯人だ!--ある人のエドガーへの告白--』(桜庭一樹による翻案)[*1]で桜庭が仕掛けたトリックと同じトリックが仕掛けられている・・ような気がします。「それでどなうなるの?」ということではあるけれど。そもそも語り手の私生活は何も描写されず、仕事・家庭・男女関係・親子関係などというものが19世紀のアメリカとは全くかけ離れているのかも知れないのですが、その実態は闇の中です。
さてこの気球船には船長のものとして琴座アルファ星の黒点まで見えるほどの超高性能望遠鏡(our captain’s spy-glass)が載せてあるのですが、この星とわれらが太陽とが連星関係にあるという2848年での定説が語られます。このことが明らかになったのは前世紀つまり2700年代のこと。それまでは太陽を含む全天体は「銀河系の全天体に共通の、そしてスバルの中で最も明るいアルシオーネ(Alcyone in the Pleiades)の近くにあると考えられる引力のまわりを」まわっていて、太陽は「一億一千七百万年のあいだまわりつづけている」という、現在(2848年)では奇妙に思える説が有力だったという話です。この奇妙な説は最初はマドラー(Mudler)によりひろめられたとのことでした。
しかしこの19世紀中旬には知られていたらしいマドラー説というのが少し調べただけではどうもよくわかりません。簡単な天文学史では1788年にハーシェルにより太陽が中心近くにあるという銀河系内構成分布が描かれた後、ハッブルによる系外星雲までの距離測定(1924年)までは、宇宙が銀河系だけなのか銀河系の外にも多数の銀河が分布しているのかという論争が行われていたという話しかわかりません。19世紀において、ハーシェルの太陽が銀河の中心にあるという説に対する反対仮説にどんなものがあったのかがわからないのです。マドラー(Mudler)という名ももじりかも知れませんし。しかしまさかポーが独自にハーシェルへの対立仮説を考え出してみた、というのも可能性としては少ないでしょう。
で、マドラー説に対して、この銀河中心の巨大な重力源が「なぜわれわれにそれが見えないのか?」という疑問が呈され、マドラーは「非発光体らしい」といいのがれ(took refuge in the suggestion of non-luminosity)、非発光体としても「その周囲の到るところで光っている明るい恒星の無数の群れによって」照らし出されて見えない理由は何か?という問いには、「それが回転しているすべての天体に共通の引力に過ぎない(merely a centre of gravity common to all the revolving orbs)」といいのがれたとのことです。うーむ、マドラー氏は銀河中心核のブラックホールを予言していたのですね(^_^)。
ところでこの琴座アルファ星鑑賞の四月六日の出だしは次のようなものです。
===========引用開始====下線は私の強調============
原文[Ref-2]
Last night had a fine view of Alpha Lyræ, whose disk, through our captain’s spy-glass, subtends an angle of half a degree, looking very much as our sun does to the naked eye on a misty day.
創元社の全集[Ref-1a]
昨夜琴座のアルファ星の素晴らしいながめを見たが、船長の望遠鏡からのぞくと、その表面はほとんど真っ平らで、もやのかかった日に肉眼で太陽を見た場合ときわめてよく似ている。
春秋社の全集[Ref-1b]
昨夜琴座(星座の名)のアルファ星の表面が船長の望遠鏡でよく見え、ちょうど霧深い日に肉眼で太陽を見るように、半度の角で対していた。
===========引用終り===============================
そうです。『ハンス・プファアルの無類の冒険』でも登場した問題の動詞"subtend"です[*2]。谷崎精二の訳も多少わかりにくいのですが、高橋正雄の「その表面はほとんど真っ平らで」はひどいですよね。 "disk" は星を見た2次元形状を指しているだけなのに。そしてその円板状の像は、肉眼で見た太陽とほぼ同じ大きさに見えたのだと定量的に書いているというのに。
さらに単なる"telescope"(望遠鏡)ではなく"spyglass"(携帯用望遠鏡)とすることで、1000年後の技術進歩のすごさを強調しているのです[*3を追加(2017/06/01)]。ここは翻訳でもきちんと表現してほしいところですね。
なお谷崎精二の訳は『ハンス・プファアルの無類の冒険』の小泉一郎の訳とも違っています。こちらの訳で示せば、
===========引用開始====下線は私の強調=============
原文 本ブログの気球に乗って月旅行のリンク先参照
Great decrease in the earth's apparent diameter, which now subtended from the balloon an angle of very little more than twenty-five degrees.
創元社の全集『ポオ小説全集 1 (創元推理文庫 522-1)』(1974/06/28)
地球の直径と思われるものが、さらに非常に小さくなりました。それはいま、二十五度を少し超える角度で地球に対していました。
春秋社の全集[Ref-1b]
地球の、見たところの直径がひどくちじまりました。それはいま気球に、二十五度とすこしの角度で対しているのです。
===========引用終り===============================
いやはや小泉一郎の訳では気球がどこかへ飛び去ってしまい、「地球の直径と思われるものが地球に対している」という頭の痛くなるような意味に解釈されそうです。谷崎精二の方が変に意訳しようとしてないだけ、意味が通りやすくなっています。
--------------------------
Ref-1)
a) 『ポオ小説全集4(創元推理文庫 522-4)』(1974/09/27) ISBN13:978-448852204-9
b) 『ポオ小説全集〈3〉冒険小説』春秋社(1962/10/15) ISBN13:978-439345033-8
Ref-2) "The Edgar Allan Poe Society of Baltimore"のサイトから
a) 書誌事項(複数テキスト・研究書などのリスト)
b) "Text-02 — “Mellonta Tauta” — February 1849 — Godey’s Lady’s Book"からの原文。
c) “Mellonta Tauta” — 1856 — WORKS — Griswold reprints Text-02, omitting the introductory letter (Mabbott text B)からの原文。
--------------------------
*1) 本ブログの探偵小説を探せ(2017/05/06)を参照。
*2) 本ブログの気球に乗って月旅行(後編)(2017/05/20)を参照。
*3) [2017/06/01追加]視角は太陽と同じに拡大できたとしても25.0光年(1.58*10^6天文単位)の距離にある星をリアルタイムで見ているのだから極めて暗くなってしまうはずだ。明るい像を得るには望遠鏡の口径を大きくして多くの光を集めるのが常道だが、なにせ "spyglass" では口径には限界があるだろう。当然ながら2048年の高度技術による増幅率の高い超高感度光検出システムを内蔵していると想像できる。適切な明るさに調整された結果が霧深い日(on a misty day)の太陽のような像となったのだろう。生兵法で「太陽と同じ大きさに見えたら目がつぶれないのか?」と突っ込む者も出そうなところだが、ポーも芸が細かいねえ。
さらに2048年ともなれば小型の補償光学装置も組み込まれているかも知れないが、それでも大気による像の揺らぎを消しきれていないかも知れない。直後に黒点の話も出てくるので、黒点が見分けられるくらいには明瞭な象かもしれないが。
『メロンタ・タウタ(Mellonta Tauta)』は語り手の手紙という形式ですが、語り手の正体、と言わぬまでも語り手の人物像というものははっきりとは描写されていません。これは本作品に限りません。ポーの多くの作品は"私"という一人称の語り手により語られるものが多いのですが、その語り手の人物像ははっきりしないことがほとんどです。まあ自然と言えば自然です。それでも語り手がどんな立ち位置の人物なのかは想像したり推定したりすることは可能で、それもポーの作品の楽しみのひとつになりそうにも思えます。
『メロンタ・タウタ』の語り手は「その全部が娯楽旅行のつもりで乗っている(ある人々は娯楽というものについてなんと奇妙な考えを持っていることだろう!)百人か二百人の愚民」と気球に同乗していますが、話し相手は昔のことしか話さないパンディットという名の人物ただ一人だけです。といいつつ船長とは気球の材料の話をしていますが。
パンディットは非常に物知りですが昔のことにしか興味がないようです。現代のSF作品の中なら「パンディットはもしかして人工知能か?」と疑うところですが、コンピュータも知られていない時代にそれはないでしょう。パンディットは語り手と同類のただの人類の一員と思われます。そして語り手とパンディットとの詳しい関係も不明ですが、最後の方では、『E・A・ポー ポケットマスターピース09 (集英社文庫 ヘリテージシリーズ)』(2016/6/23)収録の『お前が犯人だ!--ある人のエドガーへの告白--』(桜庭一樹による翻案)[*1]で桜庭が仕掛けたトリックと同じトリックが仕掛けられている・・ような気がします。「それでどなうなるの?」ということではあるけれど。そもそも語り手の私生活は何も描写されず、仕事・家庭・男女関係・親子関係などというものが19世紀のアメリカとは全くかけ離れているのかも知れないのですが、その実態は闇の中です。
さてこの気球船には船長のものとして琴座アルファ星の黒点まで見えるほどの超高性能望遠鏡(our captain’s spy-glass)が載せてあるのですが、この星とわれらが太陽とが連星関係にあるという2848年での定説が語られます。このことが明らかになったのは前世紀つまり2700年代のこと。それまでは太陽を含む全天体は「銀河系の全天体に共通の、そしてスバルの中で最も明るいアルシオーネ(Alcyone in the Pleiades)の近くにあると考えられる引力のまわりを」まわっていて、太陽は「一億一千七百万年のあいだまわりつづけている」という、現在(2848年)では奇妙に思える説が有力だったという話です。この奇妙な説は最初はマドラー(Mudler)によりひろめられたとのことでした。
しかしこの19世紀中旬には知られていたらしいマドラー説というのが少し調べただけではどうもよくわかりません。簡単な天文学史では1788年にハーシェルにより太陽が中心近くにあるという銀河系内構成分布が描かれた後、ハッブルによる系外星雲までの距離測定(1924年)までは、宇宙が銀河系だけなのか銀河系の外にも多数の銀河が分布しているのかという論争が行われていたという話しかわかりません。19世紀において、ハーシェルの太陽が銀河の中心にあるという説に対する反対仮説にどんなものがあったのかがわからないのです。マドラー(Mudler)という名ももじりかも知れませんし。しかしまさかポーが独自にハーシェルへの対立仮説を考え出してみた、というのも可能性としては少ないでしょう。
で、マドラー説に対して、この銀河中心の巨大な重力源が「なぜわれわれにそれが見えないのか?」という疑問が呈され、マドラーは「非発光体らしい」といいのがれ(took refuge in the suggestion of non-luminosity)、非発光体としても「その周囲の到るところで光っている明るい恒星の無数の群れによって」照らし出されて見えない理由は何か?という問いには、「それが回転しているすべての天体に共通の引力に過ぎない(merely a centre of gravity common to all the revolving orbs)」といいのがれたとのことです。うーむ、マドラー氏は銀河中心核のブラックホールを予言していたのですね(^_^)。
ところでこの琴座アルファ星鑑賞の四月六日の出だしは次のようなものです。
===========引用開始====下線は私の強調============
原文[Ref-2]
Last night had a fine view of Alpha Lyræ, whose disk, through our captain’s spy-glass, subtends an angle of half a degree, looking very much as our sun does to the naked eye on a misty day.
創元社の全集[Ref-1a]
昨夜琴座のアルファ星の素晴らしいながめを見たが、船長の望遠鏡からのぞくと、その表面はほとんど真っ平らで、もやのかかった日に肉眼で太陽を見た場合ときわめてよく似ている。
春秋社の全集[Ref-1b]
昨夜琴座(星座の名)のアルファ星の表面が船長の望遠鏡でよく見え、ちょうど霧深い日に肉眼で太陽を見るように、半度の角で対していた。
===========引用終り===============================
そうです。『ハンス・プファアルの無類の冒険』でも登場した問題の動詞"subtend"です[*2]。谷崎精二の訳も多少わかりにくいのですが、高橋正雄の「その表面はほとんど真っ平らで」はひどいですよね。 "disk" は星を見た2次元形状を指しているだけなのに。そしてその円板状の像は、肉眼で見た太陽とほぼ同じ大きさに見えたのだと定量的に書いているというのに。
さらに単なる"telescope"(望遠鏡)ではなく"spyglass"(携帯用望遠鏡)とすることで、1000年後の技術進歩のすごさを強調しているのです[*3を追加(2017/06/01)]。ここは翻訳でもきちんと表現してほしいところですね。
なお谷崎精二の訳は『ハンス・プファアルの無類の冒険』の小泉一郎の訳とも違っています。こちらの訳で示せば、
===========引用開始====下線は私の強調=============
原文 本ブログの気球に乗って月旅行のリンク先参照
Great decrease in the earth's apparent diameter, which now subtended from the balloon an angle of very little more than twenty-five degrees.
創元社の全集『ポオ小説全集 1 (創元推理文庫 522-1)』(1974/06/28)
地球の直径と思われるものが、さらに非常に小さくなりました。それはいま、二十五度を少し超える角度で地球に対していました。
春秋社の全集[Ref-1b]
地球の、見たところの直径がひどくちじまりました。それはいま気球に、二十五度とすこしの角度で対しているのです。
===========引用終り===============================
いやはや小泉一郎の訳では気球がどこかへ飛び去ってしまい、「地球の直径と思われるものが地球に対している」という頭の痛くなるような意味に解釈されそうです。谷崎精二の方が変に意訳しようとしてないだけ、意味が通りやすくなっています。
--------------------------
Ref-1)
a) 『ポオ小説全集4(創元推理文庫 522-4)』(1974/09/27) ISBN13:978-448852204-9
b) 『ポオ小説全集〈3〉冒険小説』春秋社(1962/10/15) ISBN13:978-439345033-8
Ref-2) "The Edgar Allan Poe Society of Baltimore"のサイトから
a) 書誌事項(複数テキスト・研究書などのリスト)
b) "Text-02 — “Mellonta Tauta” — February 1849 — Godey’s Lady’s Book"からの原文。
c) “Mellonta Tauta” — 1856 — WORKS — Griswold reprints Text-02, omitting the introductory letter (Mabbott text B)からの原文。
--------------------------
*1) 本ブログの探偵小説を探せ(2017/05/06)を参照。
*2) 本ブログの気球に乗って月旅行(後編)(2017/05/20)を参照。
*3) [2017/06/01追加]視角は太陽と同じに拡大できたとしても25.0光年(1.58*10^6天文単位)の距離にある星をリアルタイムで見ているのだから極めて暗くなってしまうはずだ。明るい像を得るには望遠鏡の口径を大きくして多くの光を集めるのが常道だが、なにせ "spyglass" では口径には限界があるだろう。当然ながら2048年の高度技術による増幅率の高い超高感度光検出システムを内蔵していると想像できる。適切な明るさに調整された結果が霧深い日(on a misty day)の太陽のような像となったのだろう。生兵法で「太陽と同じ大きさに見えたら目がつぶれないのか?」と突っ込む者も出そうなところだが、ポーも芸が細かいねえ。
さらに2048年ともなれば小型の補償光学装置も組み込まれているかも知れないが、それでも大気による像の揺らぎを消しきれていないかも知れない。直後に黒点の話も出てくるので、黒点が見分けられるくらいには明瞭な象かもしれないが。










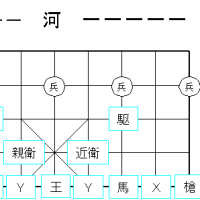
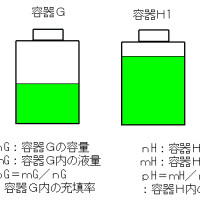
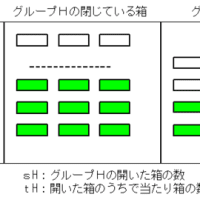
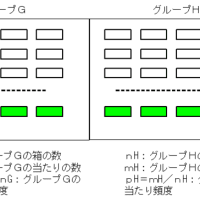
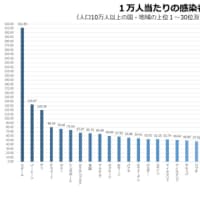
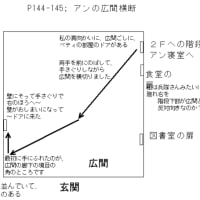
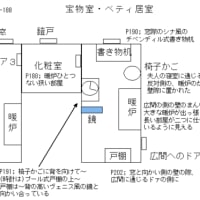

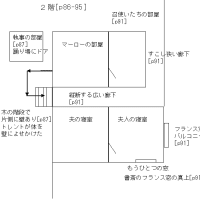
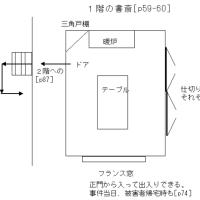






※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます