“消えゆく業界”から海外シェフ注目の食材へ
日本の食文化を守る「幻の昆布問屋」
奥井海生堂は代々、曹洞宗大本山永平寺、大本山總持寺御用達の昆布所であり、一流料理店に高級昆布を納め、品質の高さでは群を抜いている。扱っている昆布の質の高さで世界からも注目されている「奥井海生堂」だが、そこにいたるまでの道のりは決して平坦なものではなかった。
4代目主人の奥井隆氏
(写真:奥井海生堂提供)
「戦前は豊かだったそうですが、敦賀空襲で昆布蔵をはじめすべてを失ってしまったのです。父は廃業も考えていたそうですが、永平寺の方たちや同業者の助けもあって、再出発することができました」
戦後、昆布問屋としての再スタートを切った「奥井海生堂」だが、思いもよらなかった環境の変化に見舞われる。戦後のライフスタイルの変化にともなう、昆布の需要低下だ。さらにはうま味調味料の普及もそれに追い打ちをかける。
「味の素さんとは今では旨味の研究や世界展開などでもご協力させていただき、いいお付き合いをさせていただいていますが、当時、先行きには危機感を持っていました。今では笑い話としてお話できますが、私が会社に入って数年が経った頃です。
味の素さんがスポンサーの記録映画の取材のお話がきました。『どういうテーマの記録映画なんですか?』と私が聞きましたところ、『消えゆく業界を記録する』という主旨だ、と(苦笑)。父はひどく怒ってましたが、これには参りました」
簡便性と効率性が求められる時代になったことが、昆布の世界に打撃を与えた。なにかと美化されがちな昭和30年代から40年代にかけてだが、食品について言えば今よりずっと問題を孕んでいたのだ。
そんななか奥井社長は「消えゆく業界にはさせない」と、東京への進出を決める。
「父は反対しましたが、それまでの販路は限られていました。しかし、守っていくだけではこの先、難しい。でも、東京に行っても最初はけんもほろろでしたよ」
東京進出、そして海外へ
世界を魅了した“ヴィンテージ昆布”の旨味
当時「東京では昆布は売れない」というのは定説だった。
「最初に商品を置いて下さった三浦屋さんには今でも感謝しています。そこで東京の消費者の方に手にとってもらうために、昆布を小さくカットして販売しました。昆布は献上品ですし、神饌のひとつでもありますから、それをカットするという考えはなかったのです。
またそれと前後して、西武百貨店さんのバイヤーさんが目をつけてくれました」
ディスカバージャパンの流れもあり、百貨店で地方催事がはじまった頃だった。「本物」を売りたいというバイヤーからの熱心な働きかけもあり、物産展でデビューを果たす。
「しかし、東京には昆布の文化は本当にありませんでしたね。まず聞かれるのは昆布の使い方がわかりません、ということ。一番、多かった質問は「この昆布は敦賀で採れたんですか」というもの。昆布のことをもっと知ってもらわなければという気持ちになりましたし、接客の重要性にも気づかされました」
日本の食文化を守る「幻の昆布問屋」
奥井海生堂は代々、曹洞宗大本山永平寺、大本山總持寺御用達の昆布所であり、一流料理店に高級昆布を納め、品質の高さでは群を抜いている。扱っている昆布の質の高さで世界からも注目されている「奥井海生堂」だが、そこにいたるまでの道のりは決して平坦なものではなかった。
4代目主人の奥井隆氏
(写真:奥井海生堂提供)
「戦前は豊かだったそうですが、敦賀空襲で昆布蔵をはじめすべてを失ってしまったのです。父は廃業も考えていたそうですが、永平寺の方たちや同業者の助けもあって、再出発することができました」
戦後、昆布問屋としての再スタートを切った「奥井海生堂」だが、思いもよらなかった環境の変化に見舞われる。戦後のライフスタイルの変化にともなう、昆布の需要低下だ。さらにはうま味調味料の普及もそれに追い打ちをかける。
「味の素さんとは今では旨味の研究や世界展開などでもご協力させていただき、いいお付き合いをさせていただいていますが、当時、先行きには危機感を持っていました。今では笑い話としてお話できますが、私が会社に入って数年が経った頃です。
味の素さんがスポンサーの記録映画の取材のお話がきました。『どういうテーマの記録映画なんですか?』と私が聞きましたところ、『消えゆく業界を記録する』という主旨だ、と(苦笑)。父はひどく怒ってましたが、これには参りました」
簡便性と効率性が求められる時代になったことが、昆布の世界に打撃を与えた。なにかと美化されがちな昭和30年代から40年代にかけてだが、食品について言えば今よりずっと問題を孕んでいたのだ。
そんななか奥井社長は「消えゆく業界にはさせない」と、東京への進出を決める。
「父は反対しましたが、それまでの販路は限られていました。しかし、守っていくだけではこの先、難しい。でも、東京に行っても最初はけんもほろろでしたよ」
東京進出、そして海外へ
世界を魅了した“ヴィンテージ昆布”の旨味
当時「東京では昆布は売れない」というのは定説だった。
「最初に商品を置いて下さった三浦屋さんには今でも感謝しています。そこで東京の消費者の方に手にとってもらうために、昆布を小さくカットして販売しました。昆布は献上品ですし、神饌のひとつでもありますから、それをカットするという考えはなかったのです。
またそれと前後して、西武百貨店さんのバイヤーさんが目をつけてくれました」
ディスカバージャパンの流れもあり、百貨店で地方催事がはじまった頃だった。「本物」を売りたいというバイヤーからの熱心な働きかけもあり、物産展でデビューを果たす。
「しかし、東京には昆布の文化は本当にありませんでしたね。まず聞かれるのは昆布の使い方がわかりません、ということ。一番、多かった質問は「この昆布は敦賀で採れたんですか」というもの。昆布のことをもっと知ってもらわなければという気持ちになりましたし、接客の重要性にも気づかされました」














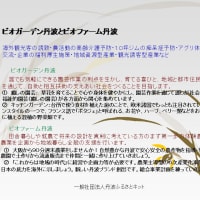
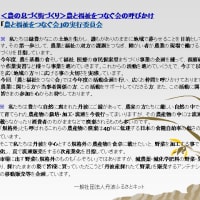

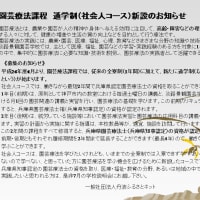


※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます