先日、鈴木秀美のチェロでハイドンのチェロ協奏曲を聴いて熱くなったが、
今夜は、バッハ「無伴奏チェロ組曲全曲」(1995年録音盤)を聴く。
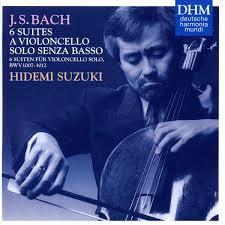
鈴木秀美(チェロ)1995年録音
これは当時の月刊・レコード芸術誌特選盤になったのか。
無伴奏チェロ組曲第1番ト長調 BWV1007
無伴奏チェロ組曲第2番ニ短調 BWV1008
無伴奏チェロ組曲第3番ハ長調 BWV1009
無伴奏チェロ組曲第4番変ホ長調 BWV1010
無伴奏チェロ組曲第5番ハ短調 BWV1011
無伴奏チェロ組曲第6番ニ長調 BWV1012
鈴木秀美はこの後2度目の録音を成している。

鈴木秀美(チェロ)2004年録音
使用楽器:
第1~5番:アンドレア・アマティのチェロ(クレモナ1570年頃)
第6番:5弦のチェロ・ピッコロ(作者不詳18世紀前半ドイツ)
弓=ルイス・エミリオ・ロドリゲス(1995年ハーグ)]
録音時期:2004年10月31日~11月3日、4日&5日、8日~11日
録音場所:秩父ミューズパーク音楽堂(DSDレコーディング)
★この作品について(以下Wikiより引用)
作曲年代は明らかでないが、その大部分はケーテン時代(1717年-1723年)に作曲されたらしい。
ケーテン時代には、ブランデンブルク協奏曲やフランス組曲、イギリス組曲など、6曲構成の楽曲が作られているが、
この時代に3の倍数が好まれたことが影響していると見られる。バッハの妻アンナ・マクダレーナの写譜が残っており、
これは長い間自筆譜と考えられてきた美しいものである。
その後、単純な練習曲として忘れられていたが、パブロ・カザルスによって再発掘されて以降、チェリストの聖典的な作品と見なされるようになった。
現代においてはバッハの作品の中でも特に高く評価されるものの一つである。
コントラバスやヴィオラ、ヴィオラ・ダ・ガンバ、ギター、サキソフォン、フルート、ホルン、マリンバ、エレキギター、テューバなど他の楽器に編曲、演奏されることも多い。
★次いで楽曲の解説
6曲の組曲は、それぞれが前奏曲(プレリュード)で始まり、
アルマンド、クーラント、サラバンド、メヌエット(第3番・第4番はブーレ、第5番・第6番ではガヴォット)、
ジーグの6曲構成となっている。
組曲ごとにひとつの調性で統一される。
各楽曲はプレリュードとアルマンド(元来舞曲であるが当時その性格は失われていた)を除いて舞曲であるが、
一見単純な構成のなかに多声的な要素が盛り込まれ、重音奏法も駆使して一つの楽器とは思えない劇的かつ多彩な効果を出す。
演奏技術的には、番号順に難しくなる傾向にあるが、
第1番はチェロを始めて2年から3年程度で挑戦可能とされ、第2番は一部に困難な運指があるものの、
第1番とほぼ同程度の難度であり、第3番までなら演奏自体はそう難しくない。
しかし、音楽の内容を汲んだ表現となると、生涯をかけて研究するほどの対象とされる。
また5番はスコルダトゥーラを前提とし、6番は5弦の楽器のために書かれているため、
現代の一般的な楽器で演奏するには高い技術が要求される。
強弱やボウイングなどについて、さまざまに解釈、編曲された演奏譜が出版されている。
★無伴奏チェロ組曲の名演奏
チェロのための代表的な楽曲であるだけに、古今の世界的チェリストが競って録音している。
現代楽器による演奏
パブロ・カザルス
ピエール・フルニエ
ポール・トルトゥリエ(2回録音)
ダニイル・シャフラン
ヤーノシュ・シュタルケル
ムスティスラフ・ロストロポーヴィチ(一部2回録音)
ミッシャ・マイスキー(2回録音)
ヨーヨー・マ(2回録音)
アンナー・ビルスマ(1992録音、「セルヴェ」〔ストラディバリ〕使用、第6番のみチェロ・ピッコロ使用)
古楽器による演奏
アンナー・ビルスマ(2回録音)
ピーター・ウィスペルウェイ
鈴木秀美(2回録音)
ヴィーラント・クイケン
スーザン・シェパード
ヤープ・テル・リンデン
ブルーノ・コクセ
オフェリー・ガイヤール
寺神戸亮(ヴィオロンチェロ・ダ・スパッラによる録音)
シギスヴァルト・クイケン(ヴィオロンチェロ・ダ・スパッラによる録音)
作品試聴の感想だが、幾分ボリュームを上げて聴くと、彫りの深い低音が聴く者に迫る。
非常に端正な演奏にしばし聴き惚れる。この人は上手いんだと思う。
だから録音に2度も挑んだのだろう。それと時を経て自己解釈の変遷をきちんと残したかったのかな。
いずれにしろ、名演に入ると思う。
日本ブログ村写真ランキングに登録しています。あなたの応援ポチが、当方のモチベーションアップになります。

にほんブログ村
今夜は、バッハ「無伴奏チェロ組曲全曲」(1995年録音盤)を聴く。
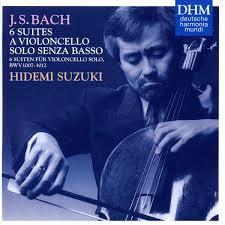
鈴木秀美(チェロ)1995年録音
これは当時の月刊・レコード芸術誌特選盤になったのか。
無伴奏チェロ組曲第1番ト長調 BWV1007
無伴奏チェロ組曲第2番ニ短調 BWV1008
無伴奏チェロ組曲第3番ハ長調 BWV1009
無伴奏チェロ組曲第4番変ホ長調 BWV1010
無伴奏チェロ組曲第5番ハ短調 BWV1011
無伴奏チェロ組曲第6番ニ長調 BWV1012
鈴木秀美はこの後2度目の録音を成している。

鈴木秀美(チェロ)2004年録音
使用楽器:
第1~5番:アンドレア・アマティのチェロ(クレモナ1570年頃)
第6番:5弦のチェロ・ピッコロ(作者不詳18世紀前半ドイツ)
弓=ルイス・エミリオ・ロドリゲス(1995年ハーグ)]
録音時期:2004年10月31日~11月3日、4日&5日、8日~11日
録音場所:秩父ミューズパーク音楽堂(DSDレコーディング)
★この作品について(以下Wikiより引用)
作曲年代は明らかでないが、その大部分はケーテン時代(1717年-1723年)に作曲されたらしい。
ケーテン時代には、ブランデンブルク協奏曲やフランス組曲、イギリス組曲など、6曲構成の楽曲が作られているが、
この時代に3の倍数が好まれたことが影響していると見られる。バッハの妻アンナ・マクダレーナの写譜が残っており、
これは長い間自筆譜と考えられてきた美しいものである。
その後、単純な練習曲として忘れられていたが、パブロ・カザルスによって再発掘されて以降、チェリストの聖典的な作品と見なされるようになった。
現代においてはバッハの作品の中でも特に高く評価されるものの一つである。
コントラバスやヴィオラ、ヴィオラ・ダ・ガンバ、ギター、サキソフォン、フルート、ホルン、マリンバ、エレキギター、テューバなど他の楽器に編曲、演奏されることも多い。
★次いで楽曲の解説
6曲の組曲は、それぞれが前奏曲(プレリュード)で始まり、
アルマンド、クーラント、サラバンド、メヌエット(第3番・第4番はブーレ、第5番・第6番ではガヴォット)、
ジーグの6曲構成となっている。
組曲ごとにひとつの調性で統一される。
各楽曲はプレリュードとアルマンド(元来舞曲であるが当時その性格は失われていた)を除いて舞曲であるが、
一見単純な構成のなかに多声的な要素が盛り込まれ、重音奏法も駆使して一つの楽器とは思えない劇的かつ多彩な効果を出す。
演奏技術的には、番号順に難しくなる傾向にあるが、
第1番はチェロを始めて2年から3年程度で挑戦可能とされ、第2番は一部に困難な運指があるものの、
第1番とほぼ同程度の難度であり、第3番までなら演奏自体はそう難しくない。
しかし、音楽の内容を汲んだ表現となると、生涯をかけて研究するほどの対象とされる。
また5番はスコルダトゥーラを前提とし、6番は5弦の楽器のために書かれているため、
現代の一般的な楽器で演奏するには高い技術が要求される。
強弱やボウイングなどについて、さまざまに解釈、編曲された演奏譜が出版されている。
★無伴奏チェロ組曲の名演奏
チェロのための代表的な楽曲であるだけに、古今の世界的チェリストが競って録音している。
現代楽器による演奏
パブロ・カザルス
ピエール・フルニエ
ポール・トルトゥリエ(2回録音)
ダニイル・シャフラン
ヤーノシュ・シュタルケル
ムスティスラフ・ロストロポーヴィチ(一部2回録音)
ミッシャ・マイスキー(2回録音)
ヨーヨー・マ(2回録音)
アンナー・ビルスマ(1992録音、「セルヴェ」〔ストラディバリ〕使用、第6番のみチェロ・ピッコロ使用)
古楽器による演奏
アンナー・ビルスマ(2回録音)
ピーター・ウィスペルウェイ
鈴木秀美(2回録音)
ヴィーラント・クイケン
スーザン・シェパード
ヤープ・テル・リンデン
ブルーノ・コクセ
オフェリー・ガイヤール
寺神戸亮(ヴィオロンチェロ・ダ・スパッラによる録音)
シギスヴァルト・クイケン(ヴィオロンチェロ・ダ・スパッラによる録音)
作品試聴の感想だが、幾分ボリュームを上げて聴くと、彫りの深い低音が聴く者に迫る。
非常に端正な演奏にしばし聴き惚れる。この人は上手いんだと思う。
だから録音に2度も挑んだのだろう。それと時を経て自己解釈の変遷をきちんと残したかったのかな。
いずれにしろ、名演に入ると思う。
日本ブログ村写真ランキングに登録しています。あなたの応援ポチが、当方のモチベーションアップになります。
にほんブログ村




















