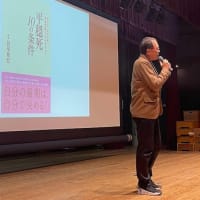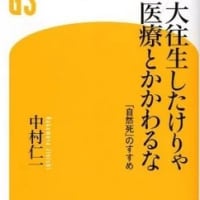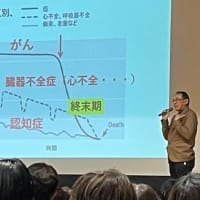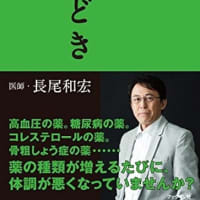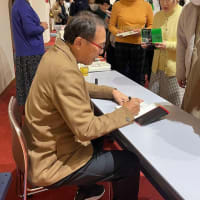バンビが愛知県豊田市で発行されているタウン紙「ぴポ」に連載しているコラム「こだわり自然派子育て」の転載です。
『豊田市に自然育児の風を!』と気合いをいれて書いておりました。
イラストも担当(日記と内容が重なる場合もありますがご愛嬌!)

※2005年8月で連載終了となりました。
…………
Vol.1「バンビママのごあいさつ」(2003/10/20)
皆さん始めまして!
今回からマザーズライフを担当するバンビです。
わが家の家族構成は、仕事が不規則な映像カメラマンの夫、カトリック系幼稚園に通う年中のウサ(アレルギー体質の4才児)、可愛い盛りの1才児のノン(次女の特権?どの時代も可愛い盛り)、じーじ、ばーば、そしてハハである私の6人。
これから紹介していく「こだわり自然派育児」のその中身とは…。
テレビはほとんどつけず、ビデオ、ゲームはもちろんなし。
就学前は「遊びが仕事」だから習い事もお勉強もなしさっ。
おやつはなるべく子どもと一緒に手作りで。
本当はお祭り騒ぎの大好きな私も、親になった以上は覚悟を決めて自分だけの楽しみは排除。
子どもと一緒にのんびりゆっくり暮らしせる日々はそう長く続きません。
せっかく、縁あって一緒になった家族だもの「子育て時代を楽しまなきゃ、損!」と思って日々生活しております。
…………
Vol.2「子ども時代にしかできないこと」2003/11/20
なぜ世間ではこうも急いで習い事やお勉強をさせるのだろうか?
「3才までが勝負」「可能性を伸ばしてやりたい」とは良く聞く話だが、私はいつも「もったいないなぁ」と思う。
ただ気の赴くままに遊び、空想の世界にどっぷり浸かれるのも乳幼児時期だけだもの。
純粋に風景だけを眺め、絵本の「絵」だけをじっくり見入ることができるのも、字を知らないからこそ。
美しいものを見て、自然の匂いを感じて、風の音や虫の声に耳を傾けること。
体に美味しいものを食べ、たくさんの温もりをもらい、小さな生き物と仲良しになること。
幼少の頃に経験すべきことはたくさんあるはず。
子どもは「こども」であり「小さなおとな」にしてはいけないとわたしは思う。
現実の世界から遠ざけ、貴重な「子ども時代」を早送りせずに、1分1秒でも長く「夢見る娘たち」でいてほしいと母は願うのだった。
…………
Vol.3「おもちゃ」2003/12/20
この時期になると目を伏せたくなるのがおもちゃの広告。
クリスマスにプレゼントされる大量のおもちゃの行く末は、飽きられ、劣化し、埋めるゴミとなる。
それに子どもは「見立て遊び」ができる才能と工夫して遊ぶ知恵を持っているのに、電池で動き、音の出るような完成度が高いおもちゃでは想像力を広げることはできない(今の子どもたちが「おもちゃに遊んでもらっている」と思うのはわたしだけかしら?)。
わが家はプラスチックのおもちゃは買わないと決めているの。
「自然素材のものを与えたい」という理由と処分時を考えての結論。
色合いの優しい素朴なおもちゃは、少々高価だけど使い込む程に「味」が出るので子どもに必要無くなってもインテリアとして活用できるし、思い出と共に孫の代までとっておける。
なにもおもちゃに大金をかけなくても、ただの木切れや木の実のような自然の産物でも遊ぶことができる能力を子どもたちは持っているのよね。
…………
Vol.4「健康的な食卓」2004/01/20
私は自称「健康おたく」である。
わが家の食卓では「1日30品目」を目標とせずに「旬の地場もの」が中心。
「身土不二…住む土地の旬のものがイチバン」をモットーにしているのさっ。
輸入食材やハウスものは避け、乳製品は控え、「食品の組織を壊す」と言われる電子レンジは使わない。
そしてできるだけ無農薬のもの、食品添加物の入っていないものを選ぶ。
わが家のエンゲル係数は高いけれど、食べ物の一つ一つが子どもの血となり肉となるわけだし、良心的にモノ作りをしている生産者や日本の農家に投資、投票するつもりで食費だけは削れないの。
うちの食卓には子ども向けメニューは並ばない。
幼い頃から「乾物と根菜の煮物」「酢の物」「煮豆」を普通に食べている娘たち。
就学前までは体を作る大切な大切な時期だから、ファーストフードもスナック菓子もしばらくはお預けなのだ。
…………
Vol.5「テレビのない生活」2004/02/20
わが家はほとんどテレビをつけない。
それは「見たくないものには目を伏せる」ことができる大人と違って、乳幼児は「乾いたスポンジが水分を吸収するように」どんな映像でも正しいと思い込んでしまうらしい(残虐なシーンですら)。
それを知ったのは長女が1才半の頃だった。
それまで超テレビっ子だった私は、授乳中でさえ画面に釘付けになっていたかもしれない。
そんな反省から私はテレビを断ったのだ。
テレビのない生活は「たいくつな時間」がたくさんある。
テレビがついていればやる気をなくしてしまう娘も、ついていなければ積み木、ままごと、お絵描き…想像力は広がっていく。
自分の頭で遊びを考えなければならないこの「たいくつな時間」こそが子どもが活き活きする時である。
友達関係が大切になる小学生になるまではこの生活を続けようと思っている。
皆さんもまずは週に1度のノーテレビデーから試してみませんか。
…………
Vol.6「8時消灯のすすめ」2004/03/20
わが家の生活は規則正しい。
それが何より「子どもが機嫌良く過ごせる方法」だと気が付いたからだ。
まだ長女だけだった頃は「子どもお任せ生活」をしていたからいちいち手こずっていたし、夜11時になっても寝ないこともしばしば。
でもそれでは成長ホルモンが出る一番大切な時間帯を無駄に過ごしてしまい、体内時計を狂わせてしまう。
今、わが家では5時半にお風呂、6時から夕飯。
7時にはお布団に入るのでたくさんの絵本を読み聞かせしたり童謡を歌って過ごす。
そして8時消灯。
そのリズムが子どもたちにプログラムされており、とてもスムーズに毎日を過ごしているのだ。
たっぷり寝た次の朝は起こさなくとも7時に目覚めて朝から機嫌も良いので「はやくしなさい」なーんて叱ることもほとんどない。
「夜、パパに会える」メリットよりも夜更かしのデメリットの方が大きいから、だんなの休みにはその分、密な時間を過ごしてもらっているの。
…………
Vol.7「親から子への贈り物」2004/04/20
「子どものためによくそこまで頑張れるね」とよく言われるが、私は「子育てが趣味」とは全然思っていない。
子育てを家に例えるなら、今は、基礎工事の段階で手抜きができないだけのこと。
安心して親離れしてもらい、子離れしたいからこそ今を大切に過ごしているの。
私は子育ての区切りを7年と考えている。
その間はできる限り心と体に有害と思われるものを排除して、良い環境を整えることを重視している。
親の役目は「正しい背中」を見せることで、過干渉は子どもをダメにする。
娘たちが本来の子どもらしくイキイキと目を輝かせてくれることが私にとって1番の喜び。
もっと愛してあげれば良かった、と後悔するのだけはいやだから「ずっと大好きだよ」「パパとママの子に生まれてくれてありがとう」と言って毎日しっかりと抱きしめる。
子どもが「自分は必要とされている」と満足してもらうことが私から娘たちへの贈り物なのです。
…………
Vol.8「子育てが楽になる方法」2004/05/20
なるべく余分なエネルギーを使わずに子どもと暮らしたい。
だからと言って一時しのぎ(ごまかしや脅し、物で釣るやり方)をすればいづれしっぺ返しが来るだろう。
理屈で説明するには早すぎる小さな子どもには物を擬人化するとスムーズにいき、叱らずに済むことも多い。
靴を脱ぎ散らかした時「お靴さんが『揃えてよ~』って泣いてるよ」と言えば娘はすっ飛んできて「ごめんね」と直すし、おもちゃにも魂が宿っていると(たぶん)信じているので乱雑に扱うこともない。
わが家にはごちゃ混ぜに放り込むような「おもちゃ箱」は存在せず、おもちゃは「家に帰る」ごとく陳列棚の所定の位置に並べられる。
次女が偏食をすれば「お野菜さんが『ぼくも食べて~』って言ってるよ」と長女は諭し、次女は納得する。
こんな純粋でいられるのはほんの数年だろうし、愛のある生活が心地よいから私もしっかり演技するのである。
…………
vol.9「絵本の読み聞かせ 〜幸せな時間〜」2004/06/20
子どもをもって得たものの一つに絵本との出会いがある。
わが家のリビングのまん中に陣取っているのは500冊ほどの絵本。
ロングセラーものは読み継がれるだけの魅力があるし、絵本の中には画集と思えるほどの素晴らしい作品もある。
何度も繰り返して読むものだからこそ、読み手であるおとなも楽しめるものを選んでいる。
読み聞かせは大切なスキンシップの時間であり、親子が同じ世界を共有できる遊びの一つだから、字を覚えるとか知識がつくという教育的な期待はしない。
読み終えても質問などはせず、パタンと閉じておしまい。
大人に読んでもらうからこそ子どもは「絵だけ」を眺められて、想像の世界に浸ることができる。
字が読めることと内容を理解できることは違うから、少なくとも小学校低学年までは読み聞かせを続けるつもりでいる。
絵本は家族の一員であり、わが家の財産であり、思い出のいっぱいつまった娘たちの嫁入り道具なのだ。
…………
vol.10「休日の山隠り」2004/07/20
夫が不定休のわが家は、休日は仲間と山で過ごすことが多い。
車などの危険から守ってやらねばならない住宅街と違って、田舎や山ではギリギリまで「危ない!」を言わずに見守ることができる。
山菜や草花を摘み、泥団子を作り、蛙や沢蟹を捕まえる…。
親の目から解放された子どもたちで遊びを考案し、いきいきと目を輝かせている。
一方、親の方も、そんな子どもたちを遠目に見ながら雑談し、しばし子どもたちから解放される。
田舎は大人のストレス発散にもってこいなのだ。
就学前の子どもたちに必要なのは知識を詰め込むことでも、何かを教え込むことでもないと思う。大人の監視下に置かれずいたずらしたり、おやつの時間も忘れて遊びに没頭する体験。喧嘩をしたり生身の人間と体当たりでぶつかる経験を今のうちにいっぱいさせてやりたい。
しあわせな幼年時代の記憶はどんな財産にも勝ると信じて週末は田舎でせっせと思い出作りをしているのだ。
…………
Vol.11「『良い子』にしない子育て」2004/08/20
「代わってあげなさい」「貸してあげなさい」「謝りなさい」…世間体を気にして子どもを叱った経験はないだろうか。
私たち大人は我慢や妥協ができる子を「良い子」と評価しがちだが、友情や思いやりなどは成長と共に徐々に芽生えていくものだから、大人の権威によって「良い子」に仕立ててはいけないと思う。
子どもは子ども同士の中で気付き学ぶことが大切だと感じ、今は仲間と一緒に子育てをしている。
そこでは物や遊具の取り合いなどの「もめ事」はできる限り子どもに解決させ、過干渉しない、が暗黙のルール。
「みんながお母さん、みんなが子ども」をモットーとし、よその子だからと遠慮したり媚びたりしない。
社交辞令で子どもを叱る必要もなければ、小言を言う機会も少ないので親も楽である。
大人が危険を排除しすぎたり平和を求め過ぎたりするあまり、子どもの冒険心や生命力を奪ってしまわないように、一歩離れた場所から子どもを見守っていきたい。
…………
Vol.12「我が家のスローライフ」2004/09/20
お金さえ出せば何でも入手できる今、「捨てれば良い」「買えば良い」という風潮が子どもにまで浸透している。
大量消費、スピード化により大切なものが着実に失われ、環境破壊が加速していく。
そんな時代だからこそ私は極力手づくりをする。
キャラクターグッズに負けないように手づくり品には気合いを入れ、子どもの癒しである「お人形」は私のお手製。
手仕事をする姿を見せたくてわざわざ子どもの目の前で作ることも多く、娘はそんな私を傍らで感じながら好きな時間を過ごす。
洋服がほつれたりおもちゃが壊れても「直してあげるね」と意識して話し、ゴミになるものを極力買わず、リサイクルに依存しすぎず、「マイ箸」を持参し、できるだけ環境に優しい生活をする。
農業体験をさせて「食べ物が食卓に上がるまで」の過程を見せる。
少々回り道のように感じるけれど、そんな大人の背中を見せることが、心豊かな子どもに育てる「早道」であると思っている
…………
Vol.14「子どもの絵」2004/11/20
私たち夫婦は娘の絵の大ファン。
小一時間、集中して描いた絵には、幼稚園の園庭で遊んでいる子どもたちの様子がびっしりと描き込まれており、表情が豊かで躍動的であると親バカながら評価している。
某集まりで絵を描く時があり、周囲の親御さんが子どもに「太陽は赤に塗りなさい」と言っていたが、果たして太陽は本当に赤色だろうか?
また「おめめは?お鼻は?お口はこうよ」と口出しをするのも余計なお世話である(それは子ども自身が気づくべきこと)。
親が期待し干渉すれば子どもは大人に誉められるような「作られた絵」を描こうとしてしまう。
私たち大人は一見、見栄えがよくバランスのとれた絵(作品)を評価しがちだが、それよりも大切なことは「描いている過程」ではないだろうか。
テレビを消すなどして集中できる環境を整えて、子どもが自分の世界に没頭できるように声を掛けずにそっと見守ることが「親の役目」だと私たち夫婦は思っている。
…………
Vol.15「クリスマスプレゼント」2004/12/20
わが家では「サンタさんは今のあなたに一番相応しいプレゼントを選んできてくれる」と言っているので、毎年、親が選ぶことができる。
玩具売り場に行くことも、チラシを見る機会もない娘は、たいして物欲もないようで「今年は何をくれるんだろう」と心待ちにし、何を贈っても「サンタさん、私が一番欲しかったもの、ちゃーんと分かってくれてたんだ!」と大喜び。
子どもの要求を聞いてあげることは「愛されている」自信にも繋がるので時には必要だとは思うが、見る目の養われていない乳幼児期は、子どもの成長に合った良質な玩具をできるだけ大人が選ぶべきだと思っている。
去年のプレゼントには積み木を選び、夜な夜な積み上げておいた。
基尺の揃った白木の積み木はは飽きが来ず(数さえ揃えば良質な積み木は小学生でも十分楽しめる玩具です)今でも彼女たちの宝物となっている。
今年は「絵本」を足跡のように並べておく計画なのである。
…………
Vol.16「子どもは『今』を生きる」2005/01/20
今春、いよいよ長女は卒園する。
3月の末が誕生日の彼女は6歳になった途端に入学するようなもの。
「勉強」「宿題」とは無縁な世界で本当はもっともっと遊ばせてやりたかったのになぁ(早生まれは「幼児期」が短いのよね)。
「大人の遊び」は休息や快楽、ストレス解消だけど、「子どもの遊び」とは困難に挑戦することや発達しようとすること(昨日よりももっと高く木登りしたい、もっと○○が上手にできるようになりたい)なのだそう。
「子ども時代」は長い人生の、ほんの僅かな期間である。
それなのに早期教育や習い事の出現で、年々「子どもの時間」が少なくなってはいないだろうか。
大人の監視から離れて仲間と遊ぶ子どもたちは心底笑い、とても輝いて見える。
「あぁ、今日も1日楽しかった!」の娘のセリフを聞くことが私にとっては至福なの(それ以上に望むことって他にはないかもしれない)。
子どもにとって大切なのは「今」が満たされていることだと私は思う。
…………
Vol.17「子どもは『今』を生きる2 ~プレーパーク~」2005/02/20
子どもの頃に秘密基地で遊んだような心ときめく思い出はありますか?
私たち仲間は今の子どもたちにそんな経験をさせたくて、「プレーパーク(冒険遊び場)」を豊田市に作ろうと活動している。
「プレーパーク」とは遊具のある整然とした遊び場ではなく、廃材が転がっているような雑然とした遊び場のこと。
そこには「禁止事項」はなく水、土、泥から生まれる遊びや、火を使った食事作りなどが誰でも自由にできる。干渉はせず、「怪我はお互いさま」をモットーとしているから責任追求もしない。
喧嘩をするから痛みや優しさ、ルールを知り、怪我をするから危険を知る。
子どもには怪我をしてでも挑戦したいことがあるのだ。
テレビやDVD、教材では決して知ることのない「生の人間ドラマ」がプレーパークにはある。
子どもが大きくなった時、「幼少の頃」の輝かしい思い出が困難に立ち向かう力になるといいな。
一緒にプレーパーク、作りませんか?
…………
Vol.18「『戦闘系おもちゃ』について考える」2005/03/20
男の子の遊びの一つに「戦闘系」がある。
男の子は本能的にそれらを好む傾向にあるようだ。
「痛みや力加減を知れるから」と肯定的な意見の一方で「平和を子どもに教えることができない」と否定的な意見もある。
国民が国に対して「武器のおもちゃを作らない」「売らない」運動をし、それを実現させた国もあると聞く。
日本の玩具メーカーは「儲ける」ためだけにそれらを作り、1年ぽっきりで処分してもらうために次々に新しいヒーローを作っていくそうだ。
昔から「ちゃんばらごっこ」のような格闘系の遊びはあったが、ではなぜ今、問題定義をされるかと言えば、今の子どもたちがメディアで日常的に「殺りくシーン」を見ていることにある。
親自身に戦争経験がなく、子どもが「死」を身近に感じる機会がないまま、バーチャルリアリティ(仮想現実)の中で「死ね」「殺す」と唱えながら遊びに興じている。
実像と虚像の区別がつきにくい幼児期は特に、玩具メーカーに煽られて子どもを戦闘意識に導くことは避けたいと私は思う。
…………
Vol.19「子どもの叱り方」2005/04/20
まったり系の次女(年少)に比べ、小1の長女は私と性格が似ているせいか衝突することが多い。
ついつい感情的になり、くどくどと叱り、なかなか気分転換できない私…反省の毎日である。
そんな中でできるだけ気を付けていることがある。
それは
「お姉ちゃんなんだから」と言わない。
人格を否定をしない(「あなたは悪い子」ではなく「あなたのことは好きだけどこれは間違ってる」と伝える)。
責任転嫁しない(「○○に怒られるよ」ではそれが何故悪いのか伝わらない)。
失敗は咎めない。
的外れな脅しはしない。
他者と比較しない。
本来の「叱る目的」とは「自分の間違いを気付かせ、さらに自信を持たせること」なのだそう。
自己を省みた結果、自然発生的に「ゴメンナサイ」が言えることが理想だと思うから、小さい子どもに強制的に謝らせることはしたくない。
一旦、子どもの気持ちを汲んでみると叱るべきことって、意外と少ないのかもしれない。
…………
Vol.20「子どもの誉め方」2005/05/20
「叱るより誉めて育てたい」とは常々思っているが、実はこの「誉め方」こそが難しいと感じることがよくある。
子どもが「大人にとって都合の良い行動」を取った時に適切でない誉め方をすると、それは一種の「成長促進剤」として子どもを背伸びさせ、大人の顔色を見て動く子どもにしてしまいそう。
「叱られるからしない」と「誉められるからする」は結局は同じことよね。
では、私の考える「子どもに自信を持たせる誉め方」とは…具体的に誉める(あなたのしてくれた○○がとても助かった。ありがとう)ことと、結果だけでなく努力したプロセスを評価すること。
一生懸命努力して失敗した時こそが誉め時なのかも。
子ども自らが「がんばった」と思えた時にその気持ちを大切にし、共感して代弁できれば理想ですね。
逆に、そうそう努力もしないのに結果的に良かったことについては取り立てて誉めることはしなくて良いと思う。
育児とは「親育ち」…日々勉強なのです。
…………
Vol.21「冷たいジュースにご用心」2005/06/20
我が家では年中、常温の「お茶」をやかんに常備し、ジュースはほとんど飲まない。
市販のジュース(350ml)には、スティックシュガー8本相当の砂糖が入っていると聞く(多いものでは17本分よ!)。
添加物、冷たさ、炭酸などは甘味を感じさせなくするそうだ。
一説によると適切な砂糖摂取量は体重1kgにつき1g(以下)と言われており、過剰摂取はイライラ、無気力、無関心、生活習慣病を引き起こす。
これからの季節は汗をたくさんかいて老廃物を排出するチャンス。
2才までにどれだけ汗をかいたかで一生の汗腺の量が決まると聞く(汗腺が少ないと、生涯に渡って温度調節できない体になってしまう)から子どもにはたくさん汗をかかせ、常温のお茶で水分補給するのが理想。
少なくとも、冷房の効いた部屋でキンキンに冷えたジュースをガブ飲みさせるのは避けたい。
我が子が「冷たいもの中毒」にならないよう、まずは幼稚園、学校に持参するお茶から見直してみませんか?
…………
Vol.22「子どもの靴の選び方」2005/07/20
キャラクターのビニール靴を買ってもらえなかった私は「足は大事」と刷り込まれつつ(?)成長し、やっぱりこの手の靴を選択しない母となった。
見た目と価格が重視されることが多い日本と違って、ドイツなどでは「靴」は足の健康を守る「体の一部」と考えられ、お下がりやリメイクなどで洋服代を節約した分で靴に投資する人が多いそうだ。
赤ちゃんの足の骨は約70%が軟骨でできているから、柔らかい靴を良しとはせず?革などの呼吸する素材で、くるぶしまでしっかり支えられるハイカットのものが理想。
また、子ども靴の1cmは、大人サイズの2cmに相当(!)するそうなので0.5cm刻みのジャストサイズを選びたい。
スリッポンタイプは「履きやすさ」と同時に「脱げやすさ」も兼ね備えているからできれば避けたい。
「足は第2の心臓」「幼少期の靴選びは一生の健康を左右する」と聞いてしまうと「たかが靴」とは思えないのである。
…………
最終回「『生きる力』が育つように」2005/08/20
私は現在、母親6年生。
「子ども」という存在のおかげで、多くの事を経験し、学び、素敵な人々と出会えることを感謝している。
今は情報が氾濫し、企業はあの手この手で子どもをターゲットにしてくるから、アンテナを張って正しい情報を得るよう努力したい。
育児において大切なことは「将来のため」と幼児期から勉強を教えたり先回りしてレールを引くことではなく、「興味の芽」を摘み取ってしまわないように子どもの成長課程を知り、子どもの心と対話し、しっかり受け止めることだと思っている。
小1の長女は随分自立したが、次女はまだまだママっ子。
次女の小さくて柔らかい手を握っていると、私に絶対的な信頼を寄せていることがひしひしと伝わってくる。
この温かい小さな手が母の手を振りほどき、自力で駆け出すようになるまで、この蜜月の日々を大切に過ごしたい。
全ての親子に温かい眼差しが注がれる社会になることを祈っています。長い間、有難うございました。
…………
「我が家の子育て日記」(2002.2月〜4月)
http://blog.goo.ne.jp/banbiblog/e/68e3779621db34f3231a10e81314ffaa
「我が家の子育て日記」(2002.5月〜6月)
http://blog.goo.ne.jp/banbiblog/e/d92d944ca6df74ef5f0c7153b4ed7449
「我が家の子育て日記」(2002.6月〜8月)
http://blog.goo.ne.jp/banbiblog/e/6129e297b32a7586d255607efcefab7f
「我が家の子育て日記」(2002.9月〜11月)
http://blog.goo.ne.jp/banbiblog/e/1f77652b13f925405d439190dd906ffc
「我が家の子育て日記」(2002.11月〜12月)
http://blog.goo.ne.jp/banbiblog/e/3ab67243a4a7194564617bf90d35bce0
「我が家の子育て日記」(2003.1月〜2月)
http://blog.goo.ne.jp/banbiblog/e/e9d8351b8bb954e1605aece940c08aef
「我が家の子育て日記」(2003.2月〜4月)
http://blog.goo.ne.jp/banbiblog/e/f88c93f4bc85ed344c9669a4ac6b1c90
「我が家の子育て日記」(2003.2月〜4月)
http://blog.goo.ne.jp/banbiblog/e/736c9f92aae118808932a861a3286127
「我が家の子育て日記」(2003.4月〜5月)
http://blog.goo.ne.jp/banbiblog/e/85335d4bc0fb02e911d03b6e3d962fe0
「我が家の子育て日記」(2003.5月〜7月)
http://blog.goo.ne.jp/banbiblog/e/67bac59cbaaf6cd6b7c4f7dd54a34d08
「我が家の子育て日記」(2003.8月〜10月)
http://blog.goo.ne.jp/banbiblog/e/7041ae1ac8214c526637ab556c8ca44e
「我が家の子育て日記」(2003.10月〜12月)
http://blog.goo.ne.jp/banbiblog/e/274578788f8a3b7956402af33d171997
「我が家の子育て日記」(2004.1月〜2月)
http://blog.goo.ne.jp/banbiblog/e/a401c61f189f79dc819b991cab6cad13
「我が家の子育て日記」(2004.3月〜6月)
http://blog.goo.ne.jp/banbiblog/e/d11ca2d29a35b79b0f2944cc847b5b30
「我が家の子育て日記」(2004.6月〜9月)
http://blog.goo.ne.jp/banbiblog/e/67002a64207030a57c4eb93577b7319f
「我が家の子育て日記」(2004.9月〜2005.1月)
http://blog.goo.ne.jp/banbiblog/e/1a076f957ab6fdc51d583d82ad487cfd
「我が家の子育て日記」(2005.1月〜8月)
http://blog.goo.ne.jp/banbiblog/e/f71cda39230c83de35e4852f65b18055
豊田市発行のタウン紙「ぴポ」コラム「こだわり自然派子育て」2003.10.20〜
http://blog.goo.ne.jp/banbiblog/e/81e4a9a8653f0156ef8f6ed8b9272978
我が家の暮らし紹介(2005.3)
http://blog.goo.ne.jp/banbiblog/e/7542984fdb86254272133f8533220c4a