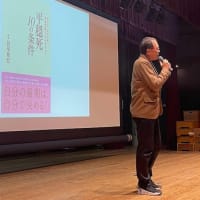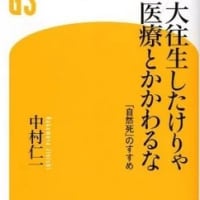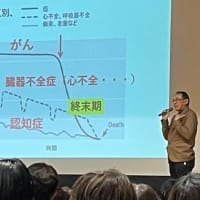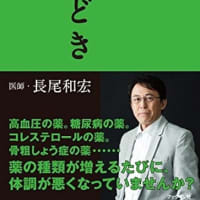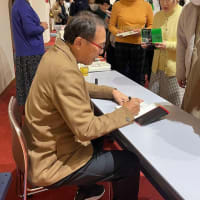「ウォルドルフ人形(はなちゃん)完成!」2003/10/13
2回の講習会(計14時間ほど)を経て、ようやくお人形が完成しました。
いやぁ、疲れた疲れた。
でもね、不思議と嫌な疲労感はなく、懲りもせず「また作りたい」と思ってしまうから不思議。
それに「体力勝負。汗だくだよ」と聞いてビビッていたほど大変ではなかったかな?というのが感想(「案ずるより生むが易し」ってやつね)。 このお人形、完成後の愛おしさもさることながら、製作段階においてもすごく意味があると思ったの。
このお人形、完成後の愛おしさもさることながら、製作段階においてもすごく意味があると思ったの。
目のくぼみをつくり、後頭部を作る。
耳の位置を観察し、腕は背中からつけるetc…「人間の体ってこうしてできているんだ」とか「子どもの頭はこういう形をしているのか」とかいろんな発見をするの。先生も1体1体を「この子」って呼んでいらっしゃったし、もはや製作段階から「お人形」ではなく「子どもの分身」という感じ。
意外だったのは、「子どもの前でお人形を作ってはいけない」ことと「製作途中を見せてはいけない」ということ。
手仕事ってわざわざ子どもの傍らですることに意味があるけれど、人形に関してはそれはタブーだそうだ。頭や体に針を刺していく行為や手足がバラバラの状態は幼い子どもにとってショッキングなんだって。
(知っておいて良かったよ…)。
完成した人形にウサコは「はなちゃん」と命名し「うちの家族1人増えて7人になったね★」ととっても嬉しそう。
頑張った甲斐があったわ(良かった~☆)。
今後もパジャマなどの着替えは私が、セーターなどの編み物はばーちゃんが、ベッドなどの家具はだんなが作成していく予定。
彼女にとっての永遠の「無二の親友」となってくれますように。
はなちゃん、ウサコを癒してやってね!
(今まで宝物だった「GAPのくまさん」はノンちゃん専用になりました。めでたし、めでたし)
ところで、シュタイナー教育をしている友だちの娘にSちゃん(小学1年生)がいるが、空想の世界にどっぷり浸かり「ごっこ遊び」がだ~い好きだったSちゃんは、小学生になったとたん、教科書を隅々まで何度も何度も読み返したり、絵本ばーっかり読んでいたり、「ごっこ遊び」をする時間がずいぶん減ってしまったそう。
「本当はもっとごっこ遊びして欲しいんだけどね…。やっぱり、みっちり遊べるのは幼稚園までだよ」って友だちは嘆いていたわ。
「宿題も出るし、かなり現実にさらされるよ」だそう。
…ということはウサコが「夢見る少女」でいられるのは後1年半(3月終わり生まれだから1年損してるのよね)。
タイムリミットは刻一刻と迫っている。いかに想像力を膨らますことができるか。1分1秒でも長くぼんやりと過ごさせてやりたいと思う母なのだった。
…………………
「公園の事情」2003/10/17
いつも通う公園のそばに家が建った。
「子どもと同い年の子が来るといいな」というほのかな期待はまるで裏切られた。
そこには小学生、中学生、高校生の3人の男の子がおり、公園は思春期真っ盛りの中高生の遊び場となってしまったのだ。
ズボンをお尻まで下げた(今時の不良のスタイルなのかな?)10人くらいの集団が公園に点在し、タバコを投げ捨て、公園内をバイクで走り回り、もちろんゴミは放置して帰る。
ノンちゃんは指を差し興味深々だが、ウサコは事あるごとに怯え「ノンちゃん、そっちに行ったら危なーい!ママ、ちゃんとノンちゃん見ててよ」と絶叫し、「バイクの音、うるさいね」「ゴミ、ちゃんと持って帰らないとダメだよね」と訴える。
…公園に彼らがいることが憂鬱だった。
忠告したくとも逆恨みされたら困る。
ゴミを届けがてら母親に文句でも言いに行こうかしら?なーんていじわるな計画を立てていた矢先、「あそこのお母さん、夜、ゴミを拾いに来てるよ」「ご近所からクレーム出てるって」と聞いて、何だか怒りが一気に覚めてしまったのだ。
一番苦悩しているのは母親かもしれない。
友だちに聞いたある家庭の話で、両親とも温かい5人兄弟、そのうちの3人は真面目に生きているけれど残りの2人は正反対の生活を送っているそうだ(警察沙汰だったり、借金取りに追われるほどの…)。
訳を聞くと「原因があるとすれば、親が忙しかったことと、厳しく叱らないことかな?」と友だちは言っていた。
もし本当に原因が「厳しく叱らなかった」ことならば、きっとこの両親は、子どもの悪い行いを「厳しく言わずとも分かるはずだ」と温かく見守った結果だったのだろう。
もしそうならば、親が正しい行いをしていて愛情さえかけていれば育児は大抵上手くいくものだと過信していた私の考え方は甘い。
ものすごくショックだった。
子どもが親の希望どうりに育つかどうかはわからない。
「できればそうあって欲しい」と願って育てているには違いないけれど「これなら絶対」ということなど何もないのよね。
加害者と言われる子どもや親を疎外することや「臭いものに蓋」をすることは簡単だけど、それでは何も解決しない。
そうなってしまった経緯や背景を考えたり、その親子と一緒に乗り越えていくことも時には必要なんじゃないかな?と思う。
(いじめっ子の多くは、自分がいじめられた経験があったり、親に辛く当たられていた場合が多いそうだ)
自分の子が「回り道」をしていることが子育ての失敗だとは言えない。
公園の少年たちも、今は成長の過程でそういう行動に出ているだけであって本当は心優しいのかもしれない。
そう思い始めてからウサコの反応にも「あのお兄ちゃん、今優しい顔してたよ」と変化が出てきたから、親の心持ち次第なのかもしれないね。
……………
「おひさまクラブ発足」2003/10/24
私ってなんだか多忙人間。
テレビとも3年くらいご無沙汰しているというのに、目を通しておきたい書類の山が机にてんこもり。
1日がもっと長ければなぁとよく思う。
多忙な理由
- 今は生活クラブの役員をしているので会合やら試食会やらに出席することが多い。美味しいご飯をご馳走になったり、素敵な先輩ママさんがいっぱいなので楽しいの。
- 手仕事がしたくてウズウズしてる。漆のお弁当箱に合う袋を姉妹お揃いで作ったの。そうそう、早くはなちゃんのパジャマも作らなくっちゃ。できれば忘れないうちにウォルドルフ人形をおさらいしておきたい。
- 12月に行われる幼稚園のクリスマス会でゴスペル発表があるので、週2ペースでレッスンに行ってるの。お腹から声を出すのって気持ちいい!ストレス発散には歌がイチバン。
- 土日のお休みにはできるだけお弁当を持って自然の多い場所に繰り出したい!
- 秋は講演会のシーズン(?)。参加したい講演会がいっぱい。
- 図書館から借りた「読みたい本」が山積みされてる(何度も借り直し)。
- タウン紙にて、夢にまで見たコラムのお仕事。イラストも。
- マザーハウスのバザーの準備

そう、楽しいことだけでスケジュールはギッシリ。
それに加えて、毎日の食事作りと、子どもとの公園通い、夜7時からの「お布団で読み聞かせ」だけは何があっても手抜きできない。
そしてそのしわ寄せで「家事を手抜き」せざるを得なくなってるのだった。
ワッハッハ。
掃除担当のだんなさまは時折「たまには掃除してよ~」なんてボヤきながら休みには家事に明け暮れております。
で、気付いてしまったの。我が家がウサコ中心で回っていることを。
「ウサコの帰宅~8時就寝までは子どもにみっちりつきあう時間」って感じで午後からの予定は全く入れていないので用事はすべて午前中。
結果、ノンちゃんはいつも私に連れ回されている状態なのさ。
そこで、「ノンちゃんペースで過ごす時間を作りたい!」とサークルを発足したの。
名付けて『おひさまクラブ』。
子どもの歩調に合わせてお散歩し、お弁当を食べて、野外で絵本を読む!それだけのシンプルな内容。
晴れの日だけじゃなくて、雨の日はカッパを着て雨を感じたり、風の強い日、雪の降る日にも遊びはいっぱいあるはず(それは子どもが教えてくれるでしょう)。
「自分の子」ではなく「みんながお母さん、みんなが子ども」。
ケンカも反抗期も大いに結構!
「仲良く順番に」を強調するのはやめておきたい。
野外だから料金も要らないし、参加も欠席も自由。
今日、第1回目を開いたけど、集まってくるママさんはみなさん素敵な方ばかりなの。
口コミでどんどん広げていく予定。
毎週月曜日に活動をしています。
……………
「子どもらしさ」2003/11/11
最近、嬉しいことがあったの!
「子どもは子どもらしく」というのが私の育児の基本理念だというのに、ウサコは赤ん坊の時から少し大人っぽい子どもだった。
やたらと冷静だったり、的を得たことをズバリと言うので「賢いよね」「大人だよね」と評されることが多く、何だか複雑な思いだった私。
それがこの度、初めて「うーちゃんはとっても純粋で素朴な子ですよ」と担任の先生に言ってもらえたの。
わ~い!(これよ、これ。聞きたかったのはこの言葉なのよ)。
「遊びの中にもお絵画きにも工作にもみんながワッと驚くような『うさこワールド』が炸裂しています」ですって!ほほほー。
思わず「そうなのね、そうなのね」とニンマリし、ウサコにハグハグしてしまった。 甘えん坊の超泣き虫だったウサコも、年中さんになった辺りから随分自立し、友だちと一緒にいる時は本当にイキイキしているし(こうなるとどうやら大人は邪魔らしい)、今ではひとりで机に向かって黙々と絵を描いている時間も随分増えて、本当に手がかからなくなった。
甘えん坊の超泣き虫だったウサコも、年中さんになった辺りから随分自立し、友だちと一緒にいる時は本当にイキイキしているし(こうなるとどうやら大人は邪魔らしい)、今ではひとりで机に向かって黙々と絵を描いている時間も随分増えて、本当に手がかからなくなった。
寝る時も「ママと抱っこして寝ると暑いし苦しいんだよね。手をつないであげるから離れて寝て」なんて言われる始末(どっちが親なんだか…)。
病院の待ち合い室でも公園でも友だちを作るのは大得意。
ウサコ曰く、「お友達を作るにはね、目が合ったら笑うの。それを何回もやってたらそのうち、向こうもニコッとしてくれるんだよ」だそーだ。
キリスト教幼稚園なだけあって他者に対する思いやりも深くて(毎日、お休みしたお友達を想い、お祈りをするの)入院したお友達に「早く元気になりますように」と願ったお手紙を毎日描き、泣いているお友達の気分転換をさせようとホッペにチュウをして「うんちモリモリ、おしっこジャージャー」と言って笑わせているそうだ。
言葉はともかくとして(笑)何て粋なはからい!母は感動したよ。
一方、反抗期を目前に控えたノンちゃんも、少々手こずる時間は増えたものの、とても落ち着いていると思う。
窓の外を眺め、鳥を見て喜んだり、雨の音を「ぽったん、ぽったん」と楽しむ。
絵本が大好きなので広げて見入っている時間も多いし、大人の気配さえあれば一人遊びも十分にできる。
持って生まれた気質も関係していると思うが、生後まもなくからテレビ音のない、自然と共存した環境で育ち、リズムのある生活を心掛けてきた成果だと思っている。
「パパちゃん、だ~いすき」
「みんな、だ~いすき」。
愛されることに慣れているノンちゃんからは「幸せ」のオーラがプンプンに漂っているのだ!
本来、子どもは誰でも無垢で純粋で素朴な生き物なんだと思う。
今の子どもがやけに大人びているのは、早くから子どもを「小さな大人」に仕立ててしまっている大人の責任に他ならない。
アイドルを低年齢化し、「子ども」をターゲットにする企業にとって、必要なのは利益だけで子どもたちの未来などどうだっていい。
乳幼児期に大切なのは、見えない心の成長。
できるだけシンプルに自然とふれあって生活をしていれば、きっと子どもが可愛く育つ、と断言できるほど自己満足。
………………
「砂場遊び」2003/12/04
「一軒家に引っ越ししたので、サンタさんのプレゼントは砂場です」とお客さんのSさんがメールを下さった。
それ、他のどんなプレゼントよりも素晴らしいじゃないの!と客観的に感動していたら、ふとあることに気がついたのだ。
「うちって砂場ないじゃん」…。
せっかく一軒家に住んでいて小さいなりにもそれなりに庭があるというのに、我が家の庭は「子ども仕様」になっていないのだ。
それには言い訳もある。私たち夫婦は落葉樹が好きでその落ち葉に風情を感じるのだが、一方、同居の実父は日本庭園のような整然とした庭が好きで毎日丁寧に落ち葉を掃いてしまう。
「頼みの綱」と期待して母に助けを求めると「落ち葉が良いのは分かるんだけど、洗濯物を干す時、雨上がりの落ち葉で足が濡れるのが嫌なんだよね」だって。
ガッカリ。
洗濯担当の母のご意見(現場の生の声?)には反論できません…ということで、私たち好みの「季節感のあるゴチャゴチャした」庭作りは、私たちの代になるまでお預け!ということが暗黙の了解のうちに成立していたのだ。
でも「それじゃ遅い」のよね。
そうこうしている間に子どもたちが成長してしまうもの。
今更ながら気付いたわ。
Sさんありがとう 泥んこ遊びや、砂場遊びは子どもの発達に必要不可欠なものらしい。
泥んこ遊びや、砂場遊びは子どもの発達に必要不可欠なものらしい。
自由自在に形が作れるので想像力(創造力)も養われるし、砂や泥を触っていると気持ちが落ち着くものだそう(日本で箱庭療法は「サンドセラピー」と呼ぶそうです)。
そして、水、砂遊びをすることによって前頭葉が育つ。
前頭葉は社会的知性や感情的知性を司るもので、前頭葉がきちんと発達していれば、マナーが守れたり、場の空気を察知できたり、我慢のできる人に成長するのだ。子どもたちが将来楽しい人生を送るためには、小さいうちにきちんと前頭葉を育ててやることが親の責務なのだろう。
ウサコは動物アレルギーなのでネコのトイレと化していた公園の砂場ではあまり遊ばせなかったが、次女ノンちゃんはアレルギーを持っていないし、2人目という余裕も手伝って(2人目って細かいことが気にならない)。
「泥んこ大歓迎!」「ネコの糞?ま、いっか」といった感じで砂場に座らせていつも夢中になって遊んでいる。
もし庭に砂場があったら、好きな時に制限なく砂遊びができるから、ウサコの今までの分も取り戻しできるかも!
思い立ったらいてもたってもいられなくなって、だんなに作ってもらったのだ~!
「いかに砂場で遊ばせるか」が勝負なのさ。
……………
「おススメ!キリスト系幼稚園」2003/12/05
シュタイナー幼稚園の話を聞く度にいつもうっとりしてしまう。
子どもたちの工作はまさに「手仕事」と呼ぶべき美しいものだったり、森でハンモックに寝そべったりするそうだ。
全粉粒の小麦粉でパンを作る経験が当たり前のようにできるなんて夢のよう。
来春から入園する友だちの話では、準備品として、ブロッククレヨンが汚れないように、クレヨンを1色づつ入れるためのポケットをつけた袋を作るらしい
(保育にブロッククレヨンを使わせてくれるなら、そんな苦労ちょろいもんよね)。
各市に1つづつでもシュタイナー幼稚園があればいいのに…。
「お勉強」「習い事」に目くじらを立てている母親も、全く正反対の保育をしている園の存在を知れば「?」と立ち止まることができるかもしれない。
昨今の育児に警鐘を鳴らすという意味でも必要だと思う。
でももしシュタイナー保育園が近場にないのならば、キリスト系をオススメする。
私はクリスチャンではないけれど、幼い子どもに宗教心を養わせることはとっても大切だと思う。
雨が降れば「雨を降らせて下さってありがとうございます」と喜び、休んだ子どもがいれば「どうか1日も早く良くなりますように」と祈る。
たとえそれが娯楽の為の休みだったとしても「無事に家に帰ることができますように」と祈る。
「お家の人をお守り下さい。先生やお友達をお守り下さい。病気の人や困っている人たちを助けて下さい」と唱える。
だから子どもたちはみんな優しい。
そして覚えてくる歌が可愛い。
いつもウサコに教えてもらっては、感涙しながら2人で歌っております。
「わたしたちのたべるもの」
- 私たちの食べるもの 田んぼのお米もお野菜も 光をおくり雨を降らせ
育ててくれたのは神様 感謝しましょう 神様ありがとう - 忘れちゃいけない それは作ってくれた人のこと
土を耕し種を巻いて 大事に育ててくれました - お百姓さま ありがとうありがとう
今日は幼稚園の「お母さんのためにクリスマス会」に参加してきた。
ゴスペル初心者だというのに図々しくソロに立候補して(自分を崖っぷちに追い込むと頑張れるタイプなのよね)熱唱してきたのだ。
暑い季節からずっと、この日のためにみんなで集まって練習してきたの…なんだかジ~ンとしてしまった。
話したこともなかったママさんたちともずいぶん仲良くなったし。
ゴスペルクワイヤの他にも夫婦で弾き語り(オールディーズを披露。カッコ良かった~)をした方もいて、笑いあり涙ありの楽しい会だった。
シュタイナー幼稚園ではないけれど、R幼稚園に私は大満足なのだった。
………………
「生き物の命」2003/12/11
写真展「サバンナに生きる」を観に行った。
雄大な大自然、野生動物の親子が寄り添う姿など、アフリカに生きる動物たちのありのままを写した迫力のある写真展だった。
写真家の宮嶋さんがそこにいらしたので「撮影していて危険なことはないのですか?」と尋ねると、驚くことに「一番恐いのは密猟者なんです」というのが答えだった。
密猟者は摘発されるのを恐れて、人がいれば辺り構わず打ち殺すので、宮嶋さんの仲間も銃殺されてしまったらしい。
「恐いのは動物じゃなくて人間」…意外だった。
聞けば、象牙を1本売ると家族が1年間暮らせるだけの収入になるので密猟者はこぞって象を殺していくそうだ。
象は情が深いといわれていて、仲間が1頭殺されると何十頭もの象が集まって悲しみそこをしばらく離れないらしい(だから密猟もし易いとか)。
「アフリカには無惨な象の死体がゴロゴロと転がっている」と他でも聞いたことがあった。
そのせいで象の数も激減しているとの話。
私はこの話を聞いて憤りを感じた。
私腹を肥やす為だけに動物を殺す人間は卑怯ではないか?
自然界は弱肉強食の世界なので、残酷に見える捕獲劇もきちんと理にかなっている。
動物はお腹がすいているときにしか獲物を捕まえない。決して無駄に殺さない、それで自然界のバランスは保たれているという。
人間はどうだろう?毎日大量の食べ物が処分されていく。捨てられる食肉も多いことだろう。
「BSE問題の詐称事件」では、企業は国産牛と偽って大量の輸入肉を焼却処分したそうだ。
食の安全神話が崩れたり、企業不信などの物議をかもしたが、私が何よりも憤慨したのは人間の勝手な都合で牛の「命」が粗末にされたこと。
人間のどこにどんな権利があってこんなことが許されるのだろうか?
私たちは地球に住む全ての生き物の恩恵を受けて生きていて、それぞれの生き物には生きる意味があるのだといわれている。
遺伝子組み換え、密猟etc…生態系や自然のバランスを崩してしまうのは、とても危険なことだと思う。
象牙の輸出先は日本と中国だそうだ(象牙の輸入は日本でも解禁になったらしい)。「象牙の印鑑」の背景にはたいした意味もなく殺された象の姿がある。人間の贅沢のために殺されているのは象だけではない。
加工され製品になるまでに何が行われているのか、消費者として知っておくべきことは他にもたくさんあるように思う。
………………
「2階へ引っ越し」2003/12/20
我が家は二世帯住宅である。
二世帯といえどもうちのだんなさんは「マスオさん」つまり私の実父母との同居なので完全分離にする必要もなく、玄関は「2階と吹き抜け」だし階段にも間仕切りがないので、声は丸聞こえのほぼ一世帯状態なのである(キッチンとお風呂は2つあるけどね)。
そしてウサコ出産後も仕事をしていた私は、母に子守りを頼んでいたこともあり、いつしか食事も生活も一緒になっていた。
そして月日が流れること5年…。
その結果、娘は2人とも超超超ばーちゃんっ子になってしまった。
母は子どもが大好きで、感情的に怒ることも私よりずっと少ないし気持ちの切り替えも早い。
根気良く相手もしてくれるし、あやとりや折り紙、童謡を歌ってくれたりと孫にとっては理想的なおばあちゃんなのである。
うん、確かに「子どもたちと祖母」いう意味ではとても良い関係なんだけど、我が家の場合は問題点も多々あるのだった。
子どもたちはばーちゃんさえいればOKなので「我が家4人」としての絆が薄いこと。
娘2人は「ばーば争奪戦」で四六時中ケンカばかりしていること。
じじばばの許容の境界線が私より甘いので子どもたちは「ダダをこねれば許してもらえるかも」といつまでもグズグズ甘えてばかりいること。
そして何より困るのは、私に「ダメ出し」されたウサコがすぐに泣いて逃げて行くこと。
「ママが恐い顔してるの。ばーちゃんが幼稚園に連れてって。お迎えにも来てね」
「ママなんて大嫌い。ママ恐いからばーちゃん一緒に寝てね」。
きちんと話し合いたくともウサコはいつも接点を断ち切ろうと逃げるので、私の怒りは解消されない。
「もうダメだー。私、今のウサコのこと本当に可愛くない」とだんなに愚痴ってみたが、だからといって子どもを替えるわけにも家出をするわけにもいかないし…(私は母親だから逃げ道はないのよね)。
そこで試しに生活をきっちり分けてみることにしたのだ。
ばーちゃんに依存しない生活に挑戦。
で、これが大正解だったのである。
ルールが一貫しているからか子どもたちの諦めも早いし泣く回数もグッと減り、私も怒ることがなくなった。
そして家族4人で過ごす時間がとても増えた。
以前よりも家事が多くなった私は必然的に子どもの相手をする時間がなくなったので、結果、姉妹で仲良く遊ぶようになった。
どうやら今までの我が家は「大人が子どもに関わりすぎ」て子ども同士で遊べなかったということらしい。
できるだけ大人が子どもと一緒に遊んでやることが良いことだと思ってきたけれど、兄弟がいるのならば2人の世界を作らせることの方が大切かもしれない(親も楽だしねー)。
相変わらずの下ネタのオンパレードにもウケてくれる妹(「1歳児に下ネタを洗脳すんな!」と思いつつ大目に見ている)。
子どもの「遊びのエンドレス」につきあえるのも、子どものお笑いの世界に心底笑えるのもやっぱり子どもでしかないのだろう。
今までは寝起きが悪くてグズグズと泣いてばかりいたウサコも、起きるとすぐに「ノンちゃん、あっちで遊ぼー」と起きて行く有り様。
仲良しとはいえなかった姉妹も、今では仲睦まじいラブラブ姉妹に様変わりしてしまったのである。
その解決策は意外にも簡単だった。
…………
「除霊」2003/12/23
私がこの世で一番嫌いなのは「お化けネタ」。
物心ついた時からずっと「歌手になること」が将来の夢だったけれど、『スターどっきり!まる秘報告』を見てから気持ちが萎えてしまったのだ。
それは「有名になった時『スターどっきり』のお化けネタで騙されたら恐い」という理由(おバカでご免なさい)。
シュタイナー教育は大好きだけれど、シュタイナーの精神世界の部分にはノータッチなのもそういう理由(その道の方、本当にご免なさい)。
でもその世界を認めざるを得ない時が来てしまったの。
ウサコに悪霊がついていると知人に言われたのだ。
実は2年前にも一度宣告されているが、その時は両耳を塞いで「何も聞かなかったもーん」と言い張っていた。でも今回はどうにも逃げられない状況だった。
なぜならば思い起こせば心あたりはたくさんあるからだ。
小さい頃から寝る前後はとにかく号泣していたし、夜泣きもすごかった。
独り遊びができず臆病者でいつも家族にへばりついていたことも、健康おたくの母から生まれた「謎のアトピー児」というのも気になる点である(医者にも治せない病は霊体が悪さしているという話も聞いたことがある)。
そして幼少の頃から外を指差しては「赤い光が恐い」だのこちらがゾッとするようなことを連呼していたし、最近は「お化けがこっちに来る~」「おじちゃんがうーちゃんを連れてっちゃうー」など毎晩何度も夢に怯えて起きていた。
しかも仲良しのママ友に「聞いてよ~」と助けを求めたら「実はね、私もうーちゃんに霊を感じる時があるよ」っておいおい…、マジかよー(泣)。
行きますよ、行きます。
私は親だもん、「恐い」なんて逃げていられないわね。出費も手間(片道1時間強の道のり)もかかるけど、それでウサコが楽になるなら最善を尽くしてみます…。
ということで、「知人が信用できる人」ということと「その先生が営利目的ではない」という2点を頼りに除霊に行って来たのだ。
不思議な処置(?)をして下さった後で先生は「こりゃ、お化けの夢も見るし、アトピーにもなるわな」とおっしゃった。
どうやら成仏されていない霊がウサコにたんまりついているらしい。
しかも天真爛漫で育て易いノンちゃんにも、順風満帆な人生を送っている私にも、悪霊はついていないということも信憑性が高い。
現在、除霊3回目。
そういわれてみれば夜泣きもしなくなったし、ママ友にも「なんだか最近のうーちゃん顔色いいね」と言われている。
やっぱりそういうものなのかな?
「霊感ゼロ」の私には今でも「???」と思うことばかりだけど…。
……………
「クリスマスの楽しみ」2003/12/25
皆さんはどんなクリスマスをお過ごしになられましたか?
我が家のパーティは、蜜ろうキャンドルを灯し、自家製ケーキと(珍しく)手の込んだ料理を食し、その後は教会で厳かな雰囲気を満喫してくるというのが恒例行事(だんなは留守番)。
そして今年のプレゼントは「童具の積み木」3箱を夜な夜な夫婦2人で積み上げておいたのだった。
朝起きたウサコは度胆を抜かれ、やっぱり今年も「サンタさんはいいものくれたねぇ」と大満足であった(「ゲームをくれますように」と願っていたことなどすっかり忘れた様子…)。
娘の作る建造物は、木を高く積み上げるだけではなく、大きな囲いを作って「町」を形成したり、ドールハウス風に仕立てたりと、大人の想像をこえたバリエーションの豊かさに脱帽しております。
やっぱり子どもは「遊びの天才」だー!
そして「シンプルなおもちゃこそ子どもがイキイキする」と断言するぞ。
 料理の方は、今回、タンドリーチキンに挑戦。
料理の方は、今回、タンドリーチキンに挑戦。
前夜から、ヨーグルト、ケチャップ、カレー粉、にんにく、生姜、レモン汁に漬け込み、オーブンで焼くだけ。
ヨーグルト効果なのか、お肉がとても柔らかだった。
そう、クリスマスは年に1度(?)の、「どどーんと肉料理を食べる日」なのである。
というのも、本来の人間の体には肉中心の食生活は不適切…と聞いてから、 なるべく「肉使用量」を減らす食事を心掛けているので、クリスマスの骨付きチキンは私の密かな楽しみなのだった。へへへ。
人間には全部で32本の歯が生えているが、その内訳はというと、穀物をすりつぶすのに適切な臼歯が20本で、野菜や果物&海藻を噛むのに適切な門歯が8本、肉や魚を引き裂くのに適する鋭い形の犬歯は2本。
つまり、人間に必要な食べ物は5:2:1の割合が適しているそうなのだ。
明らかに肉を食べることの多くなった昨今の日本人に大腸癌や生活習慣病が増えるのも納得よね。
シュタイナー教育や自然育児に興味を持つママさんの中には菜食主義やマクロビオティックを実践している方も多くいるが、私自身が肉好きなので「断つ」ことはできず、この割り合いを念頭において「なるべく減らすように心掛けている」程度。
そして、メインディッシュを迷った時は魚料理を選び、「わかさぎのマリネ」や「いわしの酢煮」といったカルシウムを吸収しやすい組み合わせ(魚+酢など)を意識している。
我が家はほとんど外食(またはテイクアウト)をしない。
だんなは仕事に出ると毎日外食なので「休みの日くらい家で食べたい」ようだし、外食産業で使われている食材に疑問を感じているから、子どもに外食させる気力が起こらない。
以前、おつきあいでランチバイキングに出かけたことがあるが、隣の席では親が子どもに「飲み放題だからどんどん飲みなさい」と初っぱなからコーラにオレンジジュース、メロンソーダなどを浴びるように飲ませ、「食べなきゃ、損」とばかりにどんどん食べさせていた。
一方、ウサコは好物の枝豆をむさぼり食べていたが、その直後の新聞欄に「中国産の枝豆に違法の農薬が検出」。
ウヒョー!である。
それが外食を尻込みする決定的な事件となった。
ま、オーガニックレストランやこだわりのお店ならば大丈夫なのだろうけど、それ相当に出費も多いので「この外食分で絵本が何冊買えるかな?」と計算してしまうケチな私には、これで丁度良いのかもしれない。
…………
「我が家の子育て日記」(2002.2月〜4月)
http://blog.goo.ne.jp/banbiblog/e/68e3779621db34f3231a10e81314ffaa
「我が家の子育て日記」(2002.5月〜6月)
http://blog.goo.ne.jp/banbiblog/e/d92d944ca6df74ef5f0c7153b4ed7449
「我が家の子育て日記」(2002.6月〜8月)
http://blog.goo.ne.jp/banbiblog/e/6129e297b32a7586d255607efcefab7f
「我が家の子育て日記」(2002.9月〜11月)
http://blog.goo.ne.jp/banbiblog/e/1f77652b13f925405d439190dd906ffc
「我が家の子育て日記」(2002.11月〜12月)
http://blog.goo.ne.jp/banbiblog/e/3ab67243a4a7194564617bf90d35bce0
「我が家の子育て日記」(2003.1月〜2月)
http://blog.goo.ne.jp/banbiblog/e/e9d8351b8bb954e1605aece940c08aef
「我が家の子育て日記」(2003.2月〜4月)
http://blog.goo.ne.jp/banbiblog/e/f88c93f4bc85ed344c9669a4ac6b1c90
「我が家の子育て日記」(2003.2月〜4月)
http://blog.goo.ne.jp/banbiblog/e/736c9f92aae118808932a861a3286127
「我が家の子育て日記」(2003.4月〜5月)
http://blog.goo.ne.jp/banbiblog/e/85335d4bc0fb02e911d03b6e3d962fe0
「我が家の子育て日記」(2003.5月〜7月)
http://blog.goo.ne.jp/banbiblog/e/67bac59cbaaf6cd6b7c4f7dd54a34d08
「我が家の子育て日記」(2003.8月〜10月)
http://blog.goo.ne.jp/banbiblog/e/7041ae1ac8214c526637ab556c8ca44e
「我が家の子育て日記」(2003.10月〜12月)
http://blog.goo.ne.jp/banbiblog/e/274578788f8a3b7956402af33d171997
「我が家の子育て日記」(2004.1月〜2月)
http://blog.goo.ne.jp/banbiblog/e/a401c61f189f79dc819b991cab6cad13
「我が家の子育て日記」(2004.3月〜6月)
http://blog.goo.ne.jp/banbiblog/e/d11ca2d29a35b79b0f2944cc847b5b30
「我が家の子育て日記」(2004.6月〜9月)
http://blog.goo.ne.jp/banbiblog/e/67002a64207030a57c4eb93577b7319f
「我が家の子育て日記」(2004.9月〜2005.1月)
http://blog.goo.ne.jp/banbiblog/e/1a076f957ab6fdc51d583d82ad487cfd
「我が家の子育て日記」(2005.1月〜8月)
http://blog.goo.ne.jp/banbiblog/e/f71cda39230c83de35e4852f65b18055
豊田市発行のタウン紙「ぴポ」コラム「こだわり自然派子育て」2003.10.20〜
http://blog.goo.ne.jp/banbiblog/e/81e4a9a8653f0156ef8f6ed8b9272978
我が家の暮らし紹介(2005.3)
http://blog.goo.ne.jp/banbiblog/e/7542984fdb86254272133f8533220c4a