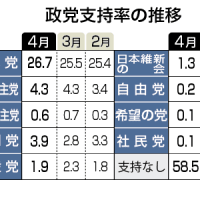雅歌第六章註解
「雅歌」は詩でもあるので、人それぞれに自由に自身の器量に応じて味わえばよいと思い、註釈もよけいに思い書かなかった。とは言え私が現時点でこの詩をからどのように美と思想を得ているか記録しておくことも多少の意義もあるのではないかと思った。文章にすることによって後からそれを反省や検討の対象とすることもできる。
ちょうどパスカルが、宇宙の広大無辺な神秘の前に畏れおののきながら、自身をもっとも弱い一本の葦に喩えたように、有限な人間が世界のすべてを認識することを夢見ることの傲慢であると同じように、「雅歌」という風雪を経た古典的宗教的作品を前にしては、私の註解もおそらく「群盲象を撫でる」の類の一知半解にすぎない。
しかし、たとえそうであっても、私たちの真理観からいえば、真理は現象的認識の総和の中から明らかになってくる。その意味では拙なりとは言え、現代日本とは隔絶した時代、風土、宗教的伝統のなかに生まれたこの「雅歌」という詩についての一知半解の私の註解のようなものも、宗教詩などとはふだんは無縁の人には参考になるかもしれない。ただ、この身の程知らずの「雅歌」の註解が誤解の種を蒔くことにならないことを祈るばかり。
「雅歌」と言う作品自体が一つの比喩的な象徴的な意味をもっている。イエスが「喩えなしに何一つ語らなかった」(マタイ書13:34)と言われているように、聖書自体が一つの喩えで構成されている。秘密を知ることのできるものだけのために、雅歌も全体としては、男女の相聞歌、恋歌であるけれども、何よりもその愛が、神の愛の比喩として、象徴として歌われている。
それは神のイスラエル民族に対する愛であり、また人となったイエス・キリストの愛を象徴している。それはもっとも聖らかなる愛である。この雅歌のなかで、人の愛とは近くて遠い青年ソロモンの愛を一つの比喩として、たとえおぼろげではあっても、そこから私たちは神の愛がどのようなものかを類推的に知ることができる。
「愛」は聖書の核心的な主題であって、愛のゆえにイエスは無垢のご自身を贖罪の生けにえとして神に捧げ、神はその血のあがないによって人類の罪を許される。イエスを犠牲の羊としてこの世におくられたのも、それもまた父なる神の愛のゆえである。この「雅歌」は全八章と短編ながらその前表として、聖らかな高貴の愛を歌った貴重な恋愛詩である。
旧約の正典である雅歌の成立は、紀元前250年頃と推測され、一部にギリシャ的な美意識も見られる。新約聖書の時代に入って、パウロはこの本の主題をさらに発展させ、希望、信仰、愛の三つのキリスト教的な徳のなかで、もっとも大いなるものは愛であると言い、たとえ山を動かすほどの信仰があったとしてもそこに愛がなければ無に等しいとも言う。愛はそれほどの「最良の贈り物であり最高の道」とされている。(コリント前書第13章)
創世記では父アブラハムの息子イサクに対する愛が、またダビデに対するヨナタンの友愛、ダビデ王のバテシバに対する性愛など、聖書の中には多くの愛が語られている。新約聖書では、放蕩息子に対する父の愛をイエスが語ったことは良く知られている。この「雅歌」の中では、青年の娘に対する愛が歌われている。この青年はダビデの息子で「平和な」という意味の名をもったソロモンである。
青年と娘は愛し合っており、先の第五章で、王である青年ソロモンは花嫁になるべき娘のところに訪れるが、行き違いから娘は青年ソロモンを受け入れることができず、戸を開いて彼を迎え入れようとしたときにはすでに彼は立ち去った後だった。娘は急いで青年の後を追ってその姿を探したが見つからず、逆に街の夜警に見つけられて打たれ、着ていた衣さえ奪われてしまう。
ここには、神を見失い迷ったイスラエルがバビロンに征服され異国の地に連れ去られるという民族としての苦難の体験が比喩されている。
愛する人を見失った娘を勇気づけるように、女たちはいっしょに探そうと申し出るが、娘には青年がどこへ行ったのかわかっている。青年は自分の領地である百合の花咲く園で羊の群れの世話をしている。
羊の群れを飼う牧童は、中近東では人を養い導く神の存在の比喩で語られる場合が多い。この雅歌においても、牧童として現れる青年ソロモンの愛は、ユダヤやイスラエルに対する父なる神の愛を象徴している。ソロモンが神殿を築いたユダの国の都であるエルサレムやイスラエルの首都ティルザの麗しさが詩のなかで娘の美しさに喩えられているように、父なる神を懐くヘブライ民族がこの娘に象徴されている。
そして、ダビデやソロモンはキリストの前表とされるから、娘に対するソロモンの愛は、やがてキリストの愛を象徴するものとなる。もちろん、イエスの愛が十字架の苦難を耐え忍ぶほどに深いもので、私たちの想像を絶するものであって、もっとも高貴な青年ソロモンの娘に対する愛も人間的で、それは私たちにはより身近なものではあっても、イエスの生涯の愛の物語とは比べることの出来るものではない。
現代の日本からは大きく異なる中近東という時代や風土を背景にして生まれた雅歌という詩には、私たちには理解しにくい表現が多い。娘の美しさはさまざまに比喩的に表現されているけれども、なかなか想像しにくい。たとえば、娘の髪や歯を、遠くの丘を駆け下りる山羊の姿や白い毛を刈られて行列をつくって列んでいる雌羊にたとえられても、実際に見て経験することもないからなかなか想像しにくい。また娘の姿をイスラエルの都ティルザやユダヤの都エルサレムにたとえているが、とくに麗しい都を実際に見たことのない者にはこれもなかなか想像しにくいだろう。
第4節や第10節などに繰り返し表現されているが、娘の美しさを、新共同訳のように「旗を掲げた軍勢のように恐ろしい」というよりも、「都市や軍隊の掲げる旗や目印のように美しさが際だっている」ということだろうと思う。第12節は、「私の気づかぬうちに(青年の乗っている、民族の守護神の名をもった)戦車のうちに運ばれていた」とも解することができ、その象徴的な意味はよくわからない。第13節は新共同訳では、第7章に組み入れられているが、「マハナイム」が軍隊の「野営地」という普通名詞なのか、あるいはそれが土地の固有名詞になったものかもわからない。










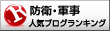

![ヘーゲル『哲学入門』 中級 第二段 自己意識 第三十一節 [自己と他者の自由について]](https://blogimg.goo.ne.jp/image/upload/f_auto,q_auto,t_image_square_m/v1/user_image/1a/f5/817b90d3f8ac7b90d39847a479009217.jpg)
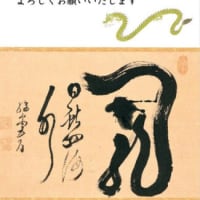
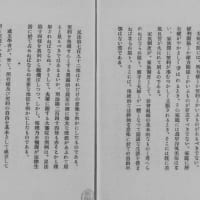

![ヘーゲル『哲学入門』第二章 義務と道徳 第三十七節 [衝動と満足の偶然性について]](https://blogimg.goo.ne.jp/image/upload/f_auto,q_auto,t_image_square_m/v1/user_image/0f/b9/ae7fc3fa05eeda789aa4d9d112b37d72.jpg)