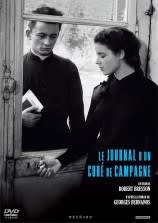
地味で退屈そう。でも、なぜか心に残る──『田舎司祭の日記』
たまたま観た映画『田舎司祭の日記』(1950年・フランス)。
正直、最初はかなり退屈そうに見えた。セリフも少なく、映像も地味。今どきの映画のような、何かが「起きる」感じがしない。終始”えっ、これで終わり?”となりそうな予感。
でも、最後まで観てしまった。そして、観終わったあと、じわじわと心に残っている。もしかしたら名作かもしれない・・・
派手さもわかりやすさもないけれど、これは確かに「芸術」だった。
映画は娯楽だけじゃない
この映画を撮ったロベール・ブレッソンという監督は、芝居がかった演技を徹底的に嫌った人らしい。
出演するのはその作品限りの素人ばかり。彼らに演技させるのではなく、ただ“そこにいる”よう求める。それがブレッソンのスタイル。
だからだろうか。映画には演技らしい演技がほとんどなく、ただ日々の風景や人々の表情が、淡々と、そして妙にリアルに映し出されている。
傷ついた若い司祭の物語
物語は、ひとりの若い司祭が田舎の村に赴任するところから始まる。
しかし、彼を待っていたのは村人たちの冷淡な態度と不信感。子どもたちとの関係もうまくいかず、孤独と苦悩ばかりが募っていく。
しかも司祭は、深刻な病を抱えている。
心も体も傷ついたまま、彼は信仰の意味を問い続ける。そして最後には、神さえも「沈黙している」と感じはじめるのだった。
遠藤周作『沈黙』を思い出す
この映画を観ていて、自然と頭に浮かんだのが遠藤周作の小説『沈黙』だった。
キリスト教信仰の核心を、神の「沈黙」を通して問いかけるあの作品。
そして、その映画版──マーティン・スコセッシ監督の『沈黙 -サイレンス-』(2016年)のことも思い出した。あちらは、日本の拷問や踏み絵という強烈なビジュアルで訴えかけてくる。
中でも、ロドリゴが踏み絵の直前に神の「声」を聞くシーンは印象的だ。
「踏め。私はお前と共にいる。」
原作にはなかったその声が、映画では強いカタルシスとして描かれている。
だが『田舎司祭の日記』の沈黙は、沈黙のまま
それに対して、ブレッソンの『田舎司祭の日記』では、神の声は一度も聞こえない。
救いの兆しも劇的な展開もない。
ただ司祭は、沈黙のなかでも信仰を手放さない。
そして、死の床で日記に記す最後の言葉は、
「すべては恵み(Tout est grâce)」
ここに至るまでの過程が、カタルシスではなく、静かな内面の解放として描かれているのが印象的だった。
『沈黙』と『田舎司祭の日記』。
一方は神の声を聞き、もう一方は終始沈黙のまま。表現方法は対照的だが、どちらも伝えていることは同じように思える。
信仰とは、神が応えてくれるから信じるのではない。
むしろ、神が何も語らない沈黙の中でも、なお信じ続ける意志。
それこそが本当の信仰なのだと、両作品は語っているのかもしれない。
派手でもないし、わかりやすくもない。
だけど、観終わったあと、不思議と心が静まり、どこかでずっと残り続ける映画だった。



















