夏休みに、日本におけるファシリテーターの未来像―音楽のチカラ、ファシリテーターのチカラ― 参加した時に、
http://blog.goo.ne.jp/aoten-ws/e/8365c2b7037750e6dd682a36d2741976
仲道 郁代さんが「音楽」と「音学」とを使い分けていたのが気になったので、手に取った本。
音楽と聞くのには興味は持っていたものの、学問として、あまり考えたことがなかったのを再認識した本となりました。
以下、抜粋■
P24 生まれ落ちた時から電子音楽やコンピュータによって作られた音楽の中で生活してきた「新しい世代」の人間にとっては、デジタル音楽こそが音楽の「基準」なのであり、生の楽器による音楽は後から経験した「新しい音」の一つにしか過ぎない
P26 人類最古の楽器は、人間の身体だったのでは?という説がある
P27 440Hzは、一説には、人間の赤ちゃんが生まれた時に泣き出す標準的な鳴き声の高さと言われ、クラシックをはじめ、ポップス、ロックも含めたすべての西洋音楽が現在基準にしている”ラ”の音のこと
P46 人間が楽器を演奏して作り出す音楽とシンセサイザーとの違いは、シンセサイザーは倍音の構造をあらかじめプログラミングしておくことは可能でも、リアルタイムに刻々と変化していく楽器と演奏者との微妙な「倍音関係」までもコントロールすることはできない
P52 それぞれの国の音楽の特徴は、それぞれの国で話される言葉と深い関わりを持っている
P55 音楽文化人類学者クルト・ザックスによると、人間な幸せな状況だから歌を歌うというよりは、ある種絶望の淵にあるような状況の方が「ウタと歌いたくなる」明るい希望を捨てまいとする願望か?
P81 他者との協調と調和が日本のムラ社会の基本にあるからこそ生まれた日本の音楽の基本も、他者や自然との調和、そして「気」を計る「間」なのである。また湿気も、さらなる「味」を加える。
P85 桑田佳祐とサザンオールスターズがしようとしたこと。日本語にシンコペーションのリズムを作ろうとしたこと、そして、子音の数を意図的に増やそうとしたこと。ロックのリズムにあれはまらない日本語の子音や母音の発音をわざと不明瞭にすることによってことばにシンコペーションのリズムをつくりロックを日本語で表現する
P91 地球の音楽を大きく二つに大別すると、(1)私たちが毎日の生活で、いつも聴いている音楽のような「平均律」という音の約束事を前提に作られた音楽(2)そういう約束事を持たない音楽
P92 ピタゴラス音階:ピタゴラスが考えた、ドの5度上がソ、ソの五度上がレ・・・などのように音を積み上げていくもの。
P93 古代ギリシャ、ローマやオリエント文明で使われていたのは、テトラコード
P97 15世紀ごろから出てきた代表的な音程が「長三度」の音程
P99 そして現在の、十二平均律音階へ
P101 世界中のルーツ音楽には、それぞれのモード(施法)が存在
P115 BGMに向く音楽は、予測可能な音楽でなければならない。BGMは、その空間の中に空気のように溶け込んでいなければならない
P117 作曲家が映像に音楽をつける場合の原則:映像のイメージをどういった音や音楽で置き換えれば、その映像を見ている人がその映像の中に自己を投影できるかということ
P179 人間にとって音楽とは、恐れの空間と喜びの空間の両方へと通じるドアの鍵のようなもの














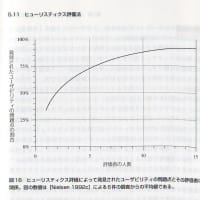
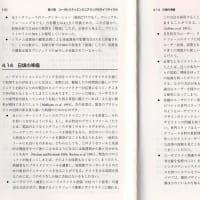
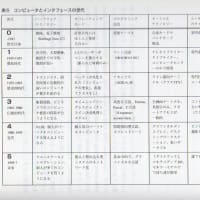
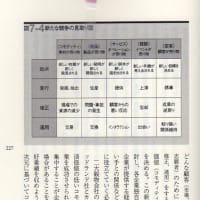
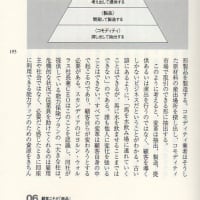
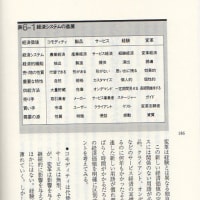
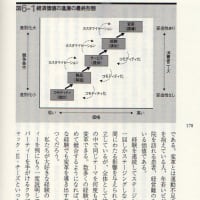
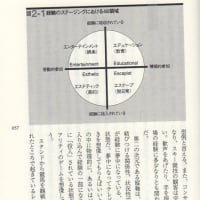
※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます