- KOELのクリエイティブ・アドバイザーである石川さんのデザイン思考の考え方を学びたかった
- デザイン思考のプロセス
- 上記プロセスを行うための組織作り
- クリエイティブ・コンフィデンス「自分の創造性に対する自信」
- 上記を持つためのマインドセット
2.旅行者、初心者の気分でいる
3.助け合える状態を作る
4.クリエイティブな行動を信じること
- チームメンバーが助け合える関係性を持つことがデザイン思考プロセスがうまく機能する。そのためには各自がコアとなるスキルを持つことが肝要
http://book.akahoshitakuya.com/b/4000254545
http://book.akahoshitakuya.com/b/4422112570
http://book.akahoshitakuya.com/b/4479792139
インタビューする時の心構えが分かります。聞く力をいかに高めて、その場に望みつつも、相手の発言や言葉に合わせて、柔軟に思考を変化させて行くことが大事であることが分かります。
「知のソフトウェア」 http://blog.goo.ne.jp/aki-nagi-kae/e/70b3ccd668096f0ee8169f606e5602c4
伝える力 (PHPビジネス新書) http://blog.goo.ne.jp/aki-nagi-kae/e/e26e4a824ef67e483f58cd1ee63e3089
知的生産の技術 (岩波新書) http://blog.goo.ne.jp/aki-nagi-kae/e/ebc9bf112d6a5efc6ca573fe297ec695
佐藤可士和の超整理術 http://blog.goo.ne.jp/aki-nagi-kae/e/fa88ed6a92ef65cc24981cdcd5d9a8f1
アイデアを形にして伝える技術 (講談社現代新書) http://blog.goo.ne.jp/aki-nagi-kae/e/601ecc3b657f7ce06c3a80383253e60e
はじめて考えるときのように―「わかる」ための哲学的道案内 http://blog.goo.ne.jp/aki-nagi-kae/e/8801965711adf57a6e60c46431dc0b77
ビジネスマンのための「行動観察」入門 http://blog.goo.ne.jp/aki-nagi-kae/e/90a1b4a32cffd20c837c8d8073098da7
以下、抜粋。
P15 人の魅力は「聞く力」にあり、人間関係の根本はそこにあるのだという気づきを持って欲しい。
AIITの人間中心デザインプログラム ユーザ調査技法の講義でおススメされていた本。
2012年に100万部売れたベストセラーです。
質問力
http://blog.goo.ne.jp/aki-nagi-kae/e/510f2c9ff2fbebaf1732b60535fcf9dc
が日本語の理論からインタビューについて分析し理論的に書かれているのに対し、より「場」の雰囲気を大切にするものとなっています。読み物としてはさっくり読めるし、面白いですが、手法として手元で繰り返し読むという感じではないかもしれません。
以下、抜粋■
P13:同じ話も新しい話も感動的な話も、人に話を聞くことで、自分の心をときめかせたい
P32:相手が「この人に語りたい」と思うような聞き手になればいいのではないか?こんなに自分の話を面白そうに聞いてくれるなら、もっと話しちゃおうかな、あの話もしようかな。そういう聞き手になろう。
P33:インタビューは質疑応答。もっと日常的な言葉を使えば「会話」
P46:「慣れる」ということはない。「慣れたな」と思ったとたん、落とし穴にはまります。だからゲストと会うときは初心者気分。
P53:質問をする。答えが返ってくる。その答えのなかの何かに疑問を持って、次の質問をする。また答えが返ってくる。その答えを聞いて次の質問をする。まさにチェーンのようなやりとりを続けてインタビューを進めていくことが大事。
P57:質問の内容はさておき、「あなたの話をしっかり聞いていますよ」という態度で臨み、きちんと誠意を示すことが、まずはインタビューの基本
P59:自分で「あれっ?」と思ったことを率直に相手にぶつけると、それだけ相手の仕事に注視しているのが伝わって、思わぬ話につながることがある
P62:事前の準備はほどほどに。相手に最低限、失礼のない知識は入れておくにしても、相手についてすべて知ってしまったかのような木本にならないよう、未知の部分を残しておくことが大事
P74:どんなに真面目な話をするつもりでも、人間同士、とりあえず相手の気持ちを思いやる余裕は残しておきたい。そういう気持ちを伝え、様子を測りつつ、こちらの聞きたいことをぶつけていかなければ、相手は聞き手に心を開きにくいだろうと思います。
P77:自分と同じであることを「正しい」とか「当然だ」と思わないようにさえすれば、目の前の人が、「私」とどう違うのか?、どのくらい近いのか遠いのかが、そのスケールをもとに質問を広げていくことは、有効な手立ての一つとなる。
P98:聞き手のさりげない反応によって、何かを触発されることもある。聞き手は語り手の、そんな脳みその捜索旅行に同行し、添いつつ、離れつつ、手助けをすればいい。その結果、意外な掘り出し物を探し当てるという楽しみも、聞き手の醍醐味となるでしょう。
P110:少しでも「面白いな」と思ったら、それを表情や態度でちょこっと話手に伝えてみてください。聞き手のそういう反応だけで、話しの内容はずいぶんちがってくると思います。
P121:いったいこの話題は世間に広く知られていることなのか、それともまだほとんどの人が知らない話なのか。それを確認するためにも、過去のインタビュー記事やご本人の著作をチェックしておく必要がある
P141:人は皆、360度の球体で、それぞれの角度に異なる性格を持っていて、相手によってどの都度、向ける角度を調節しているのではないか?
P149:ただ聞くこと。それが相手の心を開く鍵なのです。
P159:オウム返しの次につながる答えは、その言葉をさらにかみ砕いた話になることが多い
P184:相手の話を聞く時は、できるだけ視線をそらさないように気をつける。じっと見つめ過ぎて、友情以上の気持ちが相手に生まれても先方にご迷惑でしょうから、そういうときは目だけではなく、顔全体を少し移動させるとか、ときどき下を向くとか、視線の休憩時間を挟んで、でも決して落ち着かない目つきだけはしないように心掛けている
P191:相手の話を聞きながら、「ああ、わかるわかる」と思うときは確かにありますが、その瞬間、本当に分かっているのか、君は?」と問いかける作業も、同時にするように心がけています。
P216:「これは聞き流してはいかんだろう」というポイントは、得てして、ほんの小さな言葉の端に隠れているもの。さりげなくつけ加えた形容詞や、言葉の最後に挟み込んだ普通名詞や、ちょっとした小さな言葉、そういう謙虚な宝物を見過ごしてはいけません。
P222:じっと待っていると、相手の心や脳みそがその人なりのペースで動いていると感じられることがあります。決して故意に黙っているわけではない。今、相手はゆっくり考えているのだ。そのペースを崩すより、静かに控えて、新たな言葉が出てくるのを待とう。その結果、思いもかけない貴重なことばを得たことが今までもある。
P244:服装選びに「場」を考慮することは大事
AIITの人間中心デザインプログラム ユーザ調査技法の講義でおススメされていた本。
質問の仕方を論理的にきちんと説明されている本。
質の高い会話例が掲載されているので、それを見ながら自身の言葉に置き換えるのもいいかもしれません。
インタビューシナリオを作るときや、インタビューに行く前に読み返すがいいと思われます。
以下、抜粋■
P12:プライベートとパブリックの中間段階でのコミュニケーションが、実は一番大切なのである。
P13:初めて出会う人とどれだけ短い時間で濃密な対話ができるのか、実はここに社会でいく抜く力の差が生まれてくる。これからの社会で必要とされるのは、「段取り力」と「コミュニケーション力」だ。
P20:質の高い対話の例をたくさん分析し、なぜそれが優れているのかを見抜く目を養うことがねらい
P23:いちばん大切なのは「質問力」というコンセプトをいつも意識する習慣をつけること
P26:質問は3色ボールペンで色分け。相手の話は青、大事なところは赤、自分が主観的に思ったところは緑。聞きたいものごとにグレードを分ける
P32:離れたところから自分を見る世阿弥の「離見の見」
P41:楽しい場を作っていくためにはお互いに経験世界を混ぜ合わせることが大切。相手の苦労や積み重ねてきたものを掘り起こすような質問ができると、すくなくとも相手にとってはふかまった話ができた印象になる。
P43:谷川俊太郎の33の質問 http://www.amazon.co.jp/gp/product/448002042X/
谷川俊太郎の33の質問続 http://www.amazon.co.jp/gp/product/4480027475/
筆者が一番関心した質問は、「自信をもって扱える道具を一つあげてください」
P49:「あなたがいいと思うコピーを10個書いてください」という質問がすぐれているのは、よいコピーが産みだせるかどうかは、世に出ているコピーの良し悪しを見分けるセンスを密接に関係しているから。
P54:いい質問のキーワードは、「具体的かつ本質的」
P61:質問は相手の状況、相手の興味、関心を推しはかり、自分の興味や関心とすりあわせてするもの
P72:具体的な事柄を聞きながら、本質的な事柄に迫ることができるのか?具体的、本質的な「質問力」のゾーンとなる
P76:コミュニケーションの秘訣は「沿いつつずらす」ことにつきる
P77:対話において、相手に「沿う」とは、身体レベルで言うと「うなずく」にあたる。うなずきがしっかりできていると、沿ってもらっていると感じるので話す側が勇気づけられる
P78:自分の呼吸や相手の呼吸に合わせてうなずくと間がとりやすい
P79:あいづちは、語尾を上げた疑問形にしてはいけない。あくまでも語尾は上げずに繰り返す。いわばオウム返しの技だ。
P80:自分の言葉で言い換えることができれば、その内容が咀嚼されて自分の物になっていると相手に示すことができる
P81:この技はメモを取る習慣とセットになって鍛えられる。メモを取る習慣がついていると、手で書いて、目で見て、さらに文字として残っているので、見て確認することができる
P87:オウム返しの技は、上手にやらないとうっとうしい技になる。自然な形でやるには最初はぎこちないかもしれないが、「そうそう」という動作をつける気持ちで相手の言葉を繰り返すといい。とくに聞いたことのない専門用語や固有名詞が相手から出た時は、繰り返すことで自分のほうが慣れていく
P89:「なるほど」の対話は、相手の言葉を自分の言葉に組み込んで話すことで、相手と共感や同調ができる
P94:相手と自分がどこでつながっているのかを強く意識しながら対話をすることが、いい質問を生み、コミュニケーション全体を生き生きとしたものにする。大切なことは、相手と自分の好きなものに多少ずれがあったとしても、何とかつながりを見出しながら話を折り合わせていくこと。相手の経験世界や相手の言っている文脈に沿う質問によって、相手の好きなものが引き出せれば、それでもかなり親密なコミュニケーションが成立する
P96:その人間が一番力を入れている部分をしっかり認めることがコミュニケーションには必要
P104:ポイントをたくさん見つけようと意識しながら聞いているからできる。相手の言ったことに対して、「それは別のこれと似ていますか}」と質問するのは、質問の王道。
P109:比喩はやりすぎると言葉に酔っているようにみえるからまずいが、ほどほどなら相手の言うことが分かったということを相手に伝える有効なメッセージになる。相手の言葉を比ゆ的に言い換えて、自分と相手の話を絡めるやり方。「自分のキーワードで言えば、それはこういうことだろう」ということを織り交ぜて、質問する技である
P117:相手の中に起こった変化について語ってもらう。その答えは豊かになることが多い
P118:変化について語るのは、非常にやりやすい。相手に変化前と変化後を比較させて話せばいいからだ。
P121:大事なのは、人は変わった瞬間については、熱く語る!ということだ。
P131:相手が専門家の場合は特にそうだが、できるだけ相手の専門性を尊重してあらかじめ知識をつけておき、それに基づいて質問するのが望ましい。
P138:子供が発した質問の中には大人でも踏み込めないようなおそろしく本質を突いてしまった質問もある
P139:「質問力」を高める基本は、相手に対して事前に勉強をすませておいて、相手の専門性に自分を加速させて寄り沿った上で質問をするということ
P155:「具体例をあげてください」という質問は、どこでも使えるかなり応用範囲の広い技である
P159:基本技は、抽象的な話になりすぎたら、「具体的に言うとどうなるか」と質問する。具体的な話が長すぎたら本質的なテーマにもっていく。この往復運動がずらしのコツ
P165:相手の話を自分の経験に引きつけて話すとき、注意すべきポイントは、自分の話に引きつけていることを意識できていることである
P173:答えている当人が質問をされるまで思いもよらなかったことが導き出せればクリエイティブな質問。インスパイアをもった質問が最もクリエイティブな質問ということになる。これが質問力の最終目標
P175:「~として聞く」という習慣は、会話をクリエイティブに組み立てていくために大変よい方法
P178:相手が云ったことに対して、「どうしてか?}と聞き、その答えに対して、「わかるよ」と受ける段取りは共感系の基本作法。
P184:物事の結果について聞くより、何かが生まれてきた経緯について聞いた方が得るところが多い
P187:ハイレベルな「質問力」で大切なのは自分自身にその質問をした時、どう答えるかを、一応シミュレーションして、ある程度の答えを用意しておくこと
P208:相手に対してよく勉強をしていて、他の人が気づかないようなポイントを質問することによって信頼を得るのは。コミュニケーションのひとつの方法
#amazonマーケ 1円本
 ユーザビリティエンジニアリング原論―ユーザーのためのインタフェースデザイン
ユーザビリティエンジニアリング原論―ユーザーのためのインタフェースデザイン
以下、抜粋■
P10 個々のプロジェクトの必要性に合った最高の解決策を探すのがユーザビリティの仕事
P11 初期のデザインをユーザに合わせて変更する可能性を認める姿勢がユーザビリティ担当者の能力を測る指標
P13 自分たちで決めた短縮コマンドと、個人ユーザが決めたコマンドを比べたところ、ユーザが自分たちで決めた短縮コマンドを使うときエラーする回数が約2倍!
★★★ユーザビリティとユーザビリティエンジニアリングサイクルについては、こちらの方が情報が新しいので、リンクします。
http://blog.goo.ne.jp/aki-nagi-kae/e/6b8e779181a706304f45765948b60583
★★★P20 + 5章で詳しく説明(時間のある時に図解化してみる!):ニールセンの10ヒューリスティック
http://www.usability.gr.jp/whatis/methods/
1.システム状態の視認性を高める
:フィードバック、現在の状態
ー システムは妥当な時間内に適切なフィードバックを提供して、ユーザが今何を実行しているのかを常にユーザに知らせなくてはならない
2.実環境に合ったシステムを構築する
:一貫性
ー システムはシステム志向の言葉ではなく、ユーザのなじみのある用語、フレーズ、コンセプトを用いて、ユーザの言葉で話さなければならない。実世界の慣習にしたがい、自然で論理的な順番で情報を提示しなければならない
3.ユーザーにコントロールの主導権と自由度を与える
:Undo,ESC
ー ユーザはシステムの機能を間違って選んでしまうことがよくある。そのため不測の状態から別のインタラクションを通らずに抜け出すための、明快な非常出口を必要とする、UndoとRedoを提供せよ
4.一貫性と標準化を保持する
:一貫性
ー 異なる用語、状況、行動が同じことを意味するかどうか、ユーザが疑問を感じるようにすべきではない、プラットフォームの原則にしたがえ。
5.エラーの発生を事前に防止する
:例示、制約
ー 適切なエラーメッセージよりも重要なのは、まず問題の発生を防止するような慎重なデザインである
6.記憶しなくても、見ればわかるようなデザインを行う
:再認、手がかり、ガイダンス
ー オブジェクト、動作、オプションを可視せよ。ユーザが対話のある部分からほかの対話に移動する際に、情報を記憶しなければならないようにすべきではない。システム利用の説明は
可視化するが、いつでも簡単に引き出せるようにしなければならない
7.柔軟性と効率性を持たせる
:カスタマイズ、ショートカット
ー アクセラレータ機能(ショートカットキー)は、上級ユーザの対話をスピードアップするだろう。そのようなシステムは初心者と経験者の両方の要求を満たすことができる。ユーザが頻繁に利用する動作は、独自に調整できるようにする。
8.最小限で美しいデザインを施す
:適切な情報量
ー 対話には、関連のない情報やめったにしない情報を含めるべきではない。余分な情報は、関連する情報と競合して、相対的に視認性を減少させる
9.ユーザーによるエラー認識、診断、回復をサポートする
:エラートレランス
ー エラーメッセージは、平易な言葉(コードは使わない)で表現し、問題を的確に指し示し、建設的な解決策を提案しなければならない
10.ヘルプとマニュアルを用意する
:ヘルプ、マニュアル
ー システムがマニュアルなしで使用できるに越したことはないが、やはりヘルプやマニュアルを提供する必要はあるだろう。そのような情報は探しやすく、ユーザの作業に焦点を当てた内容で、実行のステップを具体的に提示して、かつ簡潔にすべきである
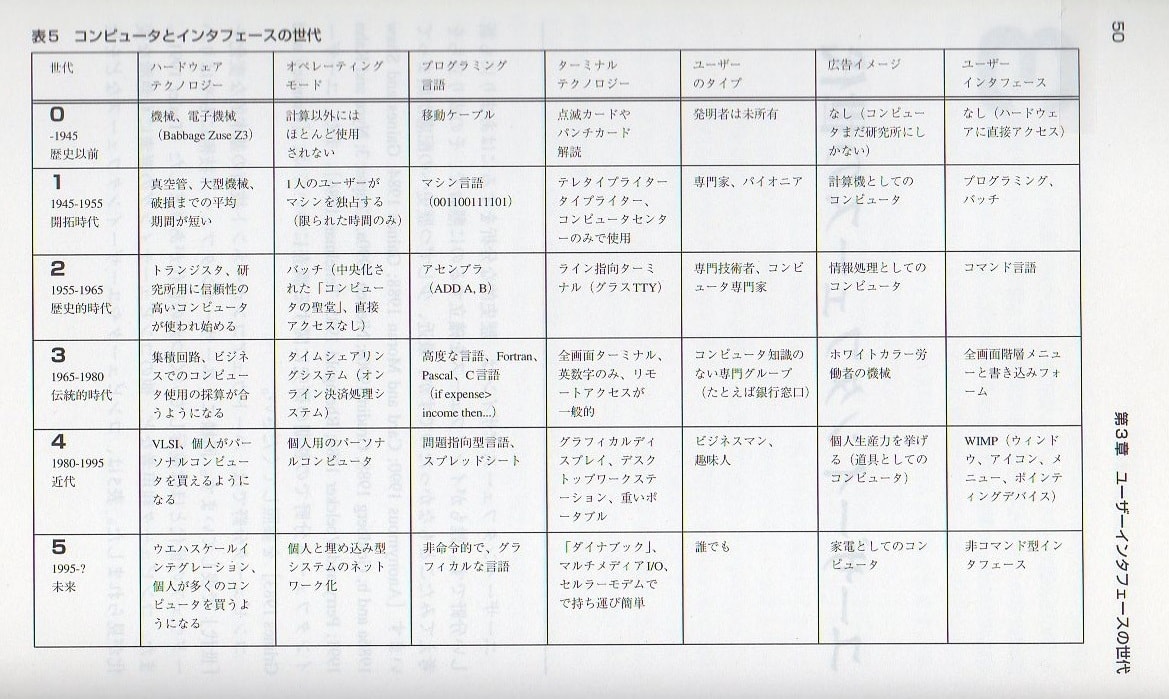

★★★(この本の)ヒューリスティクス評価

1.評価者が、ニールセンの10ヒューリスティックを使って個々に評価
2.評価者間で話し合い結果を集計
↓
(デザインのアドバイスを得たい場合は?)ブリーフィングセッション
:評価者、評価セッション中のオブザーバー、デザイナーチームの代表が参加しブレーンストーミング方式で主要なユーザビリティの問題点に対処できる新しいデザインや全般のデザインについて話し合い
★★P186 発話思考法
:考えを口に出すことによって、モニタがどのようにコンピュータを使っているのかを理解し、ユーザの誤解を容易に知ることができる。発話思考法では、ユーザがどのようにインタフェースの部分を理解しているのかが明らかになるので、実験者はどの部分が重大な問題になっているのかを知ることができる
(長所)非常に少数のモニタから多くのデータを集めることができる。ユーザのコメントには現実味があり、テストレポートが読みやすく記憶に残りやすい
ユーザが後で理屈に合った答えをこじつけるのではなく、ユーザが行動している最中に実際に何をしているのか、どうしてそれをするのかを観察するのがポイント
(短所)パフォーマンス測定ができない
★★★P214 ユーザビリティ手法の組み合わせ
・最初に整理するためにヒューリスティクス評価をし、できるだけ多くの「目立つ」ユーザビリティの問題点を取り除く。インターフェースをデザイン修正した後、反復デザインのチェックをするため、また、ヒューリスティックス評価で拾い上げることのできなかった問題を見つけるためにユーザテストにかける
:理由1 集めにくくスケジューリングしにくいユーザを浪費することなく多くのユーザビリティ評価を排除することができる
:理由2 重複することなく、相互に補完し合う形で広い範囲を網羅することができる
========関連文献
ウェブユーザビリティの法則 改訂第2版
http://blog.goo.ne.jp/aki-nagi-kae/e/6148d63da920ba63221e63c39ee9dd67

P12:サービスを買う時は、自分のために行われる形のない一連の活動に対価を支払っている。経験を買うときは思い出に残るイベントを楽しむ時間に対価を支払っている
P23:サービスは、一人ひとりの具体的な顧客の要求に応じてカスタマイズされた形のない活動
P24:消費者であれ、企業であれ、自分たちが高く評価するサービス(外食する、カフェを経営するなど)を買うために、製品への支出は倹約する。だから、メーカーのほとんどがコモディティ化に直面
P25:新たに認められた経済価値である経験は、企業がサービスを舞台に、製品を小道具に使って、顧客を魅了するときに生ずる。コモディティは代替可能、製品は有形、サービスは無形だが、経験は思い出に残るという特性を持つ
P26:経験は本質的に個人に属している。経験は、感情的、身体的、知的、さらに精神的なレベルでの働きかけに応じた人の心の中に生まれる
P30:経験は、長い間共有される
P34:ユーザ一人一人がその製品をどう使うかに注目したらどうだろうか?メーカの関心をユーザにシフトし、その製品を使用しているとき、「ING化」された状態での心や体の動きに着目する
P39:どんな感覚が消費者を揺り動かせるのかを知り、消費者の感性や感覚の活性化にフォーカスしたうえで、製品がもっと魅力的になるように改めてデザインする必要がある

P58:エンターテイメントは文字通り
P59:エデュケーションは顧客自身の積極的参加が不可欠である。何かを学び知識やスキルを身につけるには、その人自身の心身両面での積極的なかかわりがないと難しい
P62:エスケープは、単にどこかから旅立つだけではなく、時間を過ごすに値する場所や活動への旅も求めている
P65:エステティックに参加する人は「いる」ことを求める、エデュケーションは「学ぶ」こと、エスケープ経験をする人は何かを「する」経験を求め、エンターテインメント経験をする人は「感じる」経験を求める
◎P85 経験をうまくすてーじんぐできていると言えるのは、ゲストの参加があって初めて完成するように見える物語がかけているとき
◎P87 経験にうまくテーマを与える鍵は人の心を動かしたり、惹きつけたりするものをはっきりと打ち出せるかどうか?
ルール1:人を惹きつけるテーマはゲストの現実感覚を変える
ルール2:記憶にあざやかに残るような場所は、空間、時間、物質の3つの側面から人々の経験に働きかけ、そこにいる人の現実感覚を完全に変えるテーマを持っている
ルール3:魅力的なテーマは空間、時間、物質を一つリアルなまとまりとして融合させる
ルール4:一つの場所の中に、複数の「場所」を作り出すことでテーマは強化される
ルール5:テーマは経験をステージングする企業の特性に合っていなければならない
◎P91 印象の次元 時間/空間/テクノロジー/本物/洗練/規模
◎P119 経済価値は以下の条件を満たすときに個客価値につながる
条件1:顧客一人ひとりに固有であること
条件2:顧客一人ひとりに合わせた具体的な特徴あること
条件3:顧客一人ひとりのメリットになるようにという目的に特化していること
P134: 知るべきものは顧客我慢 顧客我慢=顧客が本当に求めているものー顧客が(心ならずも)受け入れたもの
P174: 人々は経験を通して自分を変えたい

P188:経済価値として変革を提供するときには、その形態と内容がどんなものであるのかを慎重に考えるべきだということを意味する。変革のガイドは顧客一人一人の固有な資質を変化させる前に、各人の望みをきちんと理解していなければならない。
P191:「ING化」の状態から製品を使用している個人いフォーカスが移る。個人が製品の仕様を通してどのように変わるのか、ということにフォーカスするのである。


◎P218:企業が何に請求しているか?このルールは顧客価値の段階すべてに当てはまる
・物質に対して請求しているならば、コモディティビジネス
・有形物に対して請求しているならば、製品ビジネス
・実行した活動に対して請求しているならば、サービスビジネス
・顧客と一緒に過ごした時間に対して請求しているならば、経験ビジネス
・顧客が達成した実証済みの成果に対して請求しているならば、変革ビジネス
P222 顧客が変革のガイド(演出家)に自らを委ねる ための信頼を企業はどうすれば勝ち取れるのか?
:1.カスタマイズすること
:2.顧客を本当に惹き付けてやまない経験をステージンぐすること
:3.役者が新しい演技をリハーサルできる場を設けること
:4.役者の演技を演出すること

P226: 企業活動の4つの普遍的な次元
・起点:何か新しいものから価値を生み出す作業
・実行:何か行われたものから価値を生み出す作業
・修正:何か改良されたものから価値を生み出す作業
・適用:何か使用されたものから価値を生み出す作業
P228:コモディティビジネスの 4つの普遍的な次元
・新物質を発見する
・素材を効率的に抽出する
・代替採取地を探査する
・市場で取引する
P228:製品ビジネスの 4つの普遍的な次元
・新しい発明を誘導する
・製品を効率的に製造する
・間違いを修正する
・ユーザと取引する
P229:サービスビジネスの 4つの普遍的な次元
・新しい手順を開発する
・オペレーションを効率的に提供する
・顧客に反応する
・顧客と交流する
P230:経験ビジネスの 4つの普遍的な次元
・新しい台本をつくる
・イベントを効率的に演出する
・記憶に残す
・顧客と出会う
P230:変革ビジネスの 4つの普遍的な次元
・新しい目標を決める
・顧客を導く
・決意を強くする
・顧客を支える
■経験ビジネスを成功させる7つの原則
1.フラグシップとなる場をつくれ
2.伝統的マーケティングから予算を奪取せよ
3.クリエイティブなアイデアこそが研究開発だ
4.幅広い経験のポートフォリオを用意せよ
5.リアルとバーチャルの経験を統合せよ
6.経験に料金を請求せよ
7.チーフ・エクスペリエンス・オフィサーを雇え!
ユーザ評価手法の授業でおススメされたいた本。
初版が1984年なので、パソコンやインターネットが普及したいまではインプット方法の部分は古いものがありますが、インタビュー方法や記事作成に対する考え方は、現代でも通じるものがあります。
インタビュー取材の心得■
◎P122 自分がその相手から聞くべきことを知っておくこと
◎P125 自分の中に問うべきものをしっかり持っている人は、質問を返されたときにすぐにきちんとした質問で返すことができるものである
◎P126 問うべきものをもつとはどういうことか?
:1.知りたいという欲求を激しくもつこと
:2.知りたい要求を質問の形をとって整理されなければならない。自分の知りたいことがどういうカテゴリに属すのかを分析検討する。第一に知ろうとしていることが何らかの事実なのか、それとも事実以外のこと、たとえば相手の意見や判断といったことなのかを区別する
:3.事実として客観的事実なのか、主観的・内的事実なのかを区別する。
◎P127 自分の知りたいことのポイントがカテゴリ別に整理されたら、それを知るための質問を考え、質問要項を作り、メモにする。こればできるだけ、ノート1ページかせいぜい見開き程度の紙におさまるようにする。簡潔にするために、文章の形にはぜず、キーワードを羅列しておく程度が良い。順序はいい加減で構わない。
◎P127 質問メモは、インタビューをしている間、いつでも目立たぬような形で参照できるといい。しかし、できるだけ見ないほうがいい。質問項目は頭の中に叩き込んでおく
◎P129 現場の雰囲気を記録するためには、ただその場の音声を受け身で録音するだけではなく、自分自身がその場で感じたこと、考えたことを、あるいは目に見えるものなどを字分でテープレコーダに録音しておくというのもいい方法である。要するに言葉によるスケッチ
◎P132 一に準備、二に想像力。準備はいくらしてもしすぎるということはない。
◎P134 相手のいうことをどこまで信じたらいいのか、相手の語ることから伝聞ないし推測を排除して裸の事実を拾い出すためにはどうすればいいのか?基本的には場数を踏んで何度か失敗を重ねることによって学習するほかない
◎P136 「その時どう思いましたか?どう感じましたか?」などどいう概括的な質問をするだけでは充分ではない。相手がそれに対して何らかの答えをしてくれても、もっと何かがあるのではないかと食い下がってといつづけることが必要
◎P136 内面的想像力を養うのに有効なのは、良質の文学と心理学を学ぶこと。内面的世界をより深く、より広く知っていることに他ならない
◎P141 聞きたいことを充分に聞くためには、相手と良好な人間関係を作ることが大切である
◎P141 ”丁重にズバリ聞く”これが一番いい
◎P142 わからないことはわかるまで聞く。恥ずかしくても、自分で後から調べようとは思わずに、わからないことはわからないといって、その場で聞くのが良い。そういう部分を問いただしてみると、意外に話が面白い方向に発展したりということがよくある
◎P143 いい話を聞くための条件を一語で語るなら、「こいつは語るに足るやつだと相手に思わせることである」。話が通じる相手になること
以下、他の章の抜粋■
○P21 インプットとアウトプットのバランス
:資料にあたっていくうちに、当初目的としていなかったプラスアルファが自然に得られる。これが大切。そのプラスアルファによって、アウトプットが当初のもくろみ以上に豊かなものになる
○P46 思考の柔軟性を養うための訓練
:人間を二分割する基準を考える。男と女 から始まり、「みかんを上から向く人、下から向く人」など1時間で100個だせれば御の字
○P47 具体的なものを抽象化し、抽象的なものを具体性と抽象性の往復の中でとらえようとする努力が、よき知的アウトプットのためには必要
○P95 できるだけ多くの金をというときの「できるだけ多く」の意味は絶対額の問題ではなく、切実度の問題。身を切る思いで出したお金ほど、より真剣にそのお金の価値ある使い方を考える
○P96 分からないジャンルに踏み込む場合
よき入門書を探す→何冊か入門書をよむ、入門書からすぐに中級書をよむことはしない
○P99 読むに値しない本は買っても読まない
○P163 文章の書き出しをうまく発見できないときには、自分が何を書こうとしているのかを人に話してみること
○P215 いかなる情報についても、それがオリジナルの現実から何段階のクッションを経て伝達された情報であるかを考えてみる
:一次情報 自分が目の前に現実を見ている状態
:二次情報 現場にいた人から現場の情況を聞く
:三次情報 記者が現場に行き、記者が報道した情報
:四次情報 記者の情報が一度デスクの手元に上がり、そこで加工された情報
○P228 「一歩でもオリジナルにちかづけ」という原則を常に忘れないこと。自分で本当のオリジナル情報をつかみ、二次情報と三次情報と比べてどんなに豊かなのかを自分で味わってみること
 インタフェースデザインの心理学 ―ウェブやアプリに新たな視点をもたらす100の指針
インタフェースデザインの心理学 ―ウェブやアプリに新たな視点をもたらす100の指針
認知心理学の知見とデザイン、そしてユーザ評価とを関連付けて説明している本。
最近分かってきたことは、プロは、白~黒のグレースケールでも、自分の主義主張をしっかりと伝えることができるデザインになっているということ。
この本も、細かいデザインにまで気を配っていて、とても読み進めやすい理解しやすい本となっています。
「ウェブユーザビリティの法則 改訂第2版」をユーザ評価本として、おススメされています。
http://blog.goo.ne.jp/aki-nagi-kae/e/6148d63da920ba63221e63c39ee9dd67
以下、抜粋■
■002 対象の「あらまし」をつかむのは中心視野より周辺視野の役目
:対象物の詳細な認識では主として中心視野を使うが、場面全体のあらましをつかむには周辺視野を使う
■004 顔認識専門の脳領域がある
:人は画像の顔が見ているところを見る
■005 物はやや上から斜めに見た形で思い浮かべる
:標準的な視点から見て描かれた絵や、この視点から見た物は、素早く認識でき、記憶もされやすいようです。
:ウェブサイトやアプリケーションでアイコンを使うなら、標準的な視点で描いたもの。
■007 人は手がかりを探す
:アフォーダンスは、アメリカの知覚心理学者ジェームス・ギブソンによる造語で、「環境内に存在する取り得る行動のすべて」を表します。その後、アメリカの認知心理学者ドナルド・ノーマンがアイデアを発展させ、「知覚可能なアフォーダンス」へという概念を提唱。取り得る行動の中でも「知覚できるもの」を重視する
:スマートフォンやタブレットなどタッチ式の機器を対象にデザインする場合は、ポインタを対象の上にもっていったときにだけ現れる手がかりは使わないようにしましょう。
■008 人は視野の中の変化を見逃すことがある
:視線追跡データは慎重に解釈しましょう。重視しすぎたり、デザイン上の決定要因にしないこと
■011 男性の9%、女性の0.5%が色覚異常
:http://www.vischeck.com/
:http://colorfilter.wickline.org/
:Adobephotoshopに比較的人数が多い赤緑色覚異常の人にどう見えるかを確認する機能がある。表示メニューの校正設定でP型・D型を選択しておいてから表示の色の校正で確認
■013 大文字がもともと読みにくいものであるという説は誤りである
:英語の場合、サッカード1回の移動は7~9文字にあたりますが、実際に知覚している範囲はその2倍あります。
:ケネス・グッドマンは、人が文章を読んでいるときは次に来る文字を周辺視野で見ているということを発見
■015 パターン認識のおかげで、フォントが異なっても同じ文字だと認識できる
:フォントが読みにくいと、人はそのうまくいかない感覚を文章の意味のほうに転嫁し、文章の内容が理解しにくいとか実行しにくいとか判断してしまいます。
■018 長い行の方が速く読めるが一般には短い行の方が好まれる
:英語の文章の場合、1行100文字が画面上で読む速さの点では最適ですが、、一般には短いか中程度(1行あたり、45~72文字)の長さの方が「好まれる」ことが示された。
:読まれる速度を重視するなら行を長くしましょう
:速度がそれほど重要でなければ行を短くしましょう
■019 ワーキングメモリ
:5歳時点でのワーキングメモリの量と高校以降の成績に相関がみられた。
■020 一度に覚えられるのは4つだけ
:バッドリーらの研究によると、魔法の数は「4」
:人がカテゴリに分類された情報を記憶して、それをあとで完全に思い出せるのは、一つのカテゴリの中に入っているカテゴリの中に入っている項目が1~3個のとき
■021 情報を覚えておくには使うことが重要
:ユーザーや顧客に対してリサーチを行う大きな目的のひとつは、「対象としている集団の持っているスキーマを見つけ出し、理解すること」です。
■024 記憶は思い出すたびに再構築される
:ある製品について顧客をテストしたりインタビューしたりする場合、皆さんが使う言葉によって相手が記憶することが大きく影響される可能性があります。
:過去の行動について自己申告を信用してはなりません。自分や他人がしたことや言ったことについて、正確に覚えてはいないのです。
■025 忘れるのはよいこと
:ユーザが忘れることを前提にデザインしましょう。本当に重要ならば、ユーザーが覚えていることをあてにしてはいけません。デザインの中に含める形で提供するか、すぐ見つけられる方法を準備しておくことです。
■027 情報は少ないほどきちんと処理される
:一度に少しづつ情報を提供することで、情報量の多さでユーザが圧倒されてしまう事態を避けると同時に、さまざまなニーズに対応することができます。
:クリックの回数は重要ではありません。むしろ、ユーザは喜んでクリックします。クリックのたびに適切な情報を得ながら先に勧めれば、クリックしていることを意識しないでしょう
:段階的開示という用語を最初に使ったのはケラー。ARCSモデルを考案(注意attention,関連relevance,自信confidence,満足感satisfaction)
■028 心的な処理には難しいものとやさしいものがある
:ヒューマンファクターの観点から、心的資源の消耗が多い順に並べると「認知」>「視覚」>「運動」
:フィッツの法則 T=a + b * log2(1 + D/W) マウスを動かしながら確実にたどり着ける対象の大きさを計算
:意図的に負荷を高くする場合(ゲーム等)もある
■029 人は30%の時間はぼんやりしている
:ユーザーが注意散漫になったときでも、「現在位置」がすぐにわかる仕組みを用意しましょう。そうすれば、元の場所に戻ることも次に進むことも、はるかに簡単になります。
■030 自信がない人ほど自分の考えを主張する
:人の考えに対して、論理的でない、支持できない、よくない選択であるといったことを示す証拠を突きつけないこと。かえって逆効果で、相手の主張はますます強くなる
■031 人はシステムを使うときメンタルモデルを作る
:筆者の好きなメンタルモデルの定義
メンタルモデルはある物事が機能している仕組みをその人がどう理解しているかを表現したものである。メンタルモデルは、全体像が把握されていない事実や過去の経験、そして直観にも影響される。こうしたものがメンタルモデルを構築している者の行動、ふるまいに影響し、複雑な状況で何に注意を払うのかの判断基準となり、問題に対するアプローチや解決の方法を決める
■032 人は概念モデルとやりとりする
:概念モデルとは実際にシステムを利用するユーザーがそのシステムのデザインやインタフェースに接することによって構築するモデル、より実態に近い具体的なモデル
■033 人は物語を使って情報をうまく処理する
:人は因果関係を探すもの
:物語はあらゆるコミュニケーションにおいて重要
■035 人は分類せずにはいられない
:誰が分類したかは重要ではない。どれだけうまく分類されているかが重要
■036 時間は相対的である
:作業が短く感じられるような何ステップに分けて、ユーザーが考える時間を短くしましょう。メンタルな処理は、時間が長く感じるように感じてしまいます。
■037 クリエイティブになるための4つの方法
:アーン・ディトリックの創造性の4タイプ
・熟考的で認知的な創造性
・熟考的で感情的な創造性
・自然発生的で認知的な創造性
・自然発生的で感情的な創造性
■038 人は「フロー状態」に入る
:難しい作業は何段階かに分けましょう。現在の目標が「困難だが達成可能」と感じられる必要があります。
■041 情報は取捨選択される
:ある情報に注目してもらいたい場合は、自分で必要だと思う提示方法よりもはるかに目立つ方法で強調しましょう。
■044 注意力の持続時間は10分が限度である
■045 人は「顕著な手がかり」にしか注目しない
:人は多くの場合「顕著な手がかり」にしか注目しないことを理解しよう
■047 危険、食べ物、セックス、動き、人の顔、物語は注意を引きやすい
:古い脳の役割は「これは食べられるか」「セックスできる相手か」「こいつ、おれを殺しはしないか」を判断すること
■049 何かに注意を向けるにはまずそれを知覚する必要がある
:信号検出理論を踏まえて、自分のデザインをどうすべきか考えてみましょう。「誤警報」で起こり得る損害のほうが顕著であればシグナルを抑え気味にし、「ミス」で起こり得る損害の方が顕著であればシグナルを強めます。
■051 報酬に変化があるほうが協力
:皆さんがユーザに求める行動パターンとは、どのようなものでしょうか?そのパターンに合わせて強化スケジュールを組み立てましょう。行動の反復を最大限に引き出そうとするなら変動比率スケジュールを用います。
■052 ドーパミンが情報探索中毒を招く
:情報を見つけやすくすればするほど、ユーザは情報探索にのめり込みやすくなる
■053 人は予測ができないと探索を続ける
:ドーパミンシステムは、情報が少しづつもたらされるとき、つまり情報への欲求が完全には満たされないときに、もっとも強く活性化される。ツイートはドーパミンシステムを最大限活性化するのに理想的な刺激
:ドーパミンループから抜け出すには情報探索環境からの離脱が必要
:情報の到着が予測不可能であればあるほど、人はその情報の探索にのめりこみます。
■054 「内的報酬」のほうが「外的報酬」よりもヤル気が出る
■055 進歩や熟達によりヤル気が出る
:ダニエル・ピンクは「モチベーション3.0」で、完全な熟達の域に近づくことはできても、決して到達できないと述べている
:退屈な作業をやらなければならない場合、その作業が退屈であることを認め、好きなやり方で行うのを許すことでヤル気を削ぐのを防ぎます。
■056 欲しいものが我慢できるかどうかは幼少期に決まる
:欲しいものが我慢できない人は、物の希少性を示す情報(「残りは3個!」「今月末まで!」)などにすぐ手を出してしまいがち
■057 人は本来怠惰な生き物である
:satisfice satisfyとsufficeを合成した語
:人は最良のものより、大体満足のいくもの を選択するものである
:第一印象でsatisficeすること これがユーザーがあるサイトを見続けるかどうかを決めるうえできわめて重要になる
■058 近道は簡単に見つかるときしかしない
:デフォルトのせいで余計に手間がかかることも少なくない
■059 人の行動は「性格だ」と判断されがちである
:開発中の製品についてユーザーにインタビューする場合、回答内容の処理や分析で「根本的な帰属の誤り」をしないようにしましょう。状況的要因を見落とし、性格的要因を根拠に「ユーザーが今後とる行動」を予測する傾向があります。
:特定分野の専門家にインタビューしたときに「ユーザーはよくこんなことをする」などと言われても、鵜呑みにせずに内容を吟味しましょう。その専門家も状況的要因を見落とし、ユーザの性格的要因を過度に重視している可能性があります。
:自分が先入観を抱いていないか別の観点から検証する癖をつけましょう。仕事柄、人がとる行動の理由について判断をくだす機会が多い場合は「根本的な帰属の誤り」をしていないか、自問自答してからにするといいでしょう。
■061 競争意欲はライバルが少ないときに増す
:競争でヤル気は増しますが、過度の競争は避けた方がいいでしょう。
■063 「強い絆」を有する集団の規模の上限は150人
:ソーシャルメディアが関心を集めているのは、こうした「弱い」つながりを素早く手軽に増やせるからで、現代の世の中では「弱い」つながりこそがもっとも必要
:「強いつながり」を目指す場合には物理的な近さをひとつの要素として取り込み、参加者がネットワーク内で相互にやり取りして理解し合えるようにする必要があります。
■064 人には生来模倣と共感の能力が備わっている
:人が何かをしているところを見るという行為には思いがけない力が人んでいるということを覚えておきましょう。ある人に行動を促したければ、その人に、誰かほかの人がその行動をしているところを見せればいい
■067 嘘の度合いは伝達手段によって変わる
:人が嘘をつくことがいちばん多いのは電話、いちばん少ないのは手書きのとき。
:顧客や利用者からのフィードバックを得たい場合にもっとも正確な回答が得られるのは、対面による聞き取り
■070 笑いは絆を生む
■071 笑顔の審議は動画のほうが判別しやすい
:ビデオで作り笑いをするほうが難しい。笑顔の持続時間がどれくらいかといった要素で真偽をはかるから
■072 7つの基本的な感情は万国共通
:ポール・エクマン 喜び、悲しみ、軽蔑、恐れ、嫌悪、驚き、怒り
■073 感情と筋肉の動きは深く結びついている
:意図しない表情をさせることによって、製品などに対して抱く感情が変わってしまう可能性があるので気をつけましょう。文字が小さいと目を細め眉をひそめて読む。そうするとうれしさや親しみやすさを実現できなくなる可能性があり、望んでいる行動をとってもらうのに支障がでるかもしれません。
■076 人は思いがけないことを楽しむようプログラムされている
:何らかの作業をするから、その場所にある程度の一貫性が望まれますが、何か新しいことに挑戦してもらいたい場合や、再訪してもらいたい場合は、新しく予想外のコンテンツやインタラクションを提供すると効果的
■077 人は忙しい方が満足を感じる
:何かをしてもらうのに待ち時間が伴うなら、待つ間、飽きずにやってもらえることを用意したほうがいいでしょう。
■079 人はまず「見た目」と「感じ」で信用するか否かを決める
:最初の「信用拒否」の段階でふるい落とされないためには、色やフォント、レイアウト、ナビゲーションといったデザイン要素が極めて重要。
■082 将来を出来事に対する自分の反応を大げさに予測する傾向
:顧客から「製品やデザインを○○のように変えてくれたら、とてもうれしい」とか、「そんなふうに変えたら2度と使わない」とか言われても鵜呑みにしてはいけません。
:好みの違いもありますが、顧客の反応はプラスであれマイナスであれ、おそらく本人が思っているほど強いものではない
■083 出来事の最中よりその前後のほうが好き
:皆さんが作った製品やウェブ調査などをユーザに評価してもらう場合、使用している最中より2~3日後のほうが好意的な評価が得られることを理解しましょう
■085 人間にノーミスは有り得ないし問題ゼロの製品も存在しない
:エラーメッセージの書き方
・ユーザーが何をしたのか告げる
・発生した問題を説明する
・修正方法を指示する
・受動態ではなく能動態を使い、平易な言葉で書く
・例を示す
■086 ストレスをかんじているときには間違いを犯しやすい
:ヤーキーズ・ドットソンの法則 多少のストレスがあると注意力が高まるため、作業効率も高まりますが、ストレスが強すぎると今度は低下する
:自分の作った製品がストレスのないところで使われると考えてはいけない
:人はストレスを感じていると画面上で起こっていることが目に入らず、たとえうまくいかなくても同じことを繰り返してしまう傾向があります。
■087 エラーがすべて悪いとは限らない
:「プラスの結果が生じるエラー」とは、望みどおりの結果こそ得られないものの、最終的な目標の達成に役立つ情報が得られる類のエラー
:ユーザーテストの際には起こったエラーを記録しておきましょう。そして、それぞれのエラーが引き起こす結果が「プラス」「マイナス」「プラスでもマイナスでもない」のいずれかであるかを書き留めておきましょう。
■088 エラーのタイプは予測できる
:ユーザテストやユーザー観察を行う前に、危険度が最大と思われる間違いを見きわめておきましょう
■089 エラーの対処法はさまざま
:間違いを修正する方法は人それぞれ。ユーザテストやユーザー観察の最中に、自分の顧客がとりそうな対処法に関するデータを集めましょう。この情報は将来起こり得る問題の予測や、デザインの改良に役立つでしょう
:年齢差だけでなく初心者と熟練者の違いも考慮しましょう
■090 無意識のレベルでの決断
:自分の望みどおりの行動をユーザーにとってもらえるような製品やウェブサイトを設計するためには、対象ユーザの無意識の動機を知っておく必要があります。
■090 まず無意識が気づく
:無意識は意識予知素早く反応します。ですから自分の行動や選択の理由が説明できないということがよくある
■094 「お金」より「時間」
:いちばん大事なのは顧客や市場を知ること
:ほとんどの人はほどんとの場合、「お金」や「所有」よりも「時間」や「体験」に心動かされ、親近感を抱くということを認識しておきましょう
■095 意思決定には気分も影響
:相手の決断の仕方が事前に調べられるなら、その人に合った決断の仕方を提案するといいでしょう。そうすれば製品価値の評価が高くなります。
■097 人は支配的な人物に影響される
:グループで話し合って何かを決めるときは、最初に提案された解決法に飛びつくことのないように注意しましょう
:会議を行う際には、出席者にあらかじめ自分の考えをめいめいに書き出させて、それを事前に回覧するようにしましょう