
子どもは、母親から信頼を、父親から規律を学べば、独立して生きていける。福音です。
p41の五行目から。
結局、大人は、自分自身が自分の母親、自分の父親になるところまで発達した人なんですね。大人は、いわば、母なる良心と父なる良心を持つにいたるのです。母なる良心はつぶやきます。「どんな過ちをしても、どんな悪いことをしても、私はあなたを大事にするし、あなたの人生に幸あれとずっと願ってます」と。父なる良心はつぶやきます。「悪いことをすれば、その報いを受けなくちゃならない。とりわけ、あなたが自分の生き方を変えなくちゃね。そうすれば、私あなたが気に入るかもね」と。大人は、眼に見える母親からも、眼に見える父親からも自由になり、心の中に父母を抱くんです。ところが、フロイトの超自我という考え方とは対照的に、母親と父親を「取り入れて」内なる父母を作るんじゃあありません。むしろ、母なる良心を、自分が≪真の関係≫において人を大事にできる手持ちの力に合わせて作り出しますし、父なる良心は、自分自身の叡智と判断力に基づいて作るんです。さらには、大人が母なる良心と父なる良心でもって、人を大事にするは、その二つの良心が相矛盾するのにもかかわらず、なのです。父なる良心しかなければ、その人は厳しく、残忍になることでしょう。母やる良心しかなければ、その人は、分別を失ってしまって、自分も発達できなければ、他者が発達するのを邪魔することにもなってしまうでしょう。
フロイトと異なり、良心は両親を取り込むのじゃない。むしろ、他を大事に思う気持ちに基づき、母なる良心を育み、叡智と分別に基づき、父なる良心を培うのですね。フロムの視点も、この部分でも非常にクリアですね。
これを実際やったのが、名前通りエリックの親になったエリック・エリクソンなんですね。













 子どもは、目の前にいると同時に、心の中にもいる、ということは、心に銘記しておいて良い命題であり、子どもに対する大事な見方だと思います。今日は別の見方が紹...
子どもは、目の前にいると同時に、心の中にもいる、ということは、心に銘記しておいて良い命題であり、子どもに対する大事な見方だと思います。今日は別の見方が紹...


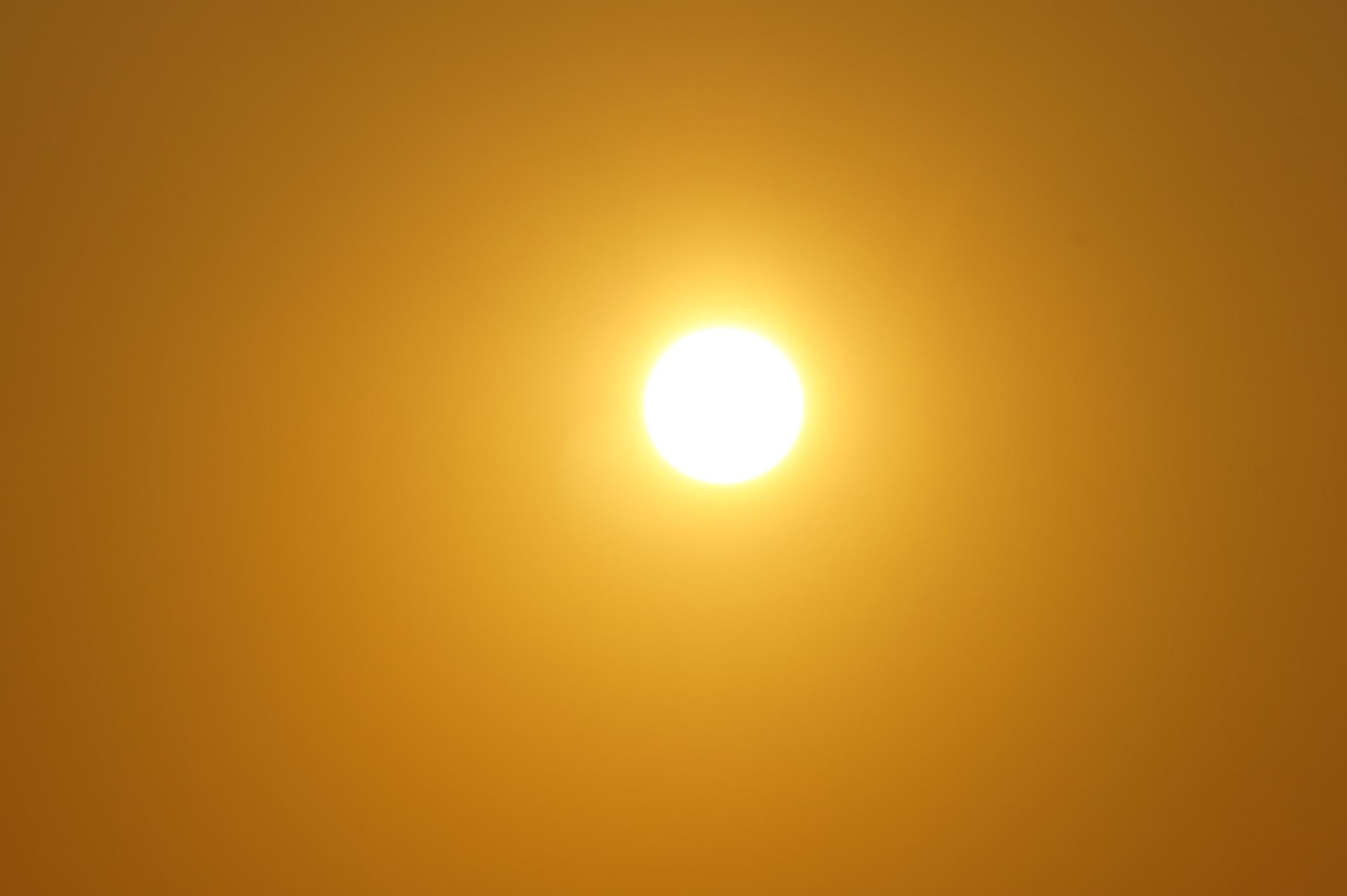
 遊びには、一級の芸術を創造する時と同様な、独創性と完成度がある、ということは驚きではないでしょうか。また、遊びには、「最も深い意味で治癒力がある」というこ...
遊びには、一級の芸術を創造する時と同様な、独創性と完成度がある、ということは驚きではないでしょうか。また、遊びには、「最も深い意味で治癒力がある」というこ...






