昨夜録画、先回の森に続いて奄美大島の中部住用町の川と海のキワ汽水域のマングローブなどから楽園を探究するもの。先回の日本で初めて動物として天然記念物に指定されたアマミノクロウサギや、固有種のルリカケスなど陸から復習して、今回は海と陸のキワと海を巡って奄美大島の大自然の秘密に迫るもの。
タモリさん初のカヌーのオールをこぎ、近江さんと案内人と3人で川をくだり、海水と淡水がまじりあう泥の土壌に生きるシオマネキガニ、コメツキガニや、青いミナミコメツキガニの砂潜りを見て、河口で見た巨大ノコギリザリガニに少しやられた15㎝にもなるという巨大シジミを手にもって、33種のカニが生育していると。
マングローブは、板根のメヒルギと膝根のオヒルギの葉がまるいものと尖った違いを観察、黄色の葉を噛んで少し塩っぽいのは、塩分を蓄えていると。そして、細長い種は落ちて泥に突き刺さり、発芽3年で30㎝ぐらい伸びたヒルギを見て、成長に100年はかかると。河口の堤防の地形が三角州の泥を溜めマングローブの森ができたと。
さらに、高知山の展望台から大島海峡を眺め、リアス式で黒潮の高い水温と豊富な栄養から、アマミノホシゾラフグが作る2mのミステリーサークルを写真で見て、久槻津から船に乗り込んで海の楽園クロマグロ養殖場で、サバの餌をやり、100㎏もある吊るしたマグロを見て、その刺身をタモリさんと近江さんが味わった。マングローブの食物連鎖と黒潮のリアス式海峡が生物の楽園となった探検の旅であった。
タモリさん初のカヌーのオールをこぎ、近江さんと案内人と3人で川をくだり、海水と淡水がまじりあう泥の土壌に生きるシオマネキガニ、コメツキガニや、青いミナミコメツキガニの砂潜りを見て、河口で見た巨大ノコギリザリガニに少しやられた15㎝にもなるという巨大シジミを手にもって、33種のカニが生育していると。
マングローブは、板根のメヒルギと膝根のオヒルギの葉がまるいものと尖った違いを観察、黄色の葉を噛んで少し塩っぽいのは、塩分を蓄えていると。そして、細長い種は落ちて泥に突き刺さり、発芽3年で30㎝ぐらい伸びたヒルギを見て、成長に100年はかかると。河口の堤防の地形が三角州の泥を溜めマングローブの森ができたと。
さらに、高知山の展望台から大島海峡を眺め、リアス式で黒潮の高い水温と豊富な栄養から、アマミノホシゾラフグが作る2mのミステリーサークルを写真で見て、久槻津から船に乗り込んで海の楽園クロマグロ養殖場で、サバの餌をやり、100㎏もある吊るしたマグロを見て、その刺身をタモリさんと近江さんが味わった。マングローブの食物連鎖と黒潮のリアス式海峡が生物の楽園となった探検の旅であった。














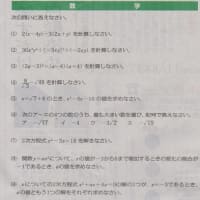


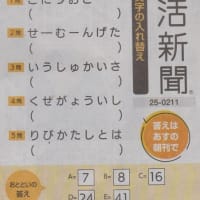


※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます