todaeiji-weblog3
建築随想
夢と共有されるべき「意味ある出来事」
シュルレアリスムを提唱したアンドレ・ブルトンは、夢と現実を一種の絶対的現実(超現実)の中で統合することによって、覚醒時の諸条件の中で方向を喪失し、迷走していた「精神」に、見失っていた条件を見つけ、確かな方向性を与え、人生の根本的な諸問題の解決につなげていけるのではないか、と考えていました。そしてその夢の奥へとつながる通路の鍵を人々に与えようとしたのです。
ブルトンが注目した「夢」とは、脳内に蓄積された、視覚などの感覚器官を直接経由しない非知覚的イメージのひとつの状態を示している、といってもいいでしょう。それは視覚が捉えた“動き”のプロセスを、同時に経験する視覚情報以外の様々な事柄とともにひとつの意味ある振る舞いとして捉え、記憶した結果、生み出された意味あるイメージの一部として、強烈な残像をともなって脳内に蓄積されています。それらは自らの脳内でフラッシュバックのごとく鮮やかによみがえる画像イメージを含んでいますが、一方で、それらはまた他者への伝達が困難なイメージでもあるのです。
この「意味あるイメージ」の生成は、世界に存在し、反応するために必要不可欠な機能であり、総ての脊椎動物に共通するものとして人類に引き継がれてきたものでした。
しかし人類と他の動物たちとの決定的な違いは、こうして脳内に形成された「意味ある振る舞い」の、「総体としてのイメージ」を、自分以外の他者へ伝達する能力を人類が獲得したことにあったのです。この他者への伝達の、最も根源的な試みは、ビジュアル的な画像のイメージを“直接”伝えようとしたものでした。
三万年前の洞窟壁画を描いた人々は、“動く”もののイメージ、特に自らの生存に直結するような「意味ある振る舞い」のイメージを、もっとも重要なものとして記憶しました。そして被写体である動物たちが直接見ることができない洞窟の最深部の壁面に、脳内に残されたイメージに従って絵を描いていったのです。彼らは暗闇の中に鮮やかによみがえる記憶の中のイメージを、洞窟の壁面に投影し、トレースすることによって、他者と共有できる実体としてのイメージを初めてつくりだしたのです。そして人類は、実体化したイメージであるこうした線画をベースに、簡略化・抽象化した「記号」をつくりだし、それらを手掛かりに、言語を直接表現する「文字」を発明していったのです。
こうしてつくりだされた「言語」と「文字」は、環境世界の中で人間が体験する「意味ある出来事」を、他者である仲間に伝達し、共有することを容易にしました。目で見たものをすぐに該当する“言葉(文字)”に置き換え、理解するというプロセスは、人々のコミュニケーションの効率を、飛躍的に向上させ、脆弱な身体しか持たない人間が、世界で生存していくうえでの強力な武器となり、人類の急速な発展につながっていったのです。
しかしながらコミュニケーションの効率性の追求は、共有されるべき「意味ある出来事」のうち、言語(文字)で表現できるところと、表現できないところの二極化を生み出します。もともと環境の中の「意味ある出来事」は、ヴィジュアル的な情報だけではなく、様々な関係・対応・経験の蓄積の総体としての「まとまり」として人々に記憶されていたもので、言語や文字で表現されるものはそのごく一部でしかありませんでした。したがって言語や文字の流通には共通の環境体験が必要とされたのです。
アンドレ・ブルトン(André Breton)1896-1966
夢の奥へとつながる通路の鍵
20世紀初頭に展開されたシュルレアリスムは、ジークムント・フロイト(1856-1939)の精神分析に強い影響を受けていました。意識的自我は私たちの人間精神の表層部分に過ぎないとし、それを無意識のうちに動機づける深層のメカニズムを明らかにしようとした精神分析は、それまでの理性万能主義に幻滅し、新しい価値の創設を希求していたシュルレアリスムに、格好の理論的基盤を提供した*01のです。
1924年に「シュルレアリスム宣言」を発表したアンドレ・ブルトンは、フロイトの夢批判に触発されて「夢」について次のように述べています。
「夢がいとなまれる(いとなまれると考えられる)かぎりでは、どこから見てもそれは継続しているし、まとまった組織体の形をとどめている。ただ記憶のみが、夢を切り刻んだり、推移を無視して、夢そのものではない、むしろいくつかの夢のつながりを、私たちに見せる権利をわがものにしている。これと同じく、私たちはいくつかの現実についてつねに一定のはっきりした印象しかいだいていないが、このような整合は意思のなせるわざである。」*02
彼は夢もまた、人生の根本的諸問題の解決に適用できるのではないか、と考えていました。覚醒時の状態を一つの干渉現象であるとし、精神は覚醒時の諸条件のもとで、方向喪失への奇妙な傾斜を示す、と彼はいいます。精神の均衡は相対的で、精神があえて己れを明らかにすることはめったになく、かりにそうする場合でも、せいぜいある思いつき、自らの主観主義的傾向の大きさを示すだけで、それ以上には進まない、というのです。
ブルトンによればその思いつきは、精神をかきみだし、厳格さの弱まる方向へと傾けます。そしてその作用によって、精神は一瞬、溶解剤から遊離して中空に浮びあがり、美しい沈澱物の形をとるのです。精神はそんな沈澱物でありうるし、現にそうなのだ、とブルトンはいいます。窮余の一策として、精神はそのとき、ひときわ曖昧な神である偶然に助けを求め、自分のすべての迷いを偶然のせいにする*02のです。
Manifeste du Surréalisme / Poisson Soluble
Aux Éditions du Sagittaire chez Simon Kra
1924.10.15
精神をゆり動かすあの思いつきの現われる角度、それこそが精神をその夢に結びつけ、うっかり見失っていた条件に精神を繋ぎとめるものではないか。さもなければ、たぶん、精神に可能なことはなくなってしまう、とブルトンはいいます。ブルトンは「夢には厚みがある」と述べています。私たちはそのもっとも表層に近い層からやってくるものしか憶えていないのですが、その夢のさらなる奥へとつながる通路があるはずだ、と彼は断言します。そのためにブルトンは「精神にこの通路の鍵を与えたい」と希求するのです。
夢の曲線がたぐいない周期と振幅とで伸びてゆく瞬間から、神秘ならざるさまざまの神秘が、この偉大な(神秘)に、地位を明けわたすことが期待できるようになる、とブルトンはいいます。彼は夢と現実という、外見はまるで相容れないこの二つの状態が、一種の絶対的現実、言ってよければ一種の超現実の中に、いつしか解消されてしまうことを信ずる、と断言し、その方法論を提示したのです。
*01:シュルレアリスムと〈手〉/松田和子/水声社 2006.12.15
*02:シュルレアリスム宣言 溶ける魚/アンドレ・ブルトン/巖谷國士訳 學藝書林 1974.04.25(原著1924)
シュルレアリスム
磯崎新さんがガウディの構造的合理性を提起する中で「保留」*01した、ガウディの作品の形態的な異様さ、そのイメージの根源がなんであるか、という問いについて、磯崎さんはのちに、ダリなどヨーロッパのシュルレアリスムとガウディをつなげて解釈する*02ことの可能性について触れています。「シュルレアリスムの持っている言語論的な両義性、意味が二重になってみえている。こういうもので現実をさらに超えていくという考え方を、ガウディの方法論の中に見つけていくと説明がもっとしやすくなるし、正確にみれる」*02というのです。
シュルレアリスムは、日本語では超現実主義と訳されています。それは「現実を無視した世界を描き、まるで夢の中を覗いているような独特な現実感」を感じさせる、詩人のアンドレ・ブルトン(1896-1966)らによって提唱された20世紀初頭の芸術運動でした。
1924年に発表されたブルトンの「シュルレアリスム宣言」*03では、シュルレアリスムを「それを通じて人が、口述、記述、その他あらゆる方法を用い、思考の真の働きを表現しようとする、心の純粋な自動現象(オートマティスム)。理性によるどんな制約もうけず、美学上ないし道徳上のどんな先入主からもはなれた、思考の書き取り」と定義しています。
この「宣言」で謳われている、一見すると非合理主義的な主張は、第一次大戦のさなか、ヨーロッパ各地に巻き起こった反芸術運動であるダダイズムを継承するものであるようにも見えます。しかし、ひたすら偶像破壊的、撹乱的なダダイズムに対して、シュルレアリスムの独自性は、その体系性、組織性*04にありました。そしてシュルレアリスムもガウディも、その実践の試みをラショナルな操作で組み立てていく、合理的なやり方をしている*02という点に磯崎さんは注目します。
ダダイズム、シュルレアリスムに大きな影響を与えたジョルジョ・デ・キリコ
De_Chirico's_ Love Song 1914, Museum of Modern Art
*01:トポロジー変換された組積造/磯崎新/みずえ 1965.4
*02:アントニ・ガウディとはだれか/磯崎新/王国社 2004.04.10
*03:シュルレアリスム宣言 溶ける魚/アンドレ・ブルトン/巖谷國士訳 學藝書林 1974.04.25(原著1924)
*04:シュルレアリスムと〈手〉/松田和子/水声社 2006.12.15
+αの建築
今井兼次が初めての邂逅の時に暗い怖しい心におそわれ、ジョージ・オーウェルが世にも恐ろしい建物と形容したサグラダ・ファミリア。それをつくりだしたガウディは、形容しがたいほど矛盾を抱えた人物、といわれていました。そこには、のちに今井兼次がサグラダ・ファミリアをして、純粋で敬虔なカトリック教徒がつくりだしたもの、神との出会いの建築、と評したこととの間に、大きな隔たりがあると感じざるをえません。
今井兼次は、機能(ファンクション)を考えない建築は現代の建築ではない、という機能主義全盛時代の中で、現代建築には機能に+αが必要である、と強調した人でした。その+αとは哲学や美の問題、各国民族の特性や地理気象条件などによる種々な価値であり、それぞれの国によって決められるべき不定値*01といっていいのですが、それ以上に今井はその+αに「ヒューマニティ」を要求*01しました。建築の意義は建築の設計以前に考えるべきものであり、人間を離れての問題ではない。建築は人間生活の器であり社会の器だということを認識し、建築の社会的意義を知り、建築理念をはっきりと持つことが大切だ*01という信念にもとづいて彼は建築教育に情熱を傾けたのです。
その彼がガウディの晩年の、名誉も捨て、家族とも親しむことなく、托鉢にその時間を費やした献身的な姿に共感し、そこにあるヒューマニティを大いに称賛したことは当然のことだったといえるでしょう。ヨーロッパ歴訪から帰国した彼を待っていたモダニズム狂想曲の中では、ガウディの存在の紹介すらままならない状況で、彼はガウディを長年封印せざるを得ませんでした。ル・コルビュジェのロンシャン教会の登場をきっかけに、その形態的な類似性からガウディの再評価の機運が高まった時、まず彼は機能主義者たちも納得できるように、ガウディの異様な形態の構造的合理性について強調します。ガウディの建築は、まさに自然の持つ卓越した機能を取り入れた機能主義建築の代表なのだ、という主張です。次に彼は、ヒューマニティという建築の在り方に通底する普遍的な価値をガウディに見いだし、それを強調したのです。
この二つの視点の強調は、ガウディを(いえ、実はガウディに強く惹かれていた今井自身を)無視し続けた機能主義全盛時代への反発であり、反論であったと言ってもいいのではないでしょうか。そのため彼のこの主張には、機能主義に対するいわば〝意識過剰”なところがあります。機能主義者にも受け入れられようという意識が、ガウディに対する彼の評価にも反映されているのです。
今井兼次は1963年の夏、36年ぶりにバルセロナを再訪します。その時、改めてみたガウディの建築の印象について、「異質なものではなく奇怪なものでもなく、むしろ親しみ深い、ものやさしい真の建築の様相を呈している」*02と述べています。創意とは神に向かう事であるというガウディの信仰精神、燃えるような設計態度、愛の精神が静かに溢れ出ている、というのです。
今井兼次は、彼をガウディへと惹きつけてやまないものを理解しようと努めました。それはいわば感覚の世界、意識下の世界で彼を虜にしたものでしたが、彼はそれを〈言葉〉で表そうとします。その〈言葉〉は機能主義・現代建築に通じる〈言葉〉でなければなりませんでした。今井は三十数年間、ガウディに惹きつけられる魅力を説明する〈言葉〉を探し続け、その〈言葉〉でガウディを説明する〈論拠〉をつくりあげてきたのです。
機能主義建築に通じる合理的〈論拠〉によってガウディを理解する姿勢は、今井兼次に限らず、多くの人びとがたどり着いた姿勢でもありました。建築家の磯崎新さんも、かなり早い段階で、ガウディの構造的・工法的合理性について指摘しています。しかし彼は、その合理性を「ガウディの作品の形態的な異様さ、そのイメージの根源がなんであるかという問いを保留」*03したうえで提起しているのです。
今井兼次設計の早稲田大学図書館(現早稲田大学會津八一記念博物館)
柱の漆喰の装飾は左官職人が丹精を込めてつくりあげたもので、今井兼次はこの建設作業を通じて、人間の手によるヒューマンな建築づくりの重要性を改めて認識したといいます。
*01:概論-建築とヒューマニティ/今井兼次/今井兼次著作集一 中央公論美術出版 1995.09.20
*02:スペインの建築-ガウディを中心として/『稲門建築』一九六四年五月号/中央公論美術出版 今井兼次著作集三 1994.01.05
*03:トポロジー変換された組積造/磯崎新/みずえ 1965.4
世にも恐ろしい建物
ガウディが亡くなった1926年から、フランコが独裁政権を確立する1939年までのあいだ、サグラダ・ファミリアもスペイン内戦(1936.7~1939.4)の戦場となり、国家や教会といったすべての権威を否定するアナーキストたちによって数度の襲撃を受けました。特に1936年の襲撃では、生前のガウディが敬虔なカトリックだったという理由で、彼の墓(サグラダ・ファミリアの地下聖堂に埋葬されていました)が暴かれ*01、また今井兼次が1926年に聖堂の地下で見た*02高さ5~6mほどの巨大な完成模型などが粉々に破壊されてしまいます。このとき図面など多くの貴重な資料が失われてしまい、サグラダ・ファミリアの全体像を示すものは、シルエットを描いた一枚のみ(しかも現存するのはそれを写真に撮ったもの)となってしまったのです。
スペイン内戦時のサグラダ・ファミリアの状況について、イギリスの作家でジャーナリストのジョージ・オーウェル(1903~1950)が記したものがあります。彼はのちに全体主義的ディストピアの世界を描いた「1984」(1948)で有名になりますが、その着想を得た実体験として、スペイン内戦のルポルタージュ(1936.12~1937.6)を「カタロニア讃歌」*03としてまとめています。彼はその中で、内戦時のサグラダ・ファミリアについて次のように述べています。
「バルセロナに来て初めて、聖堂を見に行った。モダーンな聖堂で、世にも恐ろしい建物である。銃眼模様の、葡萄酒の瓶をさかさにしたような形の尖塔が四つある。バルセロナのほかの教会とちがって、革命の時にも破壊されなかった。その「芸術的価値」のために破壊をまぬがれたのだ、と人々は言っていた。アナーキスト軍は、尖塔と尖塔のあいだに、赤と黒の旗を吊しただけで、その建物をこわせばこわせるのに、こわさなかったとは、趣味の悪いところを見せたものである。」*03
ガウディの墓が暴かれ、完成模型などが徹底的に破壊される一方、オーウェルによれば建物本体は大きな被害はなかった、というのです。他の教会はアナーキストにより焼き払われ、建物の輪郭だけしか残らず、屋根のない四つの壁が瓦礫の山を囲っていた、とオーウェルもその惨状を記しているにもかかわらず、です。
オーウェルはサグラダ・ファミリアを、モダンではあるが世にも恐ろしい建物だ、と形容しています。さらにはそこに芸術的価値を認めたアナーキストたちを趣味が悪い、と切って捨てています。なぜオーウェルはそのように評したのでしょうか。
オーウェルは、スペインのこの地方の人たちは、ほんとうに宗教心というものを持たないにちがいない、と感じていました。それも正統的な意味での宗教心をもっていない、と。彼は、スペインにいる間に、一度も十字をきる人を見かけなかった、と書いています。それはふしぎなことと彼には思えました。そういう仕種(しぐさ)は、革命があろうがあるまいが、本能のようになっているはずのものだからです。スペイン教会はいずれ復活するだろう。しかし、革命の勃発によって、この国の教会は、亡びかけている英国教会とはくらべられないほどに、すっかり打ちのめされてしまっている。スペイン国民にとって、少なくともカタロニアとアラゴン地方の人にとって、教会はまったく無縁のものであり、ある程度までアナーキズムがキリスト教に取ってかわったいるのだ。そしてその影響力は広くひろまり、それが宗教的色彩をもっている、とオーウェルは断じるのです。
この時代に猛威を振るったアナーキズムに通じるものがガウディにはあった。少なくとも当のアナーキストたちはそう感じたに違いない。だからこそ彼らにとっての「芸術的価値」があるとしてサグラダ・ファミリアを破壊しなかったのではないか。そうオーウェルは感じたのです。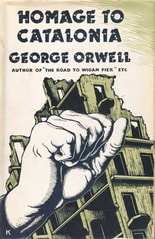
Homage_to_Catalonia,_Cover,_1st_Edition
*01:気になるガウディ/磯崎新/新潮社 2012.07.25
*02:海外に於ける建築界の趨勢(其二)/今井兼次/建築学会パンフレット第一集第一〇号 1928
*03:カタロニア讃歌/ジョージ・オーウェル/橋口 稔訳 筑摩書房 1970.12.25