todaeiji-weblog3
建築随想
Building Race of Mankind
一九世紀、イギリス・スコットランド出身のジェームズ・ファーガソン(1808-86)は、「英語で書かれた最初の本格的な世界建築史『建築史(A History of Architecture)』」*01を著したことで知られた建築史家でした。建築家の神谷武夫さんによれば、彼はその深い建築的思索と広く読まれた著作群とによって、ローマ時代の ウィトルウィウスにも比された人物だった*02といいます。さらに井上章一さんによれば「一九世紀という時代では、ファーガソンの本が決定版」*03でした。明治時代に、開校したばかりの東京帝大をはじめとして、日本で最初に行なわれた建築史教育においても、彼の著書が教科書として用いられたのです。そして石井敬吉や伊東忠太もまた、彼の著作を読み、様々な意味で大きな影響を受けたのです。
ファーガソンは、実業家としてインドに在住した時に、インドの様々な建築遺構に魅了されます。そしてインド建築史の体系化を図るとともに、数多くのスケッチにもとづく建築画集を出版し、インド建築を西欧に広く紹介していったのです。特に、彼の最初の論文である『インドの石窟寺院論(On the Rock-Cut Temples of India)』(1843)は大きな反響を呼び、イギリス人によってすでに1819年に発見されていたアジャンターの石窟寺院群などを、イギリス政府が保存に乗り出すきっかけともなったのです。
ファーガソンはさらに世界各地の建築についての資料を収集し、体系化し、発表していきました。その著作体系は インドからヨーロッパまで、また古代から 19世紀に至るまで広範囲に及びました。彼の業績は、現在、ほとんど忘れ去られてしまっていますが、それは彼の著作の内容の幅があまりにも広いがためにその全体像を捉えるのが容易でなかったことと、その最大の功績がインド建築史の体系化にあった、ことなどによる*02といわれているのです。
しかし明治初期の我が国の建築史家、特に伊東忠太の精神史において、彼の存在(著作)は大きな敵愾心とモチベーションを生み出した*03と井上章一さんは指摘します。特に彼の『A History of Architecture』の第3巻として著された『インドと東方の建築史(History of Indian and Eastern Architecture)』(1875)は大きな影響を与えました(伊東忠太の蔵書印のある本が残されており、彼の筆跡による書き込みが多く見つかっています*03)。
特筆すべきことは、この本において、日本と日本人のことが次のように述べられていたことです。
『今日までの我々の知見によると、この島には、耐久的な建造物(パーマネント・ビルディング)がただのひとつもない・・・多分、日本人は建造物を志向する民族(ビルディング・レイス・オブ・マンカインド)のひとつにはぞくしていない、そして壮麗な様式(モード・オブ・マグニフィシエンス)への興味をもちあわせてはいない。』*03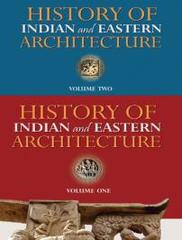
HISTORY OF INDIAN AND EASTERN ARCHITECTURE
*01:建築史学の興隆/デイヴィド・ワトキン/桐敷真次郎訳 1993.05 中央公論美術出版
*02:ジェイムズ・ファーガソンとインド建築/神谷武夫
*03:法隆寺への精神史/井上章一/弘文堂 1994.02.15
雛形としての数的原理
石井敬吉や伊東忠太が、ギリシア建築と共通する数的原理を「発見」したと信じた、法隆寺の「設計の美術に合う組織の自由なる割合」*01である比例関係は、実は「完数制」と呼ばれる日本古来から伝わる設計手法でもありました。「完数制」は、その時代の統治システムが求める度制(長さの基準)の単位寸法を基準として建物を設計する手法で、古代日本や中国、朝鮮に限らず、古代エジプトやメソポタミア、古代インドなど多くの古代文明で見られたものでした。
長さや大きさ、体積、重さに基準を与える制度、つまり度量衡制度は、専制王権の成立にともない、国家の税制、経済を支える基盤の一つとして現れます。そしてそれは理念として唯一絶対の長さの原点を形成し、王権の支配下で生み出された都市や建築も、当然のことながら、このシステムに従って計画されていったのです。つまり専制国家が生まれる過程において、それはいわば必然的に発達するものであり、古代世界に共通のものでもありました。
ところが古代ギリシア建築のそれでは、統治システムとして求められる共通の数値が重要なのではなく、そこに「数的な秩序」が成立しているということが重要でした。そしてその実現が建築の「美」と強く関わるとみなされていたのです。こうした古代ギリシアの数的秩序に美を見いだすという思想は、様々な古代文明を通観したときにも、きわめて特殊なものだったのです。
古代の日本建築に古代ギリシアと同じような「比例」を見つけたとしても、ギリシア建築と同じ「美」との関連性を見つけることは容易ではありませんでした。石井や伊東は西洋の数的秩序による「美」を「学説」として理解していましたが、「完数制」の伝統を知る多くの日本人は、そこに西洋のような数的秩序と関わる「美」の根本原理があるとは考えませんでした。
日本の封建社会は高度に意味づけられた儀礼の空間を形成していました。八束はじめさんも指摘するように、文献学的な奥行きをもった文化制度、つまり「有職故実(ゆうそくこじつ)」が礼儀作法、服飾そして日常生活を囲む物品、さらには宮殿の配置や建築空間のあり様(いわゆる室礼(しつらい)を含む)などを位置づけていった*02のです。日本古来の数的原理である完数制は、こうした儀礼の空間を様式としてタイプ化し、“雛形”とする役割を担っていたのです。
明治の日本で出版された最初の建築書といわれる「西洋家作雛形」は「美麗を目的とするのではなく、火災防御を目的」として、西洋建築の知識を広めるために翻訳されたといいます。そこでは“design”“designing”“drawing”などの翻訳語として「雛形」の語が用いられています。*03
「西洋家作雛形」シー・ブリュス・アルレン(C・ブルース・アレン)著/村田文雄・山田幸一郎訳/玉山堂/1872(明治五)年
*01:石井敬吉/「日本仏寺建築沿革略」/「建築雑誌」1893 年二月号 *04
*02:思想としての日本近代建築/八束はじめ 岩波書店 2005.06.28
*03:明治五年刊『西洋家件雛形』の建築用語/藤田治彦/Osaka University Knowledge Archive 1999
*04:法隆寺への精神史/井上章一/弘文堂 1994.02.15
確定した学説
明治二〇年代は日本美術の西方伝来という歴史観が一気に拡がった時代でした。そしてこの時代背景の中では、法隆寺の建物にも西方からの影響を「発見」するのは歴史的必然だったといっていいでしょう。
法隆寺のエンタシスは、伊東忠太が発見するまでもなく、人々がそれに気づくのは時間の問題だった、と井上章一さんは指摘します。事実、法隆寺とギリシア建築の類似性は、伊東の前任の帝大日本建築(史)の助教授であった石井敬吉によってすでに指摘されていた*01ことでもあったのです。
石井はエンタシスに限らず「建物の配置の特別なる、設計の美術に合う組織の自由なる割合の完美なる、之を希臘(ギリシア)のクラシック式に比するに美術上暗合する所あり。相並行して後るる所なからんとす」*02と述べています。それは西洋のウィトルウィウス的な数的原理による「美術建築」を、確定した「学説」として受け入れるという風潮が、すでに石井にも定着していたことを示しています。石井はそれを法隆寺に当てはめて評価しようとしたのです。
法隆寺の胴張柱/法隆寺中門
出典:「奈良六大寺大観 法隆寺一」奈良六大寺大観刊行会編 2001.07.25 岩波書店
*01:法隆寺への精神史/井上章一/弘文堂 1994.02.15
*02:石井敬吉/「日本仏寺建築沿革略」/「建築雑誌」1893 年二月号 *01
「至道」の歴史観
日本最古の仏教寺院である法隆寺において、伊東忠太は古代ギリシア神殿と共通する様々な手法やプロポーション(比例)を「発見」します。特にその比例は西洋建築の「美」を規定する“数”的原理と合致するものでした。彼はまさに、日本建築の伝統の中に西洋と同じ“根源的”な「美」が潜んでいることを実証してみせたのです。
しかし当時は、「日本美術」そのものが「発明」されるという歴史的な転換期でした。その中にあって、伊東がこのような「発見」に至るのは、半ば必然であった、といっていいでしょう。むしろ法隆寺におけるこの「発見」は、なされねばならなかった「至道」でもあったのです。
当時の日本美術をめぐる世界観の変化の歴史は、井上章一さんが「法隆寺への精神史」*01の中で詳しく述べています。
皇室の御物が納められた正倉院は、一八七二(明治五)年、明治新政府によって開封されます。それまで正倉院の御物は日本文化のオリジナルな資質をあらわしていると考えられていましたが、この時その収蔵品を検分した人々は、そこに「本邦固有」の「かたち」をそこに読み取り、その確固たる証拠を見いだした、と信じたのです。
ところが明治一〇年、正倉院を視察したイギリス人デザイナー、クリストファー・ドレッサーは、そこに全アジアの織物が一同に集められていることに驚きます。それだけでなく壺などにもギリシア的なものからアラビア風の性格をしたものまであり、西方のあらゆる諸工芸が集約されているのを「発見」するのです。しかもそれはタイムカプセルのごとく千年以上前のままに、完全に保存された状態で残っていました。
彼の「発見」の後、アーネスト・フェノロサらによって正倉院の収蔵物は詳しく調査されます。その成果をもとに一八八八(明治ニー)年、フェノロサがおこなった講演をマスコミが大きく取り上げたことをきっかけに、この「西方伝来説」は、ひろく知られるようになっていったのです。
「ペルシアをはじめとするかつての文明国は、ほろんでしまった。今では遺物も見つかりにくくなっている。だが、アジア諸国の文物は、奈良の正倉院に、無事のこされていた。まさに、奈良こそは、アジアの博物館だ」というフェノロサの日本美術の世界史理解は、のちの美術史家や建築史家だけでなく、当時の多くの日本人にも大きな影響をあたえたのです。
もちろんその理解は法隆寺にも及びます。フェノロサ自身「法隆寺は第二の正倉院」と述べています。しかし当初それは法隆寺におさめられた彫刻や絵画においてでした。伊東自身が指摘するように世間一般の法隆寺の名声は専ら「彫刻と絵画とに由」っており、その建築は「単に斯の美術を蓄蔵する一箇の器械」としか考えられていなかった*02のです。伊東はなんとしてでもそこに「東洋美術の粋」の証拠を、その収蔵物と同じく西方伝来の起源を示すことに傾注します。丸山茂さん*02によれば、それは「斯学に志す者」の「急務」にして「至道」であったのです。
ギリシアの古典古代を尊敬する西洋芸術の価値観を持ち、西洋人の視点から日本の伝統美術の復興に尽力したアーネスト・フランシスコ・フェノロサ(Ernest Francisco Fenollosa、1853-1908)/アメリカ合衆国の東洋美術史家・哲学者
*01:法隆寺への精神史/井上章一/弘文堂 1994.02.15
*02:日本の建築と思想-伊東忠太小論/丸山茂/同文書院 1996.04.15