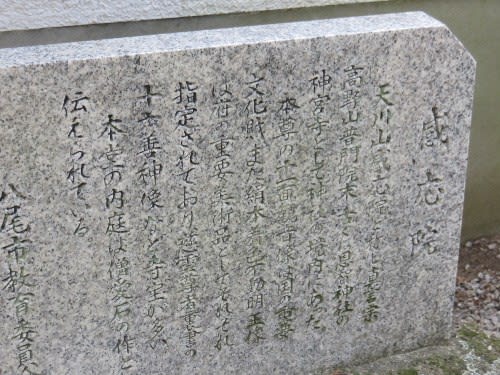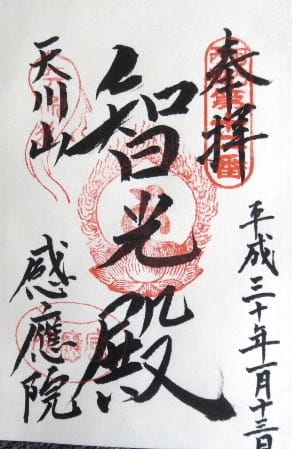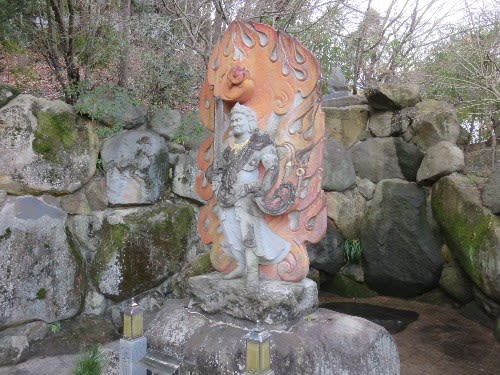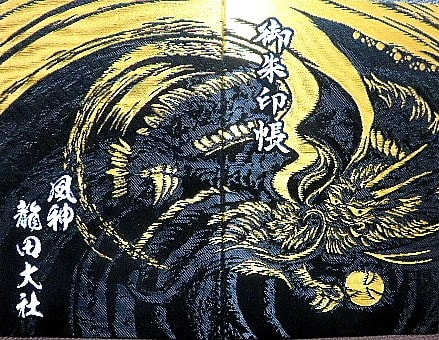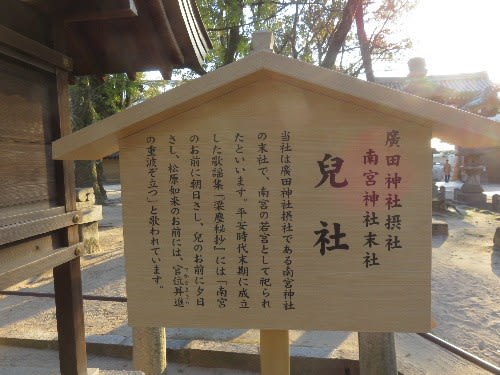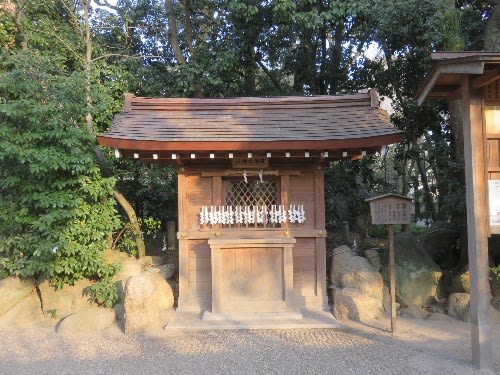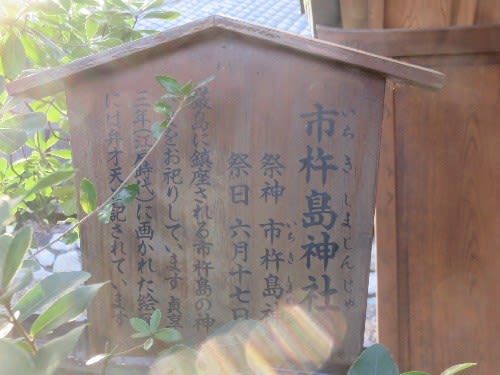外環状線を走っていると河内国二宮の恩智神社の看板発見。
参拝する予定は無かったが、
看板を見たからには参拝するしかあるまい。(^^
しかし恩智神社を目指して山の方へ行けば行くほど、
住宅街の細い道になっていく。
神社より数百メートル離れた場所に一の鳥居がありましたが、
タイミング悪く近くで道路工事していて写真が撮れませんでした。
渋い鳥居だったので撮りたかったけどね。
更に上に進むと細い道だし、駐車場があるか心配になってきたが、
意外にも数十台は停めれる無料駐車場がありました。
所在地:大阪府八尾市恩智中町5-10
御祭神:大御食津彦命、大御食津姫命
創建:雄略年間(470年頃)
社格:式内社、河内国二宮、府社
【由緒】

当社の創建は大和時代の雄略年間(470年頃)と伝えられ、
河内の国の御守護の為にお祀りされた神社で、
国内でも有数の古社であり、後に延喜式内名神大社に列する神社であります。
奈良時代に藤原氏により再建されてより、藤原氏の祖神である天児屋根命を、
常陸国「現香取神宮」より御分霊を奉還し、摂社として社を建立したその後、
宝亀年間に枚岡神社を経て春日大社に祀られました。
従って当社は元春日と呼ばれる所以であります。
朝廷からの崇敬厚く、持統天皇の元年(689)冬10月に行幸されて以来、
貞観元年(859)正月に従二位、更に正一位に叙せられ、
恩智大明神の称号を賜り、名神大社として延喜式名神帳に登載されました。
社殿は、当初天王森(現頓宮)に建立されていましたが、
建武年間に恩地左近公恩智城築城の折、社殿より上方にあるのは不敬として、
現在の地恩智山上に奉遷され、現在に至っています。
【閼伽井戸】

弘法大師に縁があり、
雨の降る前になると赤茶の濁水が流れ出るとか。
【拝殿】

平成12年(2000)に再建されたもの。
【神兎】

【神龍】

【春日神社】

御祭神:天児屋根命
香取神宮から御分霊され、後に枚岡神社⇒春日大社と、
ビッグネームの神社に祀られたとか。
この恩智神社は思ってた以上に由緒ある神社ですね。
案内看板を見逃さずに参拝して良かったよ。(^^
【愛宕神社】

【伏見桃山御陵遥拝所】

【三輪神社】

【六社神殿】


【本殿】

【神兎】

ここにも兔がおった。(笑)
【狛犬】

【皇太神宮遥拝所】

【参道】

まだ奥に境内社があるようです。
【八大龍王社】


【祖霊社】

拝殿横から左に時計回りに本殿を挟んで、
境内社が祀られていました。
【参道】

駐車場を利用するとこの131段の石段を登る必要はありません。
向かって左には神宮寺があるので後で参拝しよう。
【御朱印】

巫女さんも二人常駐し、
参拝者もそこそこ居ました。
なかなか活発な神社のようですね。
あと、御朱印帳を預けて参拝していると、
巫女さんがわざわざ境内に居る私を探して、
御朱印帳を渡してくれた。
社務所まで取りに行くのが普通で当たり前です。
でも、寒い外に出て渡してくれるなんて驚いたし、
初めての経験で嬉しかったなぁ。(^^
これはきっと私がイケメンだからに違いない。(笑)
信じるか信じないかは貴方次第!
あの巫女さんは本当に良いコだね。(^^
参拝して本当に良かったと思った瞬間でした。