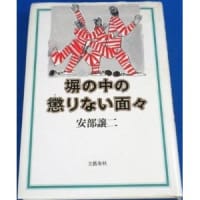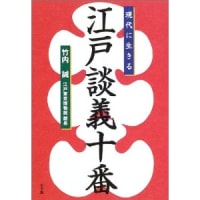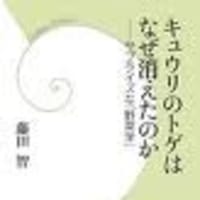早春の湯田中・小布施へ
南越谷には朝7時に着いた。
通勤ラッシュにはあわずホッとする。
大型バスがやってきた。
さいたま新都心で分乗客を乗せ、所沢から関越へ。
途中、2回ほどの小休憩があったが一路ひたすら、目的地の北志賀湯田中渋温泉へ向う。
このバスには、ガイド嬢もいない。添乗員もいない。
交通費混み1泊3食付き1万2千円の温泉ツアーである。
運転手はこれを「お値打ちツアー」と評したが、私のほうは「歓迎 ほっとけツアー」となづけた。
低額料金もさることながら、目的地には早く着き自由時間がたっぷりあれば、あれこれ工夫も生まれる。
そこが魅力で応募した。
分宿の湯の宿で昼食をとり、ほかのツアーのひとたちは地獄谷のサルを見物にでかけた。
宿からバスで出掛け、30分ほど歩いて野猿の温泉風景を眺めるらしい。
「われわれも、ひと風呂浴びられるのか」との質問が出たが、旅館側は「猿と一緒に入れません。また、そんな時間はございません」「足場は凍っていることろもあるから十分お気をつけて」の注意もあった。
私たち夫婦は、地獄谷のみなさんとは別に小布施に向った。
ほっとけ旅行はいい。
ビールを片手に新装の特急電車に入れば乗客はほかに一人だけの貸切状態。
ボックス席をぐるりと回して脚をのばす。
山麓の雪肌を眺めジワッとビールを飲む。
小布施のお目当ては、岩松院本堂の大間天井絵「八方睨み鳳凰図」。
葛飾北斎の晩年の作品を見たかったから。
天井画はNHKのテレビで紹介されたことがあり、強い印象が残っていて、機会があればと思っていた。
駅前から女性ドライバーのタクシーに乗り、岩松院へ。(写真)
ここには、福島正則の霊廟があった。
小姓として秀吉に仕えた武将が、徳川幕府によって広島藩五十万石から信州の高井野藩2万石に減封された悲劇を思う。
寺のうしろに小さな池があったが、ここが蛙合戦の場。
痩蛙まけるな一茶これにあり
この句は小学生の頃に覚えた。
継母に馴染めず江戸へ奉公に出た一茶こと小林弥太郎の芝居をさせられたのは私が小学校3年のとき。
一茶をいじめる村の子を演じさせられた。
だから、この句は、やせがえるに自分の生い立ちの姿を投影した句と長らく解していた。
だが、陽春のひきがえるの生と性の一大饗宴の句であったことを地元の女性運転手の話で知った。
数日間、数百匹のガマが集まりメスを奪いあう合戦が繰り広げられまたいづこへ消えるとのこと。
本堂に上がって天井画を見る。
北斎の意匠デザインの見事なセンスに驚かされた。
どこから眺めても睨まれているような鳳凰の眼が鋭くていい。
小布施に戻って北斎館を見学。
渡辺崋山も北斎漫画に影響を受けたとする本を読んだことがある。(注)
ひとつひとつの絵がいい。
画集を買って見たが一文に目がとまった。
富嶽百景の跋文 だ。
己 六才より物の形状を写の癖ありて 半百の此より数々画図を顕すといえども 七十年前画く所は実に取るに足るものなし 七十三才にして稍(ヤヤ)禽獣虫魚の骨格草木の出生を悟し得たり 故に八十六才にしては益々進み 九十才にして猶其(ソノ)奥意を極め 一百歳にして正に神妙ならんか 百有十歳にしては一点一格にして生(イケ)るがごとくならん
願わくは長寿の君子 予(ヨ)が言の妄ならざるを見たまふべし
画狂老人卍述
満々たる気概とこの自信と絵画への情熱。
老人パワーの原型として衝撃を受け、励まされもする。
小布施の酒屋に「七笑」の紙パック酒があったので、これも買った。
旅館に戻って夕食となったが、これが部屋食。
上げ膳、据え膳で夫婦差し向かいの旅館の食事などまったく久しぶりだ。
今までは子が一緒にいて、最近では孫も含めての山や海の旅が多い。
湯田中はまさにその名の通りで、その湯は豊富だ。
宿にある各種の温泉をくぐって遊び、酒を飲み、夜は雨音を聞いた。
翌朝、雨もあがったので近くを散策。 駅近くに小さな轆轤細工の工房があった。
中に入って、ご主人手彫りのいろいろな作品を見せてもらった。
この細工師は、明治の創業から四代目にあたる人で、桑や欅、梅、桜などの良質な木材を3~5年乾燥をして吟味し、轆轤で挽き、湯のみをはじめとするいろいろな作品に丹念に仕上げているという。
桑で作られた唐辛子入れと黒柿の楊枝入れを求めた。
帰路のバスでまた小布施に寄った。
マゴや近所への買い物などを済ませてから、昨日の酒屋にも寄った。
紙パックの七笑の酒がおいしかったので、これからの花見にそなえて計10本注文。
ご主人はお茶を出して接待してくれた。
東京での建築関係のサラリーマンからここへ戻って家業を継いでいるとのこと。
小布施に暮らしてみると、ゆったりとした時間が流れているという話は、なるほどと思った。
小布施の町は、こせついていない。
栗菓子を売る店も観光ズレしておらず、静かな品がある。
人口一万人の町に北斎館や高井鴻山など12の美術館があるというのもいい。
落ち着いたすてきな町なので再訪してみたい。
酒屋のご主人も「わたしの家にも、たくさんの栗の木があるから、その頃ぜひいらしてください。栗拾いをどうぞ」 と誘ってくれた。
買い物ツアーだけに終わることの多いバスの旅では貴重な会話の時間だった。
これもホットケ旅行だったから味わえたものと、今回の小旅行は満足できた。
■■ ブログ記憶書庫 ■■
注)
南越谷には朝7時に着いた。
通勤ラッシュにはあわずホッとする。
大型バスがやってきた。
さいたま新都心で分乗客を乗せ、所沢から関越へ。
途中、2回ほどの小休憩があったが一路ひたすら、目的地の北志賀湯田中渋温泉へ向う。
このバスには、ガイド嬢もいない。添乗員もいない。
交通費混み1泊3食付き1万2千円の温泉ツアーである。
運転手はこれを「お値打ちツアー」と評したが、私のほうは「歓迎 ほっとけツアー」となづけた。
低額料金もさることながら、目的地には早く着き自由時間がたっぷりあれば、あれこれ工夫も生まれる。
そこが魅力で応募した。
分宿の湯の宿で昼食をとり、ほかのツアーのひとたちは地獄谷のサルを見物にでかけた。
宿からバスで出掛け、30分ほど歩いて野猿の温泉風景を眺めるらしい。
「われわれも、ひと風呂浴びられるのか」との質問が出たが、旅館側は「猿と一緒に入れません。また、そんな時間はございません」「足場は凍っていることろもあるから十分お気をつけて」の注意もあった。
私たち夫婦は、地獄谷のみなさんとは別に小布施に向った。
ほっとけ旅行はいい。
ビールを片手に新装の特急電車に入れば乗客はほかに一人だけの貸切状態。
ボックス席をぐるりと回して脚をのばす。
山麓の雪肌を眺めジワッとビールを飲む。
小布施のお目当ては、岩松院本堂の大間天井絵「八方睨み鳳凰図」。
葛飾北斎の晩年の作品を見たかったから。
天井画はNHKのテレビで紹介されたことがあり、強い印象が残っていて、機会があればと思っていた。
駅前から女性ドライバーのタクシーに乗り、岩松院へ。(写真)
ここには、福島正則の霊廟があった。
小姓として秀吉に仕えた武将が、徳川幕府によって広島藩五十万石から信州の高井野藩2万石に減封された悲劇を思う。
寺のうしろに小さな池があったが、ここが蛙合戦の場。
痩蛙まけるな一茶これにあり
この句は小学生の頃に覚えた。
継母に馴染めず江戸へ奉公に出た一茶こと小林弥太郎の芝居をさせられたのは私が小学校3年のとき。
一茶をいじめる村の子を演じさせられた。
だから、この句は、やせがえるに自分の生い立ちの姿を投影した句と長らく解していた。
だが、陽春のひきがえるの生と性の一大饗宴の句であったことを地元の女性運転手の話で知った。
数日間、数百匹のガマが集まりメスを奪いあう合戦が繰り広げられまたいづこへ消えるとのこと。
本堂に上がって天井画を見る。
北斎の意匠デザインの見事なセンスに驚かされた。
どこから眺めても睨まれているような鳳凰の眼が鋭くていい。
小布施に戻って北斎館を見学。
渡辺崋山も北斎漫画に影響を受けたとする本を読んだことがある。(注)
ひとつひとつの絵がいい。
画集を買って見たが一文に目がとまった。
富嶽百景の跋文 だ。
己 六才より物の形状を写の癖ありて 半百の此より数々画図を顕すといえども 七十年前画く所は実に取るに足るものなし 七十三才にして稍(ヤヤ)禽獣虫魚の骨格草木の出生を悟し得たり 故に八十六才にしては益々進み 九十才にして猶其(ソノ)奥意を極め 一百歳にして正に神妙ならんか 百有十歳にしては一点一格にして生(イケ)るがごとくならん
願わくは長寿の君子 予(ヨ)が言の妄ならざるを見たまふべし
画狂老人卍述
満々たる気概とこの自信と絵画への情熱。
老人パワーの原型として衝撃を受け、励まされもする。
小布施の酒屋に「七笑」の紙パック酒があったので、これも買った。
旅館に戻って夕食となったが、これが部屋食。
上げ膳、据え膳で夫婦差し向かいの旅館の食事などまったく久しぶりだ。
今までは子が一緒にいて、最近では孫も含めての山や海の旅が多い。
湯田中はまさにその名の通りで、その湯は豊富だ。
宿にある各種の温泉をくぐって遊び、酒を飲み、夜は雨音を聞いた。
翌朝、雨もあがったので近くを散策。 駅近くに小さな轆轤細工の工房があった。
中に入って、ご主人手彫りのいろいろな作品を見せてもらった。
この細工師は、明治の創業から四代目にあたる人で、桑や欅、梅、桜などの良質な木材を3~5年乾燥をして吟味し、轆轤で挽き、湯のみをはじめとするいろいろな作品に丹念に仕上げているという。
桑で作られた唐辛子入れと黒柿の楊枝入れを求めた。
帰路のバスでまた小布施に寄った。
マゴや近所への買い物などを済ませてから、昨日の酒屋にも寄った。
紙パックの七笑の酒がおいしかったので、これからの花見にそなえて計10本注文。
ご主人はお茶を出して接待してくれた。
東京での建築関係のサラリーマンからここへ戻って家業を継いでいるとのこと。
小布施に暮らしてみると、ゆったりとした時間が流れているという話は、なるほどと思った。
小布施の町は、こせついていない。
栗菓子を売る店も観光ズレしておらず、静かな品がある。
人口一万人の町に北斎館や高井鴻山など12の美術館があるというのもいい。
落ち着いたすてきな町なので再訪してみたい。
酒屋のご主人も「わたしの家にも、たくさんの栗の木があるから、その頃ぜひいらしてください。栗拾いをどうぞ」 と誘ってくれた。
買い物ツアーだけに終わることの多いバスの旅では貴重な会話の時間だった。
これもホットケ旅行だったから味わえたものと、今回の小旅行は満足できた。
■■ ブログ記憶書庫 ■■
注)