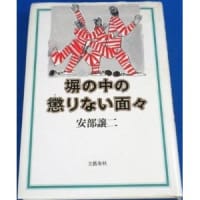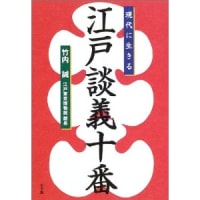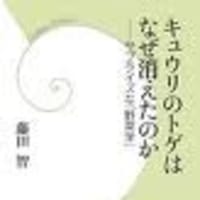〔14 七五の読後〕 【勘定奉行 荻原重秀の生涯 】 村井 淳志 集英社新書
元禄期の財務実務官僚・萩原重秀。
財務の仕事ができる男の魅力が充分に醸し出されて一冊の本となった。
著者の村井さんは寛政重修諸家譜全22巻中から勘定職関係者をエクセルファイルに抽出して論考した。
その期間3か月という。
また、ケインズと作家・吉村昭の大ファンだそうだ。
史資料を読みこなして新たな重秀像を刻んでいる。
サブタイトルの「新井白石が嫉妬した天才」というところにも関心があった。
読後のメモとして関心のあったところを抜く。
● 重秀と吉保 同期の仲
新井白石は明暦の大火の翌日にその避難先で生まれた。
明暦3年(1657年)2月10日のこと。
この大火の翌年に萩原重秀、柳沢吉保、室鳩巣が揃って誕生。
江戸を焼き尽くした明暦の大火で家綱時代の金びつは空に近い。
復興に要した金で一段と消耗した。
これ以降、幕府蓄財は大きな課題となってくる。
● せい様と蔭で言われた将軍家
四代将軍家綱は「左様せい」「よきにはからえ」が口癖で主君として何も判断しないし、できない凡将の器。
殿中の蔭では「左様せい様」と言われた。
延宝2年(1674年)の幕閣
将軍家綱 34歳
大老 酒井忠清 井伊直澄
老中 稲葉正則 堀数直(白石父子の主人の弟)
若年寄に 堀田正俊がいる。
正俊は天和元年(1681年)、忠清に代わって大老に就任したが貞享元年(1684年)同僚役の稲葉正休に城内で刺殺された。
白石は、天和3年26歳の時、この堀田正俊に仕えたが、やがて堀田家を自ら退いて浪人し、独学で儒学を学び続け貞享四年(1686年)に木下順庵に入門。
● 延宝検地 頭角現す彦次郎
荻原重秀の若い呼び名は「彦次郎」。
彦次郎は延宝2年(1674年)、勘定所に出仕、150俵の給米。
延宝5年、23歳の彦次郎(後の重秀)は畿内一円の大検地に派遣された。
この検地の活躍で能力を発揮し褒賞。
「日本史大事典 1」の「荻原重秀」の項に「延宝の畿内総検地で頭角を現し、将軍綱吉初政に断行された総代官の会計監査に特命されてあたったと言われ・・・」との記述がある。
● せい様は 40歳で身罷れり
延宝8年(1680年)。
家綱40歳で死去。
綱吉が兄の家宣に代わって五代将軍に就任。
● 綱吉の屋敷 読売新社辺りだと
平成26年(2014年)3月1日。
大手町の読売新聞社でOB招待の内覧会があった。
地上200メートル、33Fのメディア新ビルが誕生。
昔、この一帯が小笠原左京大夫邸跡にあたることは仄聞していたが、それ以前「綱吉」屋敷とこの本に指摘がありビックリ。
● 彦次郎26にて組頭
天和3年 彦次郎26にて勘定組頭に出世。
● 30歳 勘定奉行補佐となり
貞享年二年(1685年)
彦次郎は勘定吟味役。
奉行の適不適の吟味もできる立場となった。
貞享四年(1687年)
荻原彦次郎(重秀)は勘定差添役となり550石を頂戴。
百五十俵の微禄から、やがて三千七百石になるための踏み出しでもあった。
● 彦次郎 世襲代官一掃し
彦次郎 年貢上納などの管理で、きちんとしていない9人の世襲代官を切腹、免職、流罪、追放処分に追い込んだ。
また無能な勘定頭3人を罷免、と人事の大鉈を揮う。
32歳で750石に昇進。
これは、世襲代官と勘定方粛清の褒賞でもあった。
● 鎖国にて金鉱枯れにぶつかりて
江戸初期の金銀産出量は世界の年間産出量の3-4割とされている。
ジパングと言われ金産出が豊富だった国でもあったが、金鉱も枯渇気味。
● 湧き水を捨てて相川沸きかえり
元禄3年(1690年)秋、重秀は佐渡奉行就任。
重秀の佐渡金山産出のための排水工夫が効を奏して産出量がおおいに上がる。
全国から佐渡に4万人が集まって栄えた。
佐渡では新検地を実施して増税も発案。
村人からは怨嗟の声もあったが、年貢と鉱山経営を同一会計で処理。
このシステムを作って成功。
● 23年間 佐渡奉行を勤め上げ
2ヵ月半滞在して収益システムを作り同一会計に道を開き、以後一度も渡海して佐渡に渡っていない。
それでも23年間同奉行職にあったところが財務官僚として非凡。
● 彦次郎 改鋳にて幣史刻み
名高い元禄の貨幣改鋳。
これを悪貨悪政とみるか、どうかは史眼の違い。
筆者は肯定的。
ヨーロッパの経済学界よりも200年も早く改鋳で名目貨幣の考え方に気付いているとしている。
● 銀量を増やして作る金小判
元禄小判は江戸時代の金貨としては慶長小判に次ぐもの。
ただ慶長期と比して純金の含有率は57・36%。その分、銀を増やしている。
● 本郷の大根畑が造幣局
ここ、JR御茶ノ水北500メートルが吹替え場となった。
3年後には現在の日銀本店の所に移動。
元禄8年8月7日(1695年9月14日)に出された金銀改鋳に関する触書
一、金銀極印古く成候に付、可ニ吹直一旨被レ仰ニ出之一、且又近年山より出候金銀も多無レ之、世間の金銀も次第に減じ可レ申に付、金銀の位を直し、世間の金銀多出来候ため被ニ仰付一候事。
一、金銀吹直し候に付、世間人々所持の金銀、公儀へ御取上被レ成候にては無レ之候。公儀の金銀、先吹直し候上にて世間へ可レ出レ之候、至ニ其時一可ニ申渡一候事。以上
また、元禄金銀も、慶長金銀と等価に通用させるよう通達
一、今度金銀吹直し被ニ仰付一、吹直り候金銀、段々世間へ可ニ相渡一之間、在来金銀と同事に相心得、古金銀と入交、遣方・請取・渡・両替共に無レ滞用ひ可レ申、上納金銀も右可為ニ同事一
元禄8年のこの時
綱吉 50歳
吉保 38歳 重秀 38歳
● 改鋳のインフレ騒ぎなく
多雨冷夏の年で翌年の米価が高騰したが、改鋳での余波は町農民には及んでいない。
その後、米価は低落したとある。
● 白石は出目五百と推定し
慶長小判を回収して改鋳する。
質を落として多くを鋳造するのだからその差益金は厖大。
慶長小判の退蔵量が多いほど幕府の金庫は潤う仕組み。
白石は500万両と推定した。
白石は「折たく柴の記」で「荻原は26万両の賄賂を受けていた」などと根拠なき文言を繰り返し、その悪評が萩原重秀に定着して、今日に及ぶ。
● 彦次郎 勘定奉行に昇進し
元禄9年 39歳で財務のトップ。
まさにミゾユウ(未曾有)と言った現在の財務大臣の立場になったわけだ。
● 幕臣の給与システム手直しし
元禄11年(1698年)重秀の建議により財政立て直しを主目的に、給与として禄米で渡していた元高500石以上の旗本に対して、天領を知行地として与えるしくみに改めた。旗本の4割が該当。
それまでは五百石を浅草御蔵から年3回の分割支給。
「元禄地方直し」と呼ばれている。
知行地の行政は旗本自身の責任であり、年貢の徴収から輸送、売却も、当然旗本の自己負担となる。蔵米を知行地に変えることで、幕府の経費が大幅節減となる。歳出削減に大貢献。
全国400万石 → 天領
年貢収入 年間 76.7万両 40%が廩米
● 長崎と大坂銅座を結ぶ知恵
元禄14年
重秀は銀に代わる銅調達をして輸出剤の一元化を図った。
銅は長崎会所貿易決済に用いた。
この後、重秀は東大寺大仏殿再興での財源確保策として天領への賦課金方式を考案。
天領領は5年で5万両を、大名領には2年で10万の賦課金を調達。
● 切腹の祟りか大地 揺れに揺れ
元禄16年11月23日(1703年1)、関東地方に巨大地震発生。元禄地震とされたが震源分布図が大正の関東地震とよく似ている。M8.1。
この年の3月に赤穂浪士46人が切腹しており、浪士たちの恨みで起こった地震と江戸っ子は噂した。
3年後には、M8・4の宝永地震(宝永4年・1707年)が起こった。
同年12月の富士山の大噴火によって元禄文化は終焉する。
●犬公方 30年の職務終え
宝永6年(1709年)、30年在職の徳川綱吉死去。64歳。
次期将軍は六代家宣48歳。
白石の出番となる。
白石の重秀への憎悪は相当なもので病没寸前の家宣に諫言し、正徳2年(1712年)重秀の勘定奉行を罷免させている。
併読して読んだ本
■■ 【月華の銀橋】 高任 和夫 講談社
最近はほとんど小説は読まない。
でも作者の視点が面白かった。
元禄期の政治舞台の人物の並べ方にも好感が持てた。
この作者も重秀を買っている。
時代小説は考証とセリフが決めてでそれが現代風だと、ダァッツーと興ざめになることが多い。
残念だが、その例に漏れない仕上がりだった。
■■ 【新井白石】 童門冬二
著者はかっての革新都政・美濃部時代の広報課長だったらしい。
コクとか深みが感じられない教科書的な広報文体で終始。
着眼点もよくわからず、ようするに一読して「面白くない」。
■■ 【柳沢吉保と江戸の夢】 島内景二
あくび連発の前半だった。
柳沢吉保の下屋敷として造営した大名庭園「六義園」沿革の話しなどまったく興味がわかず。
後半少し面白くなり、新田次郎「怒る富士」を称賛紹介した下りからは眼が覚めた。
元禄期の財務実務官僚・萩原重秀。
財務の仕事ができる男の魅力が充分に醸し出されて一冊の本となった。
著者の村井さんは寛政重修諸家譜全22巻中から勘定職関係者をエクセルファイルに抽出して論考した。
その期間3か月という。
また、ケインズと作家・吉村昭の大ファンだそうだ。
史資料を読みこなして新たな重秀像を刻んでいる。
サブタイトルの「新井白石が嫉妬した天才」というところにも関心があった。
読後のメモとして関心のあったところを抜く。
● 重秀と吉保 同期の仲
新井白石は明暦の大火の翌日にその避難先で生まれた。
明暦3年(1657年)2月10日のこと。
この大火の翌年に萩原重秀、柳沢吉保、室鳩巣が揃って誕生。
江戸を焼き尽くした明暦の大火で家綱時代の金びつは空に近い。
復興に要した金で一段と消耗した。
これ以降、幕府蓄財は大きな課題となってくる。
● せい様と蔭で言われた将軍家
四代将軍家綱は「左様せい」「よきにはからえ」が口癖で主君として何も判断しないし、できない凡将の器。
殿中の蔭では「左様せい様」と言われた。
延宝2年(1674年)の幕閣
将軍家綱 34歳
大老 酒井忠清 井伊直澄
老中 稲葉正則 堀数直(白石父子の主人の弟)
若年寄に 堀田正俊がいる。
正俊は天和元年(1681年)、忠清に代わって大老に就任したが貞享元年(1684年)同僚役の稲葉正休に城内で刺殺された。
白石は、天和3年26歳の時、この堀田正俊に仕えたが、やがて堀田家を自ら退いて浪人し、独学で儒学を学び続け貞享四年(1686年)に木下順庵に入門。
● 延宝検地 頭角現す彦次郎
荻原重秀の若い呼び名は「彦次郎」。
彦次郎は延宝2年(1674年)、勘定所に出仕、150俵の給米。
延宝5年、23歳の彦次郎(後の重秀)は畿内一円の大検地に派遣された。
この検地の活躍で能力を発揮し褒賞。
「日本史大事典 1」の「荻原重秀」の項に「延宝の畿内総検地で頭角を現し、将軍綱吉初政に断行された総代官の会計監査に特命されてあたったと言われ・・・」との記述がある。
● せい様は 40歳で身罷れり
延宝8年(1680年)。
家綱40歳で死去。
綱吉が兄の家宣に代わって五代将軍に就任。
● 綱吉の屋敷 読売新社辺りだと
平成26年(2014年)3月1日。
大手町の読売新聞社でOB招待の内覧会があった。
地上200メートル、33Fのメディア新ビルが誕生。
昔、この一帯が小笠原左京大夫邸跡にあたることは仄聞していたが、それ以前「綱吉」屋敷とこの本に指摘がありビックリ。
● 彦次郎26にて組頭
天和3年 彦次郎26にて勘定組頭に出世。
● 30歳 勘定奉行補佐となり
貞享年二年(1685年)
彦次郎は勘定吟味役。
奉行の適不適の吟味もできる立場となった。
貞享四年(1687年)
荻原彦次郎(重秀)は勘定差添役となり550石を頂戴。
百五十俵の微禄から、やがて三千七百石になるための踏み出しでもあった。
● 彦次郎 世襲代官一掃し
彦次郎 年貢上納などの管理で、きちんとしていない9人の世襲代官を切腹、免職、流罪、追放処分に追い込んだ。
また無能な勘定頭3人を罷免、と人事の大鉈を揮う。
32歳で750石に昇進。
これは、世襲代官と勘定方粛清の褒賞でもあった。
● 鎖国にて金鉱枯れにぶつかりて
江戸初期の金銀産出量は世界の年間産出量の3-4割とされている。
ジパングと言われ金産出が豊富だった国でもあったが、金鉱も枯渇気味。
● 湧き水を捨てて相川沸きかえり
元禄3年(1690年)秋、重秀は佐渡奉行就任。
重秀の佐渡金山産出のための排水工夫が効を奏して産出量がおおいに上がる。
全国から佐渡に4万人が集まって栄えた。
佐渡では新検地を実施して増税も発案。
村人からは怨嗟の声もあったが、年貢と鉱山経営を同一会計で処理。
このシステムを作って成功。
● 23年間 佐渡奉行を勤め上げ
2ヵ月半滞在して収益システムを作り同一会計に道を開き、以後一度も渡海して佐渡に渡っていない。
それでも23年間同奉行職にあったところが財務官僚として非凡。
● 彦次郎 改鋳にて幣史刻み
名高い元禄の貨幣改鋳。
これを悪貨悪政とみるか、どうかは史眼の違い。
筆者は肯定的。
ヨーロッパの経済学界よりも200年も早く改鋳で名目貨幣の考え方に気付いているとしている。
● 銀量を増やして作る金小判
元禄小判は江戸時代の金貨としては慶長小判に次ぐもの。
ただ慶長期と比して純金の含有率は57・36%。その分、銀を増やしている。
● 本郷の大根畑が造幣局
ここ、JR御茶ノ水北500メートルが吹替え場となった。
3年後には現在の日銀本店の所に移動。
元禄8年8月7日(1695年9月14日)に出された金銀改鋳に関する触書
一、金銀極印古く成候に付、可ニ吹直一旨被レ仰ニ出之一、且又近年山より出候金銀も多無レ之、世間の金銀も次第に減じ可レ申に付、金銀の位を直し、世間の金銀多出来候ため被ニ仰付一候事。
一、金銀吹直し候に付、世間人々所持の金銀、公儀へ御取上被レ成候にては無レ之候。公儀の金銀、先吹直し候上にて世間へ可レ出レ之候、至ニ其時一可ニ申渡一候事。以上
また、元禄金銀も、慶長金銀と等価に通用させるよう通達
一、今度金銀吹直し被ニ仰付一、吹直り候金銀、段々世間へ可ニ相渡一之間、在来金銀と同事に相心得、古金銀と入交、遣方・請取・渡・両替共に無レ滞用ひ可レ申、上納金銀も右可為ニ同事一
元禄8年のこの時
綱吉 50歳
吉保 38歳 重秀 38歳
● 改鋳のインフレ騒ぎなく
多雨冷夏の年で翌年の米価が高騰したが、改鋳での余波は町農民には及んでいない。
その後、米価は低落したとある。
● 白石は出目五百と推定し
慶長小判を回収して改鋳する。
質を落として多くを鋳造するのだからその差益金は厖大。
慶長小判の退蔵量が多いほど幕府の金庫は潤う仕組み。
白石は500万両と推定した。
白石は「折たく柴の記」で「荻原は26万両の賄賂を受けていた」などと根拠なき文言を繰り返し、その悪評が萩原重秀に定着して、今日に及ぶ。
● 彦次郎 勘定奉行に昇進し
元禄9年 39歳で財務のトップ。
まさにミゾユウ(未曾有)と言った現在の財務大臣の立場になったわけだ。
● 幕臣の給与システム手直しし
元禄11年(1698年)重秀の建議により財政立て直しを主目的に、給与として禄米で渡していた元高500石以上の旗本に対して、天領を知行地として与えるしくみに改めた。旗本の4割が該当。
それまでは五百石を浅草御蔵から年3回の分割支給。
「元禄地方直し」と呼ばれている。
知行地の行政は旗本自身の責任であり、年貢の徴収から輸送、売却も、当然旗本の自己負担となる。蔵米を知行地に変えることで、幕府の経費が大幅節減となる。歳出削減に大貢献。
全国400万石 → 天領
年貢収入 年間 76.7万両 40%が廩米
● 長崎と大坂銅座を結ぶ知恵
元禄14年
重秀は銀に代わる銅調達をして輸出剤の一元化を図った。
銅は長崎会所貿易決済に用いた。
この後、重秀は東大寺大仏殿再興での財源確保策として天領への賦課金方式を考案。
天領領は5年で5万両を、大名領には2年で10万の賦課金を調達。
● 切腹の祟りか大地 揺れに揺れ
元禄16年11月23日(1703年1)、関東地方に巨大地震発生。元禄地震とされたが震源分布図が大正の関東地震とよく似ている。M8.1。
この年の3月に赤穂浪士46人が切腹しており、浪士たちの恨みで起こった地震と江戸っ子は噂した。
3年後には、M8・4の宝永地震(宝永4年・1707年)が起こった。
同年12月の富士山の大噴火によって元禄文化は終焉する。
●犬公方 30年の職務終え
宝永6年(1709年)、30年在職の徳川綱吉死去。64歳。
次期将軍は六代家宣48歳。
白石の出番となる。
白石の重秀への憎悪は相当なもので病没寸前の家宣に諫言し、正徳2年(1712年)重秀の勘定奉行を罷免させている。
併読して読んだ本
■■ 【月華の銀橋】 高任 和夫 講談社
最近はほとんど小説は読まない。
でも作者の視点が面白かった。
元禄期の政治舞台の人物の並べ方にも好感が持てた。
この作者も重秀を買っている。
時代小説は考証とセリフが決めてでそれが現代風だと、ダァッツーと興ざめになることが多い。
残念だが、その例に漏れない仕上がりだった。
■■ 【新井白石】 童門冬二
著者はかっての革新都政・美濃部時代の広報課長だったらしい。
コクとか深みが感じられない教科書的な広報文体で終始。
着眼点もよくわからず、ようするに一読して「面白くない」。
■■ 【柳沢吉保と江戸の夢】 島内景二
あくび連発の前半だった。
柳沢吉保の下屋敷として造営した大名庭園「六義園」沿革の話しなどまったく興味がわかず。
後半少し面白くなり、新田次郎「怒る富士」を称賛紹介した下りからは眼が覚めた。