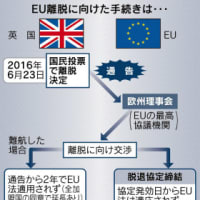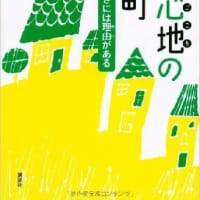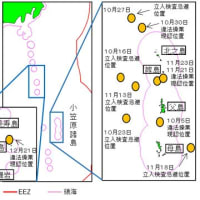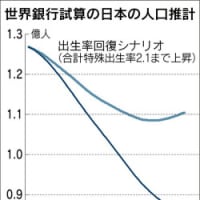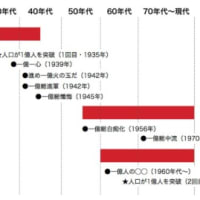3月22日付け投稿(自分史後始末記、読者と著者の間~(1)過剰の生)において、読者の感想への対応として、「過剰の生」との言葉を使い説明した。一方、その言葉の「筆者における出所」は、山口昌男の本であったとも書いた。それは以下になる。
「道化はその限界を知らぬ放恣な性格の故に、定住の世界に安住することを許されない。あらゆる慾において彼は限度というものを知らない。それは多分、ジョルジュ・バタイユ的表現を用いれば道化が「過剰の生」の表現である故なのであろう」(「道化と詩的言語」、『道化的世界』山口昌男著,筑摩書房(1975)所収,P22)。
但し、「生活世界」のなかで、バタイユ的な<過剰の生>が存在するだろうか?未だ十分な説明ができていない!とも述べた。
しかし、翻って考えれば、「過剰の生」は比喩的表現、日常生活での発想から溢れ出てくることを表現する際に使い易い表現だ。その意味で「日常言語」の対極に位置させた「詩的言語」との表現は「言い得て妙」であろう。
また、生活世界が哲学的表現であるならば、過剰の生もバタイユの「生活哲学」と言えないことはない。生活世界がその後、シュッツによって哲学から社会科学の分野で体系化され、ルックマンが共著としてまとめあげる(『生活世界の構造』(筑摩学芸文庫)。以降、社会学の一分野として定着する。勿論、そこでは「過剰の生」との言葉はでないが、日常性を突破して新たな世界を開示する現象は、生活世界でも生成する。