本当は他の記事をアップするつもりだったのですが、急遽政治的なお話を。
冒頭の写真は「Yahoo.tw」より。(http://tw.news.yahoo.com/article/url/d/a/080616/17/11cgn.html)
日本のみなさんは、ここ最近の日本と台湾の不穏なニュースにどれくらい注目しているのでしょうか。ネットのニュースで見る限り、たぶん多くの人に取っては「ふーん」くらいのニュースな感じですが、こちらでは毎日大騒ぎです。
「なんでそんなに台湾の人は大騒ぎしてるのかしら」と思っている人もいるかもなぁと思ったので、今日はちょっと日本と台湾のさまざまな事情を解説してみたいと思います。
事件の経過を簡単に説明すると、
6月10日未明 「魚釣島」の南9キロの「日本領海内」で、日本の海上保安庁の巡視船と台湾の漁船が接触。漁船が沈み、漁船に乗っていた「乗組員」16人を巡視船が「保護」する。
6月13日 台湾の行政院長(日本の首相に相当)が、対日批判を表し、「開戦も辞さない」と発言。
6月14日 海上保安部は、巡視船の船長と同時に漁船の乗組員を石垣島で事情聴取、書類送検。台湾の外交部(日本の外務省に相当)が駐日代表の許さんを召還することを発表。
6月15日夜 海上保安本部が「巡視船が船名を確認しようと遊漁船に近づいた行為は正当だったが、接近の仕方に過失があった。結果として遊漁船を沈没させ、船長にけがをさせたことは遺憾だ」と過失を認め、謝罪。
6月16日未明 日本政府の対応に不満を持ち、台湾の抗議船など10隻が再び「魚釣島」付近へ。
さて、まずは懸案の「魚釣島」ですが、「どこ?」という人もいるかもしれないのでまずは地図です。

(「海上保安レポート」よりhttp://www.kaiho.mlit.go.jp/info/books/report2006/tokushu/p034.html)
今回の事件、いろいろポイントがあるのですが、まずはこの地図を見て分かる通り、「魚釣島」は石垣島と台湾からほぼ等距離にある島で、日本においては石垣市に帰属している日本の領土と認識されていますが、台湾においては「宜蘭県釣魚台」とされています。台湾でももちろんここはまだ領土問題が微妙な土地だという認識はありますが、それでもはっきりと「日本のものだ」とはほとんど誰も思っていない状態です。
第二のポイントとして、日本の巡視船が台湾の漁船に接触事故を起こしたというのも、台湾では「わざとぶつかって沈ませた」のでは?と考えられています。その後の日本政府の対応で余計その疑惑は強まっているのかも。
なので、いわば「うっかり他国との境界空域に侵入してしまった民間航空機がそこの国の軍隊に射撃されて墜落した」みたいな感じなんですよ。台湾漁船に乗っていた人たちはほとんどが一般の釣り人ですし。
だからこそ、「開戦も辞さない」という発言になるわけです。
第三に、「海上保安本部長が謝罪したのになぜまだ抗議してるの?」と思われる方もいるでしょうが、那須本部長が使った「遺憾」という外交用語に対し大きな波紋が。
「遺憾」というのは日本のお役所ではよく使う言葉ですが、確かに「謝罪」の言葉としてはちょっと弱い感じですよね。本当は「遺憾」の後に「おわび申し上げる」というかなり陳謝な言葉があり、おじぎもしているので、誠実な態度であったとは思うのですが(琉球新報http://ryukyushimpo.jp/news/storyid-133189-storytopic-1.html)、残念ながら台湾においてはこの「遺憾」という言葉ばかりがクローズアップされてしまいました。
同じ漢字文化圏なのがまた微妙なところで、こちらでは「遺憾」というのは、例えば友達の家族が亡くなった時などにいわば英語で「I feel so sorry...」というふうに友達に声をかけるような感じで使う言葉なのです。つまり、自分をちょっと第三者的な立場において「お気持ちはお察しするわ」みたいな(^^;
日本の外交用語としての「遺憾」の使い方もいろいろ説明されてはいますが、このニュアンスのせいで、第一印象的にはかなり「誠意のない謝罪」と見られてしまいます。
さらに、以前の記事でも紹介した通り、台湾では馬さんという新しい総統が就任したばかりで、彼が国民党なので、陳前総統よりもだいぶ大陸寄りで親日派ではないこともタイミングが悪かったですね。ちなみに駐日代表の許さん(冒頭の写真で新聞記事を掲げている人)は民進党の人で、親日派として有名な人なので、今回も日本側を代弁するような発言(「遺憾」の日本での使い方など)をして、国民党にひどく叩かれるという気の毒なことになっています。
いやはや、言葉って微妙で外交って難しいですねぇ。
台湾は世界有数の親日的な国で私もそのおかげですごく快適に生活できているので、この事件で対日感情が悪くならないことを祈っています
冒頭の写真は「Yahoo.tw」より。(http://tw.news.yahoo.com/article/url/d/a/080616/17/11cgn.html)
日本のみなさんは、ここ最近の日本と台湾の不穏なニュースにどれくらい注目しているのでしょうか。ネットのニュースで見る限り、たぶん多くの人に取っては「ふーん」くらいのニュースな感じですが、こちらでは毎日大騒ぎです。
「なんでそんなに台湾の人は大騒ぎしてるのかしら」と思っている人もいるかもなぁと思ったので、今日はちょっと日本と台湾のさまざまな事情を解説してみたいと思います。
事件の経過を簡単に説明すると、
6月10日未明 「魚釣島」の南9キロの「日本領海内」で、日本の海上保安庁の巡視船と台湾の漁船が接触。漁船が沈み、漁船に乗っていた「乗組員」16人を巡視船が「保護」する。
6月13日 台湾の行政院長(日本の首相に相当)が、対日批判を表し、「開戦も辞さない」と発言。
6月14日 海上保安部は、巡視船の船長と同時に漁船の乗組員を石垣島で事情聴取、書類送検。台湾の外交部(日本の外務省に相当)が駐日代表の許さんを召還することを発表。
6月15日夜 海上保安本部が「巡視船が船名を確認しようと遊漁船に近づいた行為は正当だったが、接近の仕方に過失があった。結果として遊漁船を沈没させ、船長にけがをさせたことは遺憾だ」と過失を認め、謝罪。
6月16日未明 日本政府の対応に不満を持ち、台湾の抗議船など10隻が再び「魚釣島」付近へ。
さて、まずは懸案の「魚釣島」ですが、「どこ?」という人もいるかもしれないのでまずは地図です。

(「海上保安レポート」よりhttp://www.kaiho.mlit.go.jp/info/books/report2006/tokushu/p034.html)
今回の事件、いろいろポイントがあるのですが、まずはこの地図を見て分かる通り、「魚釣島」は石垣島と台湾からほぼ等距離にある島で、日本においては石垣市に帰属している日本の領土と認識されていますが、台湾においては「宜蘭県釣魚台」とされています。台湾でももちろんここはまだ領土問題が微妙な土地だという認識はありますが、それでもはっきりと「日本のものだ」とはほとんど誰も思っていない状態です。
第二のポイントとして、日本の巡視船が台湾の漁船に接触事故を起こしたというのも、台湾では「わざとぶつかって沈ませた」のでは?と考えられています。その後の日本政府の対応で余計その疑惑は強まっているのかも。
なので、いわば「うっかり他国との境界空域に侵入してしまった民間航空機がそこの国の軍隊に射撃されて墜落した」みたいな感じなんですよ。台湾漁船に乗っていた人たちはほとんどが一般の釣り人ですし。
だからこそ、「開戦も辞さない」という発言になるわけです。
第三に、「海上保安本部長が謝罪したのになぜまだ抗議してるの?」と思われる方もいるでしょうが、那須本部長が使った「遺憾」という外交用語に対し大きな波紋が。
「遺憾」というのは日本のお役所ではよく使う言葉ですが、確かに「謝罪」の言葉としてはちょっと弱い感じですよね。本当は「遺憾」の後に「おわび申し上げる」というかなり陳謝な言葉があり、おじぎもしているので、誠実な態度であったとは思うのですが(琉球新報http://ryukyushimpo.jp/news/storyid-133189-storytopic-1.html)、残念ながら台湾においてはこの「遺憾」という言葉ばかりがクローズアップされてしまいました。
同じ漢字文化圏なのがまた微妙なところで、こちらでは「遺憾」というのは、例えば友達の家族が亡くなった時などにいわば英語で「I feel so sorry...」というふうに友達に声をかけるような感じで使う言葉なのです。つまり、自分をちょっと第三者的な立場において「お気持ちはお察しするわ」みたいな(^^;
日本の外交用語としての「遺憾」の使い方もいろいろ説明されてはいますが、このニュアンスのせいで、第一印象的にはかなり「誠意のない謝罪」と見られてしまいます。
さらに、以前の記事でも紹介した通り、台湾では馬さんという新しい総統が就任したばかりで、彼が国民党なので、陳前総統よりもだいぶ大陸寄りで親日派ではないこともタイミングが悪かったですね。ちなみに駐日代表の許さん(冒頭の写真で新聞記事を掲げている人)は民進党の人で、親日派として有名な人なので、今回も日本側を代弁するような発言(「遺憾」の日本での使い方など)をして、国民党にひどく叩かれるという気の毒なことになっています。
いやはや、言葉って微妙で外交って難しいですねぇ。
台湾は世界有数の親日的な国で私もそのおかげですごく快適に生活できているので、この事件で対日感情が悪くならないことを祈っています

















 お洗濯物も干しにくいし、ベルちゃんだって毎日ベランダでひなたぼっこするし・・・。
お洗濯物も干しにくいし、ベルちゃんだって毎日ベランダでひなたぼっこするし・・・。
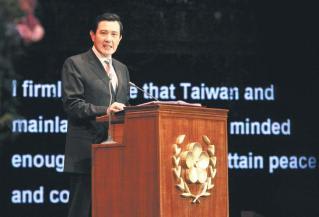


 陳前総統の奥さんは、ものすごいお金持ちのおうち出身だったせいか、ブランド好き、ジュエリー好きで、そのへんもかなり微妙なイメージだったので、今回の馬さんの奥さんの「質素さ」はそういう意味で、かなり好評なのかもしれません。
陳前総統の奥さんは、ものすごいお金持ちのおうち出身だったせいか、ブランド好き、ジュエリー好きで、そのへんもかなり微妙なイメージだったので、今回の馬さんの奥さんの「質素さ」はそういう意味で、かなり好評なのかもしれません。









 )ちょっとうれしい。でも、この日は「二二八事件」という大事件があった日で、多くの台湾の人々にとって感慨深い日です。知らない方もいるかも、と紹介することにしました。
)ちょっとうれしい。でも、この日は「二二八事件」という大事件があった日で、多くの台湾の人々にとって感慨深い日です。知らない方もいるかも、と紹介することにしました。







 、今回の選挙はさらに過熱気味。なぜかというと、今年は3月22日に総統選を控えているため、この立法委員選が総統選の行方を占う前哨戦になるからなのです。例えば、アメリカ映画界のアカデミー賞の前のゴールデン・グローブ賞のようなものです。(違うかも)
、今回の選挙はさらに過熱気味。なぜかというと、今年は3月22日に総統選を控えているため、この立法委員選が総統選の行方を占う前哨戦になるからなのです。例えば、アメリカ映画界のアカデミー賞の前のゴールデン・グローブ賞のようなものです。(違うかも)


