以前、「日本の免許証+中国語の訳文で台湾で運転できる」という記事を書いたことがありますが、一年以上台湾に滞在する長期滞在者でしょっちゅう車に乗る人ならば、台湾の免許証を取得したほうが便利です。
というのも、台湾の警察の人はかなりの割合で、上記の「日本の免許証+中文訳」で運転できる、ということをあまり知らないんですよねー
なので、検問とかなにかで引っかかった際にはかなり面倒なことになります
私はちょっと個人的な理由で、警察に車を止められることが多く、そのたびに警察の人に「なんで台湾の免許証持ってないの?」とさんざん聞かれ、大変な思いをしていました
というわけで、先月、台湾の免許証を取りに行きましたよ
基本的には
1.運転免許センターに行ってセンターに備え付けの書類に記入。
2.身体測定や簡単な検査を受ける。
3.免許証がもらえる。
という超簡単な仕組みです。試験などはいっさいありません
詳細はこちらの交流協会のサイトに出ていますが、注意したいことが一つ
同サイトでは「切り替え手続き可能な運転免許センター一覧」が紹介されていて、例えば台北付近だとこんな感じです。

が、私が最初に行った「八徳路」の免許センターでは、「うちではできません。承徳路の分処へ行ってください」と言われてしまいました
実際承徳路の「北区分処」ではすぐにできましたし、外国人の人も何人も見かけましたね。
なので、台北市付近に住んでる人ならここに行った方がいいと思います
あと、センターでは職員も日本語は片言の感じだったので、中国語に自信がない人は友達について行ってもらうといいかもしれません。
今回、面白かったのは、日本の免許証は一枚にすべての免許の情報が入っていますが、台湾の免許は分類ごとに別々に作ることでした。
というわけで、私も普通の自動車の免許証とバイクの免許証、二枚を作ってくれましたよ(^^)


実際やってみると、全部で30分くらいでできてしまったので(平日の昼間に行ったと言うのもありますが)、車を運転したい長期滞在者は
免許を取りに行った方がいいです。
それから、同様に「台湾で取った免許証も日本で無試験で日本の免許証を取得できる」ので、今現在免許を持ってない人は台湾で取ってから、それを日本にもって帰って日本の免許証をもらう、という裏技もあります。この方法だとたぶん日本の10分の一くらいの料金で車の免許が取れるんじゃないかな~~
便利ですね~
というのも、台湾の警察の人はかなりの割合で、上記の「日本の免許証+中文訳」で運転できる、ということをあまり知らないんですよねー

なので、検問とかなにかで引っかかった際にはかなり面倒なことになります

私はちょっと個人的な理由で、警察に車を止められることが多く、そのたびに警察の人に「なんで台湾の免許証持ってないの?」とさんざん聞かれ、大変な思いをしていました

というわけで、先月、台湾の免許証を取りに行きましたよ

基本的には
1.運転免許センターに行ってセンターに備え付けの書類に記入。
2.身体測定や簡単な検査を受ける。
3.免許証がもらえる。
という超簡単な仕組みです。試験などはいっさいありません

詳細はこちらの交流協会のサイトに出ていますが、注意したいことが一つ

同サイトでは「切り替え手続き可能な運転免許センター一覧」が紹介されていて、例えば台北付近だとこんな感じです。

が、私が最初に行った「八徳路」の免許センターでは、「うちではできません。承徳路の分処へ行ってください」と言われてしまいました

実際承徳路の「北区分処」ではすぐにできましたし、外国人の人も何人も見かけましたね。
なので、台北市付近に住んでる人ならここに行った方がいいと思います

あと、センターでは職員も日本語は片言の感じだったので、中国語に自信がない人は友達について行ってもらうといいかもしれません。
今回、面白かったのは、日本の免許証は一枚にすべての免許の情報が入っていますが、台湾の免許は分類ごとに別々に作ることでした。
というわけで、私も普通の自動車の免許証とバイクの免許証、二枚を作ってくれましたよ(^^)


実際やってみると、全部で30分くらいでできてしまったので(平日の昼間に行ったと言うのもありますが)、車を運転したい長期滞在者は
免許を取りに行った方がいいです。
それから、同様に「台湾で取った免許証も日本で無試験で日本の免許証を取得できる」ので、今現在免許を持ってない人は台湾で取ってから、それを日本にもって帰って日本の免許証をもらう、という裏技もあります。この方法だとたぶん日本の10分の一くらいの料金で車の免許が取れるんじゃないかな~~

便利ですね~











 」というイメージのようですが、実際台湾には本当に美味しいものがたくさんあります
」というイメージのようですが、実際台湾には本当に美味しいものがたくさんあります そして、日本人の好きな味や食材(シーフードやフルーツ)が多いことも事実。
そして、日本人の好きな味や食材(シーフードやフルーツ)が多いことも事実。










 今回のお店の情報
今回のお店の情報









 )
)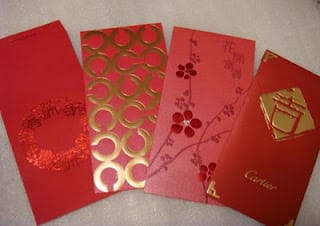





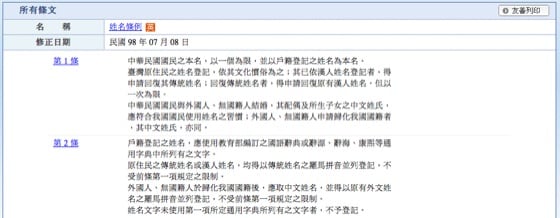
 とますます思いましたが、これはやはり昔の「外国人配偶者は台湾に帰化しなければいけなかった」時代の遺物なんでしょうねぇ
とますます思いましたが、これはやはり昔の「外国人配偶者は台湾に帰化しなければいけなかった」時代の遺物なんでしょうねぇ


 まず最初にするべきことは、上記の手続き1の「婚姻要件具備証明」を取ること。これは通称「独身証明」で、簡単に言えば「結婚できる状態である(独身である、日本で結婚できる年齢に達している)」ことの証明です。戸籍謄本とパスポートを持って行けば、交流協会で即日発行してもらえます
まず最初にするべきことは、上記の手続き1の「婚姻要件具備証明」を取ること。これは通称「独身証明」で、簡単に言えば「結婚できる状態である(独身である、日本で結婚できる年齢に達している)」ことの証明です。戸籍謄本とパスポートを持って行けば、交流協会で即日発行してもらえます 日本ではあまりない習慣ですが、台湾ではとにかく「外国の機関が発行した公文書」すべてに関して「認証を受ける」という手続きを踏まないといけません。つまり「これは本当に当該機関が発行した正式な文書である」という証明です。交流協会が発行してくれた「婚姻要件具備証明」もこれにあたり、外交部領事事務局(http://www.boca.gov.tw/mp.asp?mp=)に行って認証してもらいます。これには二日ほどかかりますよ~
日本ではあまりない習慣ですが、台湾ではとにかく「外国の機関が発行した公文書」すべてに関して「認証を受ける」という手続きを踏まないといけません。つまり「これは本当に当該機関が発行した正式な文書である」という証明です。交流協会が発行してくれた「婚姻要件具備証明」もこれにあたり、外交部領事事務局(http://www.boca.gov.tw/mp.asp?mp=)に行って認証してもらいます。これには二日ほどかかりますよ~ 日本の戸籍謄本の中国語訳を作ります。別に誰が作っても良いものなので、自分で作れる人は作りましょう。あと、印象としては台湾の役所はそんなに詳しく見ないので(「独身証明」があるから) 「正式な法律用語じゃないといけない」とかそんなこともないと思います。私も自分で普通にちゃちゃっと作って大丈夫でしたよ
日本の戸籍謄本の中国語訳を作ります。別に誰が作っても良いものなので、自分で作れる人は作りましょう。あと、印象としては台湾の役所はそんなに詳しく見ないので(「独身証明」があるから) 「正式な法律用語じゃないといけない」とかそんなこともないと思います。私も自分で普通にちゃちゃっと作って大丈夫でしたよ 台湾の「戸政事務所」に行って、結婚相手の「戸口名簿」を取り、「結婚書約」の用紙をもらってきます。日本の婚姻届と同様、二人の証人のサインが必要です。別に誰でもいいけど、普通は身内ですよね。私の場合はダーリンのご両親にお願いしました。
台湾の「戸政事務所」に行って、結婚相手の「戸口名簿」を取り、「結婚書約」の用紙をもらってきます。日本の婚姻届と同様、二人の証人のサインが必要です。別に誰でもいいけど、普通は身内ですよね。私の場合はダーリンのご両親にお願いしました。 パスポート(居留証がある人は居留証も)、戸籍謄本とその中文訳、認証をもらった「独身証明」、結婚相手の戸口名簿と結婚書約を持って、台湾の戸政事務所に行きましょう。ちなみに私たちの登録した「台北市中正区戸政事務所」では婚姻届を出すにあたって必要なものは以下のように書いてあります→
パスポート(居留証がある人は居留証も)、戸籍謄本とその中文訳、認証をもらった「独身証明」、結婚相手の戸口名簿と結婚書約を持って、台湾の戸政事務所に行きましょう。ちなみに私たちの登録した「台北市中正区戸政事務所」では婚姻届を出すにあたって必要なものは以下のように書いてあります→
 私もブロガーの端くれとしてすごく書きたい気持ちもあったし、実際書きたいこともけっこうあったのですが、なんだかばたばたしているうちにすっかり乗り遅れてしまいました
私もブロガーの端くれとしてすごく書きたい気持ちもあったし、実際書きたいこともけっこうあったのですが、なんだかばたばたしているうちにすっかり乗り遅れてしまいました
 PAPAGO! Taiwan M9
PAPAGO! Taiwan M9 


 台灣高鐵 T Express 手機快速訂票通關服務
台灣高鐵 T Express 手機快速訂票通關服務 






