年金者組合島本支部ニュース 2024年1月号が発行されました。紹介します。

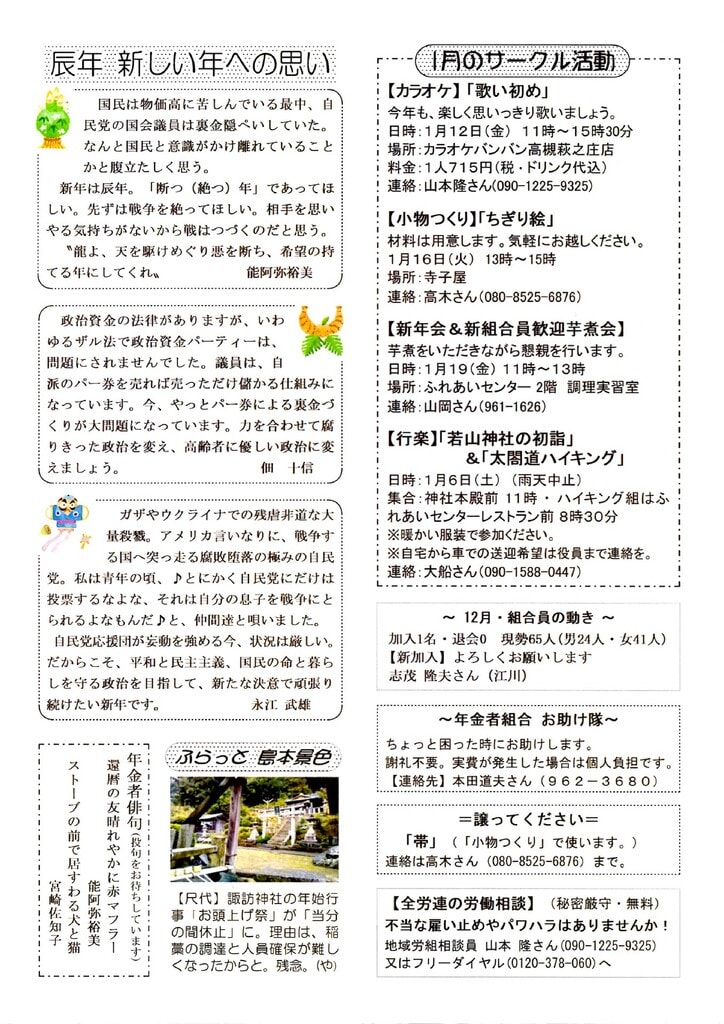
年金者組合島本支部が2023年12月8日付で山田紘平町長に提出した「要望(書)」への「回答」が12月21日付でありました。以下、全文を紹介します。(1~20までの下棒線部分が「要望」項目です。)
「高齢者がいきいき、安心して暮らせる島本町」のための要望について
1、 物価高騰下、町民の暮らし支援に町独自の「支援金」(商品券)の支給を行うこと。
●にぎわい創造課
物価高騰の影響による住民税非課税世帯を含む生活者の家計応援および事業者の負担軽減などを支援するとともに、地域における消費の喚起および下支えを目的として、物価高騰対策商品券事業を実施し、8月末から各世帯へ配付を行いました。
2、 65歳以上のインフルエンザ予防接種、来年度から有料化が予定されているコロナワクチン接種を無料で実施すること。
●すこやか推進課
65歳以上のインフルエンザ予防接種については、昨年度、季節性インフルエンザと新型コロナウイルス感染症の併発による高齢者の重症化及び両感染症患者数の増加に伴う医療提供体制のひっ迫を防ぐことを目的として、大阪府において接種者の自己負担額について無料化されましたが、町単費による無料化は、現時点において、財政上の負担が大きいことから検討しておりません。
なお、新型コロナワクチン接種については、来年度から、季節性インフルエンザと同様に、B類疾病の定期接種化が予定されており、国からの補助金も今年度末で終了となります。現時点では、使用するワクチン等の詳細が示されていないので、今後、国の動向を注視しながら、必要となる予算の確保や自己負担額の設定等、接種に必要となる体制整備に努めてまいります。
3、 特定健診項目に心電図、眼底検査、聴力検査、胸部撮影を加えること。
●保険年金課
平成30年4月から、国民健康保険が広域化され、特定健康診査の検査項目についても一定統一が図られたとともに、特定健康診査における心電図検査、眼底検査の国基準も見直しがされ、自覚症状により受診が可能となっています。特定健診の共通基準を上回る検査項目の追加については、被保険者の皆様の保険料の増額につながるおそれのあることから、費用対効果等慎重に検討する必要があるものと認識しています。また、後期高齢者及び国民健康保険加入者の肺がん検診は、無料で受診可能ですので、該当年齢の被保険者の皆様は、積極的に受診いただきますようお願いいたします。
4、 国に「加齢性難聴者の補聴器購入費助成」制度創設を求めるとともに、町独自の「助成制度」創設のために調査と検討を開始すること。
●高齢介護課
加齢性難聴者に対する補聴器購入の助成制度の創設の国への要望については、他の高齢者福祉に関する国や大阪府への要望事項の状況や優先順位等を踏まえ判断してまいります。また、町独自での当該助成制度の創設については、近隣自治体の状況等も踏まえ、検討してまいります。
5、 国保「積立」基金を被保険者の保険料負担軽減、健康増進施策充実へ活用すること。
●保険年金課
市町村が保有する国民健康保険の財政調整基金の取扱いについては、大阪府が定める「大阪府国民健康保険運営方針」に繰り出すことができる要件が定められています。今後も国民健康保険基盤の安定化のために活用してまいります。
6、 国が検討している介護保険の利用者・事業者への負担増とサービス後退に反対し、介護する人、介護を受ける人がともに大切にされる介護保険制度の実現に努めること。
●高齢介護課
介護保険制度は、超高齢化社会の進展により、給付費の増加傾向が今後も継続することが見込まれる中、サービスを後退させずに、当該制度を維持し、持続させるためには、制度の恩恵を享受される方に対し、増えていく給付費に対する一定の応分負担をしていただくことはやむを得ないものと考えています。
7 、国に「75歳以上医療費窓口2割負担」の中止を要請すること。
●保険年金課
医療保険制度は、超高齢化社会の進展により、保険給付費の増加傾向が今後も継続することが見込まれます。若年層の保険料の負担増加率も勘案し、制度の持続可能性を高めることを最重要課題と認識し、今後も国及び府に対して町村会等を通じて必要な事項について要望等を行ってまいります。
8、 国に健康保険証の廃止強行をやめ、来年の秋以降も残すように要請すること。
●保険年金課
健康保険証の廃止は令和6年秋に予定されており、保険者としては、マイナンバーカードを取得しない方又はマイナンバーを取得していても健康保険証利用登録を行っていない方等に対して、引き続き受診ができるよう資格確認書の交付準備を進めるとともに、現行制度からのサービス低下とならないよう、国及び府に対して必要に応じ要望等を行ってまいります。
9、 高齢者・障がい者が利用しやすいように、福祉ふれあいバスに低床型、車いす搭乗可能車両の導入と、増車・増便を含む運行のいっそうの改善を図ること。
●高齢介護課
福祉ふれあいバスについては、過去に庁内で今後の在り方を検討するプロジェクトチームを立ち上げ、運行目的や対象者、運行台数等の見直し等の検討を行いました。その結果、現在の利用状況や財政への負担が大きい等の理由からバスの台数を増やすことは難しいとの結論に至った経緯があります。また、福祉ふれあいバスの増便については、現在、1日6便で運行しており、運行スケジュールにこれ以上余裕がないことから、現在の台数での増便は困難な状況です。低床型車両の導入については、現在の福祉ふれあいバスの運行ルートでは、急な坂道の箇所もあるため困難であると考えています。
10、 安心・安全な水道水を守るために、有機フッ素化合物(PFAS)による河川、地下水、土壌への影響(環境)調査を行い、情報を公開すること。
●環境課
有機フッ素化合物(PFAS)による河川、地下水、土壌への影響調査については、本町といたしましても、重要であると考えており、これまでも水道事業のみならず、河川における水質検査など、適宜、対応を行ってきたところです。今後も引き続き、国の方針及び分析結果を踏まえつつ、継続的な水質分析を行い、適宜、ホームページ等で情報提供させていただきたいと考えております。
11、 歩行者、自転車・車いす利用者の通行・安全対策を。
① 歩道の段差等の点検と補修
② JRと協議を行い踏切・アンダーパスの更なる安全対策を
③ 自転車安全走行のために道路の改修(側溝への蓋の設置など)
④ 阪急水無瀬駅西側周辺の歩道整備
●都市整備課
歩行者・自転車運転者への安全対策は課題であると認識しております。このことから、対策が必要な道路については、順次、歩道の新設や拡幅など安全対策に努めており、開発等による土地利用の変化に対応すべく課題を整理し、可能な対策を検討してまいりたいと考えています。また、道路等の段差解消については、自転車や歩行者の方々の安全性や通行の利便性等に配慮し、適宜、段差解消等を実施しています。
踏切・アンダーパスの安全対策については、過去から鉄道事業者と協議を行っており、拡幅など抜本的な対策を講じるには、用地確保や技術的な課題があることから困難であると聞き及んでいますが、アンダーパス周辺については、今年度、車輌用の退避スペースを設置するなど、安全対策に取り組んでいます。今後も、鉄道事業者と連携を図り、可能な対策を講じてまいりたいと考えています。
12、 災害発生時対応と避難所対策について。
① 分かりやすく漏れのない情報提供
② 避難所への公的な移動手段の確保
③ 高齢者や障害者、女性に優しい避難所に
●危機管理室
高齢者への情報提供については、防災行政無線の放送内容を町ホームページに掲載するとともに、電話で放送内容を聞くことが出来るサービスを実施しています。また、避難行動要支援者支援制度を活用し、避難情報発令時に対象者へ連絡するなど、情報提供に努めております。避難所への移動手段については、災害が想定される数時間前に高齢者避難等の避難の呼びかけを行うことや、夜間に災害が想定される場合は、夕方までに呼びかけを行うなど、高齢者に対し避難がスムーズに行えるよう配慮を行っています。避難所設備については、段ボールベッド、便器の洋式化や手すり・ウォシュレットの設置、液体ミルクの備蓄など、避難所設備の充実を図っているところです。
13、 新しい町立体育館・プール、テニススコートの建設にあたっては、高齢者が安全、かつ快適に、安価に利用できるような施設にすること。
●生涯学習課
新体育館等の整備については、子どもから高齢者まで、全ての住民の皆さまに、安全で快適にご利用いただける施設となるよう、今後、基本計画の中で具体的に検討してまいります。
14、 ふれあいセンター中庭の整地、遊歩道へのベンチ設置など、町民が気軽に憩える場として整備すること。
●総務・債権管理課
ふれあいセンター内の遊歩道や法面の草刈りについては、現在は年2回実施していますが、次年度以降は、年4回実施することとしており、引き続き、住民の皆様に親しみやすい施設となるよう、指定管理者とともに努めてまいります。 また、中庭の利活用方法や、ベンチの設置については、今後、維持管理上の観点等を踏まえ、必要に応じ検討してまいりたいと考えております。
15、 高齢者の「いきがい活動」への支援の充実について。
① 町施設を快適・安全に使用できように日常的な点検・改修を
② 老朽化した設備の更新と充実を図る
③ 「いきがい活動」団体への財政的支援の充実を
●高齢介護課
高齢者が利用される施設の状況等については、利用されている高齢者から声がありましたら、高齢者福祉担当課として、各施設所管課に情報提供させていただきます。また、高齢者の生きがいづくりについては、本町の介護保険事業計画での基本目標のひとつに位置づけ、推進に努めていることから、関連する活動をされている団体等の事業に対する補助については、継続できるように努めてまいります。
16、 高齢者の働く場確保のために、町内事業所に高齢者雇用の要請を行うこと。
●にぎわい創造課
一般社団法人シルバー人材センターと連携しながら、高齢者の働く場の確保に努めてまいります。
17、 町議会に傍聴に行けない住民(特に高齢者、障がい者)の傍聴を保障するために、現庁舎での放映(中継・録画)について議会と協議すること。
●議会事務局
町議会は14名の議員で構成する合議体であり、町議会のインターネット中継については、設備的な検討を要することから、現在進められている役場庁舎の建て替え後に実施することで合意しているところです。今回、現庁舎での中継・録画放映の実現を求められていることについて、全議員へ周知しておりますが、町議会のインターネット中継を実施するかどうかについては、各議員がそれぞれ判断し、その合議によるものとなりますので、ご理解賜りますようお願いいたします。
18 、「街づくり」については、島本町の魅力である文化財、山並みや田畑などの「景観を生かすこと」、住民の「生活環境を守ること」を基本に、住民の合意と納得をもってすすめること。
●都市計画課
本町では、令和5年6月1日より景観行政団体へ移行し、10月1日に本町の景観計画(以下「本計画」という。)を策定し運用しているところです。本計画については、本町の自然環境や歴史的資源等を踏まえた内容となっており、また、本計画策定時にはアンケート調査やワークショップ等を実施し、住民のみなさまのご意見等をお伺いしています。本計画に基づき景観行政に取り組むことにより、本町の景観資源を生かしたまちづくりを進めてまいりたいと考えています。また、本計画以外にも、一定規模以上の開発行為等を行う場合は、自然環境及び生活環境の維持及び向上を図ること等を目的とした、「島本町開発行為等の適正化及び環境保全等に関する指導要綱」に基づき、引き続き協議を行ってまいります。
19 、JR島本駅西側を含む大型開発によって車両通行量、交通渋滞、通行危険個所の増加が懸念されます。
① 歩行者、自転車運転者に優しく、自動車にも安全な道路整備を行うこと
② 大型災害発生時にも対応できるように、道路、通行、安全対策について抜本的な検討を行うこと
●都市整備課
JR島本駅西土地区画整理事業で整備された道路については、大阪府警本部や所轄の高槻警察署、JR島本駅西土地区画整理組合と協議を行った上で整備していただいた経過があり、歩行者や車両等が安全に当該道路をご利用いただけるよう、車両用防護柵や、横断防止柵、道路反射鏡、視覚障害者誘導ブロックなどの道路付属施設についても適所に設置したうえで移管されています。
また、当該地区を含む大型開発等により周辺既存道路の交通量の増加が懸念されることについては、予測した増加交通量を反映した交通量調査において、交差点を含む、主要な道路は飽和状態にならないという結果になっているものの、今後も引き続き交通状況を注視して通行危険箇所等については対策を講じてまいります。
大型災害発生時にも対応できるよう、桜井跨線橋をはじめとした主要な幹線道路における橋梁については、耐震化を実施するとともに、長寿命化計画を策定し、計画的に修繕工事を実施するなど、適切な維持管理に努めております。
20、 町の「行・財政改革」については、住民サービスの切り下げ、住民負担増ではなく、地方自治の本旨である「住民福祉の向上」を基本とすること。
●行革デジタル推進課
行政資源が限られるなか、サービスの拡充や新たな行政課題を解決するためには、サービスの見直しや廃止が不可欠であり、新たに住民のみなさまにご負担いただくこともございます。町としては、今後も行財政改革を推進し、行政資源の最適配分による行政サービス全体の質の向上を目指してまいります。
12月22日に「年忘れおしゃべり会」を開催し、今年一番の寒さの中、12人が集いました。軽食をいただきながら、初めに自己紹介をしました。定年後にお坊さんになった方、平和の運動をしている方、身体に痛いところはあるこれど、年金者組合のつどいが楽しみで参加している方、日頃は介護しているが短時間ならと来れた方等、組合員同士お互いを知る場となりました。最高齢の92歳の方にみんなが励まされました。
年金支給額を国が引き下げたことは生存権を保障した憲法に違反するとして、兵庫県の受給者95人が訴えていた裁判で、最高裁は15日、年金の減額は「合憲」と判断し、原告の上告を棄却しました。今回の判決は最高裁では初めての判決でした。原告・弁護団などは、判決に対して抗議の「声明」を出しました。以下、「声明」の全文を紹介します。
年金引き下げ違憲訴訟最高裁判決に対する抗議声明
1 本日、最高裁判所第二小法廷(裁判長尾島明、裁判官三浦守、裁判官草野耕一、裁判官岡村和美)は、「特例水準の解消」を理由とする一律2.5%の年金減額を定めた平成24年改正法が違憲であるとして、平成25年10月の年金減額決定を取り消すことを求めた上告審で兵庫事案に上告棄却の判決を言い渡した。年金引き下げ違憲訴訟は、現在、兵庫事案を始めとして30の事案が最高裁に上告されている。われわれは、最高裁が全ての事件を大法廷に回付し、立法府の大幅な裁量を認めた「堀木訴訟大法廷判決」を見直し、憲法25条、29条、98条(社会権規約)に基づき、正面から違憲判断をすることを求めて、運動に取り組んできた。 22年11月9日の第1次要請から23年12月6日の第7次に及ぶ要請行動を取り組み、大法廷回付を要求する署名を4万9000筆と「最高裁長官への手紙」2000通を積み上げてきた。 こうした中で、最高裁第二小法廷が、大法廷に回付せず、弁論も開かないまま、年金減額を合憲として、上告棄却の判決を言い渡したことは、最高裁判所が「憲法の番人」としての役割を放棄したものであり、強く抗議する。
2 判決は、年金減額を定めた平成24年改正法が、憲法25条、29条、98条2項に違反するとする上告人らの主張に対し、広範な立法裁量を認めた堀木訴訟最高裁大法廷判決をそのまま維持し、「世代間の公平」や「年金制度の持続可能性を確保する」という国の主張をそのまま認め、憲法25条、29条に違反するものとはいえないと判断した。これは、違憲立法審査権を持つ裁判所の役割を放棄したものと言わざるを得ない。他方で、三浦裁判官は補足意見の中で「このような年金額の給付のみでは、他に収入や資産等の少ない者の生活の安定を図ることが困難であることは否定できず、そのことは、近年における生活保護の被保護世帯の高齢化等の状況からもうかがわれる。」と指摘し、「現に困難を抱える個人が必要な給付や支援を円滑に受けられることが肝要であり、適切な施策の充実が求められる。」と述べている。これは、本件年金減額による当事者の被害を無視できなかったことを示している。
3 年金裁判は12万人を超える全日本年金者組合員らが参加した「不服審査請求」を経て2015年5月29日を中心に44都道府県の組合員らが39地裁で5297人が提訴し、社会保障訴訟としては画期をなす取り組みとなった。年金引き下げ違憲訴訟は2.5%の減額と高齢期を安心して暮らせる「年金制度」の在り方を問う訴訟である。年金裁判の8年間の取り組みは貴重な前進をしてきた。第一に、法廷では全国で181人の原告が年金生活者の実態、特に女性の構造的低年金の実態を告発し、マスコミにも報道されるなど、年金だけでは生活できない実態が社会的な問題となった。第二に、年金裁判で、労働組合の役員の方々29人が証言に立った。また、憲法、社会保障の学者、研究者20人が意見書の作成や証言等、大きな協力を得た。裁判を通じ、「最低保障年金制度」の確立等、生活できる公的年金制度の確立が若者を含めた共通の課題であることが明らかとなった。
4 われわれは、今回の不当判決に屈することなく、残された事件について、引き続き、大法廷回付と違憲判断を求めて取り組みを続けていく。あわせて、最低保障年金制度など、誰もが安心して生活ができる公的年金制度の確立を求めて闘う決意である。
2023年12月15日
年金引き下げ違憲訴訟兵庫原告団
全日本年金者組合兵庫県本部
全日本年金者組合中央本部
年金引き下げ違憲訴訟兵庫弁護団
年金引き下げ違憲訴訟全国弁護団
12月14日に、年金者組合大阪北摂ブロック(吹田・摂津・茨木・高槻・島本の各支部)の交流グランドゴルフ大会が吹田の万博記念公園運動場で行われました。
当日は、総勢50人近くの参加者で、島本支部から女性3人、男性2人の5人が参加しました。島本の参加者は初心者が多かったのですが、女性でグランドゴルフ初体験だったMさんが、2回のホールインワンを取り回りを驚かせました。ゲームは3ランドの合計点で順位を争い、上位入賞者には景品が送られました。島本支部からは、ホールインワン2回のMさんとブービー賞のYさんが表彰されました。
プレー後は参加者一同が車座になって昼食をしながら交流しました。青空の下、グランドゴルフを楽しむ有意義な交流会になりました。
※写真は島本支部の参加者。