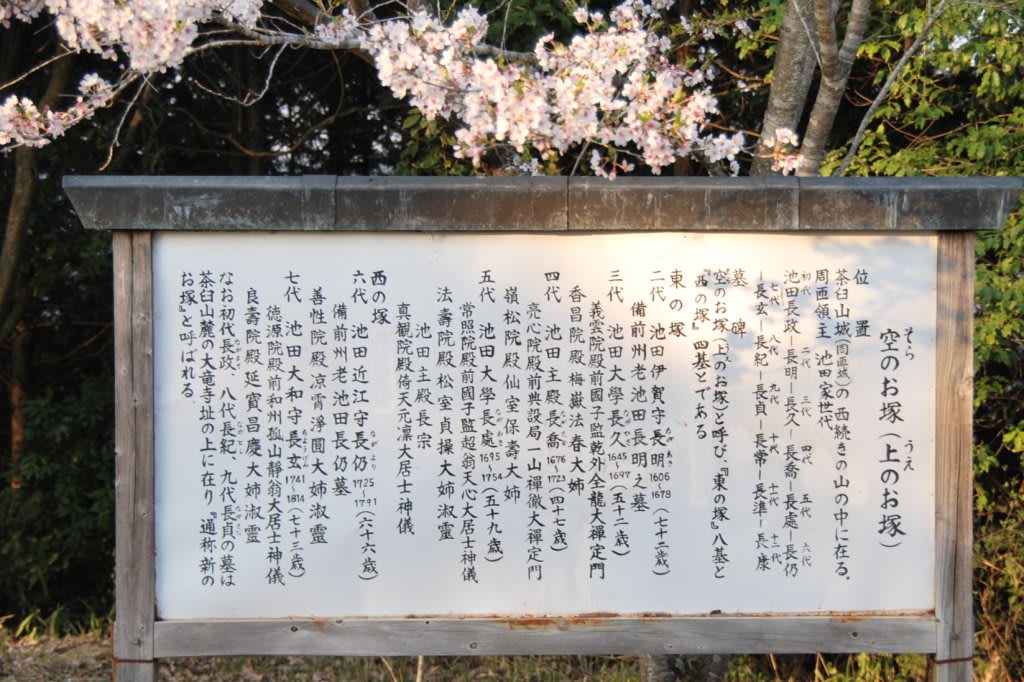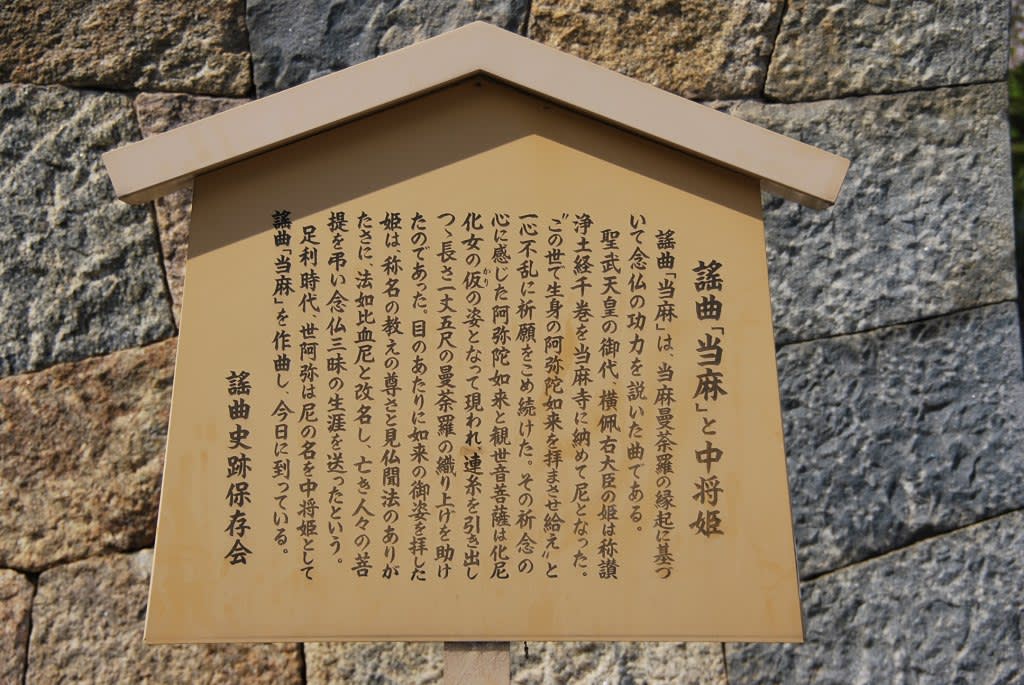後三年の役と源義家
前九年の役の勲功により清原武則は俘囚の主として鎮守府将軍に任命された。 武則はもともと清原氏の庶流であったが、兄・光頼より惣領の地位を受け継ぎ、安倍氏による奥六郡支配権を奪い取ったのである。 1070年陸奥守・源頼俊は終任にあたり、後三条天皇の親政の一環として行われてきた北海道の荒夷まで服従させたと報告する。 この征服は鎮守府将軍・清原武則の孫である真衡の功績が大きいとして鎮守府将軍に任命されたのである。真衡による奥州平定は安定し、1083年新任受領義家による初任検注も何ら妨害を受けることなく行われた。 しかし清原氏庶流から成り上がった真衡には異母弟・家衡、叔父・武衡らの反感を生むことになる。
惣領真衡には実子がなく、庶流との緊張関係のなかで惣領家の支配的地位を維持するには海道氏から成衡を養子に迎えるしかなかった。成衡は源頼義の娘を妻とすることにより惣領家の安定を図っている。ところがこの婚儀の席で、ある事件がおきたのをきっかけに、真衡側と庶流がぶつかるのである。 庶流側の吉彦秀武(清原武則の娘婿)は同じく従者扱いされてきた清衡(源頼義に討たれた経清の忘れ形見で奥州藤原氏の祖)、家衡(清原武貞の子)を見方につけた。 こうして異母兄弟、異父兄弟間の惣領家と庶流の対決が始まるのである。
ちょうどこの1083年に源義家が陸奥守として着任すると、清原真衡は義家に至極の饗宴を催し、吉彦秀武を討つべく出羽に向かった。 それを知った清衡、家衡はただちに真衡邸を襲撃するが、源義家に撃退されている。この間に真衡は出陣の途中で急死し、清衡、家衡が義家に投降した。 このとき義家は武則、武貞、真衡三代に渡って支配してきた奥六郡司職を召し上げ、これを清衡、家衡に与えたのである。 こうして清原惣領家は滅亡し清衡、家衡の間で緊張感が高まっていく。
1086年、清衡邸が家衡により襲撃され妻子は殺害されると、源義家は出羽国沼柵に立て篭もる家衡を軍勢を率いて攻めた。 これには義家の策略がからんでいる。 1086年は鎮守府終任の年であり、重任を望んだ義家が清衡、家衡を挑発して勲功を期待してのことであった。ところが家衡の猛攻はすざまじく、義家は屈辱の中で撤退した。 武名を誇る義家はこのまま終任を迎えて帰京するわけにはいかない。 1087年戦闘準備に専念し、政府は合戦を停止させるために官使を派遣するが、義家は大軍を率いて家衡が篭る金沢柵に出陣。 なかなか城は落ちる気配を見せないため、兵糧攻めに切り替えた。家衡側は降伏を求めたが義家はこれに応じず、吉彦秀武の進言どおり皆殺しにしたのである。
政府に対して武功を期待した義家であったが、後三年の役は私合戦であるとして褒賞もなく、結果的には私財を投じた義家の武勇は高まることになるが、武勇を恐れた政府(白河院・関白師実)は長きに渡って義家を陸奥前司のままとしたために、やがて源氏の棟梁としての勢力は弱まり、義家の死後源氏は分裂・衰退していくことになる。
清和天皇
┣貞純親王873-916
┃ ┣源経基897-961 藤原秀郷┓
┃ ┣経生王 ┣源満仲912-997(摂津源氏祖)⇔藤原千晴(安和の変:源高明失脚)
┃源能有娘 ┣源満政?┣源頼光948-1021(藤原道長側近)
棟貞王娘 ┣源満季?┃ ┣頼国-1058(彰子,後一条に近侍)
橘繁古娘 ┃藤原元平娘 藤原元方┓
┣源頼親?(大和源氏祖,母:藤原致忠娘)
┃ ┗頼房
┃ ┗頼俊(1070後三条の勅で蝦夷征伐)
┏━━━━━━━━━━┛
┃
┣源頼信968-1048(河内源氏祖,母:藤原致忠娘 道兼,道長に近侍)
┃ ┃ 安倍忠良┓
┃ ┣頼義988-1075 ⇔ ┣安倍頼時-1057(奥六郡司)
┃ ┃┃(1062前九年の役)┗安倍則仁┣貞任1019-1062
┃ ┃┃ ┣宗仁1032-1108(娘は藤原基衡の妻)
┃ ┃┃ ┣娘(平永衡-1056の妻)┗娘
┃ ┃┃ ┃藤原経清-1062 ┣秀衡1122-1187
┃ ┃┃ ┃┣清衡1056-1128 ┃ ┣泰衡1155-1189
┃ ┃┃ ┏清原光頼┗娘 ┣基衡1105-1157┣忠衡-1189
┃ ┃┃ ┗清原武則┓┣家衡-1087 平氏女 藤原基成娘
┃ ┃┃ ┣清原武貞?
┃ ┃┃ ┣武衡 ┗真衡-1083
┃ ┃┃ ┗娘 ┗成衡(養子)
┃ ┃┃ ┣- ┣
┃ ┃┣義家1039-1106(1083後三年役)吉彦秀武 頼義娘
┃ ┃┃ ┣義宗?
┃ ┃┣義綱1042-1132┣義親-1108(対馬守 隠岐に配流)
┃ ┃┃ ┣義弘 ┃┣為義1096-1156(養子:父は義親)
┃ ┃┃ ┣義俊 ┃┃┣義朝1123-1160(鎌倉の館を引き継ぐ)
┃ ┃┃ ┣義明 ┃┃┣義賢-1155(頼長侍従) ┣義平
┃ ┃┃ ┣義仲 ┃┃┣頼賢-1156 ┗木曾義仲 ┣頼朝
┃ ┃┃ ┗義範 ┃┃┣為朝1139-1170 ┣範頼
┃ ┃┣義光1045-1127┃┃┗行家1145-1186 熱田大宮司娘
┃ ┃┃┗甲斐源氏 ┃┣義信 義平
┃ ┃┃ ┗武田氏 ┃┗義俊 ┣
┃ ┃平直方娘 ┣義国1091-1151 ┏娘 義朝妻の姪
┃ ┗頼清? ┣義忠 ┣新田義重1114-1202 ┣
源俊娘(嵯峨源氏) ┃1083-1109┗足利義康1127-1157(鳥羽院北面)
┣義時?
┃┣義基(石川源氏)
┃┃┗義兼
┃┣義広(紺戸氏)
┃┗義資(二条氏)
┗義隆-1159
┗頼隆1159-?(森氏、毛利氏祖)