西川善文が回顧録を書いた。前半は、住友銀行で不良債権処理に成功し、頭取に上りつめるまで。後半は、日本郵政の社長として挫折するまでの裏話。
当然ながら、前半は迫力があり面白い。但し、ここに書いてあることは、表にできる裏話で、本当の裏話はもっとどろどろとしたものだろう。何といっても、許永中といった日本の黒社会に絡んだ話だ。きれいごとで済むはずがない。
後半は、これも当然のこととして、言い訳がましい。言い訳を聞いていると、この人間には、出来レースの簡保の宿売却などの自分が犯した犯罪的行為について、まったくの自覚がないようだ。
簡保の問題と異なり、新聞にはあまり書かれなかったが、郵便貯金振興会が運営していたメルパルクの問題も同様だ。メルパルクは、簡保の宿同様、郵便貯金の利用者サービス一環として、運営しており、郵政には、賃料に相当する金額を納付金として支払っていた。西川は、これを賃料も支払っていないと曲解した。さらに、この賃貸契約を、会社発足後直ちに一方的に解除し、1500名の従業員を路頭に迷わせようとした。さすがに、これは、国会で追及され、渋々雇用に最大限の配慮をすると回答せざるをえなくなった。しかし、結局たった3ヶ月の通告で、郵貯振興会の契約は解除され、密室のなか、新賃貸契約が、ワタベ・ウエディングと取り交わされた。
西川は言う。「一般取引として正々堂々、 競争入札の徹底が大事なのだ。」しかし、実際は、真逆。不透明な隋意契約を、ワタベと締結した。何とワタベの株価は、その直後からその後のピークまで5割以上高騰した。まさに、黒いバンカーの面目躍如、契約条件は、今も闇の中だ。
さらに、問題なのは、この人間は、住友の籍を抜いて郵政に来たといいながら、郵政に君臨しやりたい放題をやった後、郵政退職後は、住友の人間として、名誉会長に復帰していることだ。これは、西川が連れて来て、同じく疑惑取引を遂行した横山以下の幹部ものうのうと住友に戻っている。
しかし、西川の最大の罪は、郵便局ネットワークを引き裂いたことだろう。回顧録に書いてあることとは裏腹に、西川在任中、郵便局では狭い局内を、郵便、貯金、保険の3つを仕切りで区切る漫画のような工事が大々的に行なわれていた。
西川は、ゆうパックとペリカン便との統合も、事務方の反対を押し切って実行した。これは、結果として、売り上げは全く増えず、ペリカン便の赤字を郵政が肩代わりしただけだった。西川は、これも政治のせいにする。しかし、承認の遅れは、統合時の作業混乱に繋がったにすぎない。郵政事業に対する根本的な事業認識の誤りが原因だ。そのおかげで、国民資産で、民間企業の赤字を救済することになった。さらに、この失敗は、郵便事業に取り返しの付かない損失を与えた。
西川は、郵貯銀行の利益モデルとして、投信の窓販の大号令をかけた。国債と財投債の運用に伴う利幅では、銀行として成り立たないと考えたのだろう。しかし、窓販で手数料が転がり込む投信は、手数料が高い商品で投資のプロから見れば投資不適格に近いものだ。考えてみても、金利が0%に近いのに、手数料を2%近く取る商品が有利になる筈がない。しかし、大号令で、郵貯を信頼していた顧客に販売した。結果は、顧客の大損害。これで、郵貯の信頼を破壊した。
西川は、著書の前半でも、銀行の将来像として、投信の窓販を挙げている。そうすると、本当にそんな手数料ビジネスの将来を信じていたのかもしれない。そうだとすれば、まともなバンカーとしては失格だ。投信として意味があるのは、ETFやパッシブ運用のノー・ロード型といわれる最小手数料のもので、銀行に相当の手数料が落ちる投信は、そもそも一般人にとって投資適格がないものだ。
西川時代には、簡易局の廃業が続いた。簡易局は、田舎のじいちゃん・ばあちゃんが他の仕事と兼営でやっている場合も多い。しかし、この局の仕事に、金融庁の銀行検査が入るという、これじゃやってられないのは、当たり前だ。公社時代には、簡易な自主検査だけなので、田舎にも貯金サービスが行なえた。まあ、これは、西川の責任というよりは、民営化自体に問題があり、廃業で、過疎地のコミュニティー破壊に拍車がかかった。
西川の蹉跌の根本原因は何だろう。それは、郵政組織ひいては職員を敵視したことにある。社長が、職員を敵視してまともな経営が出来る訳がない。そして、郵政関連団体を、郵政に巣食うダニの巣窟として、叩き潰そうとした。その道具に使われたのが、茶髪学者松原聡である。松原は、証拠捏造の前田検事ばりに、前提ありきのでっち上げ報告を作成した。これは、西川の高等なメディア戦略だった。
しかし、日本の大企業で、関連会社を持たない会社は存在するだろうか。住友銀行を含め、数々の関連企業で構成されているのが、大企業だ。この経済学的根拠を明らかにしたのが、ノーベル経済学賞を受賞したロナルド・コースだ。コースは、企業の資源調達に関し、継続的取引が必要な場合、市場調達には取引コストの制約があるため、組織が出現することを理論つけた。日本の企業集団もそうして成立した(もう一つの要因は、日本に特有な人件費節約)。
つまり、西川は、国民の郵政資産を自己の思うがまま動かすため、邪魔者を消そうとしただけなのである。ちなみに、西川は、前任者の生田氏については、黙して語らない。その意味は、生田は、無能な経営者といっていることに等しい。しかし、生田氏は、商船三井では優れた経営手腕を発揮し社長にまでなった人だ。郵政の総裁になった途端に無能となったのだろうか。
例えば、西川が、誇らしげに挙げるメルパルクの運営改革。生田氏は、赤字を垂れ流していた当時のメルパルク事業を大リストラし、黒字経営を定着させた。西川体制移行時には、売り上げ絶好調で、そのままいけば郵政の立派な優良子会社になったろう。これが、西川により、ワタベに運営移管され、現在は、成績不振に喘いでいるという。どちらが、有能な経営者だろうか。
国民は、西川を恨むべきだろう。個人の名誉心と住友のため、郵便局ネットワークを破壊し国民に大損害を与えた。それは、西川が糾弾した堀田元頭取から連なる住友銀行の遺伝子のなせる業だろう。こんなバンカーは最後してほしいものだ。ラスト・バンカーとは、いいタイトルだ。
当然ながら、前半は迫力があり面白い。但し、ここに書いてあることは、表にできる裏話で、本当の裏話はもっとどろどろとしたものだろう。何といっても、許永中といった日本の黒社会に絡んだ話だ。きれいごとで済むはずがない。
後半は、これも当然のこととして、言い訳がましい。言い訳を聞いていると、この人間には、出来レースの簡保の宿売却などの自分が犯した犯罪的行為について、まったくの自覚がないようだ。
簡保の問題と異なり、新聞にはあまり書かれなかったが、郵便貯金振興会が運営していたメルパルクの問題も同様だ。メルパルクは、簡保の宿同様、郵便貯金の利用者サービス一環として、運営しており、郵政には、賃料に相当する金額を納付金として支払っていた。西川は、これを賃料も支払っていないと曲解した。さらに、この賃貸契約を、会社発足後直ちに一方的に解除し、1500名の従業員を路頭に迷わせようとした。さすがに、これは、国会で追及され、渋々雇用に最大限の配慮をすると回答せざるをえなくなった。しかし、結局たった3ヶ月の通告で、郵貯振興会の契約は解除され、密室のなか、新賃貸契約が、ワタベ・ウエディングと取り交わされた。
西川は言う。「一般取引として正々堂々、 競争入札の徹底が大事なのだ。」しかし、実際は、真逆。不透明な隋意契約を、ワタベと締結した。何とワタベの株価は、その直後からその後のピークまで5割以上高騰した。まさに、黒いバンカーの面目躍如、契約条件は、今も闇の中だ。
さらに、問題なのは、この人間は、住友の籍を抜いて郵政に来たといいながら、郵政に君臨しやりたい放題をやった後、郵政退職後は、住友の人間として、名誉会長に復帰していることだ。これは、西川が連れて来て、同じく疑惑取引を遂行した横山以下の幹部ものうのうと住友に戻っている。
しかし、西川の最大の罪は、郵便局ネットワークを引き裂いたことだろう。回顧録に書いてあることとは裏腹に、西川在任中、郵便局では狭い局内を、郵便、貯金、保険の3つを仕切りで区切る漫画のような工事が大々的に行なわれていた。
西川は、ゆうパックとペリカン便との統合も、事務方の反対を押し切って実行した。これは、結果として、売り上げは全く増えず、ペリカン便の赤字を郵政が肩代わりしただけだった。西川は、これも政治のせいにする。しかし、承認の遅れは、統合時の作業混乱に繋がったにすぎない。郵政事業に対する根本的な事業認識の誤りが原因だ。そのおかげで、国民資産で、民間企業の赤字を救済することになった。さらに、この失敗は、郵便事業に取り返しの付かない損失を与えた。
西川は、郵貯銀行の利益モデルとして、投信の窓販の大号令をかけた。国債と財投債の運用に伴う利幅では、銀行として成り立たないと考えたのだろう。しかし、窓販で手数料が転がり込む投信は、手数料が高い商品で投資のプロから見れば投資不適格に近いものだ。考えてみても、金利が0%に近いのに、手数料を2%近く取る商品が有利になる筈がない。しかし、大号令で、郵貯を信頼していた顧客に販売した。結果は、顧客の大損害。これで、郵貯の信頼を破壊した。
西川は、著書の前半でも、銀行の将来像として、投信の窓販を挙げている。そうすると、本当にそんな手数料ビジネスの将来を信じていたのかもしれない。そうだとすれば、まともなバンカーとしては失格だ。投信として意味があるのは、ETFやパッシブ運用のノー・ロード型といわれる最小手数料のもので、銀行に相当の手数料が落ちる投信は、そもそも一般人にとって投資適格がないものだ。
西川時代には、簡易局の廃業が続いた。簡易局は、田舎のじいちゃん・ばあちゃんが他の仕事と兼営でやっている場合も多い。しかし、この局の仕事に、金融庁の銀行検査が入るという、これじゃやってられないのは、当たり前だ。公社時代には、簡易な自主検査だけなので、田舎にも貯金サービスが行なえた。まあ、これは、西川の責任というよりは、民営化自体に問題があり、廃業で、過疎地のコミュニティー破壊に拍車がかかった。
西川の蹉跌の根本原因は何だろう。それは、郵政組織ひいては職員を敵視したことにある。社長が、職員を敵視してまともな経営が出来る訳がない。そして、郵政関連団体を、郵政に巣食うダニの巣窟として、叩き潰そうとした。その道具に使われたのが、茶髪学者松原聡である。松原は、証拠捏造の前田検事ばりに、前提ありきのでっち上げ報告を作成した。これは、西川の高等なメディア戦略だった。
しかし、日本の大企業で、関連会社を持たない会社は存在するだろうか。住友銀行を含め、数々の関連企業で構成されているのが、大企業だ。この経済学的根拠を明らかにしたのが、ノーベル経済学賞を受賞したロナルド・コースだ。コースは、企業の資源調達に関し、継続的取引が必要な場合、市場調達には取引コストの制約があるため、組織が出現することを理論つけた。日本の企業集団もそうして成立した(もう一つの要因は、日本に特有な人件費節約)。
つまり、西川は、国民の郵政資産を自己の思うがまま動かすため、邪魔者を消そうとしただけなのである。ちなみに、西川は、前任者の生田氏については、黙して語らない。その意味は、生田は、無能な経営者といっていることに等しい。しかし、生田氏は、商船三井では優れた経営手腕を発揮し社長にまでなった人だ。郵政の総裁になった途端に無能となったのだろうか。
例えば、西川が、誇らしげに挙げるメルパルクの運営改革。生田氏は、赤字を垂れ流していた当時のメルパルク事業を大リストラし、黒字経営を定着させた。西川体制移行時には、売り上げ絶好調で、そのままいけば郵政の立派な優良子会社になったろう。これが、西川により、ワタベに運営移管され、現在は、成績不振に喘いでいるという。どちらが、有能な経営者だろうか。
国民は、西川を恨むべきだろう。個人の名誉心と住友のため、郵便局ネットワークを破壊し国民に大損害を与えた。それは、西川が糾弾した堀田元頭取から連なる住友銀行の遺伝子のなせる業だろう。こんなバンカーは最後してほしいものだ。ラスト・バンカーとは、いいタイトルだ。















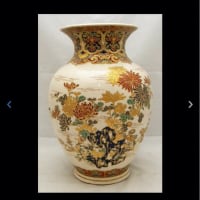



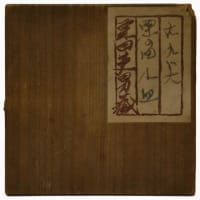
※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます