
立冬の今日は曇り空の朝だったのですが、徐々に青空が広がり晴れの(秋晴れ?小春日和?)、快適な一日となった大阪。


今日は、2人の方を案内して、9日まで秋の特別公開中の郡山宿本陣を見学し、西国街道を少し西に、春日神社とぼろ塚を散策、バスで茨木市内に入り、旧城下町と明治9年から続くJRの煉瓦造りのガード「丸また」、茨木ゆかりのノーベル文学賞作家の川端康成文学館を見学してきました。


郡山宿本陣は行ってみたかったところだったらしいので、感激してもらいました。
総歩数は、12500歩とちょうどいい程度の散策になりました。
今日の1枚の写真は、この時期、よく見かけるピンクの金平糖のような花!「ヒメツルソバ(姫蔓蕎麦)」です。
「ヒメツルソバ(姫蔓蕎麦)」は、蓼(たで)科の植物です。
ヒマラヤ地方原産で、日本には、明治中期にロックガーデン用に導入された植物です。
花はかわいい球形(金平糖のような)のピンク色で、真夏に一時途絶えますが、5月ごろから秋にかけて、長い期間咲き続けます。
この写真でもわかるように、葉っぱにはしましま模様が入り秋に紅葉します。
とっつあんは、長い花の期間でも、紅葉が始まるこの時期のヒメツルソバが一番合うと思っています。
性質は見かけによらず非常に丈夫で、持ち前の強健さと繁殖力から、空地や道端などで雑草化もしている植物です。
茎は立ち上がらずに横に這うように広がっていく多年草です。
茎の節の部分が地面に接するとそこから根をおろしてどんどん広がっていきます。
一株でおよそ直径50cmほどに広がり、むき出しの地面を覆うグラウンドカバーとしても利用されるそうです。
別名のPolygonum(ポリゴナム)は、ギリシャ語の「polys(多い)+ gonu(節)」が語源。
茎の節がふくらんで関節のように見えることに由来するそうです。
花言葉は、「愛らしい」「気がきく」です。
☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆
明日11月8日(癸未 みずのとひつじ 赤口)はこんな日です。
●「世界都市計画の日」


アルゼンチンの都市計画学者・パオレラ教授が、1949(昭和24)年に提唱。
日本では都市計画協会が1965(昭和40)年から実施。
●「レントゲンの日」

1895(明治28)年11月8日にドイツの物理学者レントゲンが発見したX線は、身体を傷つけることなく身体の中を見ることができるというものでした。
X線は服などは透過し、骨などは透過しにくいため、レントゲン写真が生まれました。
●「いい歯の日・いい歯ならびの日・いい歯ぐきの日(11月8日・9日)」
「いい(11)は(8)」の語呂合せから、日本歯科医師会が制定しました。
歯ならびへの関心を高め、かみ合わせの大切さをPRしようと、日本矯正歯科学会が制定しました。
市民公開講座を開いたり、日本歯科医師会とともに啓発活動を行う予定です。「いい(11)は(8)」の語呂合せから。
また、佐藤製薬が設けた記念日で、「歯周病」や「知覚過敏」などの予防とケアを呼びかけるため、「いい(11)歯ぐき(8日・9日)」の語呂合わせで8日と9日としました。
●「いいお肌の日」
ユニリーバのブランドのひとつ「Dove」(ダヴ)は、女性の美をサポートするスキンケアブランドとして多くの女性を支援してきました。
その女性の美しい肌の大切さを社会的にアピールするためにユニリーバ・ジャパン株式会社が制定したのがこの記念日です。
日付は11と8で「いい肌」と読む語呂合わせから。
●「刃物の日」
岐阜県関市・岐阜県関刃物産業連合会・新潟三条庖丁連・越前打破物協同組合・東京刃物工業協同組合・京都利器工具組合・高知土佐山田商工会・島根県吉田村・堺刃物商工業協同組合連合会が制定しました。
生活文化と切りはなせない道具の刃物を、作り手と使い手が一緒になって感謝する日です。
「いい(11)は(8)」の語呂合せと、ふいご祭が行われる日であることからです。
●「八ヶ岳の日」
八ヶ岳を愛する人々が結成した「八ヶ岳の日制定準備委員会」が制定しました。
「いい(11)やつ(8)」の語呂合せからです。
山梨県と長野県に位置する八ヶ岳は、その雄大さ美しさから多くのファンを持つ山脈として知られています。
●「たぬき休むでぇ~(DAY)」
信楽焼で有名な滋賀県甲賀市信楽町の信楽町観光協会が制定しました。
信楽焼の狸の徳利には「八」と書かれていることから、11月8日を全国の店先で愛嬌よく商売繁盛に頑張っている信楽焼狸の休日にとのことです。
この日には「たぬき」に感謝して腹鼓を打つそうです。
信楽焼のタヌキは「八相縁起」といって開運縁起を表すとされ、商売繁盛や開運、合格祈願、交通安全などにひと役買っています。
●毎月8日は、「薬師如来の縁日」「果物の日」「米の日」「歯ブラシの交換日」です。
●「かにかくに祭」
「かにかくに祇園はこひし寝るときも枕のしたを水のながるる」の句で知られ、祇園をこよなく愛した明治の歌人 吉井勇を偲び、毎年11月8日に「かにかくに祭」が行われます。
歌碑の前に、芸舞妓が参列して献花などが行われます。
吉井は明治末期、北原白秋らと文芸誌「スバル」を創刊。晩年には京に移り住み、「都をどり」の作詞に携わるなど、祇園とのゆかりが深い。
さきの歌碑は友人の谷崎潤一郎らが55年に建立しました。
京都市東山区元吉町白川ほとり![]() 「にほんブログ村」ランキング参加中です。
「にほんブログ村」ランキング参加中です。
今回は2921話です。「よかった!」と思われたら「季節・四季」ボタンをポチッとお願いします。













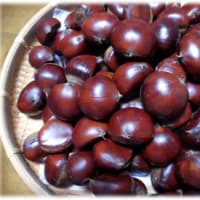






我が家の庭にこの花がいっぱい咲いています。
名前がわからなくて昨年調べてわかったのですが
金平糖みたいな花ですごく可愛いですよ^^
いつか知らない間に庭に植わっていて、どんどん増えています。
ピンクの花の中に、白い花も混ざって咲くようですね。
「ヒメツルソバ」は、長い間咲いているので、庭にあると常に可愛い花いっぱいって感じですね。
2日前に郡山宿本陣の一般公開に行っての帰り、旧茨木城下町を散策してきました。