
曇り空でもグンと冷え込んだ冷たい寒い二十四節気「雨水」の朝、曇り、最高気温10℃(+1)、洗濯指数40夕方までにはなんとか乾きそう、との予報。
朝から薄日が射す曇り空、冷たさはそれほど感じないのですが、気温は思ったほど上がらず相変わらず寒い北摂。


朝一、明日の医大化学療法センターの検診・治療のための血液検査で高槻へ…。
家から駅、駅から病院の往復とちょっと寄り道してお菓子を買って、7500歩、今日も息切れが激しく何度も立ち止まって休憩したのですが、いい運動になりました。
今日の1枚の写真は、早春の日の冬枯れの庭に彩をそえる青紫の花「寒咲文目・菖蒲(かんざきあやめ)」です。
「寒咲文目・菖蒲(かんざきあやめ)」は、花茎はほとんどなく、花筒が長いのが特徴で、花が葉の陰に隠れてしまうのが残念なところです。
原産地は地中海沿岸地域、常緑性多年草で花の色は青紫色、花被片は6枚です。
名の通り、冬に花が咲く珍しいアヤメです。
花の少ない早春に咲くアヤメの花は、寂しくなった冬枯れの庭で目を惹きつけます。
別名を寒菖蒲(かんあやめ)といいます。
花言葉は、「信じる者の幸せ」「思慮深い」「良き便り」「勇気」「軽快」です。
花言葉「勇気」は、アヤメの仲間の中で寒さの中で一番に美しい花を咲かせることから。
花言葉「軽快」は、他のアヤメの仲間に比べて花色が淡く軽やかに見える花の印象から。
☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆
明日2月20日(癸未 みずのとひつじ 大安)
●「歌舞伎の日」
1607(慶長12)年のこの日、出雲の阿国が江戸城で将軍徳川家康や諸国の大名の前で初めて歌舞伎踊りを披露しました。
1603(慶長8)年、京都四条河原で出雲の阿国が歌舞伎踊りを始めたのが歌舞伎の発祥とされています。
四条河原では、それ以後女歌舞伎が評判となりました。
●「旅券の日」
外務省が1998(平成10)年に制定しました。
1878(明治11)年、「海外旅券規則」が外務省布達第1号として制定され、「旅券」という用語が日本の法令上初めて使用されました。
それまでは、「御印章」「海外行免状」と呼んでいました。
●「普通選挙の日」
1928(昭和3)年、日本で初めて普通選挙が実施されました。
納税額に関係なく、すべての男性に選挙権が与えられました。女性も参加した完全な普通選挙が実施されるようになったのは1946(昭和21)年4月10日の総選挙からです。
●「アレルギーの日」
日本アレルギー協会(日ア協)が1995(平成7)年に制定。
1966(昭和41)年のこの日、免疫学者の石坂公成・照子夫妻が、ブタクサによる花粉症の研究からアレルギーを起こす原因となる免疫グロブリンE抗体(lgE抗体)を発見したことを発表しました。
●「愛媛県政発足記念日」
1873(明治6)年、石鉄県と神山県が合併して愛媛県が誕生しました。
太政官布告から100年目にあたる1973(昭和48)年に最初の記念行事が行われ、「愛媛県章」「愛媛の歌」が制定されました。
●「夫婦円満の日」
誰が淹れても濃くてまろやかなおいしいお茶「こいまろ茶」を飲んで、夫婦円満に暮らしてもらいたいとの思いから「こいまろ茶」を販売する京都府綴喜郡宇治田原町の株式会社宇治田原製茶場直売部が制定しました。
日付は2と20で「ふう(2)ふ(2)円満(0)」の語呂合わせから。
●「多喜二忌」
プロレタリア文学作家・小林多喜二(こばやしたきじ)の1933(昭和8)年の忌日。
東京・赤坂で特高警察に捕らえられ、その日のうちに拷問によって虐殺されました。
●毎月20日は、「発芽野菜の日」「ワインの日」です。
●「野里の一夜官女」
一夜官女(いちやかんじょ)とは、大阪市西淀川区の野里住吉(のざとすみよし)神社にて毎年2月20日におこなわれる、一風変わった神事です。
昔、この里ではうち続く水害と悪疫の流行で、住民は苦しい生活を強いられていました。ここに、この村を救うためには毎年定まった日に一人の乙女を神に捧げよとの神託があり、村を救いたい思いからこれを行っていました。
七年目の夜、官女の神事の時、武士が通りがかり村人からこの話を聞かされ、「神は人を救うが、人を犠牲に求めることはない」と怒り、正体を見極めようと乙女の身代わりとなって櫃に入り、神社に運ばれました。
翌朝、すでに武士の姿はなく、大きな狒々が絶命していました。この武士は、武者修行中の岩見重太郎と伝えられています。
一夜官女は、「神の名を騙る猿(狒々神(ひひがみ)に人身御供を捧げていた」という伝説に由来しています。
7人の少女が一夜だけ神に仕える身分になるため官女という名称がつけられたといわれます。官女たちは神に供える膳を大人に持たせて神社に行きます。
娘が官女に選ばれることは、かつてそれは、永遠の別れを意味し、悲壮極まりないことだったのかも知れません。
しかし現在のそれは、娘の純潔が神に認められることを意味しており、この地域ではポジティブに、大変名誉なこととしてとらえられています。
野里住吉神社は永徳二年(1382)足利三代将軍義満の創建と伝えられています。
野里住吉神社 大阪市西淀川区野里1 一15 一12














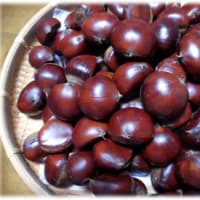






いつもご心配して頂きありがとうございます
今日は、体も歯もかなり楽になりました
親知らずを抜くと言うことは、本当に大変な
ことですねぇ~参ってしまいました (;´Д`)
今日は、午後から小雪が降ったり止んだり。。。
積雪は昨年よりも少ないのですが、まだまだ
庭には雪が山盛りです
立ち止まりながらも、いい運動はされているようですね
風邪など引かれませんように。。。
雪も少なく、葉も体調も楽になり良かったですね。
お菓子作りも久しぶりに再開され、そろそろ今までのような生活に戻られそうですね。
ブログアップ楽しみにしています。
ボチボチでも体動かしているのが一番ですね。
寒さで、体動かすのが億劫になって、体調崩しました。
挽回に頑張っていますが、明日は抗がん剤点滴の日、またしばらく.しんどい日が続きます。.