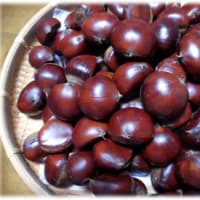毎日毎日、冷たい、寒~い寒いお正月の朝、曇り 時々 晴れ、西の風やや強く、最高気温10℃(-1)、洗濯指数60乾きは遅いけどじっくり干そう、との予報。
今日も朝からたっぷりの日差しがあり、とっつあんちのベランダのように風の当たらない日向は結構ポカポカなのですが、全般的には冷たい西寄りの風がやや強く、なかなか気温を上げてくれず寒~い寒い日となった北摂。

ウォーキングを兼ねて、初詣にご近所の西国三十三所の第22番札所、補陀洛山総持寺と疣水神社(いぼみずじんじゃ)から半額特価のカシミヤセーター求めてユニクロへ、男性物はゲットできたのですが、女性ものは昨日中に売り切れとか…、あとはドンキと関西スーパーによって、今年の歩き初めは6400歩。

と言うことで、今日の1枚の写真は、西国三十三所の第22番札所、補陀洛山総持寺の「初詣風景」です。
総持寺の創建は「藤原山蔭」という、藤原北家出身の平安時代の役人で、そのエピソードは「亀の恩返し」として「今昔物語集」にも収められているほど有名です。
ところで、皆さんは初詣は、神社ですか、お寺ですか。
どちらに行けばいいのか迷われたことはないでしょうか。
初詣の対象は神社・お寺のどちらでもかまわないそうです。
これは明治時代初期に神仏分離が行われる前は、神道と大乗仏教、ならびに祖霊信仰が一体化した神仏習合による信仰が一般化していたためです。
つまり、初詣に限らず寺社への参詣に神道・仏教の区別は無いとされていたことの名残だそうです。
寺社へ参拝を行って、社務所でお守り、破魔矢、熊手などを買ったり、絵馬に願い事や目標を書いたり、おみくじを引いたりして、今年一年がよい年であるよう祈ります。
昨年のお守りや破魔矢などは、このときに寺社に納めて焼いてもらいます。
また境内では甘酒や神酒が振るわれ、飲むと厄除けになるとされています。
初詣は、江戸時代末期までは氏神またはその年の恵方の方角の社寺に詣でること(恵方詣り)が多かったのですが、明治以降では氏神や恵方とは関係なく有名な寺社への参詣が普通になっています。
初詣は、無事お正月を迎えられた感謝と「今年もよろしく!」という願いを込めて、社寺に参拝するもの。
除夜の鐘を聞いてから出かける人も多いですが、この時間帯、有名社寺はかなりの混みよう。
初詣は、以前は元日のみのものでしたが、今では「松の内(1月7日まで)に行けばいい」、3が日を過ぎてややすいてから行ってもということになっています。
☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆
明日1月3日(乙未 きのとひつじ 先負)
●「ひとみの日」
めがね、コンタクトレンズの業界が制定しました。
瞳をいつまでも美しくということで、1月3日の「1(ひと)3(み)」の語呂合わせです。
ところでレンズの歴史は古く、古代ローマの皇帝ネロが闘技場での観戦用に、エメラルドのレンズを用いていたといいます。
●「三日とろろ」
主に東北地方の正月行事とか、南東北(宮城,山形,福島),北関東(茨城,栃木,群馬),濃尾地域(岐阜恵北,尾張など)あたりで今も残る風習のようです。
年末年始に疲れた胃腸の調子を整えるという意味が大きいようですが,それだけでなく,この日にとろろを食べると,一年中風邪を引かない,一年を無病息災で過ごせる,長生きをする,などの言い伝えがあります。
これは、山芋には整腸作用や滋養強壮作用があるとされることから、おせち料理のごちそうに疲れた胃をいたわる風習です。
●「駆け落ちの日」

1938(昭和13)年、女優の岡田嘉子と杉本良吉が、樺太の国境を越えてソ連へ亡命したことによります。
●「戊辰戦争開戦の日」
1868(慶応4)年、戊辰戦争が始りました。
京都の鳥羽・伏見で旧幕府軍と薩摩・長州軍が戦闘しましたが、装備で劣る旧幕府軍は敗退し、5日後に徳川慶喜は海路江戸へ向かい、新政府軍は慶喜追討令をうけて江戸へ進撃しました。
●「ジョン万次郎帰国の日」
出漁中に嵐に遭い、鳥島に漂着、アメリカの捕鯨船に救われた土佐の漁民だった万次郎が漂流から10年の1851年のこの日にアメリカ船に送られて琉球に上陸しました。
●「唐招提寺餅談講」
南都六宗の一つである律宗の総本山唐招提寺は、修正会護摩供と「餅談義」が行なわれます。
「餅談義」とは、鏡餅を献納した芳名を読上げた後、全国各地の名物餅を独特の節回しで談じる珍しい法会です。
唐招提寺(とうしょうだいじ) 奈良市五条町13-46 TEL0742-33-7900
●八坂神社「かるた始め」
日本かるた院によって古式豊かな衣装をつけて行われ、毎年大勢の観客で賑わいます。
祭神素戔嗚尊は、櫛稲田姫命との結婚の際に、そのよろこびを「八雲立つ……」と歌に詠まれました。
この歌は、日本で初めての三十一文字の和歌とされています。歌人たちの素戔嗚尊への崇敬が厚い由縁です。
八坂神社 京都市東山区 電話:075-561-6155(八坂神社)
![]() 「にほんブログ村」ランキング参加中です。
「にほんブログ村」ランキング参加中です。
今回は4061です。「よかった!」と思われたらポチっとお願いします。