
今日の午前中は、高槻市の文化財ボランティア講座を受講のため高槻市立しろあと歴史館に行ってきました。
本日のテーマは「文化財の鑑賞と基礎知識Ⅱ」で、刀剣、甲冑と陶磁器の鑑賞の仕方など基礎知識について、しろあと歴史館学芸員の千田康治さんの講義がありました。
刀剣、甲冑と陶磁器の話は、初めての経験だったので、興味深く拝聴してきましたが、ガイドをするには、なかなか大変だと思います。
講義のの中から、「鎬(しのぎ)を削る」の語源について…。
「鎬(しのぎ)」とは、刀の刃と棟あるいは峰つまり背の部分の間で、稜線を高くしたところで、肉を切った時、刀身に肉がつかないようにするためのものです。
互いの刀のその鎬が削り合うように激しく切り合うことから、後に、刀を用いた争い以外にも激しく争うさまを指して言うようになったそうです。
今日の1枚の写真、高槻市赤大路の鴨神社で見つけた、ちょっと珍しい正五角形の合格祈願絵馬です。
詳しくはわからないのですが、恐らく、正五角形で「正に合格」と洒落たものでしょう。
何の変哲もないダジャレのようですが、とっつあんは、初めての体験で、新鮮に感じ、明日から、センター試験が始まるので、受験生の方に、何かのご利益があれば
と、早速パチリ…。
この三島鴨神社あるいは鴨神社は、由緒書によると、創建は不明。
その昔、百済系の渡来人が関係するものと言われるが、4世紀の頃、摂津の国の県主 三島氏の氏神ともいわれ、驚くのは当社が全国数千百ある三島神社の発祥の大本の地であるということ。
境内に入ると深い森に朱を配したあざやかな社殿が浮き彫りにされ美しい。
参詣する人はその神々しさに熱いものが胸をよぎります。
なお、当社は高倉天皇ご誕生の祈願社として歴史に名を残しています。
延喜式に記載される、嶋下郡の三島鴨神社については、諸説あるようですが、旧嶋下郡の地理的な関係から、こちらが有力と考えています。
今は、神域も狭くなっていますが、由緒ある神社です。
☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆
明日1月16日(丙寅ひのえとら 先勝)はこんな日です。
●「やぶ入り」
昔、商店に奉公している人や、嫁入りした娘が、休みをもらって親元に帰ることができた日。
この日と7月16日だけ実家に帰ることが許されていました。
もっとも現在では週休制が当たり前で、この言葉も死語になりつつあります。
語源は、藪深い里へ帰ることからとか、宿下りの意味があるとか、諸説あります。
●「初閻魔,閻魔賽日(えんまさいじつ),十王詣」
正月16日と7月16日を「閻魔賽日」とし、地獄の釜のふたが開いて、鬼も亡者も休む日とされています。そのため、寺院で十王図や地獄相変図を拝んだり、閻魔堂に参詣する人が多いです。
十王とは地獄にいて亡くなった人の罪を裁く10人の判官のことで、特に閻魔王のことを指します。
●「念仏の口開け」
年が明けてはじめて、仏様を祀って念仏をする日。
正月の神様(年神様)が念仏が嫌いであるということから、12月16日の「念仏の口止め」からこの日までの正月の間は念仏は唱えないこととされています。
●「禁酒の日」

1920(大正9)年、アメリカで禁酒法が実施された日です。
清教徒(ピューリタン)の影響が強かったアメリカではアルコールに対する強い批判があり、20世紀初頭までに18の州で禁酒法が実施されていましたが、これが全国におよびました。
ところが、飲料用アルコールの製造・販売などが禁止されましたが、健康へ悪影響を及ぼす密造酒の横行や、アル・カポネをはじめとする密売にかかわるギャング出現の引き金にもなりました。
そのため、1933(昭和8)年2月に廃止されました。
●「囲炉裏の日」
1と16で「いい炉」と読む語呂合わせから、囲炉裏を囲んで暖かい会話を楽しもうと囲炉裏の愛好家らが制定しました。
●「浄土真宗本願寺派親鸞聖人忌」
親鸞聖人の命日は旧暦11月28日です。本願寺では、これを太陽暦にあらためて1月16日とし、1月9日から16日まで御正忌報恩講を修します。
宗祖親鸞聖人の遺徳を偲ぶ、年間最大の恒例法要「御正忌報恩講」です。
法要は9日の逮夜法要(14時)から16日の日中法要(10時)まで7昼夜(8日間)28座がつとめられます。
浄土真宗本願寺派(西本願寺) 京都市下京区堀川通花屋町下ル Tel(075)371-5181
●「京都上賀茂神社歩射神事」
裏に「鬼」の絵が描いてある直径約1.8メートルの大きな的を神職が射て、悪鬼退散を願い、その年の息災を祈願する行事です。
大的式弓射引始め神事とも言われ、平安時代に始まった神事で、烏帽子に狩衣姿の神職達が御幣殿前で、40メートル離れた的を射るもので迫力満点です。
武射とは「歩射」から転じたもので、馬に乗らず矢を射るのでこの名がつけられています。これだけ広大な場所での弓の神事はあまりないので、ゆっくり見物できるのが魅力です。
賀茂別雷神社(上賀茂神社) 京都市北区上賀茂本山339 TEL075-781-0011











 私のブログに興味を持たれた方、「ポチッ」とクリック、応援お願いします。
私のブログに興味を持たれた方、「ポチッ」とクリック、応援お願いします。


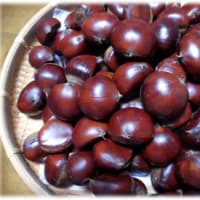






本物志向でいい作品を作っています。
彼に言わせると刀はあらゆる工芸の集大成だそうです。
本体は金属の加工、それに口金は金の細工。鞘は木工。
それの装飾は漆や鮫皮の加工と多くの工芸がかかわってるとか。言われてみるとなるほどと思います。でも陶芸だけはないようです。
つばぜり合いとか鞘当てなどもそうでしょうね。
刀剣の美術的価値は、その辺りにもあるようですね。
本来は武器ですが、色々趣向をこらしたものが、美術工芸品となり、その伝統を今に引き継いでいるようです。
目に見えないところでは、「研ぎ」も伝統工芸技術だそうです。
陶芸も立派な伝統工芸技術です。
色々勉強したいと思います。
今日は「いちごの日」
いちごワインを飲みました ♪
とても美味しいです
とっつあんさんのこと勝手ではありますが
載せさせて頂きました・・・
絵馬の正五角形とは珍しいですね
横に長いものと思っていました
受験生のみなさんには頑張って欲しいものです
なるほど納得です~
明日からは入試の話題が飛び交うのですね!
この写真を見て、受験生の皆さんに栄冠が輝きますように^^
正五角形の絵馬は私も初めてみました
娘も数年前にセンター試験を受けました
もっと早めに出会いたかったですね(笑)
文化財ボランティア講座いいですね
銭無のとっつあんさんがブログで紹介してくれるので
私も少しだけ知識人になれます
有り難う御座います
側溝をまたいで電柱の間をすり抜けて駐車したのでしょうか。もっとも、
そのテクニックに敬意を表して駐車違反にしてはいけませんね。なにしろ
土地有効活用なのですから・・・。
ブログを紹介していただきありがとうございます。感謝、感謝m(__)m
「いちごのワイン」にいちごの果汁を入れて、フレッシュな香りがいいですね。
受験生の皆さんの検討を祈ります。
正五角形で「正に合格」は、とっつあんの勝手な解釈ですが、納得ですね。
神頼みは精神面だけ、後は、実力での受験生の検討を祈るのみです。
正五角形の絵馬は珍しいですね。
受験は、神頼みではなく、実力で検討してほしいです。
精神面では、多少、頼みになるかも…。
いつまでも勉強できるのは良いですね。
人間なんて、知らないことばかりだから、なんでも学べる機会があれば活用したいです。
「鎬(しのぎ)を削る」の鎬を今まで知らなかったです。
学校でも、こんなことは習わなかったので、講座が楽しみです。
でも、こんな風に覚えたこと以外は、なかなか覚えられないですね。