
今日は、時々冷たい雨が降る大阪。


午前中は高槻市内に買い物に…。
今日の1枚の写真は、先日、酒蔵で買って来た北摂の銘酒「富田酒」の新酒の酒粕を使って作った「酒まんじゅう」です。
冬のこの時期は新酒の仕込みで、香りが高くてやわらかい酒粕が手に入ります。

まずは、粕汁を…、次にとっつあん特製のホッカホッカの「酒まんじゅう」(^^♪
暖かい蒸したての「酒まんじゅう」は、この時期身体も温めてくれるし、最高に美味しいと思います。
冬の新しい酒粕は、香りの高さも格別、清酒の香りがフワッと広がります。
簡単にレシピを紹介します。
材料:12個分
皮 酒粕………………50g
砂糖………………120g
酒…………………60g
薄力粉……………150g
ベーキングパウダー…小さじ2
中身
小豆あん…………300g(25g/1個)
打ち粉(薄力粉)
パラフィン紙………………12枚
準備:
ボールに酒粕をちぎって入れ、酒を加えて泡立て器で潰すようにすり混ぜます。
砂糖を加えてさらに混ぜます。
ラップをして、板状のかたい酒粕なら一晩、粘土状のやわらかめなら約1時間置いて充分ふやかします。
作り方:
1.酒粕の液を泡だて器ですり混ぜてなめらかにし、こし器で別のボールにこし入れます。
2.続いて、予めベーキングパウダーと合わせておいた薄力粉を加え、ゴムべらで練らないように、粉気がなくなるまで混ぜます。
3.台に打ち粉をたっぷりふり、生地をあけます。
4.手に粉をつけ生地を数回たたみながら、耳たぶより少しやわらかくします。
棒状にし、包丁に粉をつけ12個に切り分けます。
5.手粉をつけ、生地で12等分(25g)したあんを包みパラフィン紙にのせます。
蒸し:
蒸し器に熱湯を用意します。
かたく絞ったぬれ布巾を敷き、まんじゅうを間をあけて並べます。
霧吹きで、霧をまんべんなく吹いて、まんじゅうの表面全体を湿らせます。
強火で、約12分蒸して出来上がりです。
ヒント:
熱いうちに風を当てて冷まします。風を当てることで、皮の表面につやが出ます。
ただ、車の運転をする人は、チョッと我慢して下さい。
☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆
明日12月31日(乙卯きのとう 赤口)はこんな日です。
●「大晦日」
1年の終わりの日。大晦(おおつごもり)ともよばれます。
大晦日とは、長かった一年が終わり、一年の締めくくりとしてかつては暮れの支払日となっていました。
また、年越しそばを食べる日でもあります。
年越しそばを食べる習慣は江戸時代中期からはじまりました。もともと月末にそばを食べる習慣があり、大晦日だけその習慣が残りました。
金箔職人が飛び散った金箔を集めるのに練ったそば粉の固まりに引付けて集めていたため、年越しそばを残すと翌年金運にめぐまれないといわれます。
また、金は鉄のように錆びたりせず、永遠に不変の物であることから、長寿への願いも込められているそうです。
そばは長く伸びるので延命長寿や身代が細く長くのびるようにと願う説。
そば以外でも細長いものならいいという所もあります。
年の瀬にそばを食べる習慣はその他にも説があります。
鎌倉時代、年の瀬を越せない町人に「世直しそば」と言って、そば餅を振る舞ったところ、次の年から運が向いてきたため、大晦日に「運そば」を食べると縁起がよくなるという説もあります。
大晦日は、日本では、正月とならんで重要視される日ですが、世界では大晦日を特別としない国が多く、特にキリスト教文化の欧米ではクリスマスに埋もれてしまい、新年へのカウントダウンを開始する程度のものです。
●「ニューイヤーズイブ」
新年の前夜のこと。クリスマス・イブのように前夜に行う催事のひとつだか、最近は24時間オープンのコンビニエンスストアなどで客寄せのために行うケースが目立っています。
●「大祓」

大祓は罪と穢れを祓い清める神事で、6月と12月の末日に行われます。
●「シンデレラデー」
夜の12時までに帰らなければならない「シンデレラ」のように、1年で一番夜の時間が気になる日であることから。
一夜あければ全ての物が新しくなるような気にさせてくれる日でもあります。
●毎月月末は「そばの日」です。
●「除夜の鐘」知恩院の大鐘楼
除夜の鐘には一山僧侶17名により鐘がつかれ、数万人の参詣者で賑わう、総本山知恩院です。
この大鐘は寛永13年(1636)に、鋳造されたもので、日本三大名鐘の一といわれ、高さ1丈8寸(約3.3m)口径9尺2寸(約2.8m)厚さ9寸5分(約30cm)重さ1万8千貫(約70トン)あり、鐘楼とあわせ国の重要文化財に指定されています。
除夜の鐘をつく回数は108回。
眼・耳・鼻・舌・身・意の六根に苦楽・不苦・不楽の3を数え、この18類に浄・染の2つがあり、さらにこの36類を前世・今世・来世の3世に配当して6×3×2×3=108となり、人間の煩悩の数を表すとされています。
また、月の数12、二十四節気の数24、七十二候の数72を足した数が108となり、1年間を表しているとの説もあります。![]() 「にほんブログ村」ランキング参加中です。
「にほんブログ村」ランキング参加中です。
 私のブログに興味を持たれた方、「ポチッ」とクリック、応援お願いします。
私のブログに興味を持たれた方、「ポチッ」とクリック、応援お願いします。













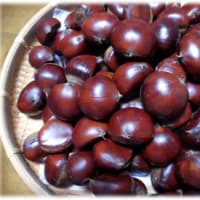






あっという間にもう今年も残り僅かですね。
今年も大変お世話になりました。
また来年もよろしくお願い致します。
手術後は少しづつ良くなっているのだと思うのですが、しびれはまだとれず、まだ、力を入れると痛いところがあります。
こちらこそ、いろいろ楽しませて頂き、勉強もさせていただきました。
ありがとうございました。
健やかな晴れやかな新年をお迎え下さい。
来年もよろしくお願いします。m(__)m