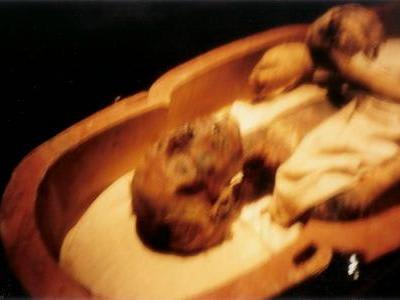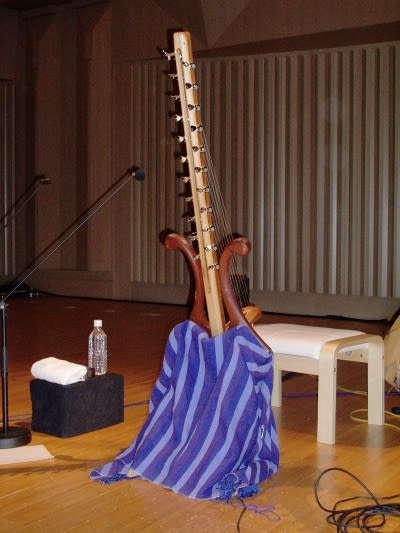ルクソールのカジノ階の上にあり、ピラミッドの吹き抜けを見渡すことのできるアトリウム階には、いろいろなアトラクション施設があります。中でも真面目に作られているのが KING TUT MUSEUM です。KING TUT、正式には KING Tut-Ankh-Amun、つまりツタンカーメンの博物館です。
1922年、ルクソールのナイル左岸の王家の谷で、ハワード・カーターが見つけたツタンカーメン王墓の夥しい発掘品の殆どは、エジプト・カイロ考古学博物館に展示されていて、ここラスベガスのツタンカーメン博物館にあるものは全てが模造品なのですが、ここの展示がユニークなのは、ツタンカーメン王墓が発掘された状態のまま展示されている点です。

この広い部屋が玄室。本当は棺がむき出しに置かれているのではなく、部屋一杯の大きさの柩の中に入れられています。棺は三層の入れ子構造で、ここに写っているのは一番内側の棺です。一番外側の棺は、有名な黄金のマスクだけ外された王のミイラが入れられたまま、ルクソール・王家の谷の墓の玄室でガラス貼りで展示されています。
この棺は側面から見ると長靴のようですが、恐らくはミイラを入れた状態で直立させることができ、墓に葬るときに横に寝かせたのではないかと思います。

王の棺の足元には、冥界の神アヌビスが番犬のごとく墓を守っています。

王が死後も不便を感じないように、玉座、寝台、装飾品、遊戯具、果ては下着まで、膨大な副葬品が納められています。豪華さは異なりますが、先日話題にした香港の「紙紮」と似ているような気がします。
下図は、カイロ博物館で買った絵葉書。墓の様子がよく分かります。

1922年、ルクソールのナイル左岸の王家の谷で、ハワード・カーターが見つけたツタンカーメン王墓の夥しい発掘品の殆どは、エジプト・カイロ考古学博物館に展示されていて、ここラスベガスのツタンカーメン博物館にあるものは全てが模造品なのですが、ここの展示がユニークなのは、ツタンカーメン王墓が発掘された状態のまま展示されている点です。

この広い部屋が玄室。本当は棺がむき出しに置かれているのではなく、部屋一杯の大きさの柩の中に入れられています。棺は三層の入れ子構造で、ここに写っているのは一番内側の棺です。一番外側の棺は、有名な黄金のマスクだけ外された王のミイラが入れられたまま、ルクソール・王家の谷の墓の玄室でガラス貼りで展示されています。
この棺は側面から見ると長靴のようですが、恐らくはミイラを入れた状態で直立させることができ、墓に葬るときに横に寝かせたのではないかと思います。

王の棺の足元には、冥界の神アヌビスが番犬のごとく墓を守っています。

王が死後も不便を感じないように、玉座、寝台、装飾品、遊戯具、果ては下着まで、膨大な副葬品が納められています。豪華さは異なりますが、先日話題にした香港の「紙紮」と似ているような気がします。
下図は、カイロ博物館で買った絵葉書。墓の様子がよく分かります。











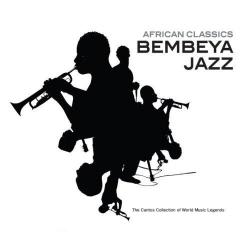


 Sweet Lullaby (Single CD Epic 49K 74919)
Sweet Lullaby (Single CD Epic 49K 74919) Sweet Lullaby (Single CD COLUMBIA 658877 2)
Sweet Lullaby (Single CD COLUMBIA 658877 2)