このブログでも取り上げましたコラ奏者ジェリ・ムサ・ジャワラ(Djeli Moussa Diawara)のコンサートに行ってきました。「モリ・カンテの弟が日本に来るらしい」などと紹介してしまいましたが、その超絶演奏テクニックを目の当たりにして、こういう表現は失礼だったかな。と反省してます。
会場の王子ホールはいつもクラシックのコンサートが行われている場所のせいか、客層は年配の方が多く(何故か詩人の谷川俊太郎氏がおられました)、演奏中もお行儀よく静まりかえっていて、音ひとつ出そうものなら睨まれそうな雰囲気が漂っていました。第一部のナンバーは伝統音楽だったからまぁ目をつむっても、第二部のナンバーはジャズやブルースやポップのアレンジで、ゲストの女性ヴォーカル、ニャマ・カンテ(モリ・カンテの姪らしく、ジェリ・ムサ・ジャワラの姪にもなるのでしょう。この方、日本人と結婚されて日本在住)が歌や踊りで盛り上げているのに、こんなにノリが悪いと、ジェリ・ムサ・ジャワラもさぞやりにくいだろうな。と思いました。コンサート終了後に、後ろの方の席で「あなた、音を立ててうるさい。あやまりなさい」と、えらい剣幕で怒鳴っている女性がいたりして、ちとシラケました。
今回は「シリーズ World Chamber Music 音の世界遺産」の一回目で「世界各地の伝統芸術音楽のなかで、古典(クラシック)と呼ぶに相応しい音楽を選んで提供する」というふれこみで、「西アフリカ、マンディング族の純粋な伝統音楽からはじまり」というのはいいのですが、「アラブ音楽やフラメンコ、ジャズ、ブルースのテイストを混ぜた曲、またジェリ・ムサ・ジャワラのオリジナル曲まで多彩な曲を披露します」と、ワールド・ミュージック、エスノ・ポップの展開を期待させたあたり、どっちもつかずになったんじゃないかな。と思いました。シリーズ二回目に呼ばれるミュージシャンとその音楽によって、王子ホールの取組の真価が問われるんじゃないかと思います。
コラの演奏については、前回もいろいろ書きましたが、コンサートで判ったことなど次回に追加します。
会場の王子ホールはいつもクラシックのコンサートが行われている場所のせいか、客層は年配の方が多く(何故か詩人の谷川俊太郎氏がおられました)、演奏中もお行儀よく静まりかえっていて、音ひとつ出そうものなら睨まれそうな雰囲気が漂っていました。第一部のナンバーは伝統音楽だったからまぁ目をつむっても、第二部のナンバーはジャズやブルースやポップのアレンジで、ゲストの女性ヴォーカル、ニャマ・カンテ(モリ・カンテの姪らしく、ジェリ・ムサ・ジャワラの姪にもなるのでしょう。この方、日本人と結婚されて日本在住)が歌や踊りで盛り上げているのに、こんなにノリが悪いと、ジェリ・ムサ・ジャワラもさぞやりにくいだろうな。と思いました。コンサート終了後に、後ろの方の席で「あなた、音を立ててうるさい。あやまりなさい」と、えらい剣幕で怒鳴っている女性がいたりして、ちとシラケました。
今回は「シリーズ World Chamber Music 音の世界遺産」の一回目で「世界各地の伝統芸術音楽のなかで、古典(クラシック)と呼ぶに相応しい音楽を選んで提供する」というふれこみで、「西アフリカ、マンディング族の純粋な伝統音楽からはじまり」というのはいいのですが、「アラブ音楽やフラメンコ、ジャズ、ブルースのテイストを混ぜた曲、またジェリ・ムサ・ジャワラのオリジナル曲まで多彩な曲を披露します」と、ワールド・ミュージック、エスノ・ポップの展開を期待させたあたり、どっちもつかずになったんじゃないかな。と思いました。シリーズ二回目に呼ばれるミュージシャンとその音楽によって、王子ホールの取組の真価が問われるんじゃないかと思います。
コラの演奏については、前回もいろいろ書きましたが、コンサートで判ったことなど次回に追加します。
















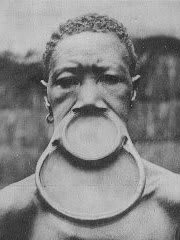
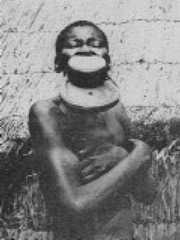
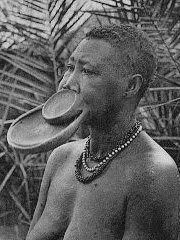




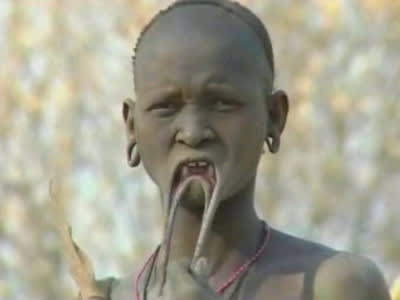




 モントリオールはフランス語圏のケベック州にありながら、市内は仏語圏と英語圏に分かれています。この店は仏語圏にあたるカルティエ・ラタンのサン・ドニ通りにあります。なんかパリの地名みたいです。サン・ドニと聞くと、パリの行ってはいけない場所、サン・ドニ門を思い出して、いかがわしいところではないか。などと心配になりますが、この一帯は地元の人で賑わうナイトスポットで、通りに沿ってレストランがたくさん並んでいます(だけど中がどんな雰囲気なのかイマイチ判りにくくてお店に入りにくいのでした。夕飯食べるためにこの通りを行ったりきたりしてました)。たいがいのレストランはワイン持込み可とのことでした。
モントリオールはフランス語圏のケベック州にありながら、市内は仏語圏と英語圏に分かれています。この店は仏語圏にあたるカルティエ・ラタンのサン・ドニ通りにあります。なんかパリの地名みたいです。サン・ドニと聞くと、パリの行ってはいけない場所、サン・ドニ門を思い出して、いかがわしいところではないか。などと心配になりますが、この一帯は地元の人で賑わうナイトスポットで、通りに沿ってレストランがたくさん並んでいます(だけど中がどんな雰囲気なのかイマイチ判りにくくてお店に入りにくいのでした。夕飯食べるためにこの通りを行ったりきたりしてました)。たいがいのレストランはワイン持込み可とのことでした。 「Nil Bleu」訳すと「青ナイル」。エチオピアにはナイル川の二つの源流のうちの一つ、タナ湖から流れ出る青ナイルがあるんですね。
「Nil Bleu」訳すと「青ナイル」。エチオピアにはナイル川の二つの源流のうちの一つ、タナ湖から流れ出る青ナイルがあるんですね。 お料理は、バスケットの中のお皿に、クレープのような、少し酸味のある「インジェラ」を敷き、この上に「ワット」と呼ばれる、スパイスの入ったピリ辛のお肉や野菜のシチューが何種類かのせられています。お皿の周りには、巻物になった「インジェラ」が置かれていて、手でこれに「ワット」を包んで食べます。手持ちの巻物がなくなったら、敷いてある方を食べられます。「ワット」のスープで軟らかくなっていて、巻物とは一味違う味です。最初はワイルドな味を想像していたのですが、食べてみると「インジェラ」の酸味と「ワット」の辛味がマッチしていて、たいへん繊細な味わいで、忘れられない体験をすることができました。
お料理は、バスケットの中のお皿に、クレープのような、少し酸味のある「インジェラ」を敷き、この上に「ワット」と呼ばれる、スパイスの入ったピリ辛のお肉や野菜のシチューが何種類かのせられています。お皿の周りには、巻物になった「インジェラ」が置かれていて、手でこれに「ワット」を包んで食べます。手持ちの巻物がなくなったら、敷いてある方を食べられます。「ワット」のスープで軟らかくなっていて、巻物とは一味違う味です。最初はワイルドな味を想像していたのですが、食べてみると「インジェラ」の酸味と「ワット」の辛味がマッチしていて、たいへん繊細な味わいで、忘れられない体験をすることができました。










