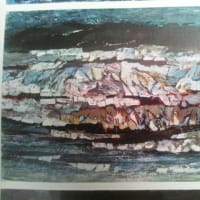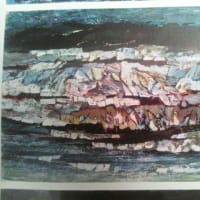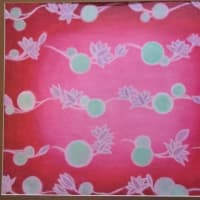「色即是空 空即是色」という、仏教の有名な言葉があります。
この言葉も、私が述べてきた、
変化の背景にある不変なるものの実在、普遍的なる存在が投影されて、
流転するこの世的存在となっていることを道破した真理の言葉なのです。
~大川隆法『太陽の法』
「空即是色 色即是空」とは、もちろん般若心経の言葉ですが、
つまり、大川氏によれば、“空”とは、不変の実在のことらしいのです。
理念としての実在ですね。
…ものすごく大胆な解釈をなさいましたね。
一体どこから、このような解釈が湧いて出たのでしょう?
大川氏は、GLAという新興宗教を作った高橋信次という人の
影響を受けているらしいのですが、その辺りでしょうか。
***
昨日も書きましたが、“空”とは、
依存しあい、影響しあっているために独立した実体がない、
という事です。
独立した実体がないことが不変の事実である、
という言い方はできるかもしれませんが、
この文脈では、単立不変の実在があるかのようにしか理解できません。
また、彼が、その究極的な実在であるとしている“理念”もまた、
仏教によれば、縁起する“空”でしかないのです。
これは勿論、もっとも理解しにくいレベルの縁起ではありますが、
理念的な存在は、理念化する思考の働きに依存して、把握されるのですから。
つまり、チューリップは
見る人の、“こういう物がチューリップである”という理念に依存して、
チューリップとして把握されるのです。
もしも見る人に“チューリップ”という理念も
“植物”“花”という理念も、すべての理念がないならば、
チューリップはおそらく、仏として把握されるでしょう。
そしてまた、理念は、理念する主体に依存して存在します。
理念するものなしに独立して存在する理念というものは有り得ません。
ですから、理念を根本的な単立不変のものとするには、
単立不変の、理念する存在がなくてはなりません。
それは、キリスト教的な造物主であり、
仏ではないと思います。
仏教ではむしろ、こうした理念・概念に拠立する知覚…概念知覚を超え、
“空”そのものである世界を直接知覚する事を目指します。
禅などは、まさにその為の手法である、というべきでしょう。
仏教では、仏は存在はしますが、
それは、理念により物を造り出す存在では無論なく、
もっとも微細なレベルの“空”を直接知覚する、“空”そのものです。
大川氏が、
理念により世界を作り出し、理念により世界を見る存在を想定するなら、
それはみ仏というよりはむしろ、天部である造物主でしょう。
***
大川氏は、八正道を修行の根幹としているようですが、
(空=実在とするなら、“正見”は有り得ないと思いますが)
“空”の理解と体得の修行なしに、煩悩を抑えていこうとすると、
胆力までが衰えて気迫のない人間になってしまうと思います。
煩悩は(肉体としてのわたしであるか、魂としてのわたしであるかに関わらず)
“わたし”が実在するという誤った考え(我執)に伴うものなのですが、
そうした状態において、煩悩と胆力は連動するものです。
仏教では“空”の理解と体得によって、煩悩を伴う意識を変性し、
煩悩を離れた胆力を養うのだと思います。
ですから、大川氏が、このままこの教えを進めていけば、
煩悩もなく胆力もない人間か、
あるいは煩悩・執着だらけでありながら、その自覚のない人間しか
育てられないと思います。
また“実体は実在している”“単立に存在する実在がある”という考えは、
仏教においては“無明”と呼ばれます。
こうした考えを持つ心は、対象を「事実とは反対のもの」と認識する
もっとも粗いレベルにあるとされます。
これが、み仏の教えを知って「疑惑」のレベルに変わり、
修行することにより次第に「正しく憶測する」レベル、
「正しい根拠に基づく推理」のレベルに、
最後には「直接知覚」に至るとされます。
ですから、大川氏の教えは、
仏教の正統な物の見方をもたらすというよりは、
むしろ、堅固な無明をもたらしてしまう物と考えられます。
この言葉も、私が述べてきた、
変化の背景にある不変なるものの実在、普遍的なる存在が投影されて、
流転するこの世的存在となっていることを道破した真理の言葉なのです。
~大川隆法『太陽の法』
「空即是色 色即是空」とは、もちろん般若心経の言葉ですが、
つまり、大川氏によれば、“空”とは、不変の実在のことらしいのです。
理念としての実在ですね。
…ものすごく大胆な解釈をなさいましたね。
一体どこから、このような解釈が湧いて出たのでしょう?
大川氏は、GLAという新興宗教を作った高橋信次という人の
影響を受けているらしいのですが、その辺りでしょうか。
***
昨日も書きましたが、“空”とは、
依存しあい、影響しあっているために独立した実体がない、
という事です。
独立した実体がないことが不変の事実である、
という言い方はできるかもしれませんが、
この文脈では、単立不変の実在があるかのようにしか理解できません。
また、彼が、その究極的な実在であるとしている“理念”もまた、
仏教によれば、縁起する“空”でしかないのです。
これは勿論、もっとも理解しにくいレベルの縁起ではありますが、
理念的な存在は、理念化する思考の働きに依存して、把握されるのですから。
つまり、チューリップは
見る人の、“こういう物がチューリップである”という理念に依存して、
チューリップとして把握されるのです。
もしも見る人に“チューリップ”という理念も
“植物”“花”という理念も、すべての理念がないならば、
チューリップはおそらく、仏として把握されるでしょう。
そしてまた、理念は、理念する主体に依存して存在します。
理念するものなしに独立して存在する理念というものは有り得ません。
ですから、理念を根本的な単立不変のものとするには、
単立不変の、理念する存在がなくてはなりません。
それは、キリスト教的な造物主であり、
仏ではないと思います。
仏教ではむしろ、こうした理念・概念に拠立する知覚…概念知覚を超え、
“空”そのものである世界を直接知覚する事を目指します。
禅などは、まさにその為の手法である、というべきでしょう。
仏教では、仏は存在はしますが、
それは、理念により物を造り出す存在では無論なく、
もっとも微細なレベルの“空”を直接知覚する、“空”そのものです。
大川氏が、
理念により世界を作り出し、理念により世界を見る存在を想定するなら、
それはみ仏というよりはむしろ、天部である造物主でしょう。
***
大川氏は、八正道を修行の根幹としているようですが、
(空=実在とするなら、“正見”は有り得ないと思いますが)
“空”の理解と体得の修行なしに、煩悩を抑えていこうとすると、
胆力までが衰えて気迫のない人間になってしまうと思います。
煩悩は(肉体としてのわたしであるか、魂としてのわたしであるかに関わらず)
“わたし”が実在するという誤った考え(我執)に伴うものなのですが、
そうした状態において、煩悩と胆力は連動するものです。
仏教では“空”の理解と体得によって、煩悩を伴う意識を変性し、
煩悩を離れた胆力を養うのだと思います。
ですから、大川氏が、このままこの教えを進めていけば、
煩悩もなく胆力もない人間か、
あるいは煩悩・執着だらけでありながら、その自覚のない人間しか
育てられないと思います。
また“実体は実在している”“単立に存在する実在がある”という考えは、
仏教においては“無明”と呼ばれます。
こうした考えを持つ心は、対象を「事実とは反対のもの」と認識する
もっとも粗いレベルにあるとされます。
これが、み仏の教えを知って「疑惑」のレベルに変わり、
修行することにより次第に「正しく憶測する」レベル、
「正しい根拠に基づく推理」のレベルに、
最後には「直接知覚」に至るとされます。
ですから、大川氏の教えは、
仏教の正統な物の見方をもたらすというよりは、
むしろ、堅固な無明をもたらしてしまう物と考えられます。