アサヒトラベルインターナショナルの福田社長より、なんとも洒落た地球儀を頂いた。
磁力のバランスにより、空中に浮きながら回転し続ける、夢とロマンを掻き立てる地球儀だ。
聞けば、会社創立50周年の記念品だとか。
そんな貴重なものを、「事務局のデスクにも飾っておいて」と、さりげなく・・・
こんな気配りこそが、まさに出来る社長のなせる業なのだろう。
早速に事務所に飾らせていただいた。

地球儀を宙に浮かせる作業に多少は戸惑いつつも、永久自転する地球儀を眺めていると、また旅に出たいという気持ちが湧いてくるから不思議である。
同社の社名入りの紙袋の中にはもう一点、「50th Anniversary」と記された冊子が添えられていた。

それとなく読み始めたら止まらなくなった。
「学ぶ旅行を通じて異文化理解の架け橋に」という社是のもと、同社が一貫して教育旅行に取り組んで来た半世紀の歴史が見事に描かれている。
と、その黎明期のページに目が釘付けとなった。なぜならそこにはこんな記述があったからである。
(1)会社のルーツ・旧アサヒトラベルの誕生
「(発起人=初代社長の任期満了に伴い、波多野武が社長に就任したものの、諸般の事情により)波多野は会社経営を断念することとなりました。その際、譲渡先を相談していたのが、国際旅行業協会(JATAの前身)の役員である吉村光雄氏でした。」(P8)
(4)新生「アサヒトラベルインターナショナル」の誕生へ
(東急観光からの独立した郡司亮一は、新しい会社設立を目指しましたが)当時は旅行業開業のための審査が約半年必要で、教育関係団体旅行を集中的に取り扱う夏休みにとうてい間に合いませんでした。そこで、前出の吉村光雄氏に相談したところ、アサヒトラベルの案件があがり、その継承を考えた方が早道だという結論に達しました。(P10)
いやはや、私が驚いたのはここに記載された二人のお名前でした。
吉村光雄氏は私が22歳で入社した「東京観光」の当時の社長であり、波多野武氏は入社の翌年に常務取締役として着任した、まさにその人だったからです。
今はトラベル懇話会の副会長として日々お世話になっている福田社長の会社が創立50年を迎えられる中、そのルーツとも言える会社設立に、若き日の私の会社役員が二人も関わっていたとは何たる驚き!
冊子に綴られた同社の50年の歴史は、まさに日本の旅行業の、そしてまたその中で私自身が歩んできた歴史そのものでした。
改めて、こんな知られざる歴史と不思議な人のご縁を教えてくださった福田社長に心よりの感謝を申し上げます。
INSPIRE THE DREAM・・・半世紀の間、若者に異文化交流の場を提供し続けてきた㈱アサヒトラベルインターナショナル様の益々のご発展を祈りつつ、トラベル懇話会設立の発起人の一人でもある故吉村光雄氏の墓前にこのご縁を報告に行こうと心に決めました。











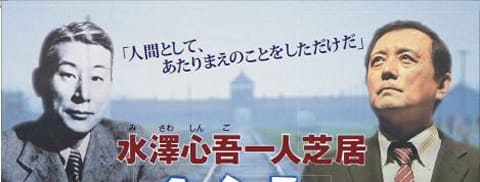









 オバマ米大統領:
オバマ米大統領:



