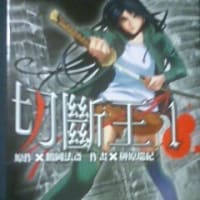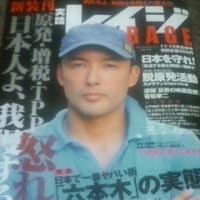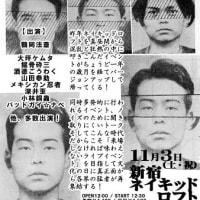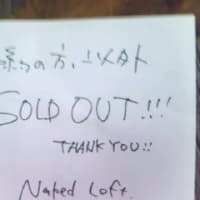以前も赤塚不二夫は紹介したのだけれども、今回も。
『アカツカNo1』(イーストプレス)である。この作品は60年代後半から70 年代前半の赤塚作品(及び事件)を収録している。私は73年生まれなので、正直なところ赤塚の偉大さはあまり知らない世代だった。ギャグマンガ家、というものは「がきデカ」以降の作家群となってしまうのである。
ただ、この作品集を読むと、自分が赤塚の本当に凄まじい時代を知らなかったことを残念に、そして悔しく思うのだ。
そしてさらにこの本は最高と最低を同時に体現できたという、希有な本でもある。それは赤塚という作家が、絶頂期に最低であり最高、という存在だったからだろう。
この作品を読んで、最初に感じたことは、漫☆画太郎も天久聖一も赤塚以降なのだなあということだ。
あいや、あえて暴言を許してもらえれば、もう所詮は赤塚を超える奴ってのはいない。この後にちょっくらくたびれて、枯れだした赤塚に引導を渡したマンガ家はいた。実際そうやって時代は流れているのだから。しかしながらこの時期の赤塚という作家に勝てる人間はいない。だって無茶苦茶なんだから。くだらないわけわかんないという言葉が最大の賛辞として与えられる作家なのだ。
歴史的事実として赤塚の無茶苦茶さは情報として知ってはいたけど、こうして一冊に濃縮還元されて、いまの世に叩きつけられると、本当にたまらないのね。もうこの時代に自分が生まれていなかったことが悔しくて悔しくて。この狂気を同時代の『事件』として体感してみたかったものだ。
まずヘタウマという言葉が登場する以前に、左手で描いたというマンガを発表する。しかもご丁寧にその理由まで表紙で説明してくれる。
アシスタント全員と五十嵐記者は十月十七日の朝右手を骨折してしまいました(ほんとはウソ)
人を馬鹿にするのもいいかげんにしろ、と思わずいいたくなってしまう。ちなみに五十嵐記者とは当時バカボンを連載していた少年マガジンの担当編集者である。
さらに少年サンデーで同時期に連載されていた『レッツラゴン』になるとさらに酷くなってきている。
まず担当編集者である武居記者とのバトルが楽屋オチとしてどんどん本編を侵略していく。鳥山明におけるマシリトや江口寿史におけるワッキーなどよりずっと以前にである。
この武居記者との構想は悪のりの一途を辿り、読者から武居記者の似顔絵募集はするわ、その騒ぎを週刊朝日が取材するわ(その該当記事全文が本書に収録されている)、赤塚不二夫の描いた表紙の上からマジックで「赤塚へたくそかきなおし 武居」と思い切り殴り書きされたのを雑誌に掲載してしまうしともはや暴走しまくりなのである。
また本書の最大の山場としては、赤塚の改名事件がある。ある日、赤塚が何を思ったか(何も思っていないのかもしれない)、『山田一郎』と改名。当然全ての連載は山田一郎名義となる、がまたまた約3ヶ月後に元の赤塚に戻るのである(これは蛇足だが80年代にも一度『赤ノ塚不二夫』と2週間くらいだけ改名した。この時は石ノ森章太郎のマネをするとか自分でいっていた)。
ほんの10年、しかし10年。赤塚という作家はマンガ家という枠すら超え、怪物として、現象として、事件として君臨していたのである。
この濃密な馬鹿馬鹿しい本を読んで私は「ああ、何か自分はたかが二十代後半で大人しくなったらいかんよなあ。もっと本格的にデタラメで目茶苦茶な人間にならないと」と心から誓った。
そんな気にさせる本だ。こんな時代だからこそ、馬鹿をやり続けるのは体力がいるだろう。
それにしても赤塚って凄いよなあ。この後に時代とズレまくり、崩壊というか凋落してしまうのだか、この本を読んでからは、それすら美しく見えたりするのだから偉いもんだ。
(ガロ掲載。01年。『大先生を読む』書評の後編(結果的に。偶然完全)としてお読みください)
『アカツカNo1』(イーストプレス)である。この作品は60年代後半から70 年代前半の赤塚作品(及び事件)を収録している。私は73年生まれなので、正直なところ赤塚の偉大さはあまり知らない世代だった。ギャグマンガ家、というものは「がきデカ」以降の作家群となってしまうのである。
ただ、この作品集を読むと、自分が赤塚の本当に凄まじい時代を知らなかったことを残念に、そして悔しく思うのだ。
そしてさらにこの本は最高と最低を同時に体現できたという、希有な本でもある。それは赤塚という作家が、絶頂期に最低であり最高、という存在だったからだろう。
この作品を読んで、最初に感じたことは、漫☆画太郎も天久聖一も赤塚以降なのだなあということだ。
あいや、あえて暴言を許してもらえれば、もう所詮は赤塚を超える奴ってのはいない。この後にちょっくらくたびれて、枯れだした赤塚に引導を渡したマンガ家はいた。実際そうやって時代は流れているのだから。しかしながらこの時期の赤塚という作家に勝てる人間はいない。だって無茶苦茶なんだから。くだらないわけわかんないという言葉が最大の賛辞として与えられる作家なのだ。
歴史的事実として赤塚の無茶苦茶さは情報として知ってはいたけど、こうして一冊に濃縮還元されて、いまの世に叩きつけられると、本当にたまらないのね。もうこの時代に自分が生まれていなかったことが悔しくて悔しくて。この狂気を同時代の『事件』として体感してみたかったものだ。
まずヘタウマという言葉が登場する以前に、左手で描いたというマンガを発表する。しかもご丁寧にその理由まで表紙で説明してくれる。
アシスタント全員と五十嵐記者は十月十七日の朝右手を骨折してしまいました(ほんとはウソ)
人を馬鹿にするのもいいかげんにしろ、と思わずいいたくなってしまう。ちなみに五十嵐記者とは当時バカボンを連載していた少年マガジンの担当編集者である。
さらに少年サンデーで同時期に連載されていた『レッツラゴン』になるとさらに酷くなってきている。
まず担当編集者である武居記者とのバトルが楽屋オチとしてどんどん本編を侵略していく。鳥山明におけるマシリトや江口寿史におけるワッキーなどよりずっと以前にである。
この武居記者との構想は悪のりの一途を辿り、読者から武居記者の似顔絵募集はするわ、その騒ぎを週刊朝日が取材するわ(その該当記事全文が本書に収録されている)、赤塚不二夫の描いた表紙の上からマジックで「赤塚へたくそかきなおし 武居」と思い切り殴り書きされたのを雑誌に掲載してしまうしともはや暴走しまくりなのである。
また本書の最大の山場としては、赤塚の改名事件がある。ある日、赤塚が何を思ったか(何も思っていないのかもしれない)、『山田一郎』と改名。当然全ての連載は山田一郎名義となる、がまたまた約3ヶ月後に元の赤塚に戻るのである(これは蛇足だが80年代にも一度『赤ノ塚不二夫』と2週間くらいだけ改名した。この時は石ノ森章太郎のマネをするとか自分でいっていた)。
ほんの10年、しかし10年。赤塚という作家はマンガ家という枠すら超え、怪物として、現象として、事件として君臨していたのである。
この濃密な馬鹿馬鹿しい本を読んで私は「ああ、何か自分はたかが二十代後半で大人しくなったらいかんよなあ。もっと本格的にデタラメで目茶苦茶な人間にならないと」と心から誓った。
そんな気にさせる本だ。こんな時代だからこそ、馬鹿をやり続けるのは体力がいるだろう。
それにしても赤塚って凄いよなあ。この後に時代とズレまくり、崩壊というか凋落してしまうのだか、この本を読んでからは、それすら美しく見えたりするのだから偉いもんだ。
(ガロ掲載。01年。『大先生を読む』書評の後編(結果的に。偶然完全)としてお読みください)