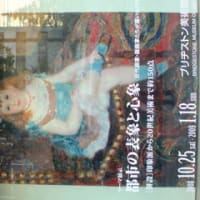シリーズとして、筆者がこのBlogを立ち上げる前にやった思い入れ深いギャルゲーを(思い出しつつ)レビューしてみる。今回の第一回は、数ある名ギャルゲーを押しのけて、CIRCUSのへっぽこゲーム『最終試験くじら』である。なぜかと言えば、筆者はこのゲームをかなり好きなのだが、世間的には ほとんど評価されていない。そこで、このゲームを拾い上げてみたいのである。以下、ネタバレもありつつ。
さて、このゲームはオープニングの歌『ディアノイア』(riya)とムービーが素晴らしいことと、内容のへっぽこさで知られている。ヒロインは7人いるのだが、それぞれに対応したシナリオは大体4パターンに分かれる。物語の謎に直接関わらない普通のギャルゲーシナリオが4本(Aパターン、胡桃、仁菜、優佳、美佳)。物語の謎に直面し選択を迫られるシナリオ2本(Bパターン、春香、くじらの少女)。おまけ的ネタシナリオ1本(Dパターン、香倶耶)。一応、分けては見たものの、Bパターンのシナリオにも、くじら世界を続けるか放棄するか、という選択で大分様相が変わってくるし、あくまで便宜的なものだと思ってもらいたい。
それぞれのシナリオに簡単な解説を。優佳と美佳のシナリオは双子ネタのわりと平凡な学園ものシナリオである。胡桃と仁菜のシナリオでは、物語の鍵になっている「くじら」が、この作品のジャンル「不条理アドベンチャー」の名そのままに関わり、ファンタジックな様相を呈している。春香のシナリオは、一見普通の義妹ものだが、クライマックスで、主人公と春香が主役の劇をやるなかで「くじら」世界の一端が暴かれ、主人公にある選択を迫ることとなる。くじらの少女シナリオで「くじら」世界はどうしてできたのかなど、作品の謎が一応全てわかる、トゥルーエンド的なシメ方をする。その上で、香倶耶シナリオは、あばかれた「くじら世界」観をもとに、ぶっとんだ話になる。プレイヤーはだいたいこの順番にゲームを攻略していくことになる。筆者が気にいったのは、仁菜と春香のシナリオ。順を追って紹介していこう。
まず、前提。主人公は旅芸人の一座の花形の女形で、ある町に到着する。その街には、宙に大きな一匹のくじらが浮いており、謎の存在ながらも街の名物となっている。
仁菜シナリオは、ファンタジックな要素に彩られているが、凡庸なギャルゲーシナリオである。主人子は転校早々、体が宙に浮いてしまうという御影仁菜先輩と仲良くなるのだが、彼女が自分の意志で飛ぶことはできないため、自由に飛ぶための練習を手伝うことをかって出る。その練習のなかで、主人公と仁菜は仲良くなっているのだが、仲良くなればなるほど、主人公は仁菜が何かを隠しているのではないかと気づいていく。実は、仁菜は幼い頃に軍の実験で体に「くじらの欠片」を埋め込まれ、そのせいで宙に浮く体質になっていたのだ。しかも、幼い頃に義理の父親(?この辺りは描写があいまいでいまいち良くわからない)に強姦され、「くじらの欠片」の様子を調べるため、毎週病院に通うことが義務付けられているのだが、そこの医師にも強姦されている。そんなわけで、主人公と仁菜は体を重ね愛情を確認しても、その後になって仁菜は、自分は汚れているから睦くん(主人公)とは一緒にいられない、と言って、空に昇りくじらのおなかの中で殻に引きこもってしまう。主人公は、仁菜を追うため、たまたまペットになった子くじら「しろたま」に乗ってくじらのおなかに入り、自分が幼い頃、義理の良心とどうやって家族になったかという話とかをして、一生懸命仁菜を慰め、殻の中から出そうとするのだ。このシーンが、かなりいい。自分の家族への想いや仁菜への想いが詰め込まれていて、本作屈指の名シーンとなっている。本作は、あえて「ご都合主義」なファンタジーに走り、そのエクスキューズ(言い訳、理由付け)として「くじら」を持ち出しているが、くじらのおなかの中で半透明の卵型の殻にうずくまる仁菜に主人公が何時間も何時間も懸命に語りかけるシーンは、ファンタジーのイメージ性がまさに功を奏したシーンだと思う。
仁菜シナリオが変わった衣装を着た凡庸なギャルゲーシナリオ(凡庸とはつまらないということではない。形式としてよくある、ということだ)だとしたら、春香シナリオは、一見平凡な義妹シナリオに見え、最後に一転ギャルゲーそのものを突き崩すような非凡さを見せるシナリオである。春香は旅芸人一座で衣装関係の仕事を主にやっている、主人公の義妹である。彼女は兄が通う高校にも人見知りなどの理由で当初は通わなかったが、胡桃のおかげもあってある日から高校に通うことになる(余談だが、春香が高校に入った当日の自己紹介は傑作)。そして、主人公と春香の関係はいつしか兄妹のものではなく、恋人同士のものになっていく(他にも、旅芸人一座の中での話など、結構いいエピソードがある)。そんななかで、旅芸人一座の次の出しものとして、主人公と春香を姉妹として(主人公が妹、春香が姉)主役に据えた劇をやることが決まる。劇の練習のさなか何度も主人公は幻覚に襲われる。ついに、劇の初日。その劇はある姉妹が理不尽な親から逃げ出すところから始まる。姉の努力や出会った人の善意でなんとか日々を暮らしていく姉妹。だが、ある日姉は仕事から帰らず、妹は親に見つかり連れ戻されてしまう。帰った家で真実が明かされる。実は姉は何年も前に死んでいたのだ。この劇中劇を演じる中で主人公は、自分が今いる世界(くじら世界)や春香たちが実は自分の幻想の産物であることを悟る。けれど、春香を愛していた主人公は、本当の現実へと還りそうになる意識を幻想の中に向けなおし、春香たちとともに生きることを選択する(このシーンも、「夏に降る雪」というイメージを最大限に利用した名シーン!)。
つまり、この作品で描かれている「くじら世界」は実は主人公の幻想の産物で、本当の現実との関係は「現実(作外)/幻想(作中「くじら世界」)」という図式で表せる。その中に、主人公と春香が演じる劇中劇の「現実(姉は死んでいる)/幻想(姉が生きている)」という図式が折り込まれる。『現実(作外)/幻想(作中「くじら世界」<現実(姉は死んでいる)/幻想(姉が生きている>』。こうして、二つの「現実/幻想」という図式の片方がもう一方に再参入したことでくじら世界はひずみ、主人公はそのひずみから今まで唯一の現実だと信じていたくじら世界が自分だけの幻想の産物だったと気づくのである。作外の「現実」に言及するという手法は、その頂点である『Ever17』や多少趣が違うが『CROSS†CHANNEL』『最果てのイマ』という田中ロミオ作品、『Fate/hollow ataraxia』など、プレイヤーの視点(仮構世界に対して超越している視点)を作品に持ち込むことで、『現実/幻想』という差異を移入し、ギャルゲーというジャンルに対する批評性を獲得した作品に特徴的なものである(正確には『最終試験くじら』は、プレイヤーの視点を作品の中に明確に移入まではしていないのだが)。筆者が一度強調しておきたいのは、ギャルゲーに限らず、あらゆるフィクションは、『現実/幻想(仮構)』という差異の図式を基点に成り立っているということである。とは言え、この図式は厳密なものではない。どんなに荒唐無稽な(くじら的な!)フィクションであろうと、それ自体が(それ自体言及不可能な)<現実>を構成するモニュメントなのだから(どんなにフィクションに耽溺したオタクであっても、その存在自体はきわめて現実(実際)的である)。だが、『現実/幻想』という差異自体は取り返しの効かない(フィクションは、あえてなされた嘘だからこそ価値がある)ものである以上、ギャルゲーを含めたフィクションが再生産されるなかで、その度にこの差異図式が構成される。たとえ、フィクションの中で「本当の現実は……である」という言明を繰り返しても、それ自体またフィクションである(あるいは、本物の批評家が「本当の現実……である」という言明をしたとしても、それはせいぜい現実の顔をしたフィクションである。正確には、現実とは仮構をもふくめた「すべて」である(より正確には、すべては幻想であり、現実とは幻想の中に生きる私たちが直接言及できない、「失敗」のようなものである))。
話が大きくなったが、単純にいえば、ギャルゲーを含めた全てのフィクションが『現実/幻想』という差異図式に根ざしている以上、この差異を作品中に意識的に導入するかどうかで、(あくまで作品形式の話だが)作品のレベルが一段変わるのである。そして、『最終試験くじら』こそは、この差異図式を、これ以上ないくらい素朴に導入した作品なのである。そして、その作品の中で、あえて幻想の中で生きよう、という選択を下したのが春香シナリオなのである。まあ、言ってしまえば、オタクが現実の恋愛をあきらめ、ギャルゲーに没入していくような話なのだが、ギャルゲーというオタク向けジャンルの中には、こういうシナリオはあってしかるべきだし、オタクの試金石とも呼べるシナリオである。少なくとも筆者は、空虚な幻想を捨て、豊かな現実に還れという、それ自体空虚なお題目よりはよっぽど感動した。それに、『愛』は、他の全てを捨て、二人の世界へ…というイメージがついて回るが、主人公の春香への愛はそのイメージにもっとも忠実でさえある。逆に、くじら世界という幻想に引きこもってしまった理由を発見し、その理由であるトラウマを回復し、「現実」へと帰ってしまうくじらの少女シナリオは、せっかく春香シナリオで思い切った選択をしたのにそれを捨ててしまい、筆者にはシラけを感じさせた。これぞ、『マトリックス』以来、使い古され続けたまさに凡庸なテーゼである。
『最終試験くじら』という作品の評価が悪いのは、筆者が評価するまさにこの点の解釈によるものなのだ。くじらの少女シナリオで、実は胡桃も仁菜も春香も現実には存在せず、せいぜいそのもととなった人がいるのみ、本当にいるのは、くじらの少女のもととなった幼い頃に友達だった女の子だけ、という事実が明かされる。そんなわけで、せっかく大変な想いをして胡桃や仁菜と結ばれても、それは全くの幻想であった、ということが作中で暴露され、プレイヤーがシラけてしまったのである。だが、筆者の視点からすればこれは『最終試験くじら』という作品を貧困にするだけの読み方でしかない。少なくとも、他ならぬ「オタク」にはやってほしくない評価である。オタクこそは、幻想の現実(事実)性をもっともよく理解するのみならず、それを実践している人種だからだ。別に私は「オタク」を積極的に擁護しようとしているわけではない(例えば、オタキングの「オタク=ニュータイプ」論のように)。ただ、『最終試験くじら』の春香シナリオで筆者が受け取ったメッセージ、「幻想の中に生き続けることは、その労力と代償に可能である(許されうる)」に忠実でありたいのだ。
さて、このゲームはオープニングの歌『ディアノイア』(riya)とムービーが素晴らしいことと、内容のへっぽこさで知られている。ヒロインは7人いるのだが、それぞれに対応したシナリオは大体4パターンに分かれる。物語の謎に直接関わらない普通のギャルゲーシナリオが4本(Aパターン、胡桃、仁菜、優佳、美佳)。物語の謎に直面し選択を迫られるシナリオ2本(Bパターン、春香、くじらの少女)。おまけ的ネタシナリオ1本(Dパターン、香倶耶)。一応、分けては見たものの、Bパターンのシナリオにも、くじら世界を続けるか放棄するか、という選択で大分様相が変わってくるし、あくまで便宜的なものだと思ってもらいたい。
それぞれのシナリオに簡単な解説を。優佳と美佳のシナリオは双子ネタのわりと平凡な学園ものシナリオである。胡桃と仁菜のシナリオでは、物語の鍵になっている「くじら」が、この作品のジャンル「不条理アドベンチャー」の名そのままに関わり、ファンタジックな様相を呈している。春香のシナリオは、一見普通の義妹ものだが、クライマックスで、主人公と春香が主役の劇をやるなかで「くじら」世界の一端が暴かれ、主人公にある選択を迫ることとなる。くじらの少女シナリオで「くじら」世界はどうしてできたのかなど、作品の謎が一応全てわかる、トゥルーエンド的なシメ方をする。その上で、香倶耶シナリオは、あばかれた「くじら世界」観をもとに、ぶっとんだ話になる。プレイヤーはだいたいこの順番にゲームを攻略していくことになる。筆者が気にいったのは、仁菜と春香のシナリオ。順を追って紹介していこう。
まず、前提。主人公は旅芸人の一座の花形の女形で、ある町に到着する。その街には、宙に大きな一匹のくじらが浮いており、謎の存在ながらも街の名物となっている。
仁菜シナリオは、ファンタジックな要素に彩られているが、凡庸なギャルゲーシナリオである。主人子は転校早々、体が宙に浮いてしまうという御影仁菜先輩と仲良くなるのだが、彼女が自分の意志で飛ぶことはできないため、自由に飛ぶための練習を手伝うことをかって出る。その練習のなかで、主人公と仁菜は仲良くなっているのだが、仲良くなればなるほど、主人公は仁菜が何かを隠しているのではないかと気づいていく。実は、仁菜は幼い頃に軍の実験で体に「くじらの欠片」を埋め込まれ、そのせいで宙に浮く体質になっていたのだ。しかも、幼い頃に義理の父親(?この辺りは描写があいまいでいまいち良くわからない)に強姦され、「くじらの欠片」の様子を調べるため、毎週病院に通うことが義務付けられているのだが、そこの医師にも強姦されている。そんなわけで、主人公と仁菜は体を重ね愛情を確認しても、その後になって仁菜は、自分は汚れているから睦くん(主人公)とは一緒にいられない、と言って、空に昇りくじらのおなかの中で殻に引きこもってしまう。主人公は、仁菜を追うため、たまたまペットになった子くじら「しろたま」に乗ってくじらのおなかに入り、自分が幼い頃、義理の良心とどうやって家族になったかという話とかをして、一生懸命仁菜を慰め、殻の中から出そうとするのだ。このシーンが、かなりいい。自分の家族への想いや仁菜への想いが詰め込まれていて、本作屈指の名シーンとなっている。本作は、あえて「ご都合主義」なファンタジーに走り、そのエクスキューズ(言い訳、理由付け)として「くじら」を持ち出しているが、くじらのおなかの中で半透明の卵型の殻にうずくまる仁菜に主人公が何時間も何時間も懸命に語りかけるシーンは、ファンタジーのイメージ性がまさに功を奏したシーンだと思う。
仁菜シナリオが変わった衣装を着た凡庸なギャルゲーシナリオ(凡庸とはつまらないということではない。形式としてよくある、ということだ)だとしたら、春香シナリオは、一見平凡な義妹シナリオに見え、最後に一転ギャルゲーそのものを突き崩すような非凡さを見せるシナリオである。春香は旅芸人一座で衣装関係の仕事を主にやっている、主人公の義妹である。彼女は兄が通う高校にも人見知りなどの理由で当初は通わなかったが、胡桃のおかげもあってある日から高校に通うことになる(余談だが、春香が高校に入った当日の自己紹介は傑作)。そして、主人公と春香の関係はいつしか兄妹のものではなく、恋人同士のものになっていく(他にも、旅芸人一座の中での話など、結構いいエピソードがある)。そんななかで、旅芸人一座の次の出しものとして、主人公と春香を姉妹として(主人公が妹、春香が姉)主役に据えた劇をやることが決まる。劇の練習のさなか何度も主人公は幻覚に襲われる。ついに、劇の初日。その劇はある姉妹が理不尽な親から逃げ出すところから始まる。姉の努力や出会った人の善意でなんとか日々を暮らしていく姉妹。だが、ある日姉は仕事から帰らず、妹は親に見つかり連れ戻されてしまう。帰った家で真実が明かされる。実は姉は何年も前に死んでいたのだ。この劇中劇を演じる中で主人公は、自分が今いる世界(くじら世界)や春香たちが実は自分の幻想の産物であることを悟る。けれど、春香を愛していた主人公は、本当の現実へと還りそうになる意識を幻想の中に向けなおし、春香たちとともに生きることを選択する(このシーンも、「夏に降る雪」というイメージを最大限に利用した名シーン!)。
つまり、この作品で描かれている「くじら世界」は実は主人公の幻想の産物で、本当の現実との関係は「現実(作外)/幻想(作中「くじら世界」)」という図式で表せる。その中に、主人公と春香が演じる劇中劇の「現実(姉は死んでいる)/幻想(姉が生きている)」という図式が折り込まれる。『現実(作外)/幻想(作中「くじら世界」<現実(姉は死んでいる)/幻想(姉が生きている>』。こうして、二つの「現実/幻想」という図式の片方がもう一方に再参入したことでくじら世界はひずみ、主人公はそのひずみから今まで唯一の現実だと信じていたくじら世界が自分だけの幻想の産物だったと気づくのである。作外の「現実」に言及するという手法は、その頂点である『Ever17』や多少趣が違うが『CROSS†CHANNEL』『最果てのイマ』という田中ロミオ作品、『Fate/hollow ataraxia』など、プレイヤーの視点(仮構世界に対して超越している視点)を作品に持ち込むことで、『現実/幻想』という差異を移入し、ギャルゲーというジャンルに対する批評性を獲得した作品に特徴的なものである(正確には『最終試験くじら』は、プレイヤーの視点を作品の中に明確に移入まではしていないのだが)。筆者が一度強調しておきたいのは、ギャルゲーに限らず、あらゆるフィクションは、『現実/幻想(仮構)』という差異の図式を基点に成り立っているということである。とは言え、この図式は厳密なものではない。どんなに荒唐無稽な(くじら的な!)フィクションであろうと、それ自体が(それ自体言及不可能な)<現実>を構成するモニュメントなのだから(どんなにフィクションに耽溺したオタクであっても、その存在自体はきわめて現実(実際)的である)。だが、『現実/幻想』という差異自体は取り返しの効かない(フィクションは、あえてなされた嘘だからこそ価値がある)ものである以上、ギャルゲーを含めたフィクションが再生産されるなかで、その度にこの差異図式が構成される。たとえ、フィクションの中で「本当の現実は……である」という言明を繰り返しても、それ自体またフィクションである(あるいは、本物の批評家が「本当の現実……である」という言明をしたとしても、それはせいぜい現実の顔をしたフィクションである。正確には、現実とは仮構をもふくめた「すべて」である(より正確には、すべては幻想であり、現実とは幻想の中に生きる私たちが直接言及できない、「失敗」のようなものである))。
話が大きくなったが、単純にいえば、ギャルゲーを含めた全てのフィクションが『現実/幻想』という差異図式に根ざしている以上、この差異を作品中に意識的に導入するかどうかで、(あくまで作品形式の話だが)作品のレベルが一段変わるのである。そして、『最終試験くじら』こそは、この差異図式を、これ以上ないくらい素朴に導入した作品なのである。そして、その作品の中で、あえて幻想の中で生きよう、という選択を下したのが春香シナリオなのである。まあ、言ってしまえば、オタクが現実の恋愛をあきらめ、ギャルゲーに没入していくような話なのだが、ギャルゲーというオタク向けジャンルの中には、こういうシナリオはあってしかるべきだし、オタクの試金石とも呼べるシナリオである。少なくとも筆者は、空虚な幻想を捨て、豊かな現実に還れという、それ自体空虚なお題目よりはよっぽど感動した。それに、『愛』は、他の全てを捨て、二人の世界へ…というイメージがついて回るが、主人公の春香への愛はそのイメージにもっとも忠実でさえある。逆に、くじら世界という幻想に引きこもってしまった理由を発見し、その理由であるトラウマを回復し、「現実」へと帰ってしまうくじらの少女シナリオは、せっかく春香シナリオで思い切った選択をしたのにそれを捨ててしまい、筆者にはシラけを感じさせた。これぞ、『マトリックス』以来、使い古され続けたまさに凡庸なテーゼである。
『最終試験くじら』という作品の評価が悪いのは、筆者が評価するまさにこの点の解釈によるものなのだ。くじらの少女シナリオで、実は胡桃も仁菜も春香も現実には存在せず、せいぜいそのもととなった人がいるのみ、本当にいるのは、くじらの少女のもととなった幼い頃に友達だった女の子だけ、という事実が明かされる。そんなわけで、せっかく大変な想いをして胡桃や仁菜と結ばれても、それは全くの幻想であった、ということが作中で暴露され、プレイヤーがシラけてしまったのである。だが、筆者の視点からすればこれは『最終試験くじら』という作品を貧困にするだけの読み方でしかない。少なくとも、他ならぬ「オタク」にはやってほしくない評価である。オタクこそは、幻想の現実(事実)性をもっともよく理解するのみならず、それを実践している人種だからだ。別に私は「オタク」を積極的に擁護しようとしているわけではない(例えば、オタキングの「オタク=ニュータイプ」論のように)。ただ、『最終試験くじら』の春香シナリオで筆者が受け取ったメッセージ、「幻想の中に生き続けることは、その労力と代償に可能である(許されうる)」に忠実でありたいのだ。